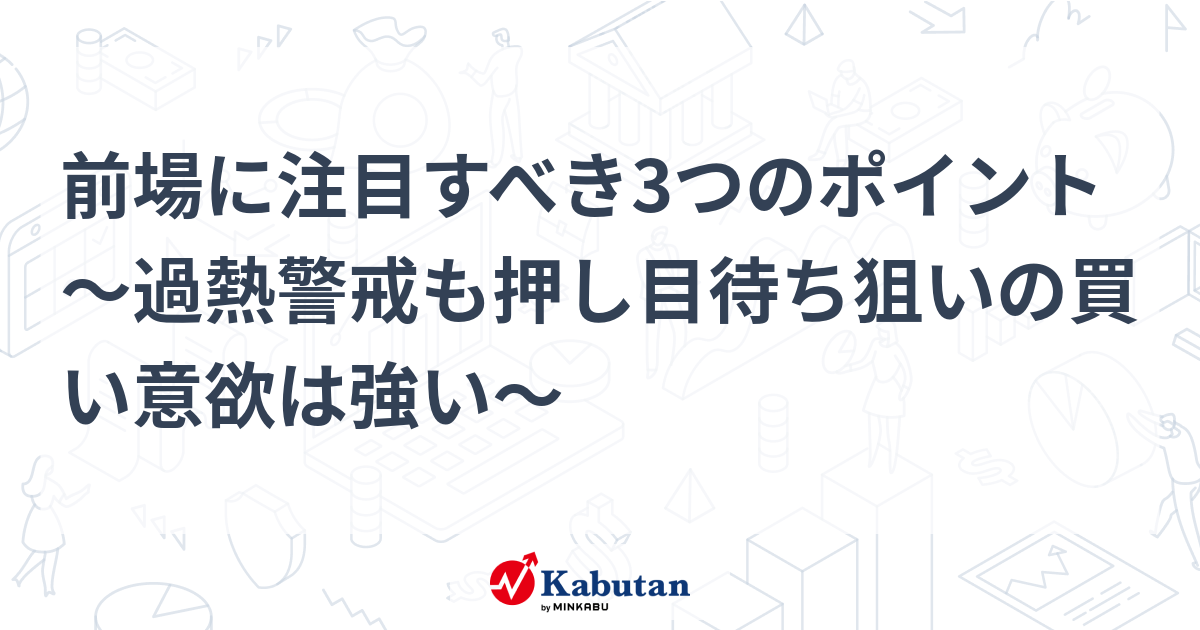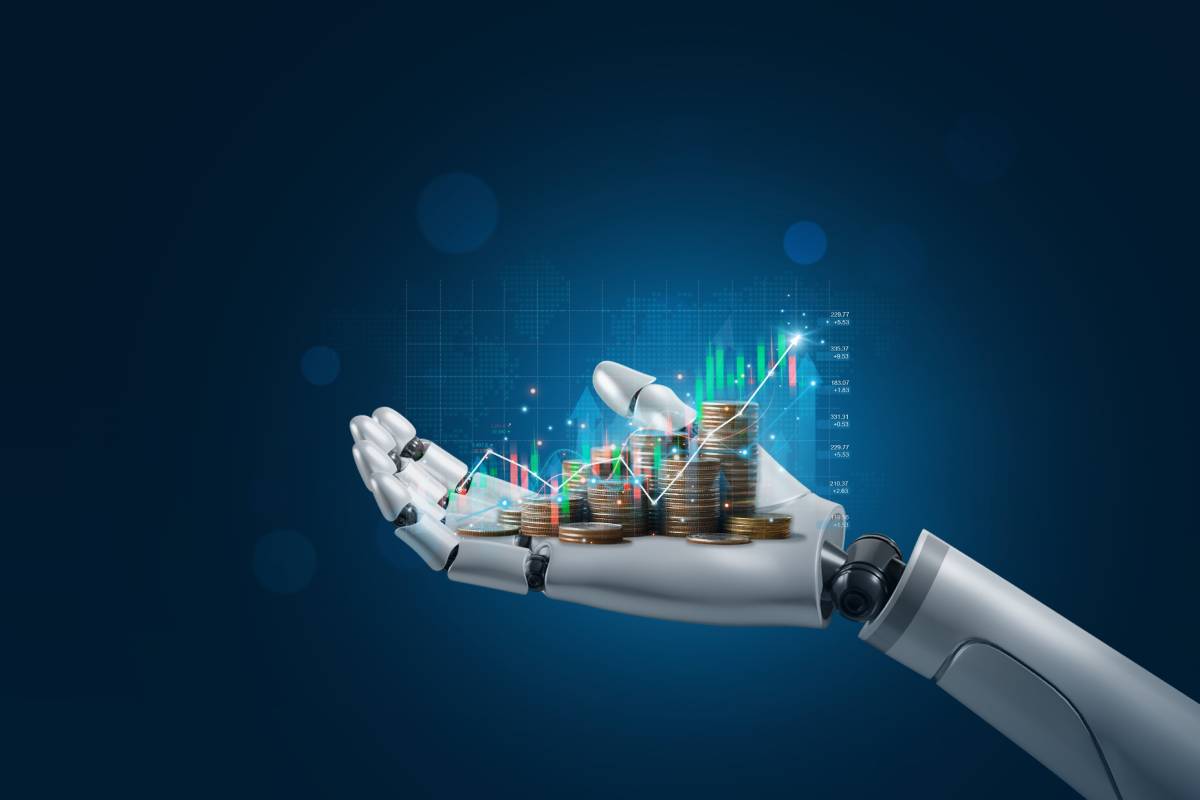日産とセブン&アイのディール崩壊、開かれた日本企業の脆弱性示す

経営不振の日産自動車や、海外企業に買収されそうになり四面楚歌(そか)だったコンビニエンスストア大手セブン&アイ・ホールディングス救済のため国内の大手企業が立ち上がった。それは驚くべき愛国心や団結心の表れのように見えた。
それからおよそ半年後、ホンダと日産による共同持ち株会社の設立やセブンの経営陣が参加する買収(MBO)という野心的な計画はどちらも頓挫した。両社は打開策を模索するが、海外企業による買収の危機にさらされる可能性も高まっている。
日本を代表する両社が国内資本のまま確実に継続できるような解決策を見つけられなかったことは、ガバナンス(企業統治)改革が急ピッチで進む日本株式会社にとっての新たな時代の幕開けを告げ、急ごしらえの対抗策は市場の圧力に屈してしまう可能性があることを示している。
海外企業が特定の技術や人材の獲得に関心を持っているのであれば、今こそ日本企業にアプローチする絶好の機会だとニューバーガー・バーマンでポートフォリオ・マネジャーを務める岡村慧氏は話す。
実際、投資家たちはすでに資生堂やアステラス製薬など経営不振の企業や京成電鉄や京浜急行電鉄などの鉄道会社に投資ポジションを構築しつつある。保護主義と経営陣の抵抗という点で悪名高かった日本の大手企業の扉が開かれようとしていることに賭けているのだ。
歴史的に日本企業は「対等な合併」という理念について高尚な考えを持ってきた、と岡村氏は言う。株主や従業員、取締役会もそれを当然としてきたが、ここにきて投資家や取締役会が疑問を持つようになった結果、多くの企業が異議を唱えられるようになっていると指摘する。
関連記事:
日本には、割安で放置されているキャッシュリッチ企業が数多く存在するが外国企業による大規模買収が成功した例はほとんどない。そうした企業は昔なら買収の申し出を無視することで追い返すことができたからだ。しかし、経済産業省や東京証券取引所などが旗振り役となったコーポレートガバナンス(企業統治)改革が進んだ結果、企業への圧力は着実に高まっている。
セブン創業家である伊藤家は当初、ライバルであるファミリーマートを運営する伊藤忠商事の出資も受け、アポロ・グローバル・マネジメントやKKRなどの協力も得ながらクシュタールの提案を上回る9兆円のMBOで対抗する予定だった。だが、伊藤家と伊藤忠は最終的に、MBO実施後の会社の議決権比率や取締役会構成などで合意に至らなかったと、事情に詳しい関係者は述べた。
12月に発表されたホンダと日産の共同持ち株会社設立計画はホンダによる実質的な救済だったが、台湾の鴻海精密工業が日産株取得の考えを示していたことが拍車をかけた側面があるとされる。しかし、ホンダが業績が悪化している日産を子会社化する案を提示したことで日産の大株主で株の売却にプレミアムを望む仏ルノーなどから強い抵抗を受けて実現に至らなかった。
L.E.K.コンサルティングの藤井礼二氏は日本企業同士であれば、リストラを含むコスト削減が「生ぬるい環境のまま入れるという考えもある」との考えを示す。一方、外国企業が買収すれば、不採算事業は容赦なく切られるが「それは株主に対するアカウンタビリティーの現れだ」とした。
国内企業同士による解決策を見つけられなかった両社の失敗例を前に、雇用の確保などを念頭に今後政府が介入する可能性もある。そうなれば自らが進めてきた改革と逆行する皮肉な動きとなる。
買収提案など重要な案件に関する決定をくだす際、昔の文脈で考えることは許されない時代になったとニューバーガー・バーマンの岡村氏は強調した。