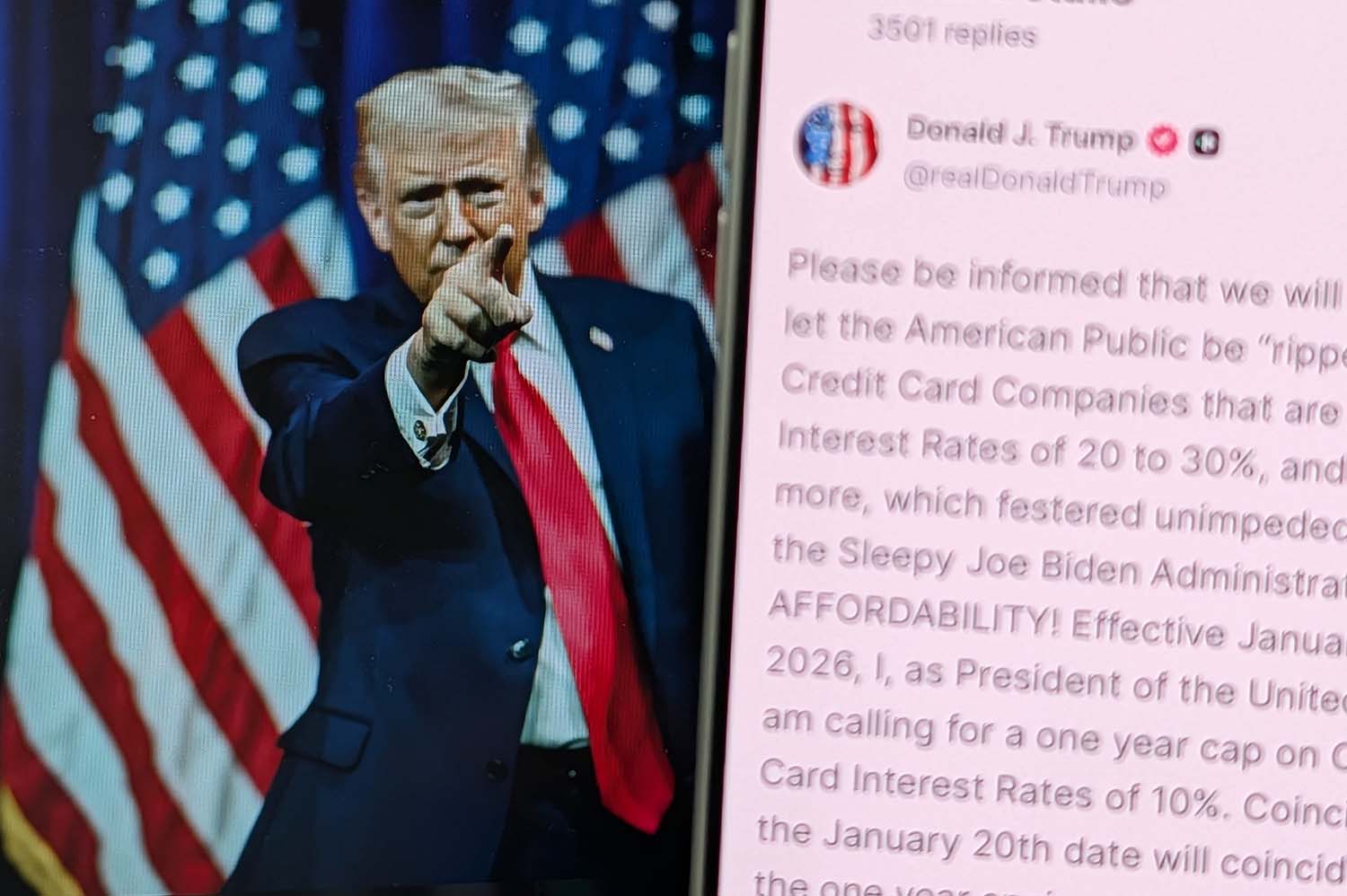コラム:高市総裁で進む円安、問われる成長戦略とトランプ政権対応=熊野英生氏

[東京 6日] - 相場は、自民党の高市早苗新総裁の下で大きく動きそうだ。株価上昇、長期金利上昇、そして円安加速が予想される。選挙後の10月6日は、日経平均株価の終値が、47944.76円まで上った。
これまで日銀の次の利上げが年内、早ければ10月末にも行われるとの観測があった。もしも高市氏が利上げに待ったをかける言動を取れば、さらに円安は進むだろう。日銀側も高市氏から厳しい対応を受けることを強く警戒するので、おのずと利上げに関して慎重化することだろう。暗黙の縛りが日銀の利上げを抑制させ、その結果として円安圧力になっていくだろう。
高市氏の経済政策は拡張的なものになりそうだ。財政出動を行う一方で利上げは抑制的となれば、インフレ圧力はおのずと高まる。物価高対策として、減税・給付拡大で応じることは元々、需要をより押し上げることになり、意図せざるかたちで物価上昇リスクを高めてしまう。そうすると、円安圧力と相まって本当に物価高を助長しかねない。さらに、それに財政出動で応じると長期金利は上昇して、政府の利払い費を増やすことも起こると考えられる。
<野党との連携も財政悪化要因>
少数与党の下での国会運営は、野党の政策要求をいくらか受け入れることを迫られる。今までは財源がないことを理由に容易に受け入れられないとしてきたが、高市氏が積極財政の姿勢であれば、財源の制約を理由にしにくくなる。ガソリンの暫定税率廃止、給付付き税額控除の導入はいずれも大きな財源が必要となる。
与党としてはなるべく解散・総選挙を避けたいため、野党との連立も視野に入れて行動することになる。するとますます野党の要求が通りやすくなり、財政悪化を招いてしまうリスクが高まる。
目先、注目されるのは、臨時国会での野党とのかけ引きと、近々まとめられる秋の補正予算の編成である。自然増収の余力はそれほど大きくないから、ここで新規国債発行を追加することになるだろう。年末には来年度予算案の編成が控えている。政府は、2025、26年度に基礎的財政収支の黒字化を掲げているが、その方針がどこまで尊重されるのか懸念される。
<気になる成長戦略の空白>
ここまで、財政・金融政策にスポットを当てて、円安が進んでいく圧力があることを指摘した。10月6日には1ドル150円台まで円安が進んだ。円安要因としては、日本の成長力そのものの問題もある。日本の潜在成長率が低く、日銀の利上げもスローペースで進めざるを得ないという構造的背景である。
5人の候補の間で行われた自民党総裁選では、そうした日本の成長力を高めようという議論は乏しかった。賃上げを強調する候補でさえ、それをバックアップする成長プランは手薄だと感じた。税制優遇で投資誘発ができたとしても、それは成長予想が高まった結果として増えるのとは異なっている。経済成長を口にしていても、財政的な刺激によるものだ。高市氏の財政出動も、潜在成長率を高めるものとは別ものなのだ。経済学をベースにした成長観ではなく、政治的フレーズとしての「成長を目指す」という意思表明だったと思う。特に高市氏の議論には、その成長観にやや不鮮明な印象があった。
本来はアジア・欧州連合(EU)向けの輸出を増やしたり、競争力のあるハイテク産業を地方に誘致したりすることが成長支援になる。地方の消費拡大に向けた取組みとしては、東京都・大阪府・京都府の3地域に全体の6割が集中するインバウンド消費を、他地域に分散することも有益だ。観光客の中には行動が問題視される者もいるが、それはごく一部である。安倍元首相が掲げた「三本の矢」のうち、最後の成長戦略のところが、後継の自民党のリーダーの間で弱いという点は少し残念である。
<今さらながらトランプ関税>
影に隠れている問題には、トランプ米政権の「相互関税」15%に対米輸出をする日本企業がどう対処するかということもある。石破首相は、25年4月にこれを国難と呼んだ。まだ国難から半年しか経っていないのに、それを忘れてもらっては困る。対米輸出が減ってしまうことは円安要因である。国内的には、26年の春闘交渉に暗い影を落とす。筆者は、石破政権が関税対策として全国1000カ所に相談窓口を設けるくらいしかできなかったことにやや失望している。
高市氏の評価は、トランプ政権がかけてくる外圧をどのようにはねのけるかにかかっている。対米投資80兆円も国益にかなうかどうかわからない。追加的な要求が来る可能性も否定できない。不安なのは防衛費の上積みである。岸田前政権は、防衛費を国内総生産(GDP)の2%まで増やすことを約束し、その財源確保を27年度までに行うべく、防衛増税や歳出削減など14兆6000億円の捻出を決めた。この帰結を見届けることなく岸田首相は政権を去った。高市氏は日本の防衛には熱心だと思うが、アキレス腱は米国からの要求にあるのではないか。NOと言える日本になれるかどうかが問われる。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*熊野英生氏は、第一生命経済研究所の首席エコノミスト。1990年日本銀行入行。調査統計局、情報サービス局を経て、2000年7月退職。同年8月に第一生命経済研究所に入社。2011年4月より現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab