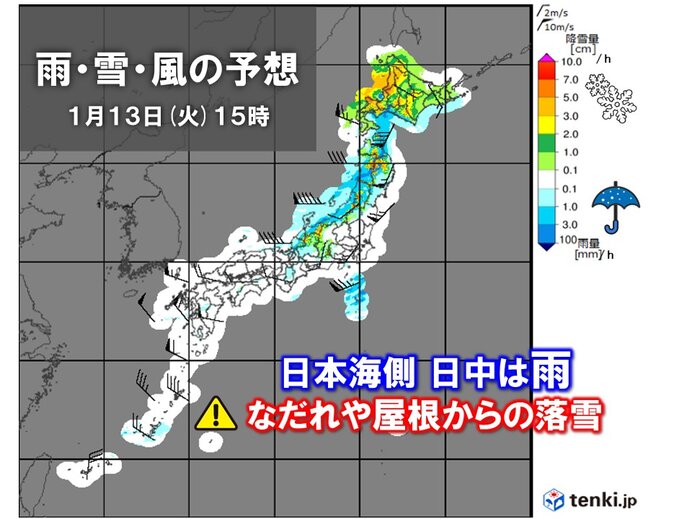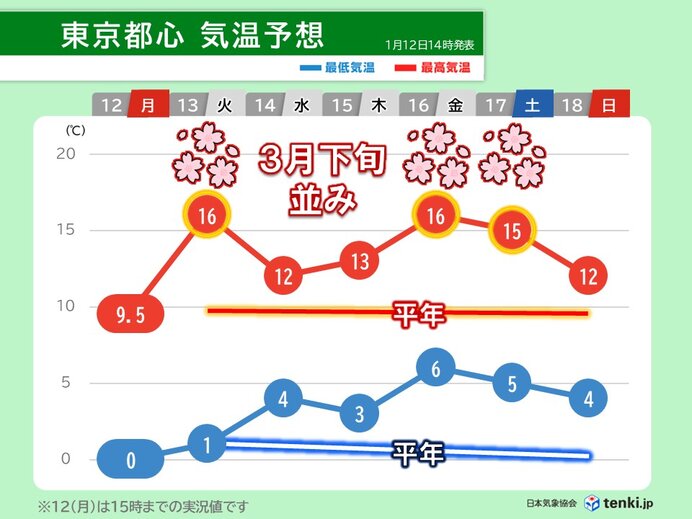学習用端末を見切り導入、児童は不在…専門家「科学的根拠に基づいて政策決めるプロセスを軽視」

「紙の教科書がなくなってデジタルだけになれば、授業は成立しない」。東京都内の公立小学校に勤める50歳代の女性教員は、中央教育審議会作業部会の「中間まとめ」に、ため息をつく。紙の「代替教材」のデジタルが「教科書」になれば、教育委員会が選ぶ一方しか使えなくなるからだ。
デジタル教科書は1人1台の学習用端末で見る。だが、受け持ちの5年生のクラスで端末を使おうとすると頻繁に手が挙がる。「家に忘れてきました」「電池切れです」。2月下旬の算数の時間、そんな児童はクラスの4分の1に上った。
女性教員は「教育委員会に端末の使用状況を聞かれることもあり、『端末を使ってほしい』との意向を感じる。だが、教室の実態とは合っていない」と訴える。
「日本は海外に後れを取っている。ICT教育を急ぐべきだ」。デジタル教科書の導入を声高に叫び始めたのは、一部の政治家と財界人だった。2009年に旧民主党政権の原口一博総務相が「15年までにデジタル教科書を小中学校の全生徒に配備する」と表明。教育のデジタル化を求める超党派の議員連盟もできた。
この頃の文部科学省は、まだ慎重だった。<紙の教科書が我が国の教育に大きな役割を果たしてきたことに疑いはない。紙の教科書が目の前からなくなる状況には、不安を覚える者も多い>。16年12月、文科省の有識者会議がまとめた報告書は、教科書は紙が基本だと明記した。ある幹部は「教科書は子どもが毎日使う。紙は絶対になくすべきではないと思っていた」と振り返る。
そんな省内の空気は、コロナ禍で一変する。休校や学級閉鎖が相次ぎ、国が19年に打ち出したGIGAスクール構想が加速。総額4600億円を費やし、21年には小中学生に学習用端末がほぼ行き渡った。
「端末整備が早まり、デジタル教科書が現実味を増した。そこからは、デジタル教科書をいつ、どのように実現するかの検討に変わった」。有識者会議の議論を知る関係者は語る。
文科省が設置した2回目の有識者会議は21年の報告書で、前回にはあった「紙が基本」との文言を消した。そして今回、中教審作業部会がデジタルの正式教科書化を提起するに至る。
東北大の大森不二雄教授(教育政策)は「デジタルの導入ありきで、科学的根拠に基づいて政策を決めるプロセスが軽視されている。義務教育は基礎学力を形成する重要な時期。やり直しがきかないという責任を自覚し、再検討すべきだ」と指摘している。(教育部 渡辺光彦)