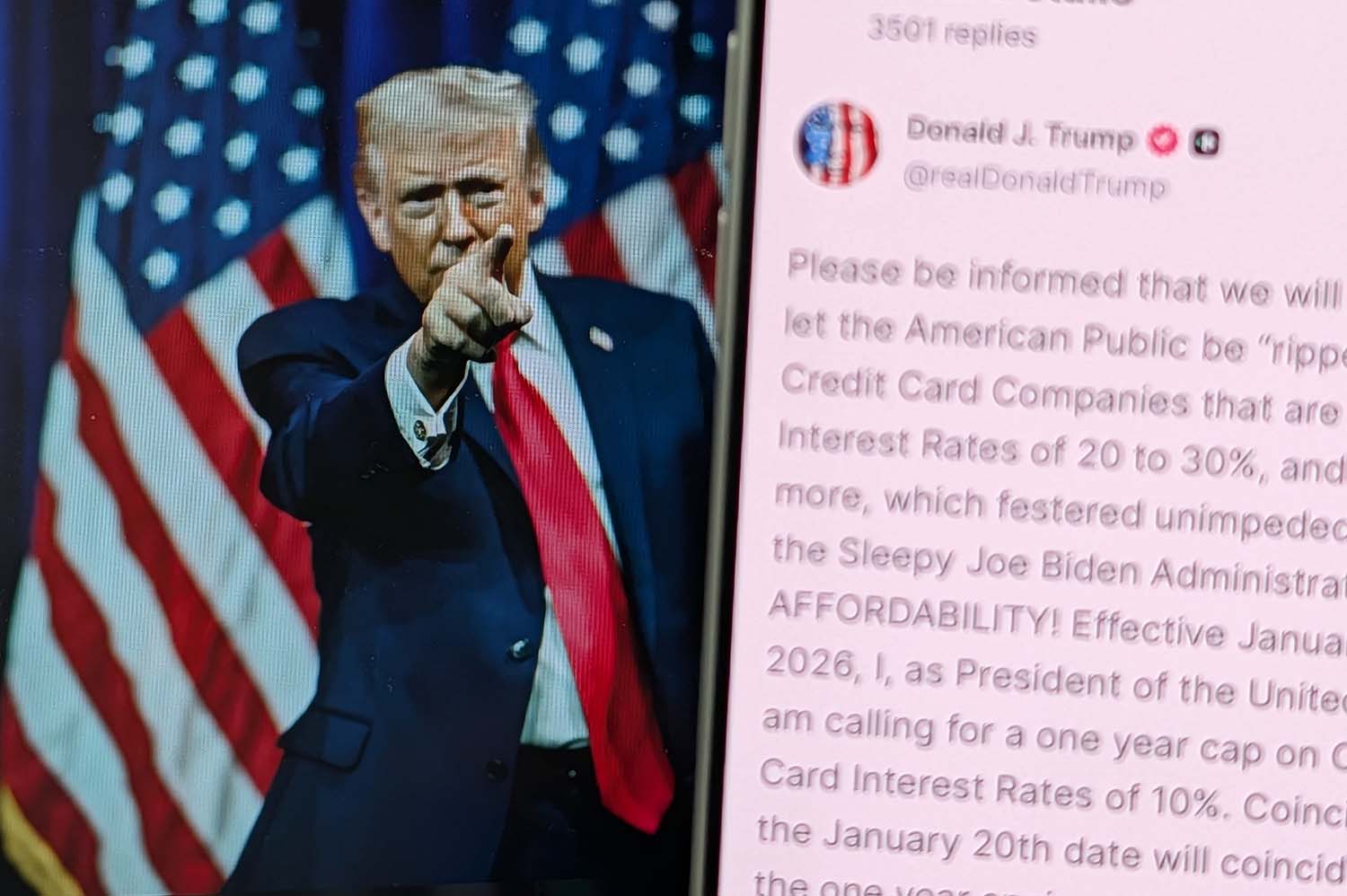神戸市のタワマン空室税、議論の行方は 京都市の例から見える納得の「目的」と「使い道」

投資目的の購入などでタワーマンションの空室が増える懸念を踏まえ、空室への課税の是非を議論する神戸市の2回目の検討会会合が28日、開かれる。不動産関連団体からのヒアリングなどが行われ、以後も議論が進められる予定だ。課税には私有財産権の侵害という面があり、納得できる目的や使い道が早期に示されなければ、タワマン住民以外からも市の税政策に対する不信を招きかねない。この点、2029年度からの実施が予定される京都市の「非居住住宅利活用促進税」が大きなヒントとなりそうだ。
「『タワマン建設や空き部屋の抑制』『ごみ処理といった行政需要への対応』など、複数の事柄が税制の目的として(議論のたたき台の)報告書に盛り込まれている。達成したい政策目的を議論する必要がある」
5月30日に開かれた神戸市の検討会の初会合で、ある委員はこう話した。目的が早くはっきりしなければ、実効性ある制度のありかたや効果をはかる方法の議論も深まらない。
初会合で「研究すべきだ」と意見が出たのが、京都市の非居住住宅利活用促進税だ。空き家や別荘など住民が居住していない住宅に課され、おおむね固定資産税の半額程度の負担となることが多い。税を避けるため空き家に住む人を増やしたり、税収を空き家活用の支援策に充てたりすることを狙う。
議論は16年からの検討委員会でスタートした。同市は観光客の増加による交通渋滞、ゴミ問題などが深刻で、行政対応が必要となる一方、財源が不足。アイデアの一つとして上がったのが、市外に住む人が持つ別荘やセカンドハウスへの課税だ。だが、検討委では対象住宅の線引きなどを「慎重に検討する必要がある」として保留。代わりに宿泊客に課す「宿泊税」を答申し、18年の導入につながった。
20年、京都市は新たな検討委を置き、議論を継続。ただ、人口減を背景に空き家の増加が深刻になっており、別荘やセカンドハウスだけにとどめるべきではないとの声が出て、比較的早期に「空き家問題」への対処策という、より広い地域課題の解決策として課税をとらえるようになった。
京都市の担当者によると「居住者のいない住宅への居住を促進し、土地や建物の有効活用を誘導するため生活の本拠以外に住宅を持つ人に負担を求める。防災・防犯も含めた社会的費用の負担を地域の人と同様に求める。この2つの目的が固まると(議論が)流れるようになった」という。
議論の対象がはっきりしたことで、実効性ある検討に役立ったとみられる。そして、21年に税の創設を答申し、その後、条例が成立。必要な総務相の同意もすでに得ており、29年度に施行される予定となっている。
神戸市のタワマン課税も、多岐にわたる課題を早く整理し最優先すべき政策目的を明確にすることが、議論の方向性を定める上で不可欠になる。
多様な意見を聞くことも求められる。神戸市では検討会の初会合で、管理組合理事長など現場からも意見聴取が必要との声も出た。また、京都市の場合、パブリックコメントを行い300件以上の意見を集めている。
並行して不公平感をなくす制度設計も重要だ。そのためには正確に居住実態をつかみ課税することが求められる。京都市は住民票がないが住んでいるケースを想定し、文書を送ったり現地調査したりして緻密に把握することを考えている。
さらに、「税収の使い道がもう少し明確になってもいい」とする寺川政司・近畿大学准教授(都市・地域計画)は「税収を、地域やコミュニティーの再生、福祉、教育といった具体的な『まちづくり』に活用する基金を行政がつくってはどうか」と提案する。
周辺地域も考慮した「エリアマネジメント」の観点で、寺川氏は「地域にプラスになることを丁寧に提案していくことが大切だ」と語った。(山口暢彦)
国民民主党は「空室税」を公約
空室の増加に課税で対応しようという動きが広がり始めている。20日に投開票がおこなわれた参院選では、国民民主党が公約で「空室税」の導入を打ち出した。
同党はマンションの価格や家賃が大都市で高騰しており、「安心して住み続けられないとの不安が広がっている」と指摘。「外国人による不動産取得が、この不動産価格の上昇の一因とされている」とした。
そして、「国民の手取りを増やすため、不動産価格や家賃の高騰を抑制する」と言及。「外国人による居住目的ではない投機目的の不動産取得に対し追加の税負担を求める『空室税』の導入などを検討する」と訴えた。海外でもカナダで同様の税があるとした。
神戸市では1月、別の有識者会議がタワマンの空室に対する新税の創設を提言し、検討会はその当否を話し合うためつくられた。
問題視しているのは、投資目的の購入などによりタワマンの空室が増えかねないという市の現状。報告書では、空室が増え所有者に連絡がつかないケースが多くなれば修繕や解体の合意が難しくなり、最悪の場合、「廃虚化」する恐れがあると懸念している。
5月30日の検討会の初会合では、課税目的の明確化を求める声のほか、課税という手段が本当に必要なのか、同様の問題を抱える大規模マンションも対象にするかの議論などが必要との意見も出た。部屋の居住実態を調べるため、水道メーターをチェックするアイデアも提案された。
タワマンは全国で増えており、東京カンテイの調査によると、昨年44棟が竣工し、12月末時点で1561棟に達した。今年は41棟の竣工が予定されている。タワマンの問題は全国でも予想され、神戸市の課税のありようは今後のモデルケースとなる可能性もある。