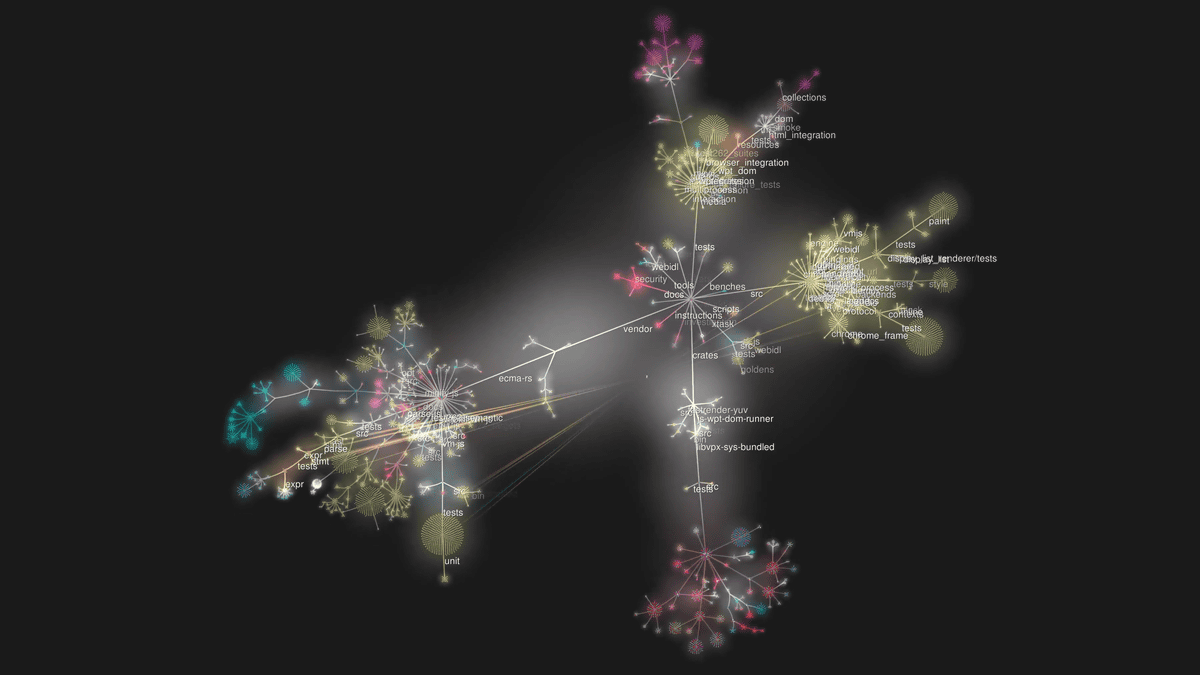ゲーム機を持っていなくて欲しい人は4.3%のみ…ゲーム機の所有・利用状況(不破雷蔵)

昨今ではインターネット接続が当たり前となりオンラインゲームも多数発売され、一方で同様のゲームが遊べるスマートフォンとのし烈な市場の覇権争いが繰り広げられているゲーム機。その所有・利用実情を総務省が2024年6月に情報通信政策研究所の調査結果として公式サイトで発表した「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(※)の公開値を基に確認する。
次に示すのはゲーム機(据置型ゲーム機と携帯ゲーム機の双方。回答用紙には「ニンテンドースイッチ、 PlayStationシリーズなど」とある)の所有および利用状況。自宅にある・無いを回答者に答えてもらい、ある場合には回答者自身が利用しているか、それとも利用していないか(置いてあるだけなのか、家族の別の人が使っているかは問わない)、無い場合には自宅に欲しいか、必要ないかを答えてもらっている。単純にあるか無いかの回答だけでなく、ある場合には利用状況を、無い場合には所有希望の有無まで尋ねることで、細かい需要を確認できる。
↑ 据置型ゲーム機所有状況(自宅、属性別)(2023年)↑ 据置型ゲーム機所有状況(自宅、「無い」、属性別)(2023年)全体では自宅所有率は67.6%。しかし利用率は37.7%にとどまっている。かつて使っていたが今はほこりをかぶっているとのケースもあろうが、むしろ子供が使っているが保護者である回答者は遊んでいない事例が多いのだろう。実際年齢階層別ではおおよそ低年齢ほど利用率では高い値を示している。10代では所有率87.9%、利用率70.7%。
就業形態別ではパート・アルバイトの人はフルタイムの人よりも所有率・利用率は低い。金銭面で余裕があるからだろうか。他方、自分で自由に使えるお金に余裕があることが多く、そして時間ではかなりの余裕があり、ゲームへの興味も深いであろう学生・生徒が一番高い値を示している。他方、無職の値は低いが、これは多分が高齢者であるため。世帯年収別では、600-800万円未満の層までは大体低世帯年収ほど低所有率・低利用率を示している。一方で都市規模別では規則性のようなものは見られない。
非所有者の状況だが、属性に限らずほとんどの人がゲーム機は必要ないと回答している。かろうじて30代の「無い・欲しい」率が1割に届きそうな程度。現在自宅にゲーム機がある人がもう一台、あるいは買い替えで購入する可能性までは推し量れないが、少なくとも現在一台も無い世帯において、新たに購入される可能性はほとんど無いと見てよい。一言で表現すれば世帯ベースでは飽和状態にある。
今件はあくまでも回答時の状況で、しかも13歳以上の回答者に限られている。大学生や社会人になり一人暮らしを始める=新世帯で暮らすようになる場合の環境変化、12歳以下の子供の所有願望は反映されていない。
しかし少なくとも現状では、ゲーム機は飽和に近い状態であることは否定できまい。新規需要の多くは「故障などによる現行利用機が利用できなくなった場合」「新型機への乗り換え」にあるものと考えられる。さらに今後の動向を見守る必要があるが、タブレット型端末やスマートフォンの普及で、稼働率が低下する、つまり自宅にあるが使っていない人の割合がこれまで以上に増える可能性は大いに考えられよう。
■関連記事:
【任天堂のゲーム機の販売動向推移をさぐる(2024年公開版)】
※令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査
今調査は2023年12月2日から12月8日にかけて、全国125地点をランダムロケーションクォータサンプリング(調査地点を無作為に抽出、地点ごとにサンプル数を割り当て、該当地域で調査対象者を抽出する方法)によって抽出し、訪問留置調査方式により、13歳~69歳の1500サンプルを対象としたもの。アンケート調査と日記式調査を同時並行で実施し、後者は平日2日・休日1日で行われている。よってグラフの表記上は「10代」だが、厳密には13~19歳を意味する。
調査のタイミングにより一部調査結果においてイレギュラー的な動きが確認できるが、これについて報告書では「経年での利用時間などの変化については、調査時期の違いによる影響や単年の一時的な傾向である可能性も否定できず、継続的な傾向の把握については今後の調査などの結果も踏まえる必要がある」と但し書きを入れている。さらに2020年分の調査については「令和2年度調査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、11都府県を対象とした緊急事態宣言下で行われたものであることにも留意が必要」との補足があった。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項のない限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項のない限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記のない限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。