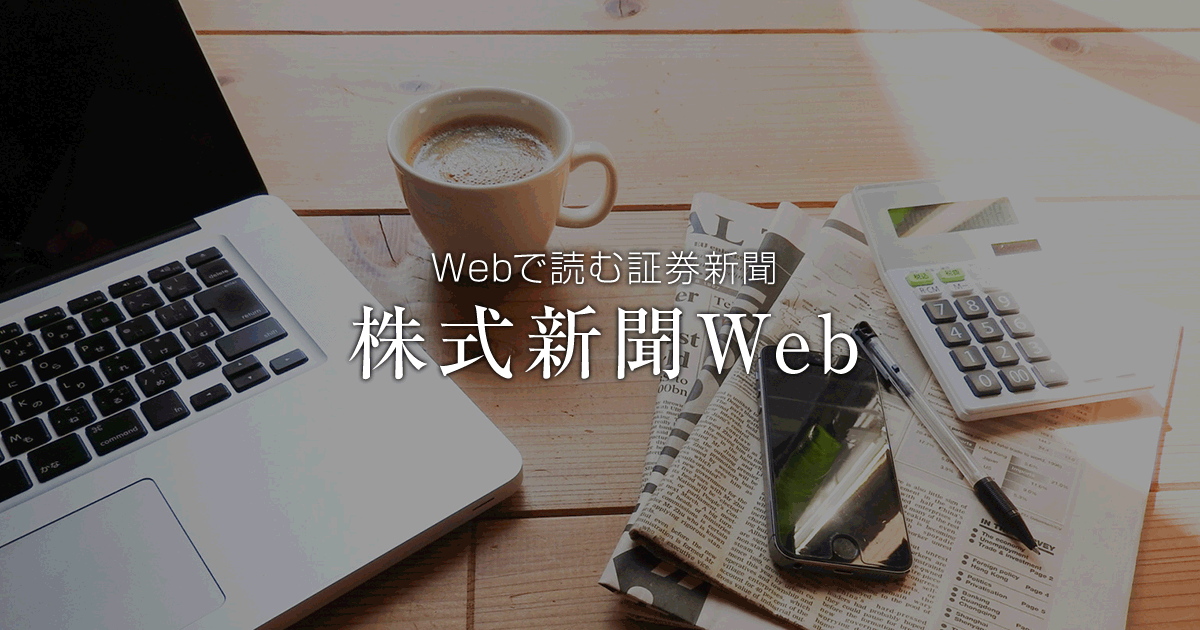コラム:「のりしろ」を巡る攻防、試合の流れはなお日銀有利=上野泰也氏

[東京 29日] - 筆者は昨年12月24日に寄稿した際、日銀が追加利上げに関して考えそうな点として、以下の3つを指摘した。
(1)利上げに動けるうちに「のりしろ」をできるだけ作っておきたい。(2)説明をつけにくい(納得が得られにくい)利上げは望ましくない。(3)「政治との間合い」も現実としてケアすべき問題。
その後、1月24日の金融政策決定会合で0.5%への追加利上げがあったので、上記3点のうち、まず(1)と(3)について、あらためて考察したい。
<のりしろ:将来に備えた「利下げカード」が2枚では不十分>
日銀が利下げに動く際の1回当たりの幅をたとえば0.1%にでも変えるなら別だが、通常の0.25%幅で動くという前提で言うと、現在の0.5%の政策金利水準では、将来いずれかの時点で起こり得る景気悪化や物価下落の際に用いることのできる利下げカードは、2枚に過ぎない。
しかも、仮にそれらを使い切ってしまうと「ゼロ金利」になり、さらなる金融緩和が必要になる場合に日銀としてどうするつもりなのかを、市場の内外に対して、ある程度コミュニケートしていかなければならないだろう。
日銀は昨年12月に行った「金融政策の多角的レビュー」において、量的緩和やマイナス金利といった非伝統的金融政策には一定の効果があったものの、弊害や副作用が伴ったことも強調し、そうした政策にはできれば戻りたくないという考えを漂わせた。
したがって日銀としては、利上げに「追い風」が吹いているうちに、チャンスが到来すれば着実にものにして、できるだけ「のりしろ」を大きく(将来の利下げカードの枚数を多く)しておきたいだろう。
<政治:「政府との間合い」は波風立たず>
1月の金融政策決定会合にかけて目立ったのは、「少数与党内閣」である石破内閣の閣僚による、追加利上げ容認色の強い発言である。政府がそうしたスタンスをとった理由として考えられる要素は2つある。まず、為替相場の円安地合いが続いており、モノの値上がりに対して有権者が引き続き神経質になっている中で、わずかなりとも円安進行阻止につながり得る日銀の利上げに政府として反対姿勢を明確にするのははばかられるということ。次に、25年度予算の年度内成立(予算案の3月2日までの衆院通過)を目指す野党3党との交渉で手いっぱいで、日銀の利上げ問題に熟慮して対応する余裕がない、ということだ。
「トランプリスク」をじっくり確認することのないまま、氷見野副総裁と植田総裁の発言連発によって追加利上げ時期に関する市場の織り込みをかなり強引に手前に引き寄せつつ、3月ではなく1月の会合で、日銀は利上げに動くことになった。
賃金・物価を中心とする国内の経済情勢について、解釈権者である日銀が「オントラック」(見通しに沿っている)だと説明できる限り、上に記した「のりしろ」や政治との間合いについての考察を背景に、日銀は利上げを重ねていく構えだろう。
トランプリスクが日銀の追加利上げに対して強い逆風になるなど、外的要因が急変することでもない限り、残る問題は説明のつけやすい利上げが可能かどうか、である。
<納得が得られにくい利上げ>
最新のESPフォーキャスト調査の集計結果を見ると、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)、いわゆるCPIコアの予測値総平均は、25年10-12月期(前年同期比プラス1.92%)以降、2%を下回り続ける姿になっており、26年度は前年度比プラス1.71%である。
前回の本欄でも述べた通り、このCPIコアが「物価安定の目標」であるプラス2%を下回り続けるようだと、日銀が利上げ路線を前面に出し続けるのは困難だろう。
足元では、コメ小売り価格の高止まり、円安再進行をうけた輸入物価の上昇、原油など国際商品市況の水準切り上げなどが起こっており、これらはCPIコアを押し上げる方向に作用する。しかしながら、サービスの価格上昇に力強さがないことからすると、財の価格上昇が一巡すれば、CPIコアの前年同月比がプラス2%を割り込む動きが現実になると見込まれる。
そうした状況が到来するまでの間に、日銀は利上げに何回動けるのか。確定的なことは誰にも言えないが、日銀内にはあと2回、1%に届くまでは利上げしたいという声があると報じられている。利下げカードを現在の2枚から4枚に倍増させたいという願望である。
昨年9月に米国で連邦準備理事会(FRB)の利下げが始まり、日米金利差が淡々と縮小する見通しが強まった際には、いわば試合の流れが変わり、日銀の追加利上げの「間口」が為替相場動向の面からも狭まっていく道筋が見えてきたと、筆者は受け止めた。
ところが、米国の景気・雇用がその後底堅く推移した上に、インフレ率の下げ渋りが当局者の警戒するところとなっている。さらに、トランプ大統領が関税上乗せ策、不法移民の国外送還、「トランプ減税」の延長・拡充に動くとなると、FRBの当面の利下げ余地は小さくならざるを得ない。為替相場の円安地合いが続いているゆえんである。
日銀に有利な試合の流れは、どうやらまだ続いているようである。これがいつ変わるのか(あるいは変わらないのか)が、日銀の「のりしろ」作りの最終的な成果と、金利・為替相場の今後の展開を、大きく左右する。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*上野泰也氏は、みずほ証券のチーフマーケットエコノミスト。会計検査院を経て、1988年富士銀行に入行。為替ディーラーとして勤務した後、為替、資金、債券各セクションにてマーケットエコノミストを歴任。2000年から現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab