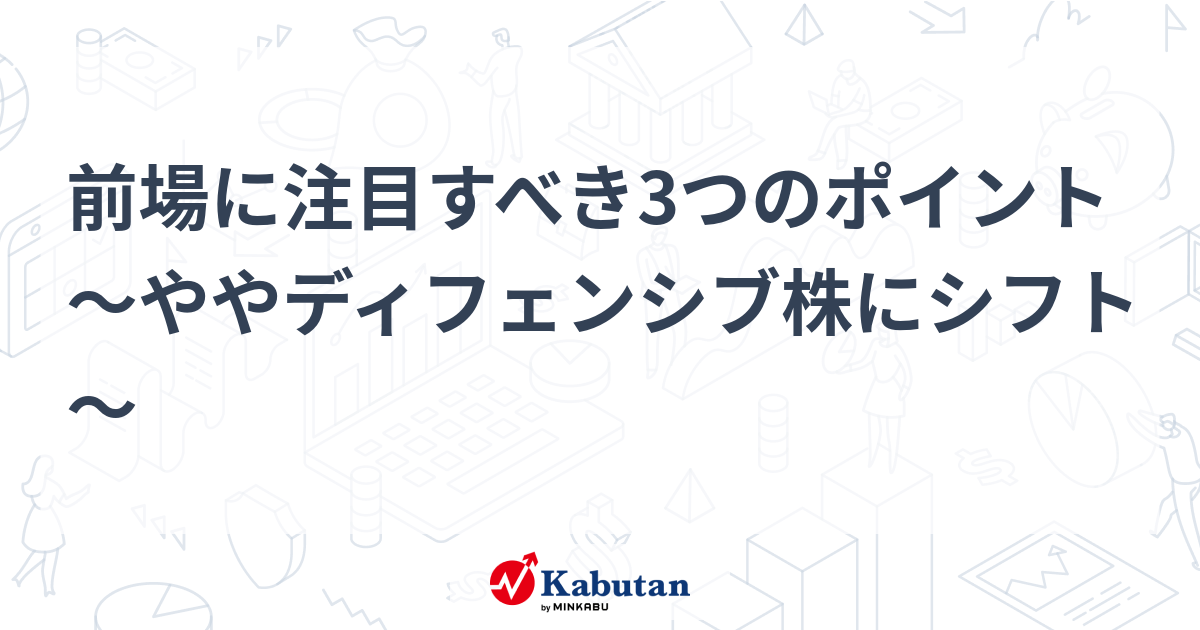MBO「安過ぎ」批判続く、隔靴掻痒の東証新ルール-株主保護に課題

経営陣が参加する買収(MBO)について、東京証券取引所が企業に情報開示の厳格化を求めてから1カ月あまり。一部の案件を巡って今もなお「買収価格が安過ぎる」との批判があり、市場では一般株主の保護にはより踏み込んだ対応が必要だとの声も聞かれる。
東証は7月下旬から、MBOや支配株主などによる買収で市場を退出する企業に対し、手続きや価格の公正性などの説明を義務付けた。企業が過度に割安な価格で非上場化するなどして一般投資家が不利益を被るのを防ぐための措置だ。
議論を呼んだのが、ルール改正後の発表第1号となった自動車部品の太平洋工業によるMBOだ。買い付け価格は公表前日の株価に約40%のプレミアムが付いたものの、株価純資産倍率(PBR)は0.7倍にとどまった。投資会社ナナホシマネジメントの松橋理代表は、会社が「統合報告書でPBR1倍を掲げていた」として価格の妥当性を疑問視する。
8月にMBOを発表したカーケア用品のソフト99コーポレーションも、買い付け価格ベースのPBRは1倍をやや下回る。
東証ルールの限界を指摘する声も聞かれ始めた。カナメ・キャピタルの槙野尚パートナーは「企業の説明責任は増したが、ある程度は作文できてしまう」と指摘。金融規制などに詳しい渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の都築翔弁護士は「会社側は手続きさえ整えれば公正性を主張できる」と、今回の改正だけでは一般株主は安心できないと話す。
太平洋工業の経理担当者はブルームバーグの取材に対し、仮に同社が清算する場合は工場の取り壊し費用などで簿価純資産額の相当程度が毀損(きそん)されることなどから、PBR1倍割れの価格には合理性があると説明した。ソフト99に問い合わせたが、現時点ではコメントを得られていない。
ウエムラ(非上場、鹿児島県薩摩川内市)によるインフラ建設のコーアツ工業への株式公開買い付け(TOB)も波紋を広げている。価格はプレミアムで11%、PBRでは0.4倍台。8月19日には個人株主が価格引き上げを求め、臨時株主総会の招集を請求したことが明らかになった。
コーアツによれば買い手の子会社や関連会社ではなく、東証ルールの対象外という。ただ、買い手が属する植村企業グループはコーアツ株を少なくとも計30%程度持ち、同社の設立にも深く関わる。ナナホシの松橋氏は「植村グループの経営判断に基づく取引であることが示唆されており、実態としては東証規則の趣旨に照らして検討されるべき事案だった」と主張している。
コーアツ管理部の森山聖氏はブルームバーグの取材に対し、財務アドバイザーが算定した株式価値の範囲内であることや今後は厳しい事業環境が見込まれることなどから、価格は妥当だと説明した。
過去最多ペース
企業統治に詳しい牛島総合法律事務所の石田哲也弁護士は、社内の議論を全て開示するよう義務付けると、事業の機密情報が含まれる場合もあり、線引きは難しいと話す。PBRについては企業の解散価値を基にした指標であり、「全ての案件に形式的に当てはめていいのかという問題はある」と言う。
とはいえ、株式の非公開化を選ぶ企業は増えており、一般投資家の保護は喫緊の課題だ。レコフデータによると、今年の日本企業のMBO件数は8月25日時点で20件と、過去最多だった2011年通年(21件)を上回るペースで推移。親子上場の解消を含む他の上場廃止も高水準にある。投資家からの企業価値向上への要請が強まる中、今後も非公開化案件は増える公算が大きい。
アリアンツ・グローバル・インベスターズの日本株最高投資責任者(CIO)、中塚浩二氏は一般論として、利益相反の可能性がある中でTOB価格が決まる状況は「日本株市場の魅力を低減させてしまう可能性がある」と指摘。フェアネスオピニオン(価格の公正性に関する意見書)取得の義務化といったルール策定が有効になるとの考えを示した。
東証の広報担当者はブルームバーグの取材に対し、規則見直し後の状況をフォローアップし、必要な施策については継続的に検討していくとコメントした。