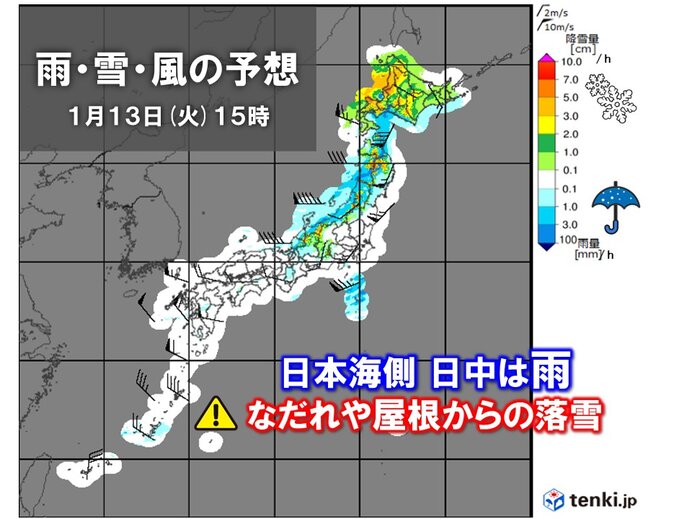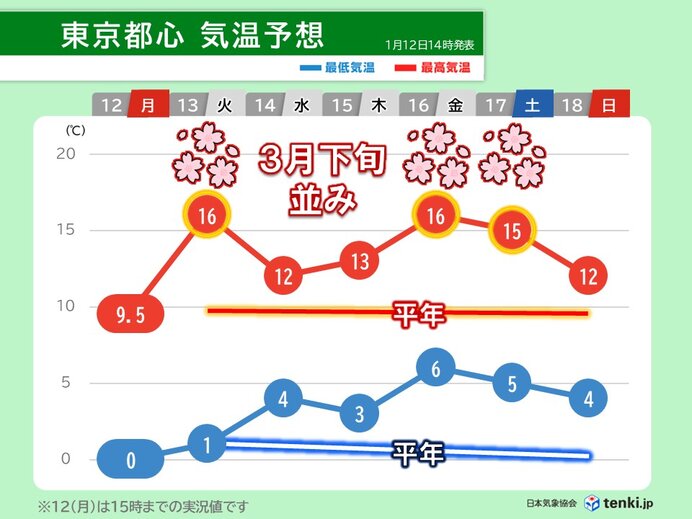日中関係悪化「カラー出したい」高市首相 元外務省田中均氏の処方箋
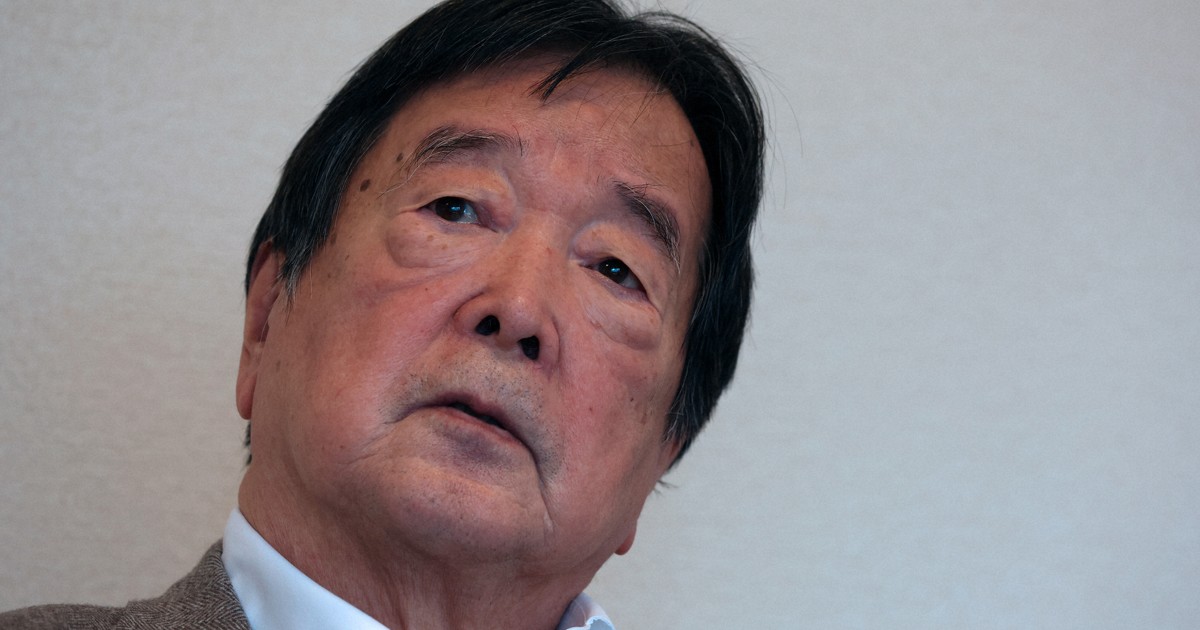
台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁をきっかけにした中国との関係悪化は、経済的威圧もいとわない中国に対する強硬な世論も目立ち、収束の見通しが立たない。
外務省で外務審議官や、18日に北京で中国側と協議した金井正彰氏と同じアジア大洋州局長も務めた田中均・日本総合研究所国際戦略研究所特別顧問は、国会答弁に先立つ日中首脳会談から「完全なすれ違い」があったとみる。
<主な内容> ・悪化する日中関係 ・首相に発言撤回を求める理由 ・米中「休戦」下での戦略とは ・過熱する世論と政治の役割
・安保政策転換の要諦
高市政権の発足後、日中関係は急速に悪化の一途をたどっている。
10月21日に首相に就任した高市氏は、過去に意欲を見せていた靖国神社への参拝を見送り、31日には韓国でのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に出席した習近平国家主席との日中首脳会談にこぎ着けた。
雲行きが怪しくなったのは、翌11月1日に台湾の林信義・元行政院副院長(副首相)と会談し、交流サイト(SNS)で発信した後だ。
中国は外務省報道官談話で「『一つの中国』原則などに著しく違反する」と反発した。
対立の決定打は、首相が今月7日の衆院予算委員会で台湾有事について「(中国が)戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と答弁したことだ。
首相は後日、「特定のケースを想定して明言することは慎む」と反省の意を示したが、「内政干渉だ」と発言の撤回を求める中国に対して応じるそぶりを見せていない。
こう着した状況に中国側は対応を強め、日本への渡航を当面自粛するよう国民に呼びかけ、日本産水産物の輸入を事実上停止。人的交流や経済活動にも影響が及ぶようになった。
答弁撤回で守る政府方針
問題となった「存立危機事態」。実際に台湾有事が発生し、日本の同盟国である米国が介入して中国から攻撃される展開になれば、安倍晋三政権下の2015年9月に成立した安保関連法が定義する「密接な関係にある他国が攻撃され日本の存立が脅かされる」場合に該当する可能性は否定できないが、歴代政権は同事態について「個別の状況に応じて総合判断する」とし、台湾有事と直接関連付けてこなかった。
首相は「政府の従来の見解に沿ったもの」として発言を撤回しない考えを述べているが、田中さんが問題視するのは、存立危機事態の認定について台湾という地域が限定された状況で答弁したことだ。
「存立危機事態の認定は『特定の地域についての議論だとは言えない』というのが政府の基本方針だった。地域を言えば、その地域に含まれた相手国に敵国視されていると思わせ刺激をする。こんなに愚かな…