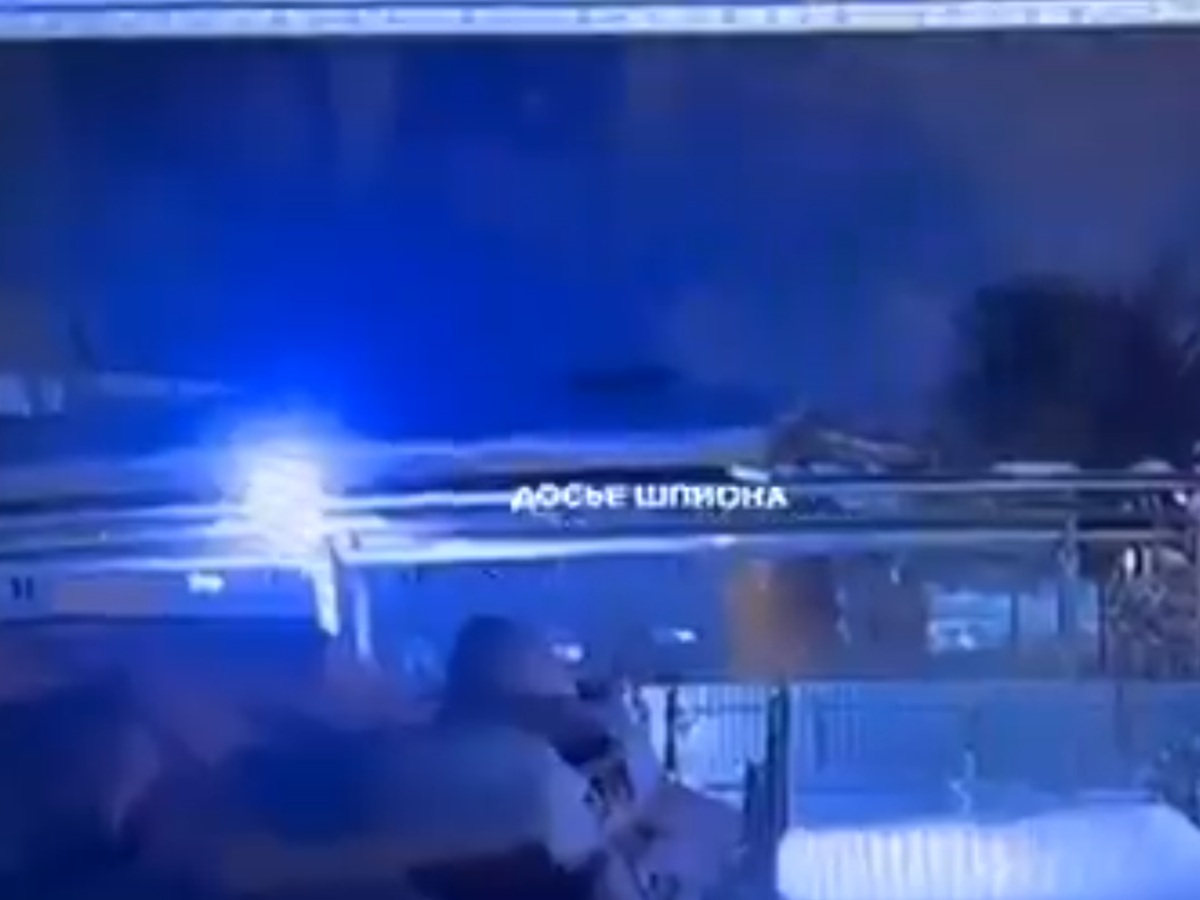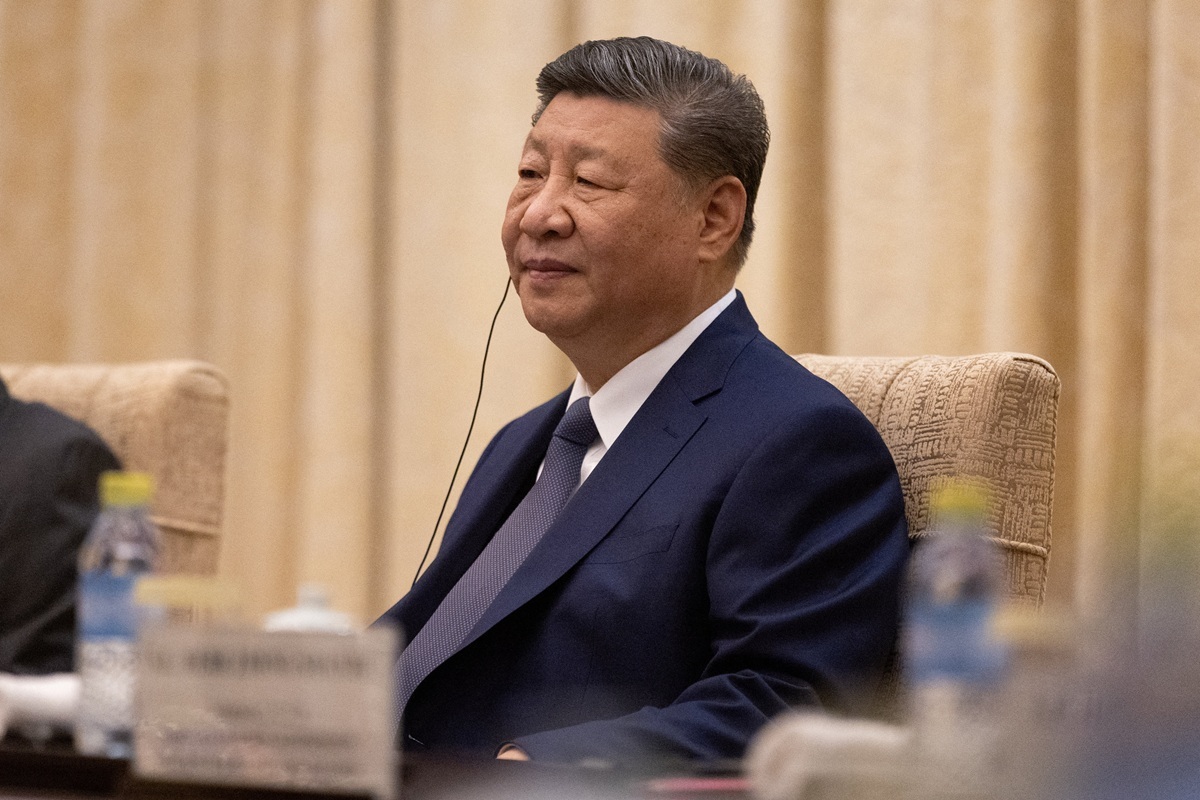1945年7月16日、オッペンハイマーが見た閃光…物理学史の転換点となった「トリニティー実験」の恐怖(山田 克哉)
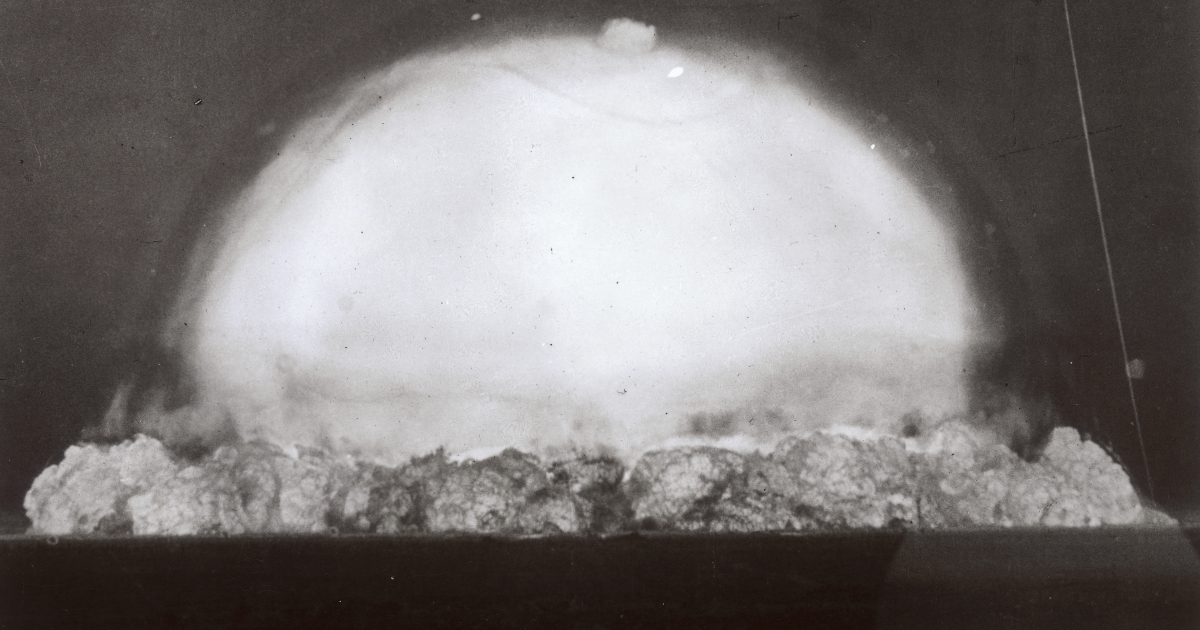
「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか?
核分裂の発見(1938年)から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。
近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わります。
ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介していきます。今回は、人類が初めて目撃した核爆発の威力と、そのわずか数年前だった核分裂現象の発見を見ていきます。
*本記事は、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。
山田 克哉(やまだ・かつや) 【ブルーバックスを代表する人気著者の一人】
米国テネシー大学理学部物理学科大学院博士課程(理論物理学)修了。Ph.D.。元ロサンゼルス・ピアース大学物理学科教授。アメリカ物理学会会員。講談社科学出版賞を受賞。詳しくはこちら。
1945年7月、ニューメキシコ…人類初の核実験
1945年(昭和20年)7月15日夜、アメリカ・ニューメキシコ州ーー。
人里離れた砂漠地帯にある「ホルナダ・デル・ムエルト」とよばれる地点は、異様な雰囲気に包まれていた。そこに集まっていたのは、アメリカ陸軍関係者に加え、ノーベル賞受賞者を含む一線級の科学者たちであった。
これから何が始まろうとしているのかは、当事者以外にはいっさい知らされていなかった。この地点は、ニューメキシコ州の最大都市アルバカーキより約250km南下したところにあり、そこから100km近く離れたところにはアラモゴード空軍基地がある。ホルナダには高さ30mあまりの鉄塔がそびえており、そこでまったく前例のない、史上最大規模の物理学実験がおこなわれようとしていたのである。
現在の米陸軍・ホワイトサンズ・ミサイル実験場の一角にあるトリニティー実験場の記念碑 photo by gettyimages極秘実験であるため、この実験地および実験は、総括的に「トリニティー」という言葉で暗号化されていた。実験装置の組み立て作業のほとんどは科学者自らの手によっておこなわれ、作業の進展に比例するように彼らの緊張度は増していく。
ところが、組み立て作業が進むにつれて気象状況が悪化し、しまいには雨、雷、そして風をともなう嵐になっていったのである。
真夜中が過ぎた7月16日午前2時、相変わらず天候は好転せず、暗い空は重い雲で覆(おお)われているのがわかった。鉄塔の天辺(てっぺん)には、デリケートな実験装置が据えつけられている。しかし、午前3時、実験は夜明けの午前5時30分に決行される決断が下されたのである。
アメリカは、この実験にまつわる開発計画に20億ドルという巨費を投資していた。当時の20億ドルは、現在の500億ドル以上に匹敵するであろう。当時の緊迫した国際情勢や政治的な問題を考えると、実験の延期は難しかった。
ここまで来て失敗は許されない。
投資額の問題もさることながら、失敗したら、せっかくそれまで必死に保ち続けてきた秘密が外部に漏れてしまう可能性が出てくる。緊張と不安が続き、ここ数日間は誰も十分な睡眠をとっていない。実験の決行命令が下され、ついに準備が終了した。
実験用の鉄塔 photo by gettyimages閃光、そして遅れてやってきた轟音
全員がサングラスかゴーグル、あるいは溶接用の眼鏡をかけて、鉄塔から10kmほど離れた場所に用意されたいくつかの観測地点に身を置いた。観測地点の一つに設けられた司令室で、カウント(分読み)が開始された。
20分前、10分前、5分前……、秒読みは途中から自動装置に切り換えられた。カウントは各観測地点に備えられているスピーカーから報じられた。
5秒前、4秒前……、緊張は極点に達した。午前5時30分、誰もが固唾(かたず)を飲んで見守っているなか、スイッチは押された。
その瞬間、暗い状態から一挙に、晴れ上がった真夏の真昼よりもはるかに明るく鋭い閃光(せんこう)が走った。観測地点から4.8km先にある山々がハッキリと見えた。少し間を置いてから凄まじい轟音が続き、観測地点を強風が襲った。
観測地点から10kmも離れている実験地点から、さまざまな色をともなった巨大な球形の雲が盛り上がってくるのが見え、それがやがて、いわゆるキノコ雲を形成していった。
盛り上がるキノコ雲1945年7月16日、夜明けの午前5時30分ーー人類は初めて、原子爆弾を実現させたのである。実験に使用した30mの鉄塔は、一瞬にして蒸発・消滅してしまった。
原子の「核」
実をいえば「原子爆弾」という名称そのものに、ある意味では誤りがある。なぜなら、原子爆弾は「原子が爆発を起こす爆弾」ではないからである。
「原子」には、2025年6月時点で水素、酸素、炭素、窒素、鉄、金、銀、銅、ウラン、プルトニウムなど118種類が確認されており、あらゆる物質はこれらの原子が多数、寄り集まって構成されている。
原子一つの大きさは1億分の1cm程度で、人間の感覚ではとてもとらえられないような小さな粒子である(図「原子の構造」)。たとえば、50gの鉄の中に含まれている鉄という名の原子の数は、1の後にゼロが23個つくほどの数(10²³)であり、我々が日常生活で接する物質はこのように膨大な数の原子からできている。
しかし、鉄に限らず、どんな種類の原子を取ってみても、一つひとつの原子は内部構造を持っている。原子の中心には「原子核」というさらに小さな、しかも重い核があり、その核のまわりを「電子」とよばれる軽い粒子が回っている。
原子の構造そのようすは、太陽系を彷彿(ほうふつ)させるものである。太陽系は太陽が中心にあり(太陽系の核)、太陽のまわりに水星や金星、地球、火星などの惑星が回っている。太陽系では、その核を成す太陽が最も重い。すなわち、太陽が原子核に相当し、惑星が電子に相当する。
原子核は当然、原子よりも小さく、原子核の大きさは10兆分の1cm程度である。そして、原子爆弾が爆発するのは、この核が爆発を起こすのである。
したがって、より正確には原子爆弾は「原子“核”爆弾」と称されるべきであろう。
原子の中心の核の、さらなる内部構造
そして、原子の中心を成すこの核自体も、さらなる内部構造を持っている。すなわち、核は「何か」からできているということである。
その何かとはなにか。核は、2種類の粒子から構成されており、それらは「陽子(プロトン)」と「中性子(ニュートロン)」と称されるきわめて小さな粒子で、二つともほぼ同じ重さである。
核はいくつかの陽子といくつかの中性子が寄り集まって構成されているが(図「原子の構造」参照)、原子の種類によって、その核内の陽子の数や中性子の数が異なる。核自身がすでに10兆分の1cmときわめて小さいのであるから、その構成粒子である陽子や中性子はもっと小さいことになる!
核の中には、いくつかの陽子といくつかの中性子が所狭しとほとんど隙間なくギュウギュウに詰められている。原子内の核は重く、そのまわりを回っている電子はきわめて軽い。したがって、原子1個の重さのほとんどは、その核の重さに等しい。
この核の爆発が原子爆弾となる。核一つひとつの爆発は「核分裂」とよばれている。一つの核が二つに割れる現象である。