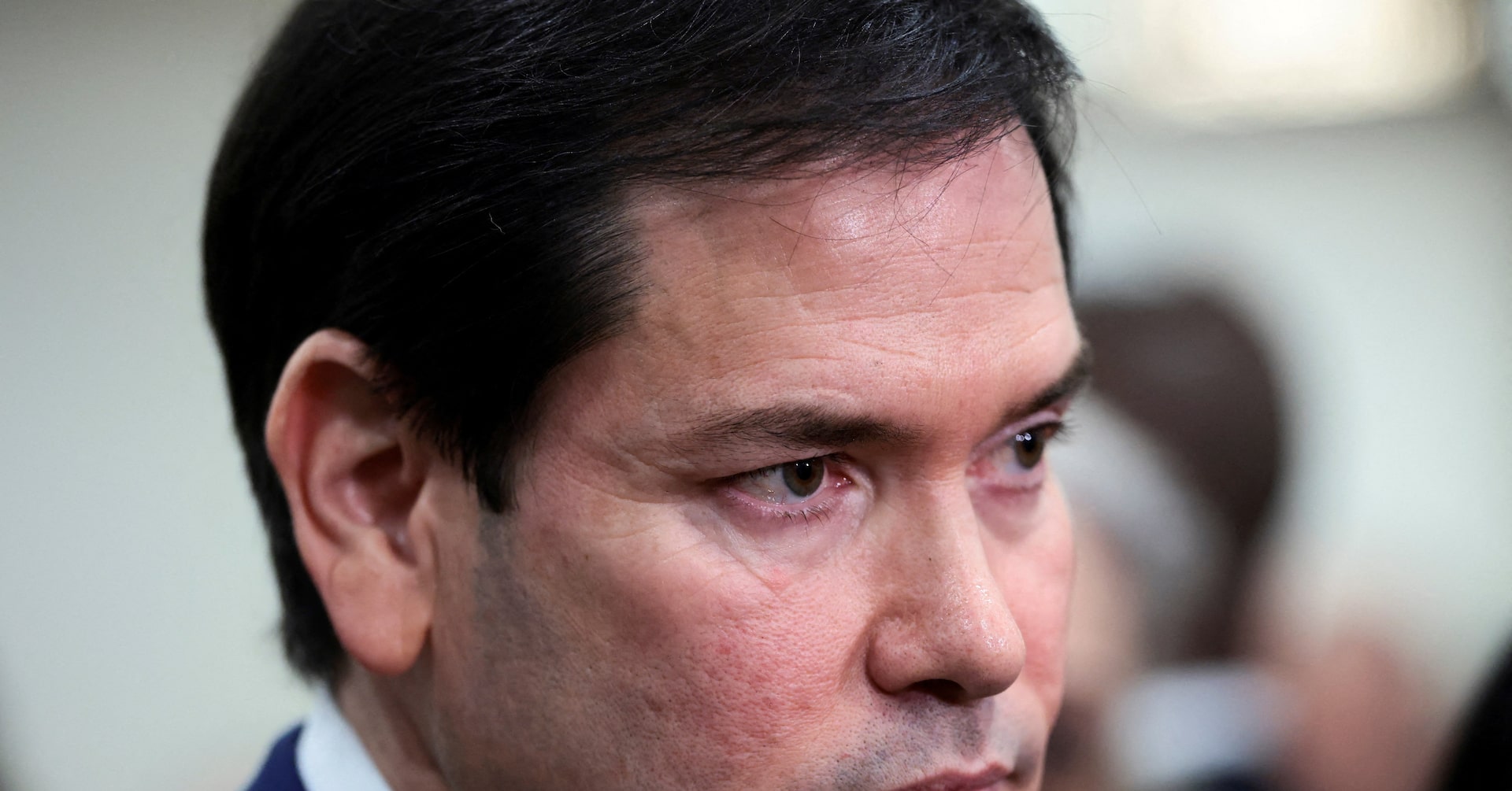暖炉の横にライフル銃…「悪人が来たら、これでズドンだ」 NYなど東海岸と違う米中西部 国際舞台駆けた外交官 岡村善文氏(50)

公に目にする記者会見の裏で、ときに一歩も譲れぬ駆け引きが繰り広げられる外交の世界。その舞台裏が語られる機会は少ない。戦後最年少(50歳)で大使に就任し、欧州・アフリカ大陸に知己が多い岡村善文・元経済協力開発機構(OECD)代表部大使に、40年以上に及ぶ外交官生活を振り返ってもらった。
アル・カポネ、にあらず…
《2011年秋、米シカゴ総領事に就任した》
シカゴと聞くと、アル・カポネのマフィア暗黒街を思い浮かべる人もいると思います。しかし、とんでもない。ミシガン湖と運河沿いに摩天楼が並び、夏には緑で覆われる美しい都市。私の担当は、シカゴが位置するイリノイ州だけでなく、「中西部」と呼ばれる北部ノースダコタ州やミネソタ州から、中部ミズーリ州、カンザス州に至る計10州の広大な地域でした。
ミシガン湖畔にあるシカゴの街(岡村善文氏撮影)《シカゴから各州を回りながら、驚いたことが2つあった》
1つ目は、私が思っていた米国と違う米国が広がっていたということです。大陸は広大で、千キロも内部に行くと全然違う。
そして、そこに住む人々は、およそ私が考える米国人、つまり、首都ワシントンや大都市ニューヨークで相手にする人々とは、かなり異なっていた。
各州の町を訪れると、何をどう食べるとそうなるのか、とんでもなく太った人が多かった。町の郊外には、延々と貧しそうな地域が広がる。コンテナが散らかり、それが家なのだという。居住していたのは、アフリカ系ではなく白人。町のバーやレストランに行って、聞こえてくるのは英語ではない。スペイン語のようでした。
「警察を待つ余裕ない」
田舎の宿に宿泊し、宿の主人のサロンに行くと、暖炉の横にライフル銃が立てかけてあった。恐る恐る聞くと、「悪人が来たら、これでズドンだ」と平然と言うのです。「警察を待っている余裕はない。自分で仕留めないと」とも言いました。私が想像していた米国人とは、かけ離れた人々ばかりでした。
《シカゴでは、主要紙シカゴ・トリビューンが世界情勢はおろか、ワシントンの動きもほとんど報じていなかった》
当時、アフガニスタンから米軍が撤退するのかどうかが、世界的な懸案だったのに、そんな記事は全然ない。イリノイ州の予算、政治スキャンダルの話ばかり…。連邦政治、ましてや世界政治に、中西部の人々は全然関心がない。
オバマ氏を誇らない人々
オバマ元米大統領(左)(ゲッティ=共同)オバマ大統領はイリノイ州選出上院議員で、ちょうど12年の大統領再選を控えた時期でした。シカゴ市長は、最近まで駐日米大使を務めたエマニュエル氏。オバマ氏の首席補佐官から市長に転じていました。
岸田文雄前首相(右)と面会するエマニュエル氏日本の外務省から「政治情勢を探るように」と指示され、注意深く人々の言動を観察していたが、シカゴで交流する人々はオバマ氏を誇るどころか、ほとんど愛着も見せない。
「彼は『シカゴ南部の人』だから」と言うのです。シカゴ南部はアフリカ系の人々の住む地域で、年間500件超の殺人事件がある。「そんな地区のことは考えたくもない」という雰囲気なのです。
「これでズドン」のメンタリティー
《米国の大統領選で、中西部は共和党支持者が圧倒的に多い地域だ》
大統領選の帰趨は、共和党支持と民主党支持が拮抗する「スイングステート」(揺れる州)の動向によります。このため、報道もそうした地域からのものばかりです。
共和党支持が当然で、取材されない中西部にこそ、トランプ支持層が存在する。彼らは東海岸や西海岸のエリート層からは遠くかけ離れており、どんな物の考え方をするのかは、ほとんど報道されることはない。トランプ大統領の言動は、「これでズドンだ」と言う人々のメンタリティーには、ピッタリくるのでしょう。
米東部の人々、驚く
《ニューヨークでこうした話をすると、周りの米国人は驚いた》
サンフランシスコの街から海を望む(黒沢潤撮影)東海岸の知識人は、中西部のことをあまり知らない。私たちにとって米国といえば、ワシントンやニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスなど、東西の大都市から知る米国です。本当の米国の姿はどうも、その米国とは違う。
ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストの記者も、それを知らないのじゃないか…。日本のメディアは、そうした主要紙の記事だけ読んでいるためなのか、トランプ大統領が再選されて驚いている。しかし、米国の〝ど真ん中〟を見て回ると、彼の人気はそれほど不思議なことではないのです。
出会いに、知的興奮
《もう1つ驚いたのは、美術館の素晴らしさだった》
有名なシカゴ美術館以外にも、中西部インディアナ州のインディアナポリス▽ミネソタ州のミネアポリス▽ネブラスカ州のオマハ▽ミズーリ州のセントルイス-に立派な美術館があり、豊富なコレクションを誇っています。
米中西部ミズーリ州セントルイスのオブジェ(黒沢潤撮影)傑出している1つが印象派。美術の教科書などで馴染みがあるのは、パリのオルセー美術館など欧州の印象派の絵です。ところが、米国の美術館には、モネやゴッホやゴーギャンら巨匠たちが描いた、見たことのない作品がずらりと並ぶ。その出会いには知的興奮を覚えるほどです。
明治日本から海渡る
もう1つは日本美術。仏像、工芸品、狩野派の屏風、浮世絵の数々など、相当な数に上ります。日本ではなかなか目にできない立派な縄文火焔土器も展示されていた。
識者に聞き、得心しました。19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、米国、とりわけ中西部に鉄道や製鉄、製造業で大富豪が相次ぎ誕生し、お金に物を言わせて、美術品を争って収集したということです。
当時、収集家の間で人気が高かったのが、印象派絵画と日本美術でした。明治時代の日本から、名品が海を越えて来たようです。それらが後に、大富豪の地元、中西部の美術館に寄付された。中西部をわざわざ訪れてでも、一見の価値ありです。(聞き手 黒沢潤)
<おかむら・よしふみ> 1958年、大阪市生まれ。東大法学部卒。81年、外務省入省。軍備管理軍縮課長、ウィーン国際機関日本政府代表部公使などを経て、2008年にコートジボワール大使。12年に外務省アフリカ部長、14年に国連日本政府代表部次席大使、17年にTICAD(アフリカ開発会議)担当大使。19年に経済協力開発機構(OECD)代表部大使。24年から立命館アジア太平洋大学副学長を務める。