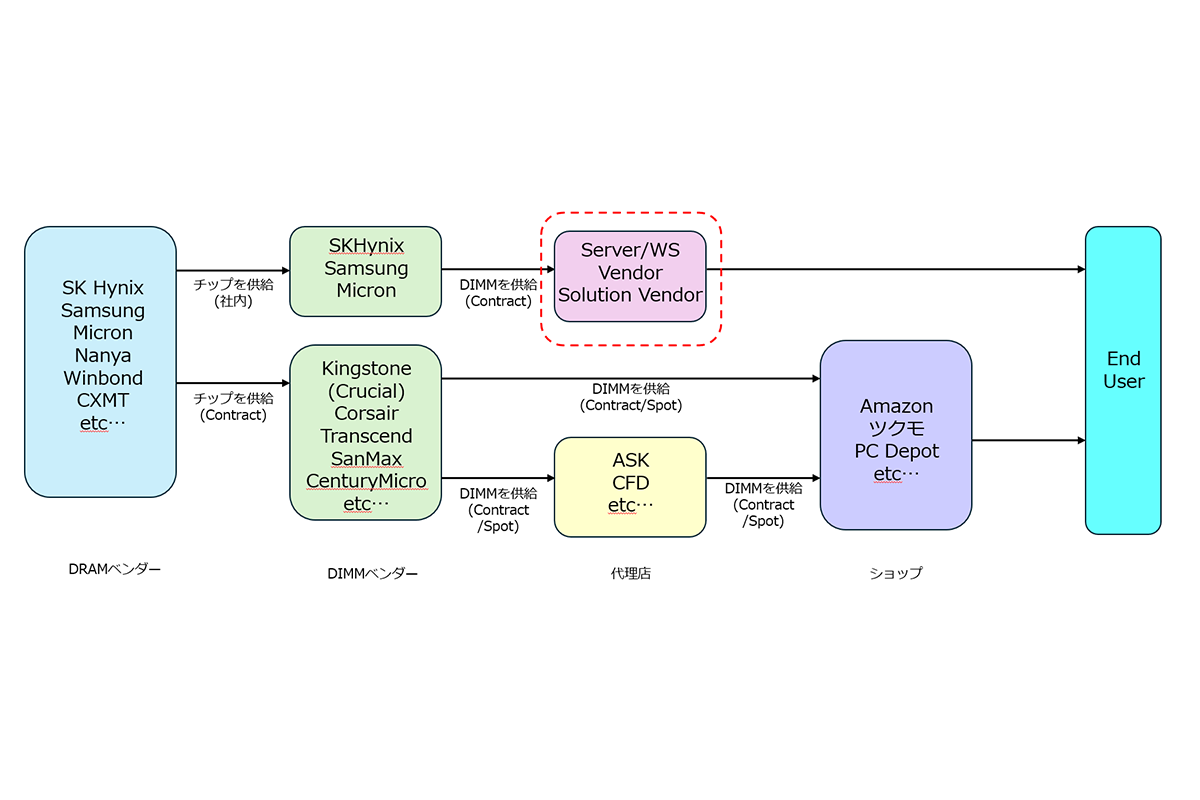コラム:ポスト「正常化」における日銀の金融政策=井上哲也氏

[東京 17日] - 日銀にとっての金融政策の「正常化」は、2%のインフレ目標を持続的かつ安定的に実現する下で、政策金利が中立水準にある状態を指す。また日銀は、目標達成のいかんを基調的インフレ率に即して判断する考えも示している。現時点で、日銀が基調的インフレ率の代理指標として示している値は上昇しているが、2%目標の持続的かつ安定的な実現を達成していないので、「正常化」はまだ先の話となる。
もっとも、基調的インフレ率と密接な関係をもつインフレ期待も、家計や企業に対するサーベイ調査の結果などを見る限り、同時に明確に上昇している。日銀の「多角的レビュー」が確認したように、かつてはインフレ期待が長期にわたってゼロ近傍に固着していたことを考えると、家計や企業が少なくとも一定の条件が揃えば物価は上昇し得ると考えるようになったこと、つまりインフレ期待が上方に柔軟化したことは、それ自体大きな意味を持つ。
なぜなら、次の景気後退の際にもインフレ期待の急速な低下を回避することによって、利下げによって実質政策金利をマイナス圏内に引き下げる可能性が生まれるからである。その意味で、こうしたインフレ期待の正常化は金融政策の「正常化」にとって重要な前提条件の一つが満たされたと考えることができる。
<ポスト「正常化」の政策環境>
日本の物価や景気が今後も日銀の見通し通りに推移し、今回の景気局面の中で日銀が「正常化」を実施し得るかどうかには、相応の不確実性がある。
トランプ政権が引き起こした通商摩擦は、相手国による報復関税も含めて世界経済を減速させる恐れがあり、結果として国内の景気にも下押し圧力を及ぼし得る。また、前回の本稿で指摘したように、トランプ政権の矛先が日本円の「過小評価」に向かった場合には、円高調整を通じた物価への下押し圧力となる。
それでも、実際に「正常化」が達成された後の金融政策の運営を今から考えておくことには重要な意味がある。
その際、考慮すべき点を2つ指摘しておきたい。第一に、政策金利が「正常化」しても、巨額の国債保有が残存しているという意味では「正常化」が完結しない点である。この点は、国債市場の機能回復に影響を持つだけでなく、いわゆる「ストック効果」による長期金利の押し下げを通じて財政政策にも影響を持ち得る。
第二に、より重要なことは、基調的インフレ率の意味でのインフレ目標の達成の維持が容易でない可能性である。これまで、基調的インフレ率を押し上げてきたのは、1)輸入インフレが数年にわたって継続したことと2)賃金も数年にわたって高い伸びを維持したことの双方の要因であり、これらによって適合的な期待形成の下でもインフレ期待が上昇してきた。これらは、日銀が使用した用語に即して「第一の力」と「第二の力」と呼んでも良い。
「第一の力」は、商品市況の上昇と円安の双方によってもたらされたが、これらの要因が「正常化」後にどう推移するかは見通し難い。商品市況には、世界経済の停滞とサプライチェーンの毀損(きそん)という硬軟双方の要因があるほか、円相場には上記の要因のほかに米国での急速な金融緩和の可能性も加わる。
さらに、円相場の市場要因による変動が国内物価に影響を与え続ける可能性も高い。その理由は日本円が「巨大なローカルカレンシー」だからである。
日本円は、世界の経済や安全保障でのプレゼンスの高さという点を除くと、世界屈指の取引量、巨大で流動性の高い金融資本市場、法の支配、政策や規制の予見可能性の高さといった国際通貨に求められる特性のほとんどを具備している。それだけに、グローバルな投資家にとっては安心して投機的なポジションを作ることができ、結果として円相場に大きな影響が生じ得る。
一方で、「第二の力」は国内での人手不足という構造要因も背景であるだけに、相対的に見通しやすいと考えることもできる。しかし、マクロの賃金が今年を含む数年のような高い伸びを維持することは、生産性の動きからみて考えにくい。実際、ここ数年の賃金上昇は円安によって企業収益が増加する下で労働分配率の中期的な修正が生じたとみることもできる。一方で、人手不足が深刻な業種では、生産性の改善で賃金コストの上昇を吸収することには限界がある。実際、こうした業種では、人手不足に対して業容の縮小や事業からの退出といった対応がみられる。
<暗黙の政策目標>
上記の要因を踏まえると、日銀が「正常化」の後に直面するのは、「第二の力」だけではインフレ目標の達成を維持することが難しい一方、円相場の変動に伴う輸入物価の変動によって国内インフレ率が左右されることへの対処を迫られる状況となることが考えられる。
これは現状とあまり変わらないとも言えるが、円相場は相当の期間にわたって一定の方向に動く場合も少なくないだけに、持続的な輸入インフレないしディスインフレの継続によって、適合的な期待形成の下でもインフレ期待に双方向の影響を与える可能性は排除できない。
日銀がこの問題に対処する上でのシンプルな選択肢は、円相場の動向を政策運営の上で参照することだ。上記のように輸入インフレへの影響が焦点である以上、円相場の具体的な指標は、日本が輸入する財やサービスの構成によってウエイト付けした円相場の加重平均となる。しかもそのウエイトは、例えばアジアから米ドル建てで食料を輸入している実態を考慮すれば、相手国別ではなく決済通貨別とした方が望ましい。
こうした枠組みは、国際金融論における「カレンシーボード」に似ているが、日本の国内経済が相応の規模を有し、上記の「第二の力」を含めて自律的な要素による影響も大きいので、「カレンシーボード」のような厳密な運営である必要はなく、あくまでも円相場の加重平均も参照するというスタイルで十分だ。実際、日銀はこれまでも実質的に円相場の変動に対応して政策を変更したケースもあるだけに、円相場の参照は極端な政策変更とは言えない。
日銀が円相場の加重平均を参照するようになっても、2%のインフレ目標を維持することは引続き重要である。この点は、単に家計や企業のインフレ期待を安定させるだけでなく、新興国の金融政策において指摘されるように、円相場に対しても一種のアンカーとしての機能を持ち得るからである。
同時に政府の為替介入と日銀の金融政策の方向が整合的であることも重要だ。こうした連携が実体経済に与える影響は理論的には不確定であるとしても、少なくとも金融市場に対するアナウンスメント効果を持ちうる。
一方で、円相場への参照がインフレ目標の運営を複雑化し、企業や家計にとってわかりにくくするという副作用は確かに存在する。ただし、日本に限らず米欧も含めた中央銀行は、インフレ目標の達成には経済環境や達成期間の点でもともと柔軟に対応してきた。日銀の場合には、その柔軟性の重要な要素が円相場だと位置づけることができる。
最後にコミュニケーションの点では、日銀がこの暗黙の政策目標を金融市場とどう共有するかという課題がある。金融市場もかねてからそう理解していたというのであれば特段の対応は不要だが、例えば、米国での「テイラールール」のように、日銀の幹部が講演で言及したり、「展望レポート」に図表を示すといった地ならしを経て、金融市場の観察者が日銀による政策運営の実績を踏まえて「発見する」形に導くことも選択肢となり得る。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*井上哲也氏は、野村総合研究所の金融デジタルビジネスリサーチ部シニアチーフリサーチャー。1985年東京大学経済学部卒業後、日本銀行に入行。米イエール大学大学院留学(経済学修士)、福井俊彦副総裁(当時)秘書、植田和男審議委員(当時)スタッフなどを経て、2004年に金融市場局外国為替平衡操作担当総括、2006年に金融市場局参事役(国際金融為替市場)に就任。2008年に日銀を退職し、野村総合研究所に入社。金融イノベーション研究部・主席研究員を務め、2021年8月から現職。主な著書に「異次元緩和―黒田日銀の戦略を読み解く」(日本経済新聞出版社、2013年)など。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab