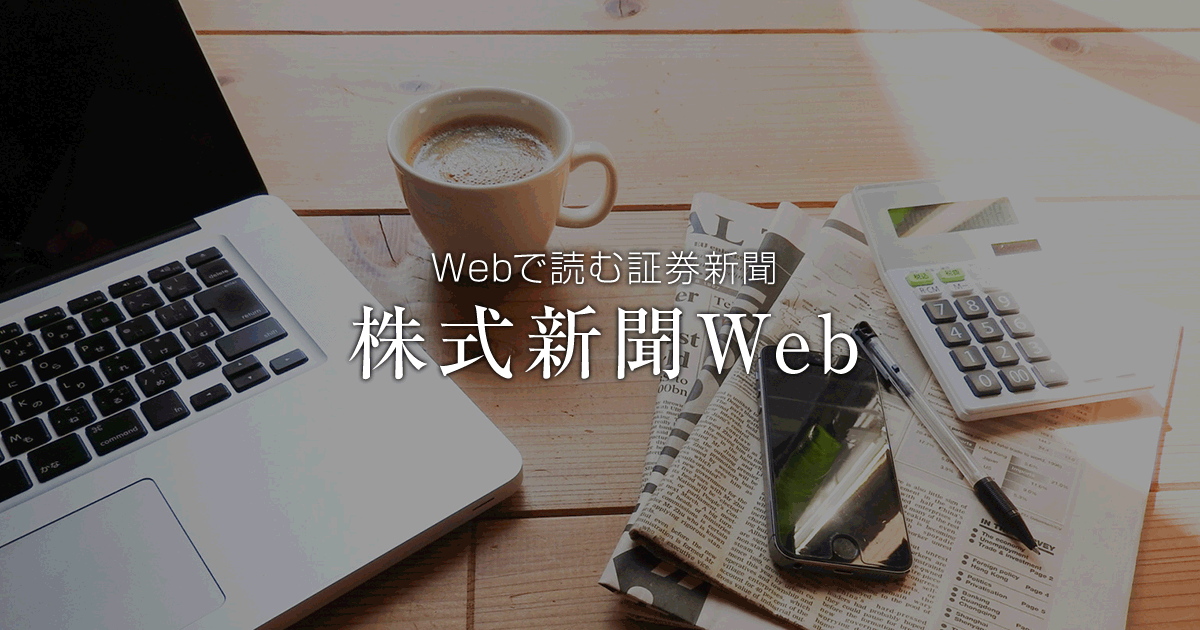コラム:始まった日米関税協議の行方とドル/円相場=尾河眞樹氏

[東京 17日] - 「もともとこうした戦略だった。大統領は交渉で有利に立てるようにしているのだ」、「この瞬間まで方針を貫くには、彼にとって大きな勇気が必要だった」――。4月9日、ベッセント米財務長官はホワイトハウスで記者団に対しこのように述べ、米政府が発動後たった13時間で「相互関税」の一部停止を発表したことについて、あたかも事前に決めていたことであるように語った。
しかし、金融市場の猛烈な攻撃を受けて最も冷や汗をかいたのはベッセント氏自身だったのではないか。少なくとも前週4日までは、米株価は急落していた一方で、米国債価格はむしろ上昇していた。長期金利の変動要因は、「期待政策金利」と、投資家が保有期間のリスクに対して求める上乗せ利回りの「タームプレミアム」で構成されるが、「相互関税」発表直後は、米景気悪化による利下げ観測の高まりから、「期待政策金利」が低下し、米長期金利も低下していた。しかし、週明けからは米国でインフレと景気減速が同時進行する「スタグフレーション」への懸念が高まるなか、一転して「タームプレミアム」が上昇。米国債が投げ売り状態となって米長期金利は急騰し、米株安、ドル安の「トリプル安」に陥った。激しい米国売りとドル離れが進み、ドルの信認が揺らぐ可能性すらあったと言えよう。市場の米国売りに追い込まれる形で、トランプ政権が方針転換したのは明らかだ。
トランプ大統領自身も9日、「債券市場はやっかいだ」などと述べており、米国債の投げ売りに促される形だったことを示唆した。報道によれば、相互関税一部停止に至るまでのいきさつは諸説あるようだが、ウォールストリート出身で投資家のベッセント財務長官がトランプ氏に強く進言した可能性は充分あり得る。
問題は、ドルの一度崩れかけた信認が完全に元に戻るかどうかだ。筆者は、信認の回復はあくまで今後の米国の関税政策次第であり、各国と相対で交渉するとなれば、金融市場全体が安定するまでは、まだ時間がかかるとみている。相互関税については、幸か不幸か日本が最初の交渉相手となった。
相互関税を決定する前に、米通商代表部(USTR)は各国の非関税障壁の「公募意見」を募ったが、その際在日米国商工会議所(ACCJ)は意見書で、日本の「根強い貿易障壁」を列挙した。中には、自動車に対する厳しい安全基準や、コメ、小麦などの輸入制限などが挙げられており、これらの緩和や米国への投資増加などが求められる可能性はありそうだ。
米国時間の16日、赤沢亮正経済再生相は第1回の日米交渉に臨んだが、突然トランプ大統領も会談に参加するという異例の事態となった。トランプ氏にとってこの交渉がいかに重要で、肝いりであるかがよくわかる。なるべく早く実績を出して、国民や世界にアピールしたいのだろう。交渉材料の1つとして注目を集めていた為替問題については、赤沢氏の直後の会見がヒントになる。記者団からの、安全保障問題や、為替問題は交渉に出たのかとの質問に対し、大臣は「為替は出ませんでした」と2回答えた。日本の交渉団には三村淳財務官も同行しており、為替が交渉のテーブルに載ることは、ある程度身構えていたと思われるが、先方からは「なかった」という。
仮に、日米間で「ドル高・円安の是正」で合意し、市場が過剰に反応してドル全面安などになれば、米国の輸入インフレが上昇するリスクがあるため、米国にとってもセンシティブな問題だ。一方日本は、米国政府からすでに基礎税率10%に加え、鉄鋼・アルミ製品と自動車で25%の関税がかけられているため、仮に10%を超えるような大幅な円高進行となれば、それ自体がさらなる追加関税と同様の効果となり、経済へのダメージは大きくなる。米国が為替問題を持ち出さないのであれば、日本からわざわざ提案するはずはなく、「ドル高・円安是正」が交渉の俎上(そじょう)に上がる可能性はやや低下したと言えよう。
ただし交渉はまだ始まったばかりだ。赤沢氏の会見によれば、まず日本からは関税に対して遺憾の意を表明し、見直しを強く申し入れたことに加え、今回決定したのは、1)双方が率直に、かつ、建設的な姿勢で協議に臨み、可能な限り早期に合意し、首脳間で発表できるよう目指す。2)次回の会合を今月中に実施する。3)閣僚レベルに加え、事務レベルでの協議も継続することの3点だけである。今後の交渉の行方次第で、為替問題が再浮上する可能性はゼロとはいえないだろう。仮に、日米協調でドル/円を押し下げる場合、日米当局が合同で円買いドル売りの「協調介入」を行うか、日銀の利上げにより円高を促す、の2つの方法が考えられる。ただ、前者の場合は、相場がオーバーシュートして、想定以上のドル安・円高が進むリスクが大きく、上述の通り日米双方にとってマイナス面が大きい。その意味では、どちらかと言えば後者の可能性のほうが高いかもしれない。
ソニーフィナンシャルグループは、関税の日本経済への影響が不透明なうえ、市場も依然不安定であることから、日銀の利上げは今年10月と予想している。しかし、もしも今後為替問題が交渉の俎上に上がるようであれば、予想より早い利上げの可能性もないとは言えない。日銀は「円安是正の目的」との理屈付けはできないものの、足下賃上げが進むなかで利上げの説明はつきやすいうえ、多少の円高であれば、家計にとっては輸入物価の低下に繋がりプラスと言える。同時にトランプ政権は「日本から利上げによる円高・ドル安を勝ち取った」と国民にアピールできるだろう。
米国の関税交渉はまだ始まったばかりであるうえ、米中間の終わりの見えない報復関税の応酬は、世界経済の減速への懸念に繋がり、金融市場は当面、不安定な状態が続きそうだ。その意味では、赤沢氏の「為替は出なかった」との発言を好感し、ドル/円はいったん大きく上昇したが、不透明感が払しょくされたわけではなく、上値は限られよう。落ち着きどころを見いだせば、しばらく様子見のレンジ相場が続くとみている。
一方、トランプ政権の関税を巡る混乱によって、米調査会社リアル・クリア・ポリティクスによるトランプ大統領の支持率を見ると、1月20日の就任時の52.3%から、4月16日時点では46.9%に沈んだ。同支持率は、全米各社の世論調査による支持率の平均値であることから、あまり極端な動きを見せない特徴があるが、このところの低下は注目に値する。
トランプ政権は既に相互関税の90日間の停止に加え、スマホやPCなど電子機器の除外措置を発表するなど、今後まだ方針が変わる可能性はありつつも、早くも関税政策を緩和しつつある。米国の信認回復と支持率の回復に努めているようにも見える。当面金融市場はボラティリティーの高い環境が続くものの、少なくとも年後半は来年の米中間選挙も見据えて、関税の緩和や、2026年からのトランプ減税の恒久化、規制緩和に関する法整備など、マーケットフレンドリーな材料が続くと思われる。このため、市場のセンチメントは徐々に改善すると予想している。ソニーフィナンシャルグループは、米連邦準備理事会(FRB)による年内2回の利下げを予想しているが、そうなれば来年以降の景気回復期待なども相まって、米長期金利も底堅く推移し、ドル/円も緩やかに反転上昇すると予想する。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*尾河眞樹氏は、ソニーフィナンシャルグループの執行役員チーフアナリスト。米系金融機関の為替ディーラーを経て、ソニーの財務部にて為替ヘッジと市場調査に従事。その後シティバンク銀行(現SMBC信託銀行)で個人金融部門の投資調査企画部長として、金融市場の調査・分析を担当。著書に「〈最新版〉本当にわかる為替相場」、「ビジネスパーソンなら知っておきたい仮想通貨の本当のところ」などがある。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。