科学者が「不安」の正体を可視化...脳では一体何が起こっている? 治療への応用は?【最新研究】
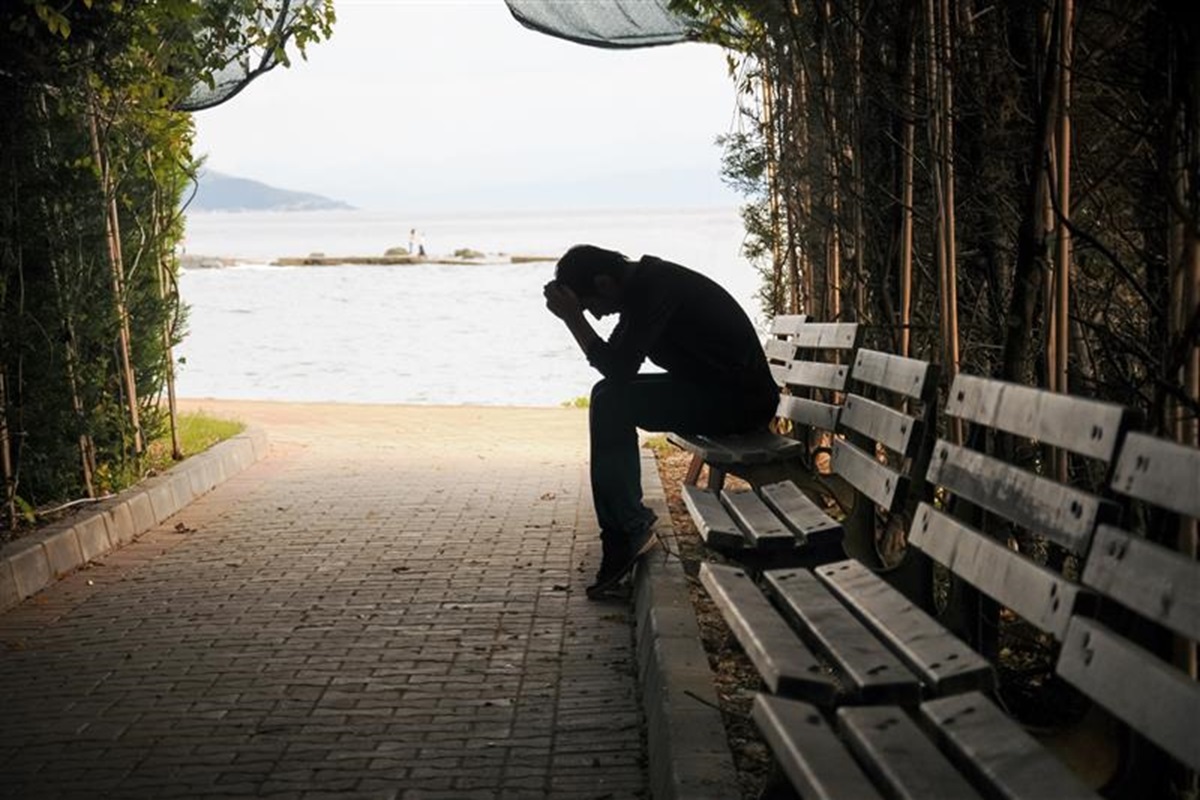
これまで、不安とは、世界中で何百万人もの人々が日々経験しているが、「目に見える」ものではなかった。 【動画】正常な不安は?不安障害とは? しかし、英ポーツマス大学の科学者たちは、不安を可視化する脳スキャン技術を開発した。この技術は、不安の理解、診断、治療を改善することを目的としている。 従来の不安研究では「接近―回避型葛藤」、すなわち良い選択肢とあまり良くない選択肢を比較するような状況に焦点が当てられてきた。 しかし、今回の研究では、人が「勝ち目のない状況」、つまりどちらを選んでも悪い結果になるような二択に直面した際の葛藤、「回避―回避型葛藤」が、脳内でどのように不安を生じさせ、どのような経過をたどるのかをマッピングした。この不安は、より現実的な不安の状況を反映すると考えられている。 論文著者で神経心理学者のベンジャミン・ストッカーは、「不安は脳内でさまざまな形で現れる。我々の研究は、どの選択肢もネガティブに感じられるような『勝ち目のない葛藤』に関わる状況に着目した。この種の葛藤に対して脳がどう反応するのか、リアルタイムで調べた最初の研究だ」と本誌に語った。 「これまで誰も見たことがなかったような、不安に関わる複雑な意思決定が脳内でどのように展開されるのか、初めて視覚的に捉えることができた」
この研究には18~24歳の若者40人が参加。ジョイスティックを使って画面上の物体を避けるという、テレビゲーム形式の課題に取り組んだ。課題には、比較的簡単に回避できる葛藤が少ないシーンと、どちらを選んでも悪い結果になるような強い葛藤を惹起する難しいシーンが組み込まれていた。 研究者たちは、脳波計を用いて参加者の脳活動を測定した。「回避―回避型葛藤」の状況に脳波計を統合したのは、本研究が初だ。 ストッカーは「脳波計は、痛みがなく非侵襲的でありながら、脳の電気的活動を非常に効果的に記録できる手法である」と説明する。 「勝ち目のない」状況下では、被験者の脳に特有の活動パターンが見られた。脳の右前頭葉領域において「シータ波」と呼ばれる脳波の活動が高まることが確認されたのだ。また、状況のストレス度や対処の難易度に応じて、他の脳領域も活性化したという。 研究チームは、こうした脳波のパターンが、不安に関連する葛藤の証となる可能性があると考えている。 ストッカーは「不安の処理中にどの脳領域が働いているかだけでなく、それらの領域同士がどのように連携しているのかを明らかにすることができた。勝ち目のない状況の処理は、単一の脳領域だけで完結するものではなく、複数の領域が協調して取り組んでいるのだ」と述べた。



