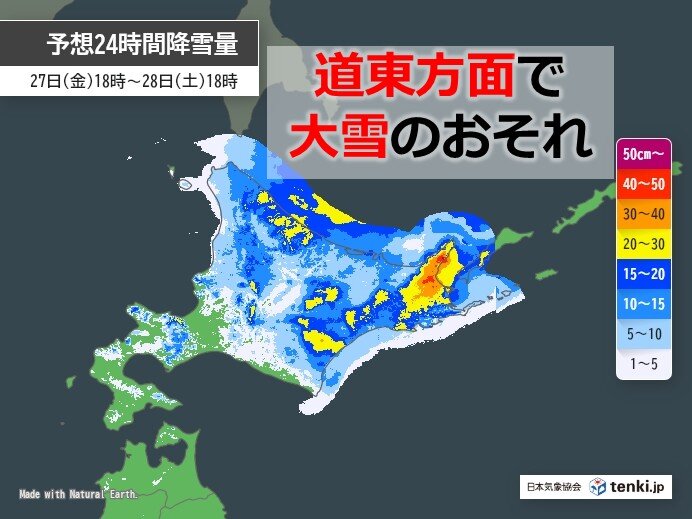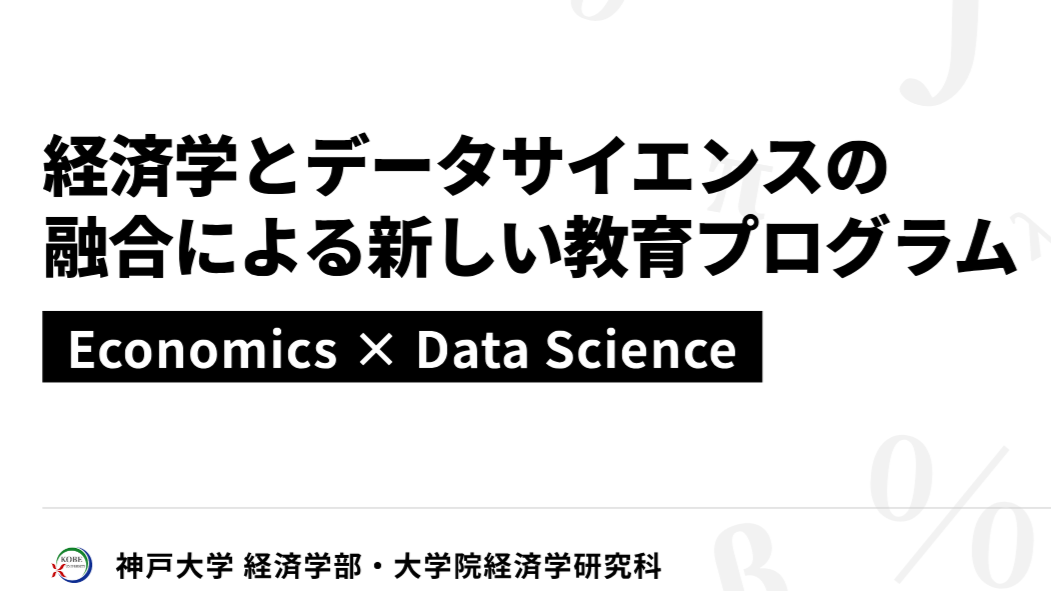「もずく」は痛風、高尿酸血症の改善に? 実は歯&骨にも効果的 専門家が解説

4月20日は「もずくの日」です。そこで、もずくの栄養について、海藻科学研究所の吉積一真さんに聞きました。
4月20日は「もずくの日」です。沖縄県もずく養殖業振興協議会が毎年4月第3日曜日に制定し、沖縄産のもずくの最盛期である4~6月を強調するため設けられたということです。そんな、もずくの栄養について、海藻科学研究所の吉積一真さんに聞きました。
Q. もずくは、どのような海藻なのでしょうか。
吉積さん「ナガマツモ目ナガマツモ科に属する海藻(褐藻)です。沖縄地方では、三杯酢で食すことから『酢海苔(スヌイ)』とも呼ばれています。 温かい地方の浅い海に分布していて、他の海藻に付着して生息することから、『藻付く』という名がついたといわれています。
日本で消費されている95%以上が沖縄県で養殖されたもので、独特のヌメリとつるんとした食感が特徴です。
私たちが“もずく”と称して食べているものは『オキナワモズク』で、『太もずく』とも呼ばれています」
Q. もずくにはどんな栄養が含まれていて、どのような効果が期待できるのでしょうか。
吉積さん「水溶性食物繊維を多く含み、糖質含量が低く、低エネルギーです。骨や歯の形成に大切なミネラルであるカルシウムとマグネシウムも含まれています。
水溶性食物繊維の一つであるフコイダンを多く含んでいることから、便通、食塩の吸収の抑制(排塩)、胃もたれ、胸やけ、免疫機能を向上させる効果などが期待されます。血液や尿をアルカリ化することで痛風、高尿酸血症を予防、改善する効果も期待できます」
Q. もずくを上手に摂取する方法はありますか?
吉積さん「無味無臭のため、いろいろな料理にアレンジすることができます。味のついていないもずくは、サラダのトッピングやみそ汁の具としても使用できます。
スーパーなどで売られている『もずく酢』は、サンラータンや酢豚など酸味のある料理に加えることができると思います。砂糖で甘く煮詰めて、あんとして果汁ゼリーなどのトッピングにもすることができます。
摂取するタイミングとしては、朝食を食べる直前にとるのがベストです。もずくに含まれている水溶性食物繊維を朝食の前に食べると、最初の食事=ファーストミールが次の食事=セカンドミールの血糖値に影響を与える『セカンドミール効果』が期待できます。
また、摂取する頻度についてですが、もずくの効果を得たければ毎日食べるのがベストなのですが、最低でも週に3日食べるのがよいと思います。
もずくの1日当たりの摂取目安量は20~40グラム(市販のカップもずく酢1カップ程度)にしましょう。
カキと食べ合わせ(食い合わせ)するのは控えた方がよいです。もずくが豊富に含んでいる水溶性食物繊維と、カキが豊富に含んでいる亜鉛を同時に摂取すると、食物繊維が亜鉛を体外に排出し、摂取した亜鉛がうまく吸収されない可能性が生じます」
(オトナンサー編集部)