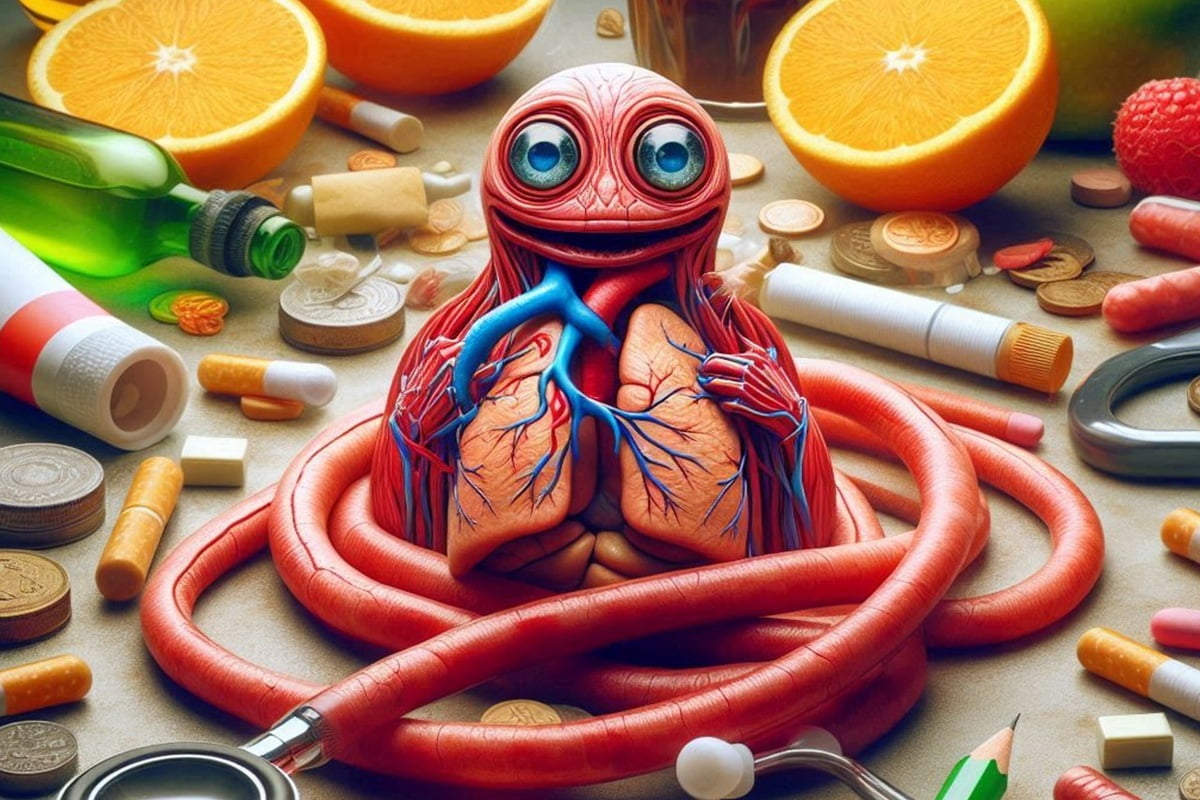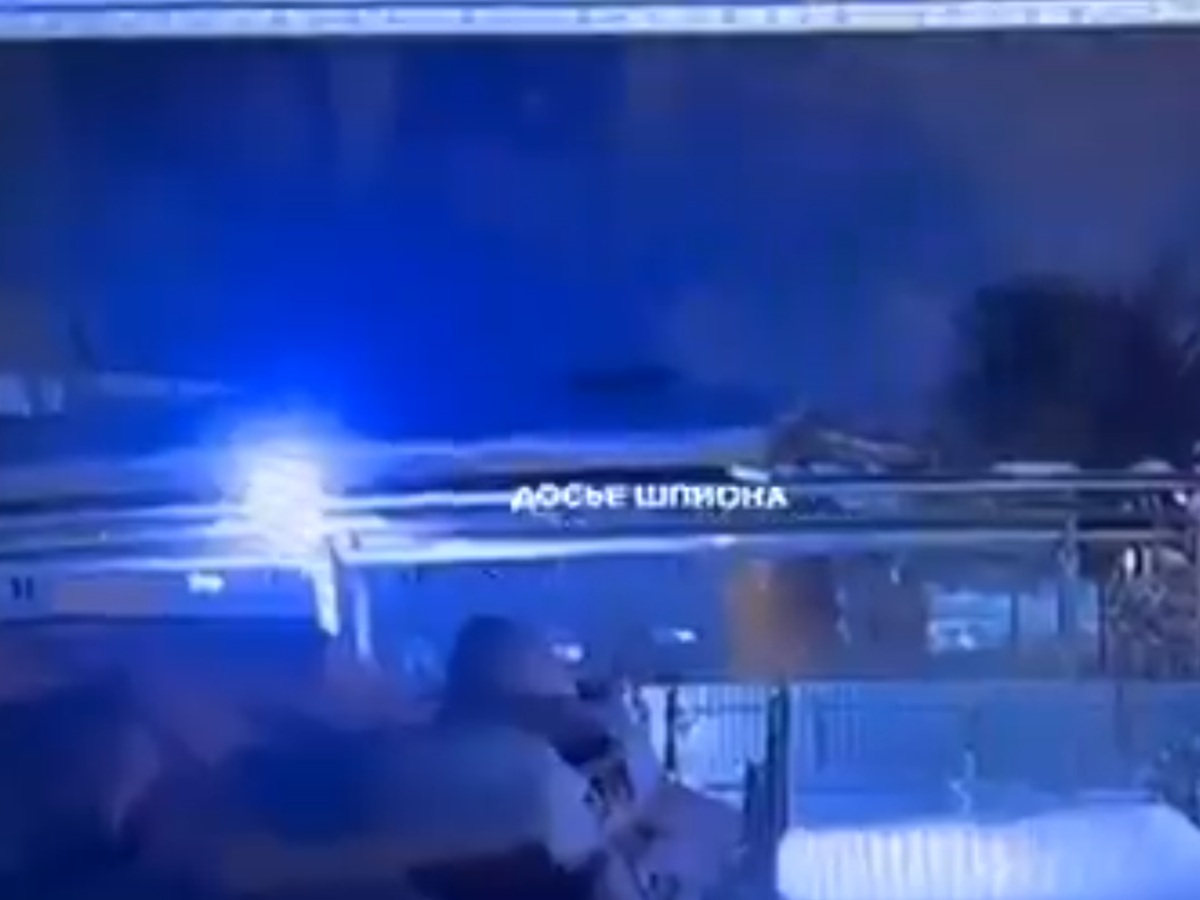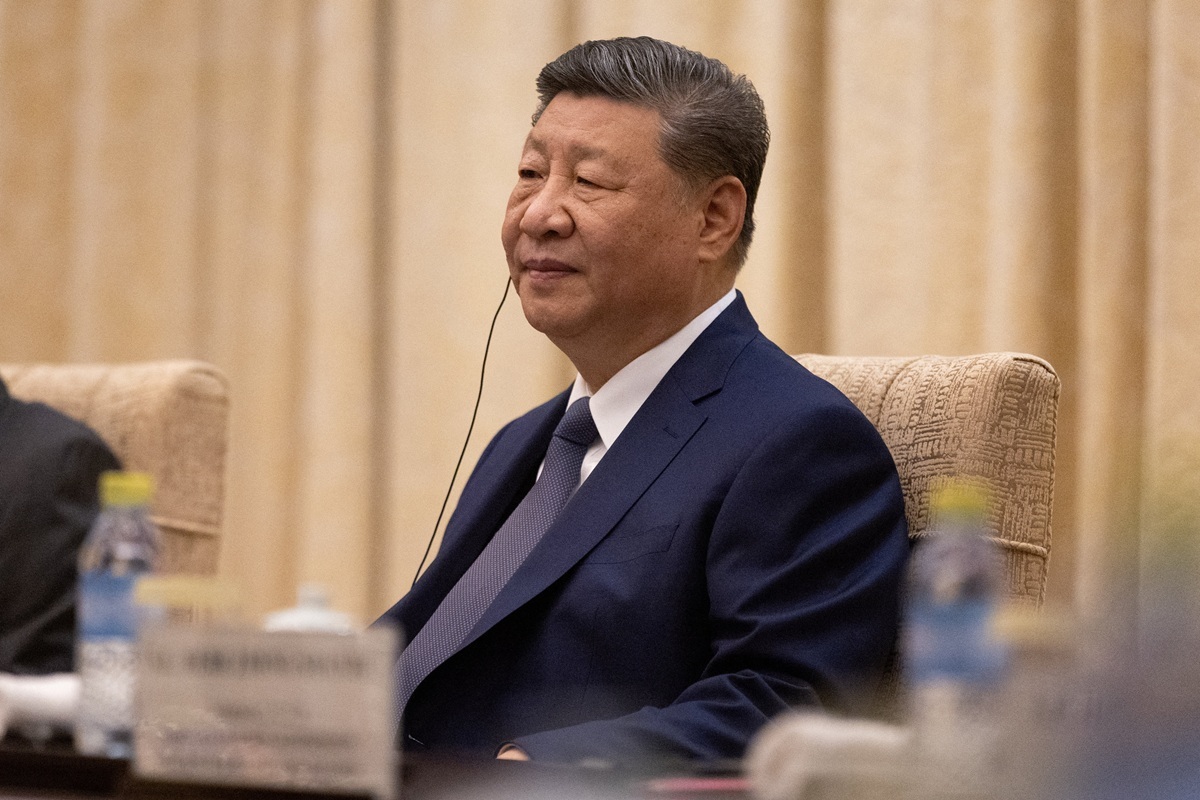【毎日書評】「ラッキー」と「自分は運がいい」の違いを知れば、もっと生きやすくなる

『精神科医が教える 幸運になる心の習慣』(水島広子 著、リベラル文庫)の著者は、「対人関係療法」という精神療法を専門とする精神科医。さまざまな人たちと関わるなかで、「自分についての感じ方」が心の健康や人生の質を左右することを実感してきたのだそうです。
たとえば、「自分は運がいい」という感じ方について。
「自分は運がいい」という人は、本人が意識していないとしても自己肯定感が高いといえます。一方、「自分は運が悪い」と思っている人は、自分についての感覚も悪いといえそうです。
重要なのは、ある出来事について「幸運」と感じることと、「自分は運がいい」と感じることは、決して同じではないこと。どれほどの幸運に恵まれたとしても、健康な自己肯定感がなければ「自分は運がいい」と感じることができないとも考えられるわけです。
ところで著者は本書において、「運のよさ」についての使い分けを以下のように定義しています。
・出来事としての「運のよさ」(いわゆる幸運)=「ラッキー」と呼びます。
・「自分は運がいい」という感覚=「運のよさ」と呼びます。
(「はじめに」より)
このふたつを区別すると、「運」についてのとらえ方の混乱を整理することができるというのです。たとえば“運のよさ”と“努力”が相反するものだというような苦しい考えから解放され、気持ちのよい努力をしながら「運のいい人生」を楽しむこともできるようになるわけです。
こうした考え方を念頭に置いたうえで、第1章「絶対に知っておきたい原則 『運』と『べき』は最悪の相性」を確認してみたいと思います。
「運のいい人」を目指したいのであれば、まず最初に手放さなければならないのが「べき」だそう。いうまでもなく「〜であるべき」「〜すべき」といった考え方のことで、「べき思考」などと呼ばれることもあります。
ただし「べき」には2種類あり、まず1つ目は「運のよさ」にむしろプラスになるもの。
・何かの目的に向けて進んでいる人が、「今こそ行動を起こすべき!」というような、必然を感じたときのすがすがしい「べき」です。
・「これが私のあるべき姿だ」というタイプの、自分を肯定する感じの、やはりすがすがしい「べき」。
(24〜25ページより)
こうした「べき」は達成感や充実感につながるため、「自分は運がいい」という感じ方にも違和感がないはず。使命感を見つけられ、そこに達成感を覚えることができれば、そんな自分は「運がいい」わけです。
しかし、もう1つの「べき」には注意が必要。「本当はやりたいこと」「自分の自然体」とは異なるのに、「こうあらねばならない」「これをすべき」などという考えに縛られてしまう「べき」だからです。
それでは「運のよさ」どころか、いつも「なにかをさせられている感」「自分が足りていない感」を持つことになってしまいます。また、そうした「べき」は、「あの人はすべきことをしていない」など他人に向けられることもあるでしょう。
そんな状態では、「運がいい」とはいえないわけです。(24ページより)
「運がいい」と「ラッキー」は違う
前述のとおり著者は、「運のよさ」を「ラッキー」と「運がいい」とに分けて考えていますが、そもそも両者はどう違うのでしょうか?
「ラッキー」というのは、目で見てわかる、出来事としての幸運のこと。
例えば、
・宝くじに当たる。
・持っていた不動産の価値が、たまたま上がる。
・ギャンブルで大もうけする。
・予期していなかった遺産が手に入る。
(29〜30ページより)
つまり、努力して得られるレベルではない、“本当に降ってわいたようなもの”を、本書では「ラッキー」と呼んでいるわけです。
誰が見てもうなるような「ラッキー」に恵まれる人は、むしろ稀です。
「ラッキー」を追いかける生き方は、「自分は運がいい」とは似て非なるものであって、本書は「ラッキー」の有無にかかわらず「自分は運がいい」と思えることを目標にしています。そして、実際に、「ラッキー」に恵まれていなくても、「自分は運がいい」と思いながら生きている人はたくさんいるのです。(30ページより)
なお、「ラッキー」と感じられることのなかにも、実際はそうでないものもあるようです。
たとえば、「希望していた部署に空きが出て異動できる」「よい転職先に恵まれる」というようなことを「ラッキー」と呼ぶ人もいることでしょう。そういったことについて日常会話のなかで「ラッキーだった」といっても違和感はありませんし、本当に「ラッキー」な場合も考えられます。
しかし、その空いた「枠」を自分がつかめるかどうかは、「ラッキー」だけで片づけられるものではないはず。むしろ、「面接時の印象がよい」「その分野で努力した実績がある」など、それまでの努力の積み重ねの結果であることのほうが多いのではないでしょうか。
社内での異動であれば、「それが向いていると気づいてくれる人」や「それを希望していることを知っている人」などに支えられるケースも多く、単に「ラッキー」では語れない要素がたくさんあるのです。
これらがそうであるように、「単なるラッキー」に見えるものでも、それまでの努力や築いてきた信頼などによるものも非常に多いということ。いずれにしても重要なのは、単なる「ラッキー」ではない側面に気づけること。そしてそれを肯定することができれば、自己肯定感も上がる可能性があるのです。(28ページより)
「運がいい人生」とは、ネガティブな目詰まりがなく、「まあ、なんとかなるだろう」という感覚をもとに、いろいろなことがプラスに循環しているものだと著者はいいます。
そんな生き方ができるときに、「自分は運がいい」と感じられるのだとも。運の悪さを感じている方は、そこから抜け出すためにも本書を活用するべきかもしれません。
>>Kindle Unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
作家、書評家、音楽評論家。1962年東京都生まれ。広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。「ライフハッカー・ジャパン」で書評連載を担当するようになって以降、大量の本をすばやく読む方法を発見。年間700冊以上の読書量を誇る。「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク日本版」「サライ.jp」などのサイトでも書評を執筆するほか、「文春オンライン」「qobuz」などにもエッセイを寄稿。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社、のちにPHP文庫)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)など多数。最新刊は『現代人のための読書入門 本を読むとはどういうことか』(光文社新書)。@innamix/X
Source: リベラル社