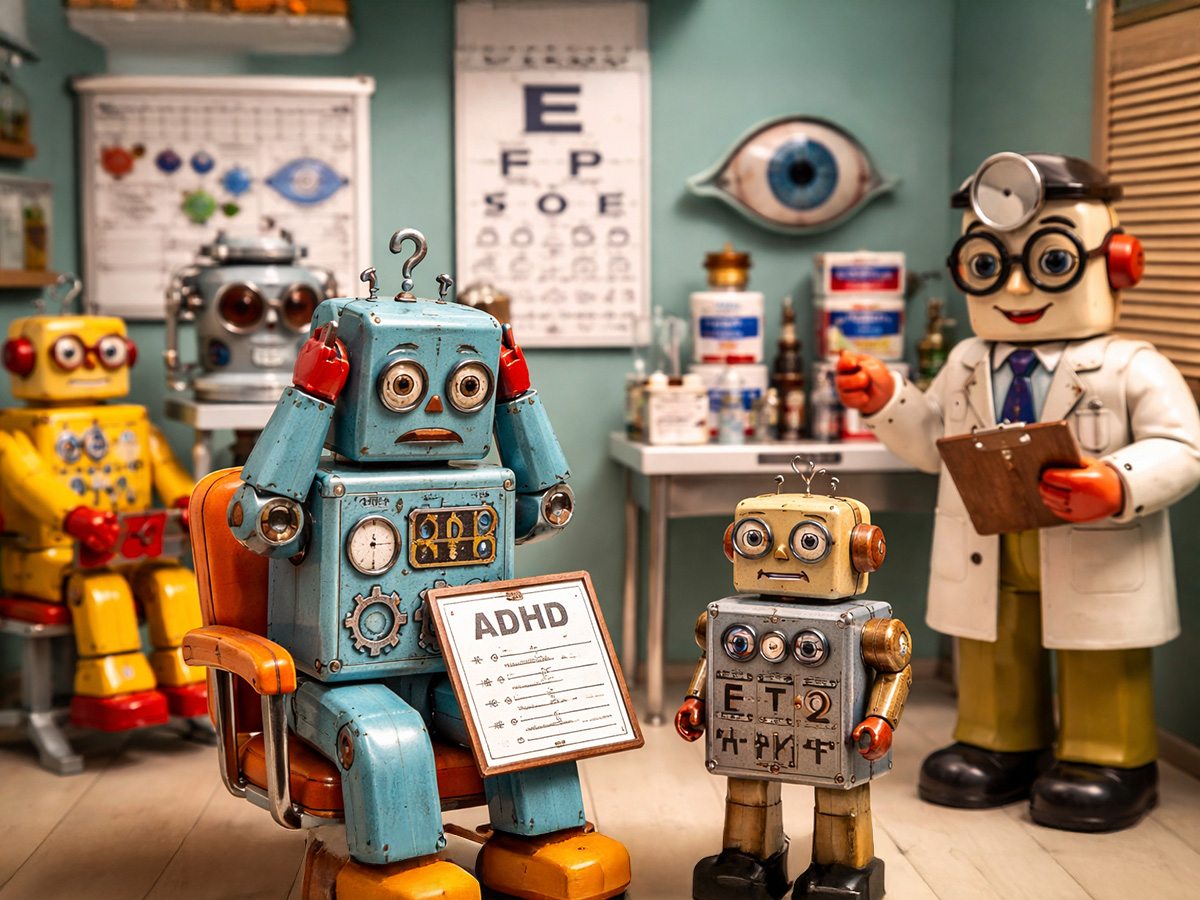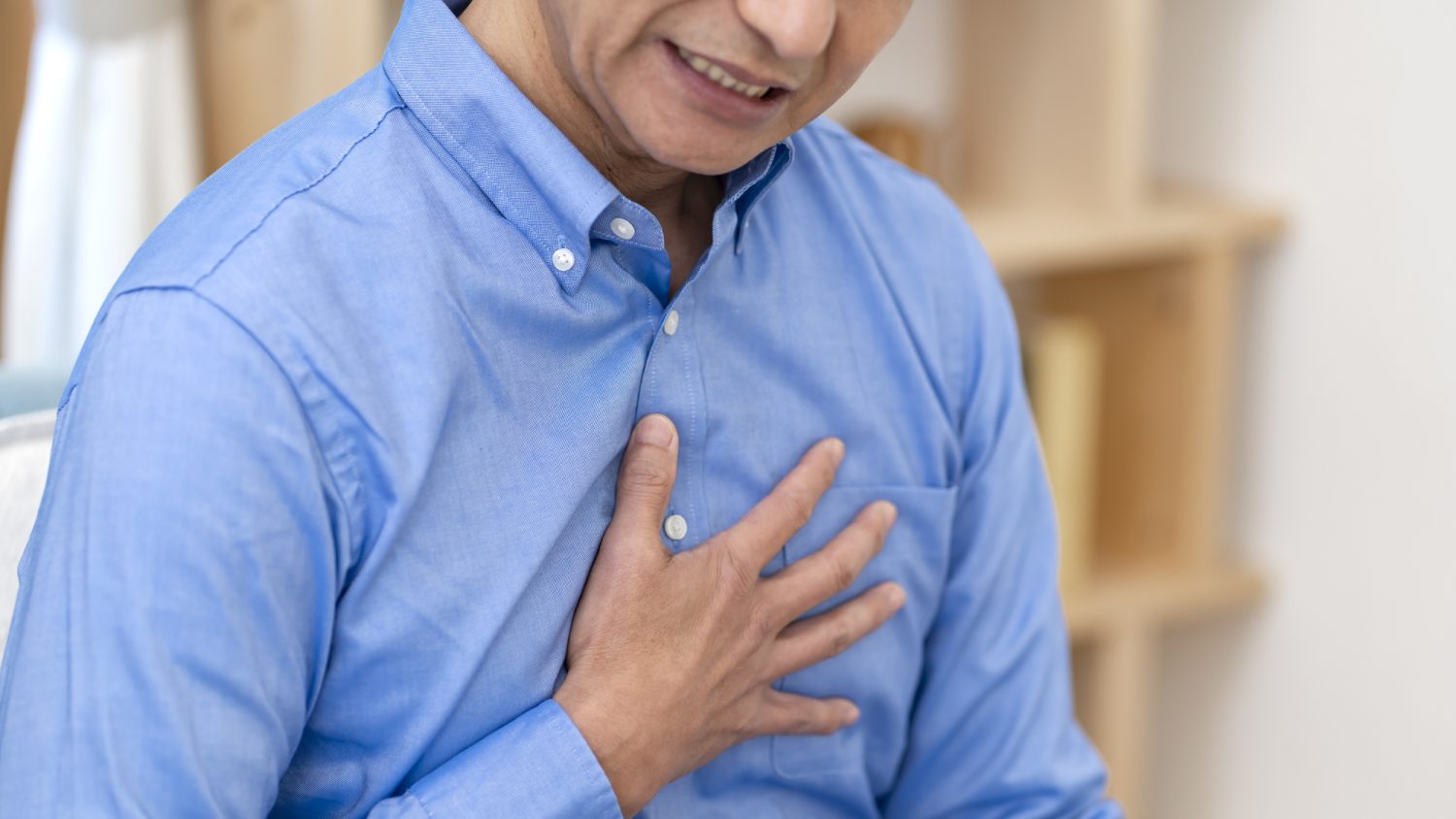誤診多いレビー小体型 多様な症状の認知症 前兆を発見の糸口に

認知症のうち比較的発症頻度の高い「レビー小体型認知症」は、「アルファシヌクレイン」と呼ばれるタンパク質が脳組織にたまることで引き起こされ、幻視や歩行障害を特徴とする。治療薬の開発が進みつつあるアルツハイマー病と比べ、いまだに根本的な治療法がない。前兆を手がかりに早期発見に向けた研究が進むものの、誤診されたり診断に至らなかったりするケースも多い。
▽「天井裏に猫」
「多様な症状に戸惑いました」。長野市在住の宮坂知芳さん(48)の母豊子さん(85)に2020年冬、「暑い」「寒い」といった感覚を繰り返し訴える症状が現れた。 複数のクリニックを受診し、処方された抗うつ剤や精神安定剤、自律神経の調整薬の服用を続けた。症状は改善せず、「天井裏に猫がいる」「家を燃やすというメールが来た」などの幻視や妄想が出現。夜中に大声を出したり、小刻みに歩いたりする症状も現れ、ぼーっとして問いかけに応じない時間が増えた。
昨年8月には誤嚥(ごえん)性肺炎で入院した。リハビリのために移った病院で初めてレビー小体型を疑われた。11月、大学病院で診断が確定し、幻視などの症状を抑える薬の服用を始めた。 8月の入院時、家族の判断で向精神薬の服用を止めると豊子さんの意識がはっきりする時間が増えた。「もっと早く診断が下っていれば対応を間違えず、もう少し幸せな状態にしてあげられたかもしれない」と知芳さん。豊子さんは今年1月以来、再び誤嚥性肺炎で入退院を繰り返し、食事を取れない日が続いている。 ▽物忘れ以外も
国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)の鈴木啓介医師(脳神経内科)によると、レビー小体型には歩行障害や動作が緩慢になるなどのパーキンソン病に似た症状に加え、意識の変動、睡眠中の行動異常なども出る。一方でアルツハイマー病と比べて記憶障害は軽く、家事や薬の管理ができなくなるといった「遂行障害」が目立つ。
自律神経障害や嚥下機能の低下、うつ症状などの精神症状を伴うことや、薬剤に過敏に反応して副作用が強く出る傾向もある。一部は時間の経過と共に進行するとされる。
心臓の自律神経の働きを調べるなど診断方法はあるが、鈴木医師は「診断に至っていない人がたくさんいる」と推測。パーキンソン症状を正確に見分けることが難しく、精神疾患と間違われる可能性もあるためだ。「認知症イコール物忘れと考えていると発見が遅れる可能性がある」 ▽予備軍 近年、レビー小体型に、パーキンソン病も含めた「レビー小体病」の早期発見に向けた研究が進む。発症する10~20年前から便秘や嗅覚異常、睡眠中の行動異常といった前兆に注目し、予備軍を抽出する試みだ。 名古屋大や長寿研は共同研究で、50歳以上の健康診断受診者約2万6千人の約7%に複数の前兆があり、うち一部の人に軽度の認知機能の低下などがあったことを確認した。こうしたハイリスク者に先行的に薬を投与する臨床試験や、血液中のタンパク質を解析して病気の指標を見いだそうとする研究も行われている。
ただ治療薬は症状を個別に和らげるものしかなく、病態の根幹に作用する薬の開発が求められている。リハビリで筋力低下や体が硬くなるのを防ぐことなど薬を使わないアプローチも大切だ。鈴木医師は「薬剤過敏などがないかを医師がよく問診し、正確な診断につなげることが重要」と話した。(共同=高木亜紗恵)