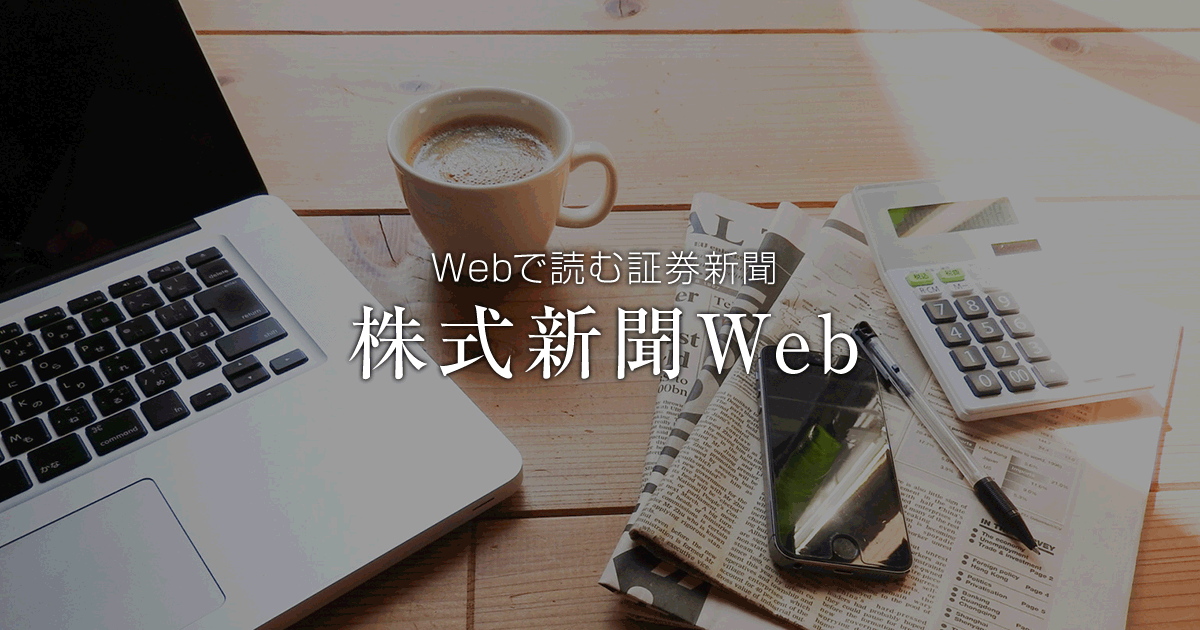コラム:AI競争で西側を猛追する中国、既に先行部分も
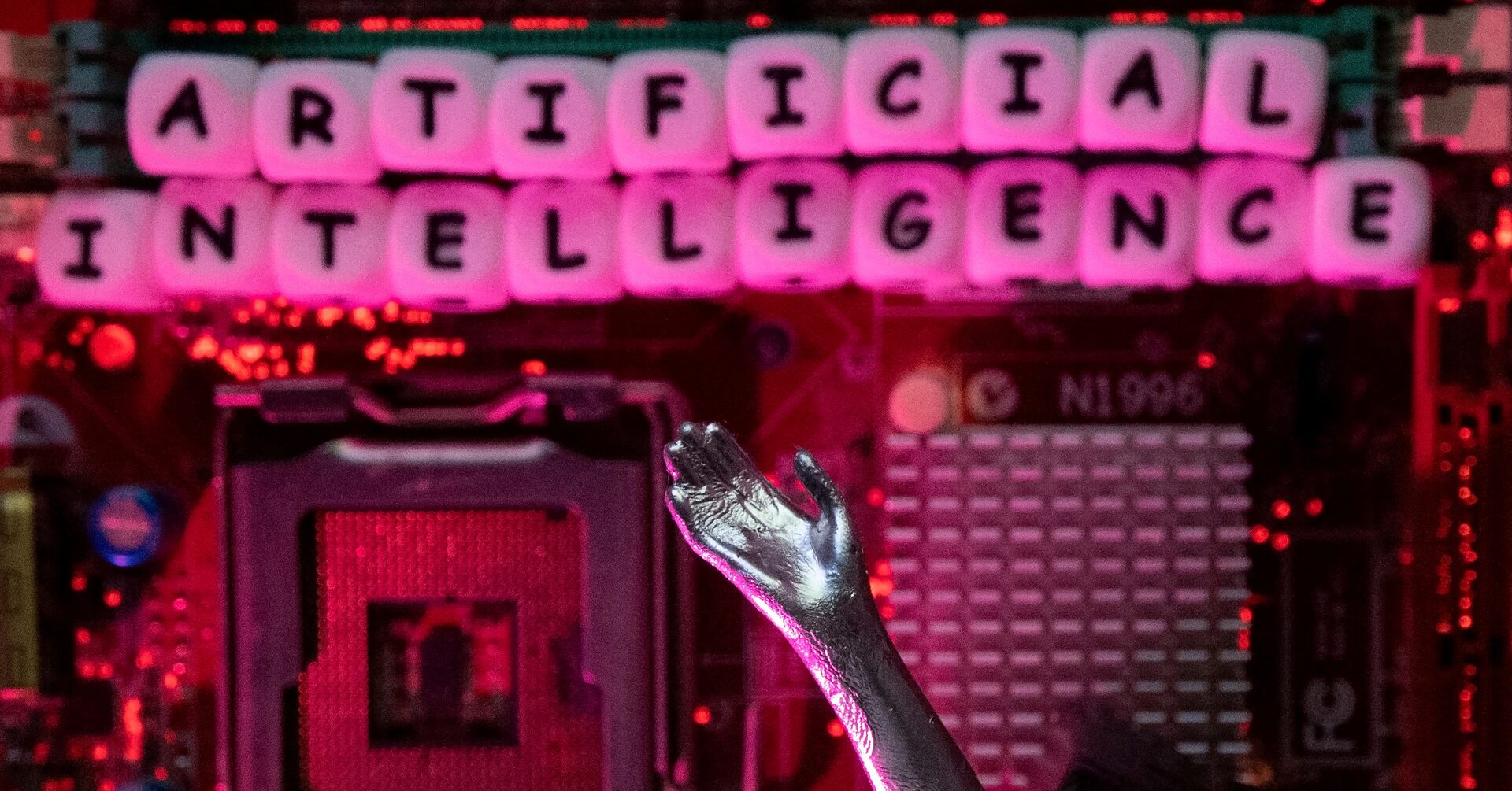
[香港 24日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 2023年、スマートフォンから半導体まで手掛ける中国の華為技術(ファーウェイ)は、ひっそりと主力スマホ「Mate 60 Pro」を発売した。静かな門出ながら、中国にとっては祝うに値する出来事だった。米国の制裁措置により、以前は手が届かないと考えられていた中国製半導体を搭載していたからだ。
欧米諸国は中国におけるAIの進歩を抑えようと躍起だが、上記のような成果を見れば、中国は対処法を見つけ出していることが分かる。マッキンゼーの推計によると、AIは年間6兆ドルの経済効果が見込める可能性を秘めた分野だ。また習近平国家主席は、無人兵器やデータ処理などにおけるAI能力の開発を含め、人民解放軍を世界トップクラスの軍事力にすることに重点を置いている。その取り組みはまだ初期段階ではあるが、これまでの実績を見る限り、中国は西側諸国とほぼ肩を並べることができるかもしれない。
バーンスタインのアナリストによると、カンブリコンの売上高は今年、2倍以上の43億元(5億8700万ドル)に増える見通しだ。十分な資金と国家の支援を得た中国の半導体設計企業によって、エヌビディア製半導体の不足は打開できると期待されている。
しかし中国企業は、この制約に適応している。例えばファーウェイはSMICの製造能力に適合させるため、AIプロセッサの再設計に4年以上を費やした。その他の対処法としては、処理能力の低いプロセッサをグループ化する「クラスタリング」や、より小規模なデータセットを使ったモデルの訓練などが挙げられる。ソフトウエア開発者も、電力効率を最大限に高めるためにアルゴリズムを微調整しており、企業は訓練済みのモデルを迅速に展開して、より初期の段階で回答を生成するようにしている。
アルファベットのルース・ポラット最高投資責任者(CIO)は今週のインタビューで「中国は基礎的な能力の普及という点で(中略)同等か、若干リードしている可能性さえある」と語った。これはAI処理を経済全体に広げる能力を指しており、多くの企業がデジタル化で遅れをとっている中国においては、特に期待の持てる評価だと言える。
軍事用AIにおける中国の進展度合いは、これらに比べて判断が難しい。一部の安全保障アナリストは、中国の精密誘導ミサイルなどは米国の同等の兵器ほど洗練されていないとしている。理論上、性能の劣るハードウエアをAIシステムに統合しても、その影響は最小限にとどまるはずだ。
しかし兵器の格差は縮まる可能性がある。米国防総省が発表した中国軍に関する最新の報告書では、無人航空機システム(ドローン)が急速に進歩し、「米国の水準に匹敵した」とされている。中国の軍部はAIアプリケーションの開発でも進展しており、学術論文やアナリストの意見を引用したロイターの報道によると、社内モデルやメタのようなオープンソースのモデルを使用している。
長期的には、真の成果がもたらされるのはSMICがプロセッサ2023のような製造上の飛躍を再び成し遂げ、より小型で高性能な半導体の製造が可能になった時だろう。そうなれば、先進国による高性能ハードウエアの牙城は弱まる。中国政府が理論上、この問題に投じることができる資源に鑑みれば、こうした状況が現実化しないことに賭けるのは難しい。バイデン前米政権のレモンド商務長官は12月、中国の半導体の進歩を止めようとするのは「無駄足」だと語った。 AIについても同じことが言えるかもしれない。
(筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
Robyn Mak joined Reuters Breakingviews in 2013. Previously, she was a Research Associate for the Global Policy Programs at the Asia Society in New York. She has also worked at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington DC and interned at several consulting firms, including the Albright Stonebridge Group. She holds a masters degree in international economics and international relations from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies and is a magna cum laude graduate of New York University.