昏睡状態の人の睡眠を研究:目覚める可能性は、眠りのパターンから予想できるのか
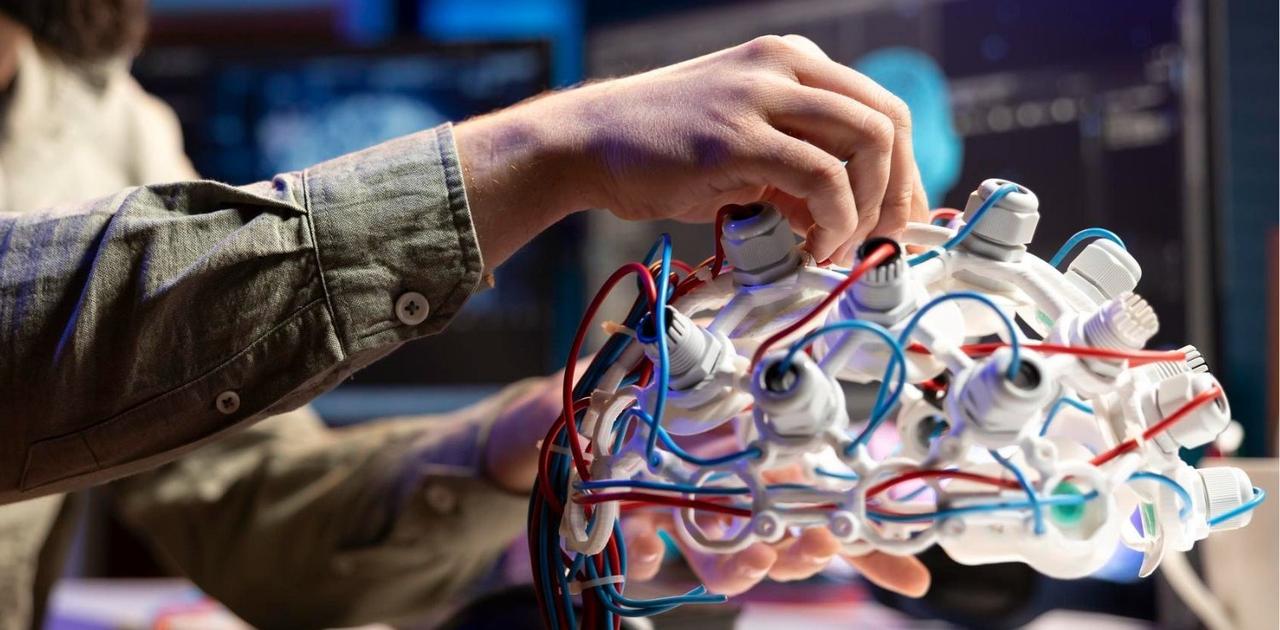
昏睡状態で眠り続ける人が、いつ目を覚ますのか。そもそも覚ます日が来るのか。
現在の医療・科学ではそれを知ることはできません。しかし、新たな研究で、その予測が立てられるようになるかもしれません。
眠りのパターンを解析
コロンビア大学とニューヨーク長老教会病院の共同研究にて、昏睡状態患者の眠りのパターンと回復確率を調査。注目すべき関連性があることがわかりました。
研究論文の主執筆者であり、コロンビア大学の神経内科医Jan Claassen氏の研究チームは、脳に損傷を負った昏睡状態患者の最大4人に1人は、外からわからないだけで意識があるのではないかと考えました。
認知と運動が解離している状態で、例えば「右手を挙げて」という指令は認知できているのに、実際に右手を動かすことができない状態がこれにあたります。
これを調べるため、Claassen氏は、患者が聴こえている・理解できているが、体を動かせないことを識別するテクニックを開発しました。
「(この研究は)神経内科ケアとして非常に興味深いところにあります。意識のない状態に見える多くの患者さんが、実は私たちの気づかないところで回復してきているかもしれないのですから。回復のサインをリアルタイムで、今、少しずつ見つけようとしているのです」
Claassen氏は、睡眠中の脳の動きに着目。前述のClaassen氏の認知と運動が解離を調べるメソッドを受けたことがある、226人の患者のひと晩の脳の電気活動を解析しました。
結果、一見カオスに見える脳の動きですが、時に一部患者で整然とした速い周波数が出ることがわかりました。これは睡眠紡錘波(ノンレム睡眠時に見られる)で、外からはわからないが認知できている状態、または目が覚める前、長期的回復する前に現れる傾向があることもわかりました。
Claassen氏のメソッドと睡眠紡錘波の両方の反応が出た患者の多くが目を覚まし、大きな回復を見せました。退院までに認知力が回復したのは76%、退院後1年以内に日中自立できるほど神経機能を回復したのは41%。
眠りが深いノンレム睡眠
ノンレム睡眠=深い眠り、質の高い眠りが、患者の回復の機会を高める可能性は否定できないといいます。問題は、昏睡状態にある患者はICUにいる場合が多く、常に周辺機器の音や、検査・ケアが入るので、眠りにくい状況にあること…。
一方で、以上の研究調査はあくまでも関連性を示すものにすぎず、昏睡状態からの回復と睡眠紡錘波が直接的に関係すると証明するものではありません。実際、どちらにも反応のなかった139人の患者のうち19人は、その後意識を取り戻しています。
眠りの質を向上させるという治療を実践するには、今後さらなる実験が必要です。
家族のために
Claassen氏は、大学のプレスリリースにてこう語っています。
「患者さんの家族の方が本当によく聞くのは、目を覚ましますか? 3ヶ月後、半年後、1年後にはどういう状態にありますか?という質問です。
ほとんどの場合、私たちはこれに正確に答えることができません。家族の方の方向性、決断をサポートするためにも、この予測は必要だと考えます」
研究論文はNature Medicineに掲載されています。



