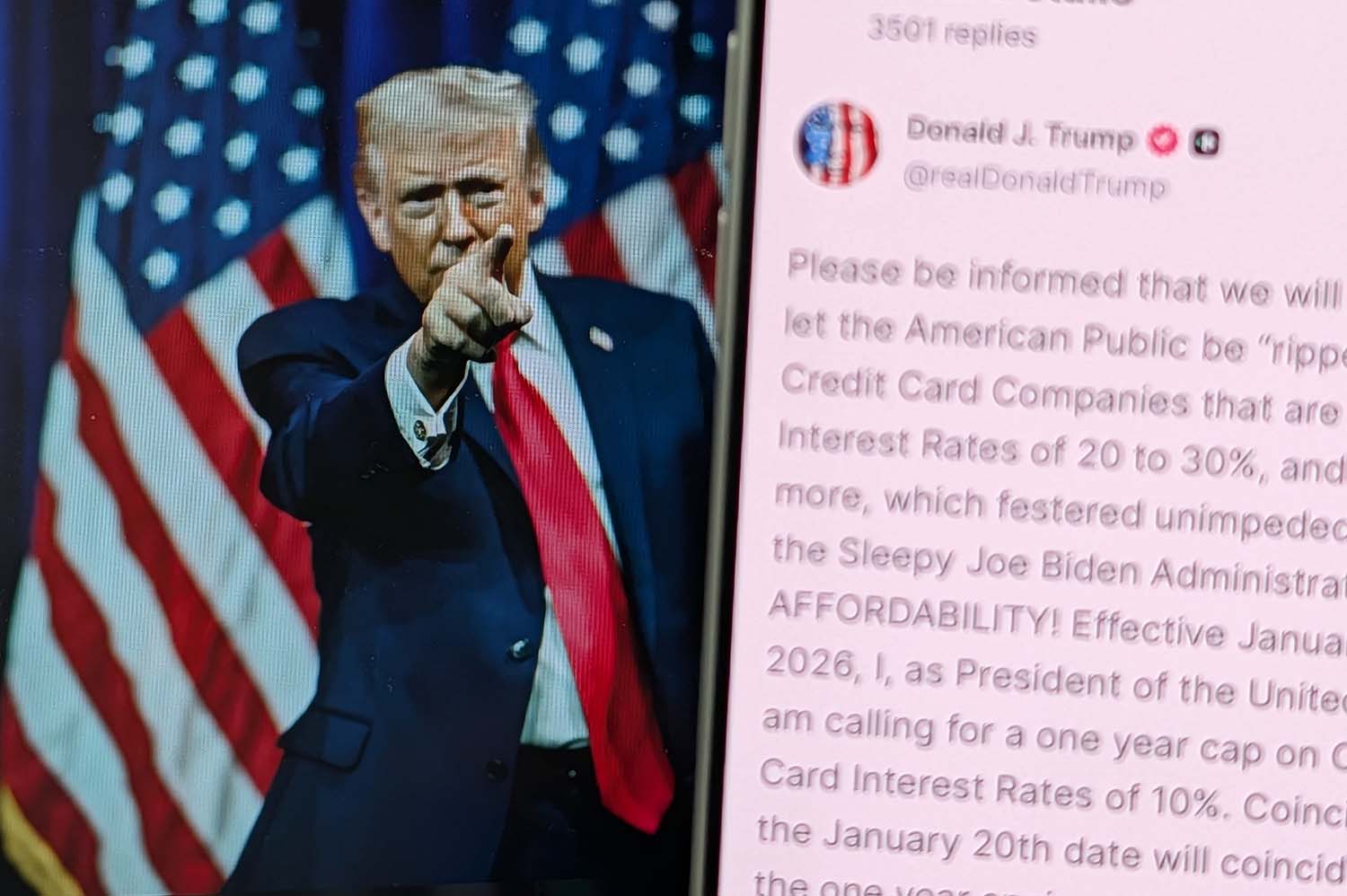モバイルバッテリー発火、4年で2・6倍に 背景に海外の低品質電池か 劣化と温度に注意

日常生活の必需品として定着しつつあるモバイルバッテリーが突然発火する事故が相次いでいる。8月には、電車や新幹線の車内で発火する事例が続き、運行にも支障が出た。発火源はバッテリーに使われるリチウムイオン電池で、同様の事故はここ数年で急増。低品質な海外製の普及が背景にあるとみられるが、リチウムイオン電池は身の回りの電化製品に多く使用されており、取り扱いには注意が必要だ。
鉄道内での事故相次ぐ
スマートフォンの充電などのためにモバイルバッテリーを持ち歩く姿は、どこでも見られるようになった。その半面、多くの発火事故が発生している。
8月28日午前8時ごろ、大宮-上野間を走行中の上越新幹線で、乗客の男性がキャリーケースに入れていたモバイルバッテリーが発火し、車内には煙が立ち込めた。男性は軽いやけどを負い、安全確認などのため一部列車に遅れが出た。
これに先立つ22日には、JR新大阪駅に向かっていた東海道新幹線の車内で、座席ポケットに入れられていたモバイルバッテリーから発火。7月にもJR山手線の車内で、スマートフォンを充電中のモバイルバッテリーから火が出た。
製品評価技術基盤機構(NITE)によると令和2~6年、リチウムイオン電池を搭載した製品による発火などの事故は計1860件。このうち、モバイルバッテリーによる事故は2年には47件だったが、6年には123件と2・6倍に増加している。
適切に廃棄されず
充電して繰り返し使用できるリチウムイオン電池は現在、モバイルバッテリー以外でも、スマートフォンやワイヤレスイヤホン、ゲーム機やパソコンなど、身近な電子機器に幅広く搭載されている。
適切に廃棄されずに、火事の原因となる事例も増えている。東京消防庁の発表によると、令和5年中にごみ収集車から出火した火災41件のうち、半数を超える21件がリチウムイオン電池を含む製品が発火源だった。
猛暑が続く中、若者を中心に広く普及しているハンディファン(手持ち扇風機)にも搭載されており、環境省は、使用が終わったハンディファンの廃棄などが増える11月を火災防止月間に設定。兵庫県芦屋市などの各自治体も、製品ごとの正しい廃棄を呼びかけている。
品質管理の甘い製品が流通
リチウムイオン電池は、どのような場合に発火するのか。
電気化学を専門とする関西大化学生命工学部の石川正司教授によると、①劣化②気温が高い③熱のこもりやすい場所-など、いくつかの条件が重なったときに発火事故が起こりやすいという。
リチウムイオン電池は長い期間使っていると、中の「電解液」が劣化し、ガスが発生する。この状態で、落下による衝撃など何らかの理由で内部でショートが起こると、過熱状態となって火が出るというしくみだ。
石川氏は、近年特に発火事故が増加している背景として、「品質管理の甘い海外製の電池が大手メーカーの電化製品に使用され、流通したことが要因の一つではないか」と分析する。
予防策としては、電池の劣化を遅らせるために、「適温下で扱うことが重要」と説明。モバイルバッテリーなどを毎日使用する場合、3年を目安に劣化していないか確認し、落とした場合も使用時に温度が高くならないか注視することを勧めている。(堀川玲)