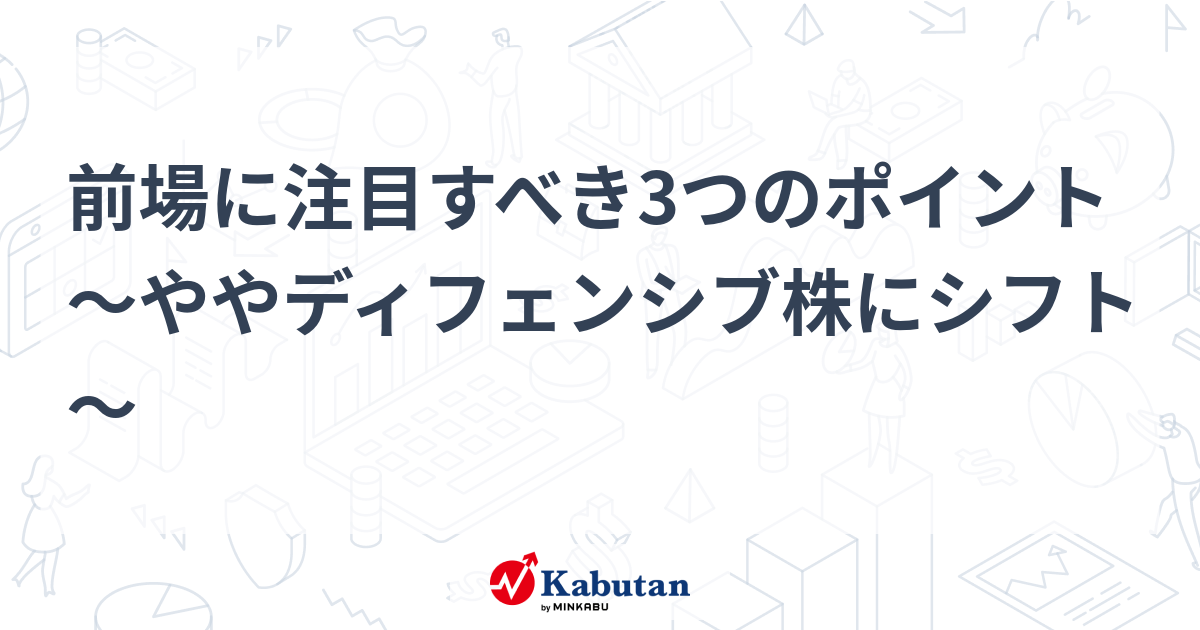真夏の暴落から1年、再び上昇気流に乗る日本株-円急騰リスクに耐性

外国為替市場での急激な円高進行が東京からニューヨークに至る株価急落の連鎖を招き、投資家の心胆を寒からしめた1年前と比べると、日本の株式・金融市場は安定を取り戻している。
この1年で日本株は2度の急落を経験した。1度目は昨年8月で、日本銀行の予想外の利上げや米国経済統計の悪化をきっかけに東証株価指数(TOPIX)は同5日の取引で12%安と史上2位の下落率を記録。2度目はトランプ米大統領が追加関税政策の詳細を明かした今年4月だ。いずれも円相場の急伸と重なり、為替市場では低金利の円を売り、高金利のドルを買う「キャリートレード」の巻き戻しが加速した。
関連記事:200兆円消えた日本株暴落、元凶は過剰な持ち高整理-買い好機の声も
最初の急落から1年が経過したTOPIXは、再び史上最高値圏で推移している。以前よりもキャリートレードの影響が薄れ、日銀の利上げの道筋が見通しやすくなるなど為替や金利に対する耐性が強まっているからだ。企業のガバナンス(統治)や資本効率改革も継続し、日米関税交渉の決着も投資家の安心感につながっている。
相場の短期過熱を示す幾つかのテクニカル指標は昨年8月の急落前と類似し、1日に発表された米雇用統計が市場予想よりも悪く、パニックの再来が懸念されたが、現時点では円や日本株の変動率は1年前と比べはるかに小さい。
関連記事:最高値のTOPIXに黄信号、過熱感や割高警戒で短期調整の可能性
英国で日本株の調査会社を率いるペラム・スミザーズ氏は「今の相場環境は昨年よりもかなり安定し、株式市場がさらに上昇する余地がある」とみている。
グローバル投資家が運用成績を計るベンチマークとしているMSCIワールド指数で、日本のウエートは6月末時点で5.5%と米国の63%に次ぐ2位だ。日本株の上昇基調が続き、時価総額で見た相対的な価値が高まれば、米国や欧州などから投資資金がシフトする可能性がある。
バンエックでクロスアセット・ストラテジストを務めるアンナ・ウー氏(シドニー在勤)は、日銀は「過去の教訓を学んだ」と指摘し、市場とのコミュニケーションを改善したことが為替や金利の落ち着きにつながっていると分析する。
昨年7月に政策金利を15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げた際、投資家は唐突だと受け止め、キャリートレードの巻き戻しが円急騰を招いた。しかし、日銀による対話姿勢の変化で市場は利上げが進んでも円と他通貨の絶対的金利差があまり変わらないことを認識し、キャリートレードの解消リスクは減ったとウー氏は話す。
日銀が今年1月に25bpの追加利上げを行った際、10日前に氷見野良三副総裁が利上げの可能性を示唆し、植田総裁も後押しするなど事前に市場での織り込みが進んだため、実際の利上げを受けて日本株は銀行株中心に上昇した。
三菱UFJアセットマネジメントの小口正之エグゼクティブ・ファンドマネジャーは、昨年夏の市場混乱にもかかわらず、今年1月に再び利上げを決断したことで利上げ路線の継続が明確になり、「先のシナリオを描きやすくなった」と言う。
ホットマネーの一掃
スミザーズ氏は、投機筋が株価を押し上げていた面も強い昨年夏とは違い、足元の日本株相場の足腰は強く、潜在的なショックに対する耐性は高まっているとの認識を示す。2度の急落を経て短期的な「ホットマネー」が一掃され、現在の市場に残っているのは「日本を信じる投資家」だからだ。
日本取引所グループによると、昨年8月の急落後に日本株市場から一時撤退していた海外投資家は今年4月以降に回帰。7月第4週まで17週連続で現物株を買い越し、買い越し記録は2013年以降で最長となっている。海外勢の評価ポイントの一つが日本企業のガバナンス改革や自社株買い、増配など株主還元の強化だ。
M&Gインベストメンツのサニー・ロモ日本株投資ディレクターは、日本企業の「ガバナンス改革と株主還元はまだピークに達しておらず、さらなる高みに到達しつつある」と指摘。グローバル投資家は、トランプ関税の影響が今後経済に跳ね返ってくる米国以外の市場に分散投資を模索し始めており、日本株にもさらなる上昇余地があると予想している。
7月の参院選で自民・公明が大敗し、衆参両院で少数与党となったため、野党の多くが主張する消費税減税に歩み寄る可能性が小売りなど内需セクターの株価に追い風になるとの見方も出ている。フィリップ証券の笹木和弘リサーチ部長も日本株の状況は1年前とかなり違うとし、「政府が財政拡張に踏み込めば、内需銘柄を中心に投資家が期待できる材料は多い」と述べた。
日本株の先高観の強さは、海外の大手金融機関による株価指数目標の引き上げに顕著に表れている。日米の関税合意を受け、米ゴールドマン・サックス・グループは12カ月先のTOPIX目標値を3000から3200ポイントに上方修正し、米バンク・オブ・アメリカ(BofA)も25年末の目標を2850から3050に引き上げた。
とはいえ、日本株は依然として為替動向に左右されると警戒する声も根強い。トランプ関税の米経済への影響に不確実性が残るほか、石破茂政権の先行きも不透明なためだ。
インタルコン・アセット・マネージメントのクラウス・ウォッベ最高経営責任者(CEO)は日銀の金融政策にかかわらず、関税への懸念や国内政治の不透明感から安全資産としての円が買われ、為替のボラティリティーが高まる恐れがあるとみている。
ウォッベCEOは、米連邦準備制度理事会(FRB)が第4四半期に利下げを行い、日銀が金融引き締めを続ければ、「円は再び140円を抜ける可能性がある」と予測。同水準は円キャリートレードの真の巻き戻しが進むことを示すシグナルで、「140円が最後の防衛線」だと述べた。