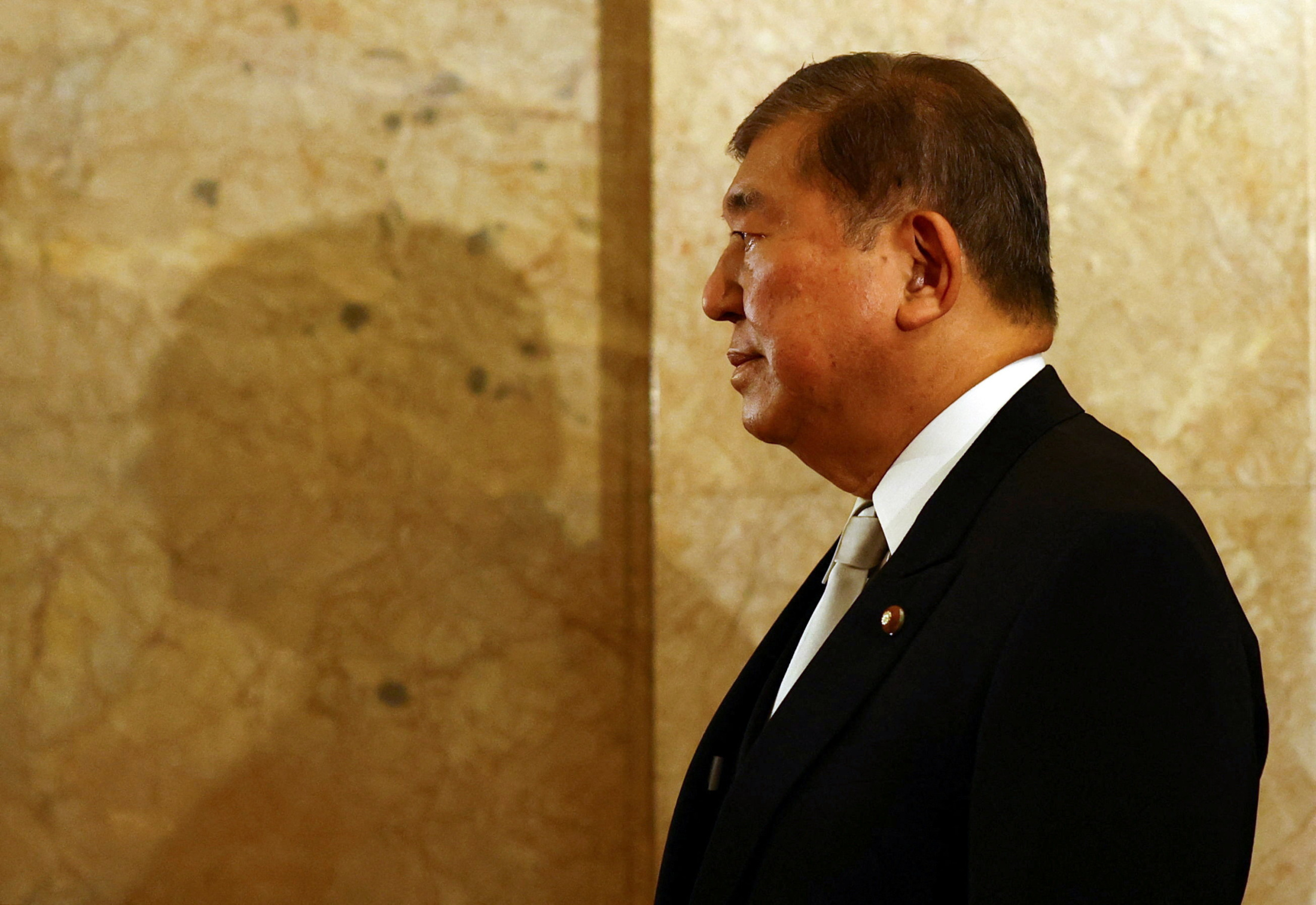気づいたら生まれてた、全長500kmの「巨大クローン海藻」。“クローン故の弱点”を科学者たちが問題視

500kmって東京大阪間の距離やないですか…。
研究者はこれまで、バルト海の小さな茂みのような海藻をNarrow wrackという種だと考えていました。ところが、最新の研究で実は別の種で巨大なクローンだったと判明。その規模は科学史上最大級かもしれないそうですが…科学者たちは心配してる様子です。
全長500kmのクローン海藻
学術誌Molecular Ecologyに発表された研究結果で、ヨーテボリ大学の研究チームがバルト海に500kmにわたって広がる藻類の遺伝子解析を行ないました。その結果、ヒバマタ類(Bladderwrack)の海草であり、しかもこの巨大な海藻がクローンだったことが判明しました。
無性生殖で広がる。通常は有性生殖なのに
今回の研究では、元々のメスの海藻の断片が、北バルト海のボスニア湾の海流に乗って500km以上にわたって広がり、新たなクローン集団を形成していることが確認されました。
通常、ヒバマタはメスとオスのメスの有性生殖で繁殖するのですが、この巨大クローンは無性生殖で広がったようです。
ヨーテボリ大学の海洋科学者であり、研究の遺伝子解析を主導したRicardo Pereyra氏は、大学の声明で次のように述べています。
このクローンは数百万の個体からなり、地域によっては完全に優勢である一方、他の地域では有性生殖による個体とともに生育しています。
バルト海では他にもいくつかの大規模なクローンが見つかっていますが、スウェーデンのボスニア湾沿岸に広がるメスのクローンは圧倒的に最大であり、まさに『リアル・スーパーフィメール』と言えるでしょう。
一気に絶滅したらまずいのでは?
クローンは、無性生殖によって自然に生まれる遺伝的に同一の性質を持つ生物のコピーを指します。クローンは遺伝的多様性がないとも言えます。そう、種の個体群を脅かすような環境の変化に対して脆弱(ぜいじゃく)なんですよね。
この発見は、気候変動などの脅威に対してこの海藻の適応能力や回復力が低下する可能性を示唆しています。ヒバマタは、水面から10mの深さまで広がる大規模な海藻の森を形成し、若い魚や巻き貝、甲殻類、大型魚などが住みついて、海洋生物の重要な生息地になっているのですが。
研究の共同責任者であるヨーテボリ大学の生物学者Kerstin Johannesson氏は、その点について以下のように説明します。
バルト海の海水は、今後さらに温暖化と淡水化が進むと予測されています。こういった新しい環境下では、ヒバマタを含めすべての種が生き残るために適応しなければなりません。特にクローンには遺伝的変異がほとんどなく、環境変化に対応できる個体が存在しないため、結果的に種全体が絶滅するリスクが高くなります。
遺伝的に多様な個体群は、病気やその他の脅威に直面した際、一部の個体が抵抗力を持っている可能性があるため、全滅のリスクが低くなります。しかし、同一の遺伝子を持つクローンの個体群は、病気が発生すると一気に絶滅する可能性があるのです。
この原則は幅広い脅威に適用されますが、ヒバマタが気候変動による脅威にどう対応するのかはまだわかっていません。
研究チームは、ヒバマタに似た別の海藻も見つけましたが、この種は有性生殖だけで繁殖するため、クローンのリスクを回避できているようです。
アメリカはユタ州に生息するポプラの単一生物であるパンドも、今回の研究対象になったヒバマタも、生態系にとって重要な役割を果たしているので、なんとかして生き残ってほしいものです。