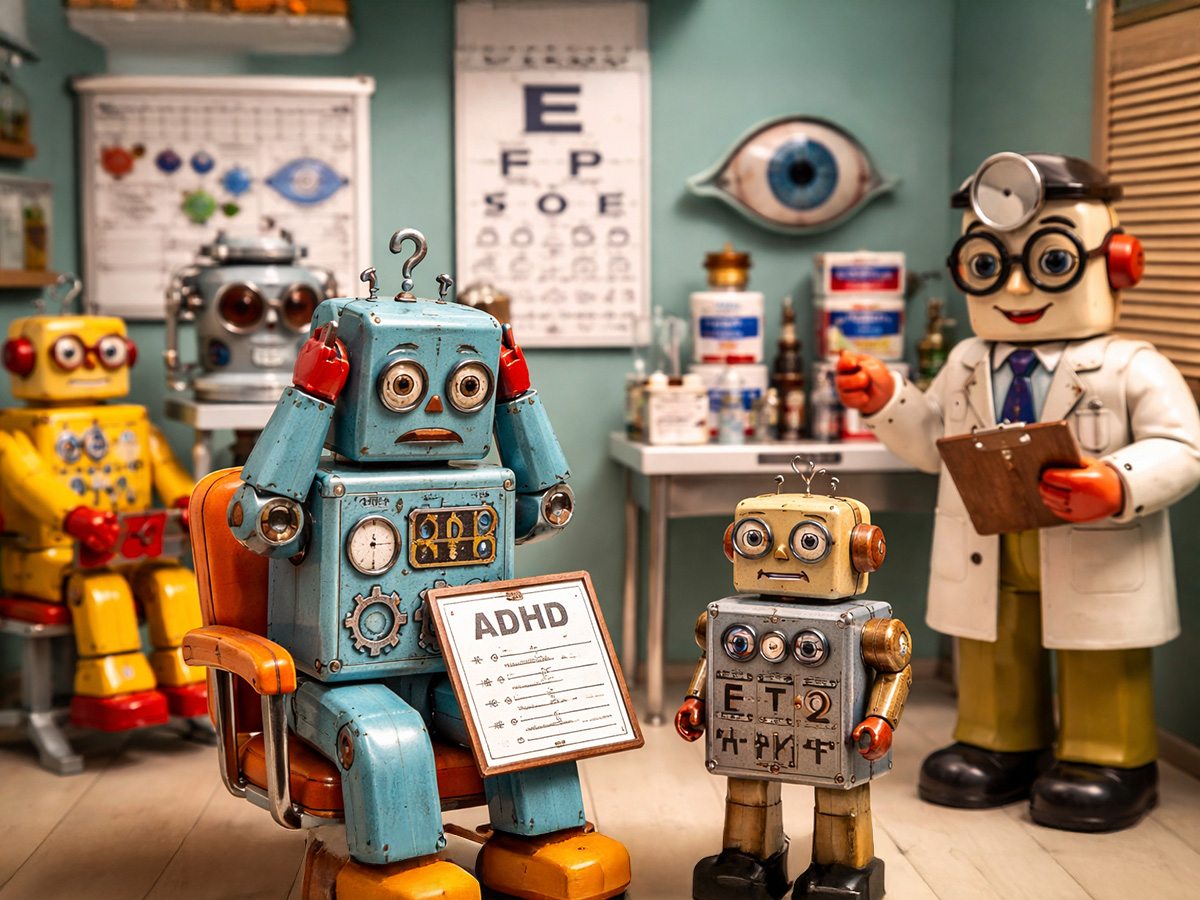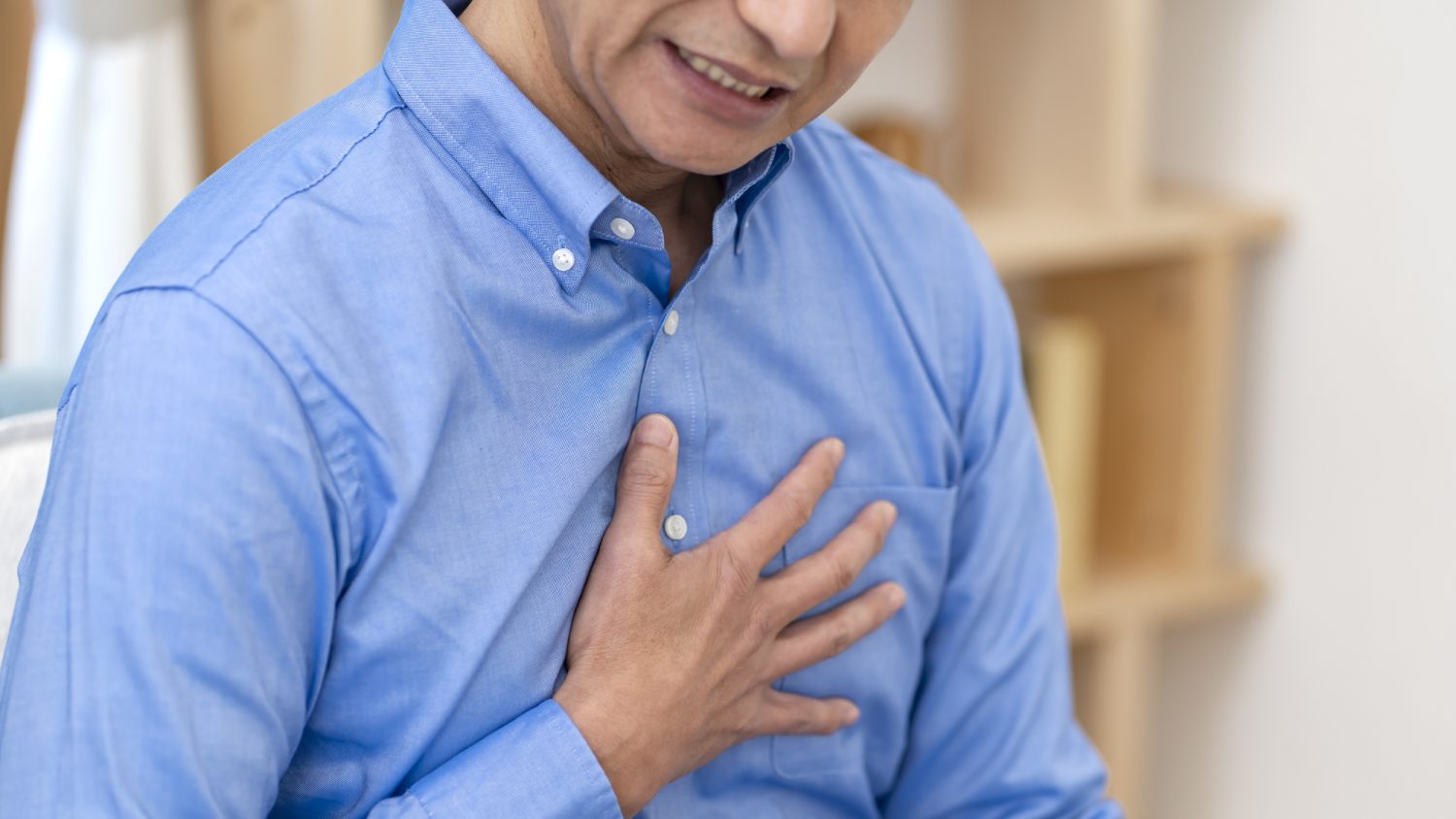"安静にする"が逆効果に…痛み研究の専門家「関節の痛みが"なかなか治らない"医学的な理由」(プレジデントオンライン)

■体は「動かし方」を忘れてしまう もう一つ重要なのは、ずっと動かさない状態でいると(使わない状況が続くと)、動かし方がぎこちなくなったり、ひどい場合はどうやったら動かせるのかわからなくなったりするケースがあることです。 思い返してみると、たとえば小学校の夏休みで全く鉛筆などを使うことなく過ごしたあと、新学期の直前になって鉛筆で文字を書こうとすると、妙にぎこちなくなった覚えがあります。子供の頃に感じたあの感覚の、よりひどい状況と言えるかもしれません。 コンピュータは、機械的な部分のハードウエアと、プログラムなどのソフトウエアとで成り立っていることはご存じのとおりですが、悪質なコンピュータウイルスが入るとハードウエアの部分までが壊されてしまうことがあります。■「怖い」が痛みを長引かせる それと同じように、CRPSももともとは些細なケガですが、「痛い⇔動かさない」がもとで血流が変わり、組織も変容し、骨や関節なども変化してくる、と考えると理解しやすいと思います。 痛いから動かさないという患者さんの反応のおおもとにあるのは「不安」です。怖かったり不安があったりすることで動かさなくなると、手が冷たくなるなどの血流不全にもつながってしまいます。怖さや不安に伴う交感神経系の反応がそれにさらに拍車をかけます。 こうしたことを踏まえると、僕たち医療者が、患者さんへの初期対応として、ただ痛みの要因を取り除くだけでなく、怖い気持ちや不安を取り除いていくことがいかに大切か痛感させられます。まずは不安を除くこと、それが痛み治療の第一歩なのです。 ※1 Akeson, W. H., Amiel, D., Abel, M. F., Garfin, S. R. & Woo, S. L. Effects of immobilization on joints. Clinical Orthopaedics and Related Research 219, 28-37 (1987).※2 Akeson, W. H., Amiel, D. & Woo, S. L. Immobility effects on synovial joints. The pathomechanics of joint contracture. Biorheology 17, 95-110 (1980).※3 Gupta, R. C., Misulis, K. E. & Dettbarn, W. D. Activity dependent characteristics of fast and slow muscle: biochemical and histochemical considerations. Neurochemical Research 14,647-655 (1989).※4 Okamoto, T., Atsuta, Y. & Shimazaki, S. Sensory afferent properties of immobilised or inflamed rat knees during continuous passive movement. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume 81, 171-177 (1999).※5 Ushida, T. & Willis, W. D. Changes in dorsal horn neuronal responses in an experimental wrist contracture model. Journal of Orthopaedic Science 6, 46-52 (2001).※6 Lissek, S. et al. Immobilization impairs tactile perception and shrinks somatosensory cortical maps. Current Biology 19, 837-842 (2009).※7 Terkelsen, A. J., Bach, F. W. & Jensen, T. S. Experimental forearm immobilization in humans induces cold and mechanical hyperalgesia. Anesthesiology 109, 297-307 (2008).----------牛田 享宏(うしだ・たかひろ) 愛知医科大学医学部教授愛知医科大学医学部教授。慢性痛に対し集学的な治療・研究を行なう日本初の施設「愛知医科大学疼痛緩和外科・いたみセンター」で陣頭指揮を執る。1966年生まれ。高知医科大学(現高知大学医学部)を卒業後、テキサス大学客員研究員、ノースウエスタン大学客員研究員などを経て現職。国際疼痛学会の痛みの定義作成メンバーであり、厚生労働研究班の班長として「慢性疼痛治療ガイドライン」を作成するなど日本の痛み治療をリードする存在である。
----------