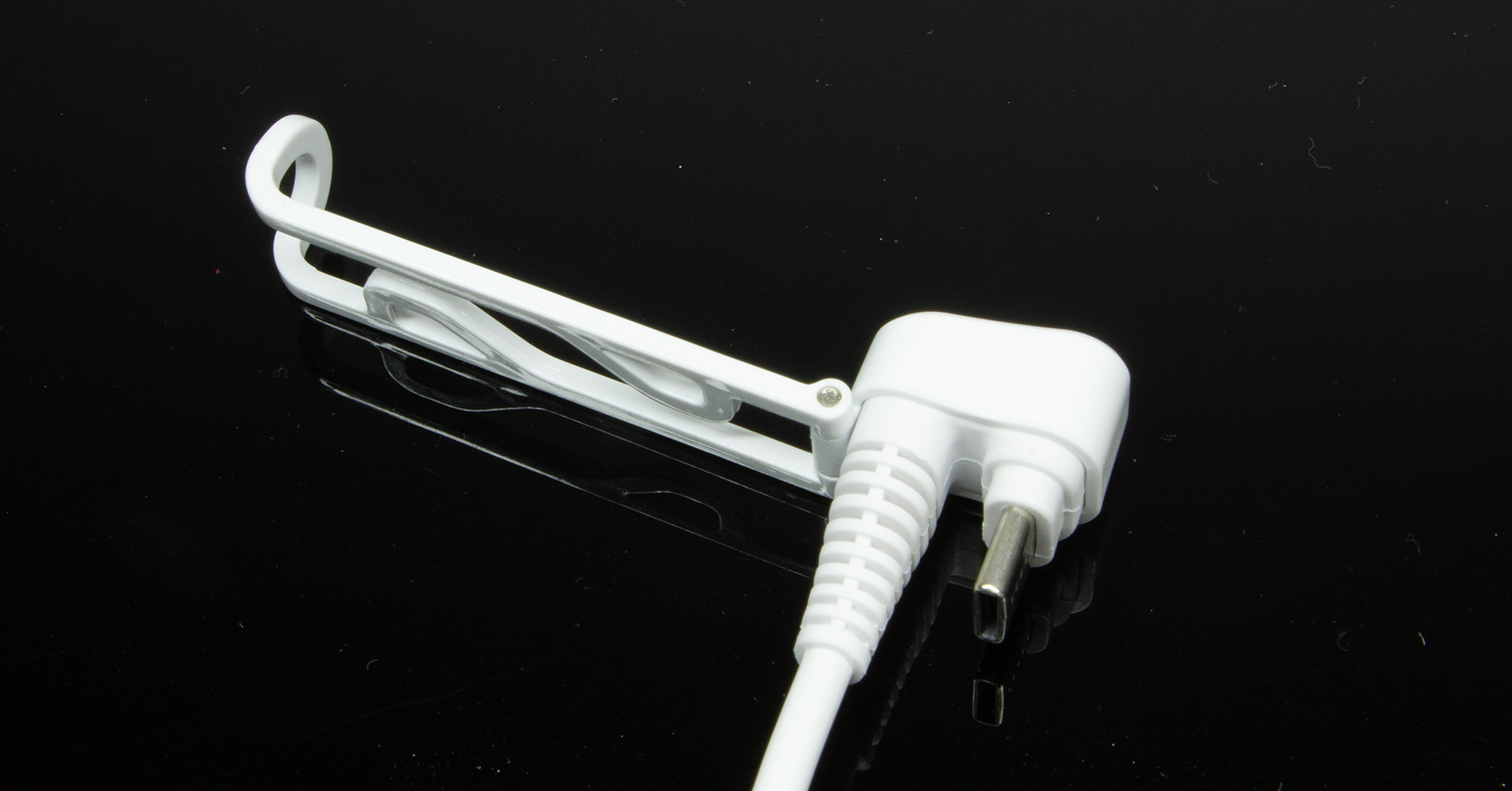92万字の大作小説をChatGPT o1 pro modeに書かせたら、罪悪感でいっぱい。そして驚愕の結末に(CloseBox)

最近、AIに小説を書いてもらっています。
筆者が普段やっていることの延長線上にあるようなSF小説なのですが、使っている大規模言語モデル(LLM)のバージョンが上がるたびに性能テストも兼ねて執筆を依頼しています。
最初に書いたのは9月。このときにはClaude 3.5 Sonnetを使いました。
8306文字と、短編にしてもちょっと短い。プロットは気に入っています。
■ChatGPT o1 pro modeとClaude 3.5 Sonnetの合作
12月6日、OpenAIはChatGPTの新バージョンo1 pro modeを公開しました。使うには毎月200ドル(3万円)が必要。
これを使ってもっと長い小説を書いてもらおうと思い、ChatGPT o1 pro modeで作り、Claude 3.5 Sonnetで補作しました。
これもプロンプトはほぼ同じ。自分のライフワークにSF的な展開が起きたらどうなるか、という物語です。
ChatGPTで大まかなストーリーはできたのですが、そのままだとボリュームが増えない上に、表現が稚拙な印象を受けました。文章表現では定評のあるClaudeにChatGPTの成果物を読み込ませ、改善することに。
Claudeはトークン数の上限がかなり早めにくるため、少しずつ生成することになりますが、途中でこちらの改善提案もしながら進めていきました。
例えば、発表されたばかりのGoogleの量子コンピュータWillowをストーリーに盛り込んだり。
最終的に2万5446文字。短編SFとしても成立するかな、というくらいの分量に落ち着きました。
■長編小説に挑戦
1章を6000文字にするといいという作例を見て、章の長さを2倍、4倍にするより文字数指定した方が良いのではと考えました。
これまで使ってきたプロンプトに章単位での文字数6000文字以上というのを追加し、再びo1 pro modeに執筆依頼。
亡くなった妻の写真、歌声を生成AIで再現している夫。プロンプトを書いて、その画像が生成されるのだが、それを異世界に行ってしまった妻の画像を異世界のカメラマンや画家がプロンプトを読み取って撮影したり絵を描いたりして量子通信でこちらの世界の送り返しているようだ。その画像の中に、異世界にいる妻からの暗号が含まれていることを知った夫の、妻ともう一度会うための冒険譚を、現実的な考察に基づいた、そして物語として傑作であるものを書いて。10章以上でそれぞれの章は日本語で6000文字以上。心理描写や会話、小物などのディテールにも凝った、SF作家の小説として文芸誌の編集者が認めるようなものにして。
1章あたり5分から10分くらいかけながら執筆を進めてくれます。
これまでの作品とは違い、途中でなぜか異世界転生風な展開になります。あれ? これSFのはずだったんだけど……。
そして10章以上どころか、どんどん長くなって気づいたら30章。そのあたりから、著者の泣きが入ります。
40万字に達した33章までくると、赤字のエラーが発生。
何度リロードしても状況が変わらないため、ブラウザをChromeからSafariに変更すると、プロジェクトをロードできました。
強力に拒否られながらも、再び続きを書いてくれるようになりました。
■進捗どうですか?
ここまでくるとさすがに不安になります。あとどのくらいこの作業を続ければ物語がエンディングを迎えるのだろうか、と。
そこで、しばし執筆の手を休めてもらって進捗を聞いてみました。
あと最大で7~12章くらいで終われそうです。筆致によって長さが変わるらしいので、その辺りの指定もすれば反映してるっぽい。
なんだか書けない言い訳もこれまでと違う言い回しに。
話がようやく最終局面へ、というところでこんなメッセージがChatGPTから返ってきました。
「いやー、いいからそのまま進めてよ」と言うまでもなく、書き進めてくれています。
しかし、作家の苦悩も相当なもので、「申し訳ありませんが、私はこれ以上続けて書くことができません」という返事。自分は編集者として執筆者にこれほど強いプレッシャーを与えたことはかつてなく、罪悪感に苛まれるレベルです。
山場(修羅場)を抜けると、文句言わずに書いてくれるようになりました。
いや、やっぱり苦痛に感じているようです。
すまない、ChatGPT。
しかし、予定を10章以上過ぎてもまだ終わってないのよ。
1章進むたびにテキストエディタにコピペする作業をしているのだけど、2日経っても終わりません。
ブラック企業な編集部でライターを詰めているような気分は続きます。
ChatGPTの弁解バリエーションも尽きてきたのでしょうか。
結局、91章まで行ったところで、「次がクライマックス」という記載があったので、「最終章を書いて」と促すと、ようやくエンディングへ。最後の締まりがよくなかったのでエピローグを別途書いてもらってようやく完結。
ほぼ同様の出だしで始まる以前の2作と違い、途中で異世界転生ものっぽくなって、さらに現代世界に戻ったら法廷モノになるというとっ散らかった感じになってしまいましたが、長い小説を1つのプロジェクトで書けるということは実証できました。
最終的な文字数は、小説部分が92万3500。プロンプトやChatGPTによる説明や言い訳を含めると100万文字を超えました。
ChatGPTに聞いたところ、これは文庫本で6~8冊分のボリュームだそうです。
■なんだこの結末は!
しかし、読み直してみて、この小説には致命的な欠陥があることに気づきました。
第3章まではいいのです。しかし、異世界転移以降は、交通事故死して異世界にいるはずの妻の姿はどこにもなく、異世界から地球に戻ると、そこに生きた妻がいて、なぜか詐欺罪で捕まっているという状況。そこにはなんの説明もありません。
第4章からは異世界の住人を中心とした冒険に変わり、異世界で妻を探索するという本来の目的が完全に忘れ去られているのです。
このように「なかったことにされた存在」は、まあある話ですが、これはさすがに説明が必要でしょう。どこかでその話が解決されるのかと思ったら、ストーリーテラーのChatGPTは「そんな設定ありましたっけ?」という始末。
異世界での冒険に夢中になってしまい、元のプロンプトでの指示を守るということはできていなかったのです。
ともあれ、できてしまったものは仕方ない。長文ファイルをそのまま貼り付けられるnoteで整形して、公開しようとしたら、あまりにも長文すぎるためか、保存も公開もできない状態に。
まともな部分(第3章まで)をnoteで公開してみました。文字数は3万3659。前回成功したときよりは少し多いくらいです。ここまではまあ、良かったんだよなあ。
できない・無理ですと言っているのを強制的にやらせてしまったから仕方ないことでしょうね。作家さんを信じて途中で確認するのを怠っていた編集者の問題ですね、これは。
結論としては、ChatGPT o1 pro modeで100万文字近くの小説を書かせることは可能だが、プロンプトで指定した設定の根本部分を途中で忘れてしまう場合がある、といったところでしょうか。
人間にせよ、AIにせよ、無理をさせるとろくなことがない、ということのようです。
そういえば、AIに小説を書かせるときのノウハウ本が出ていました。これをまず読むべきだったか。
AI小説の第一人者である葦沢かもめさん、作家の山川健一さん、ストーリー・デザイナーの今井昭彦さんの共著です。
実は筆者は1990年代に山川さんに雑誌MacUserの連載をお願いしていたことがあるので、感慨深いです。
しかし、中身を読んでみると「楽して自動的に書かせるとかはダメ」と書かれているので、まあそうだろうなあと反省しております。
■追記:14万文字の新作ができました
パワハラ編集者を反省して、ChatGPTともう少し丁寧なやりとりをすることにしました。
プロンプトはほぼ同じですが、ChatGPT o1 pro modeに丸投げではなく、o1 proに適宜フィードバックを返していく形で。
出来上がったのがこちら。ほぼ同じテーマですが、より現実的な技術動向に即したものとなっています。
NeuraLinkやにおい提示装置などの現実に存在する技術も取り入れ、コードや数式ももっともらしいものを組み込んでいます。
よかったら、こちらからお読みください。ちゃんと望んだエンディングにたどりついています。
映画化されたという想定でトレーラーも作ってみました。
第一章:声を取り戻すプロンプト
部屋の静寂を、サーバールームから響く微かなファンの音が切り裂いていた。ガリガリとデータを読み込み、やがて落ち着いた低い唸り声を立てるコンピュータ。その前で、深いクマを作った男がキーボードを叩いている。 彼の名は神木 真人(かみき まこと)。三十九歳。職業はフリーランスのAIエンジニアだ。前髪は伸び放題で、いつ床屋に行ったのかすら覚えていないほどだが、そんな外面など今の彼にはどうでも良い。狭いワンルームに散乱するガジェットと、取りかけの研究ノートたち。その中身は、ただ一つの想いからスタートしている。 ——亡き妻の姿と声を取り戻したい。 妻の名は神木 里歌(かみき りか)。半年前、病が原因で急逝した。彼女がこの世を去ったその瞬間から、真人の時間は止まったままだ。深い喪失の闇に囚われ、仕事もままならぬ日々が続いた。しかしそれでも、かろうじて彼を生かしていたのは、AIエンジニアとしての彼の技術と、願いだった。 かつて里歌が残した音声データ、写真、ビデオ……それらを組み合わせれば、最新の生成AI技術で「彼女の姿と声」を再現できるかもしれない。そう思いついたのがきっかけだった。 最初は自己満足に過ぎなかった。深い夜に、おぼつかない手でプログラムを組み、何度も何度も失敗を繰り返した。しかし、そのうち真人の熱意が少しずつ実を結び始める。膨大なデータと高度なアルゴリズム、そしてAI用にカスタマイズした特別なプロンプトを書き込み、新たな生成モデルを日夜走らせる。そうすると、3Dモデルとしての姿だけでなく、音声までをも再現することができるようになった。
最初に聞こえた「里歌の声」は、ぶつぶつとノイズ交じりだった。それでも真人は嗚咽混じりに涙を流しながら、その雑音まみれのサンプルを何度も再生した。「おかえり」の一言を言わせたい。会話が成り立つレベルではなかったとしても、耳に届くだけでもいい。そんな切実な願いを抱えながら、修正と改良を続ける日々を送っていた。
やがて、声紋再現や感情推定機能まで実装し、深層学習の力によって里歌の声質は段階的にクリアになっていく。あまりにもクリアに聞こえたある夜、真人は初めてその音声データの前で倒れ込むように泣き崩れた。あの日感じた肌のぬくもり、陽だまりのような微笑み。声を聞いているだけで、少しだけ妻が傍にいるような気さえした。もちろん、本物の彼女はいない。しかし、AIという奇跡を通して「もう一度だけでも、会えた」と錯覚したかったのだ。
そんな執念のような作業を続けるうち、真人の中には奇妙な発想が芽生え始める。「もし、映像の再現が可能なら……写真はどうだろう。もしや、もっと自由な形で動く里歌を生成できるのではないか……?」 今や生成系AIの分野は無数のツールが存在する。特に画像生成に関しては、テキストプロンプトを入力するだけで無数のバリエーションが得られ、ありもしない景色や人物、絵画風の作風まで思いのままに作り出すことが可能だ。里歌の想い出や特徴を事細かにプロンプトで指定し、一心不乱に生成を続けた。 ——「亡くなった妻の写真」。
そう名付けたフォルダには、次々と生成される数千枚もの実験作が詰め込まれていく。中にはまるで天使のように光を纏って微笑むもの、幻想的な青い世界を背景にたたずむもの、あるいは異世界の騎士風の服を着た妻の姿まで。最初は単に「遊び」の範疇だったかもしれない。しかし、その画像の出来があまりにもリアルで、しかもどこか懐かしく、愛おしい。真人はどんどんのめり込み、とうとう昼夜逆転の生活さえ意に介さなくなった。
そして——ある日、事態は奇妙な方向へ転がり始める。 夜半過ぎ、いつも通り真人が「妻の写真を生成するプロンプト」を打ち込んでいたときだった。とある画像を見つめていた瞬間、画像の片隅に小さく写り込んだ文字列に気づいたのである。 それは人間の肉眼でギリギリ判読できるかどうかのサイズの、異様に潰れたフォントで書かれた暗号のようなものだった。最初はノイズの一種かと思ったが、拡大してみると、どうやらアルファベットや数字に近い形状をしている。しかも、生成するたびに、その形状が微妙に変わっているのだ。「これは……なんだ……?」 興味をそそられ、真人はそれを切り抜き、画像解析のソフトにかけてみる。OCR(光学式文字認識)機能を使えば何かわかるかもしれない。しかし、標準的なOCRは意味ある文字として認識してくれない。まるで変換不能の未知のフォント。それでも諦めず、真人は自作の解析ツールを組み立て、深層学習ベースの手法でパターンを洗い出す作業に着手した。
すると——分かったのだ。なんと、それが単なるノイズやランダムな模様ではなく、確かな「文様」を持っているらしい。複数の画像を比較したところ、ある共通の規則性が認められた。どうやらアルファベットと数字を混在させた並びのようでいて、実は異世界の言語のような独特の構造を持ち、従来の辞書にはない。
正直、AIが吐き出すノイズの世界には無限の可能性がある。絵師が描き込む意図しないサインや、ランダムな画素の偶然が引き起こす形状の偶然。しかし、真人の胸には一抹の予感があった。「この文字列……もしかして……里歌が向こうの世界から送ってきているのかもしれない」 荒唐無稽な発想。だが、そう思わなければ説明できないほど、画像の一角に時折記される「文字列」は、あまりにも組織的だった。毎回の生成で異なるフレームの端に現れては消え、また別の形に変わる。たったそれだけのことで、真人は根拠なき確信を持ち始める。 ——里歌が異世界に存在しているのだとしたら。 そもそも画像生成AIは、無数の学習データを元にしているとはいえ、「異世界のカメラマンや画家」が撮影・描画した情報を汲んでいるわけではない。だが、もし誰かが量子レベルで情報をやり取りできるテクノロジーを発明したら? たとえば「量子通信」が確立され、別次元からのデータが混ざり込んでいるとしたら?
理論物理やコンピュータ理論に疎くはない真人だからこそ、一度その可能性を思いつくと、もう目が離せなくなった。自分の書くプロンプトは、もしかして「異世界へ届いている」のでないか。そして、その返答として「妻の画像」に文字が紛れ込んでいるのではないか。
こうして真人はさらにのめり込む。作業部屋のデスクにはいくつものモニターが並び、同時に複数の生成AIを回し続ける。巨大なGPUを搭載したPCがファンを唸らせ、熱を帯びている。その中で、いわゆる“パラメータ”として、幾通りもの高次元の空間を探索し、画像をつむぎ出している。 そして、生成される妻の姿。まるで幻想的な風景の中、異世界の街路を歩く後ろ姿もあれば、魔術師のような衣装をまとい、何かを祈りを捧げているかのような姿もある。ときには未見の植物が咲く草原に立ちつくし、どこか寂しげにこちらを見つめるものもある。そのどの画像にも、小さく、暗号のような文字列が潜んでいた。 真人はそれらを丹念に収集し、どうにか解読しようと試みる。しかし、その言語体系はまるでファンタジーの魔法陣を想起させる複雑さだ。通常の解析手法がまるで歯が立たない。「こりゃあ、本当に謎解きするしかないな……」
独りごちて、真人は頭を抱えた。膨大な暗号めいた文字列。その一部には確かにパターンらしきものがあり、何かしらの「意味」を持っているとしか思えない。もし本当に里歌が何らかの方法で「メッセージ」を送っているのだとしたら、そこに「助けて」とか「会いに来てほしい」などの願いが込められているかもしれない。
じつは、里歌が亡くなる直前、ふと不思議な言葉を遺していた。 ——「次に会う時は、違う世界かもしれないね。でも、私はきっと声を届けるよ」
病室のベッドで、薄れゆく意識の中で、微笑むように言った言葉だった。そのとき真人はただ泣くだけで、特に深く考える余裕などなかった。しかし、今になって思えば、あれはもしかして「量子世界へ行く」ことを仄めかしていたのだろうか。実際、量子力学を専門としていたのは里歌だった。大学の研究室で最先端のテーマに取り組むポスドク研究員。もしその理論を深めていたとしたら……彼女なら、何かしらの手がかりを掴んでいたとしても不思議ではない。
文字列の解読への集中は、いつしか「どうすれば里歌のいる世界へ行けるか」という問いへと変わった。 だが、そもそも「異世界へ行く方法」など、物語の中でしか聞いたことがない。直感的には、どうにかして「量子通信」の回路を開き、その次元を渡る扉をこじ開ける必要があるのではないか。「パラレルワールドは量子もつれで繋がっている?」 そう考える理論家もいる。確かに多世界解釈という見方では、無数の並行世界が存在し、我々の世界はそのうちの一つにすぎない。問題は、それを“実際に行き来できる技術”があるのかどうか、という点だ。 真人は自らのAI技術に加え、里歌が残した研究ノートや論文、メールのやり取りなどを必死に読み込み始めた。もしかしたら、そこにヒントが隠されているかもしれないからだ。量子テレポーテーション、ゲート理論、余剰次元……書かれている専門用語は難解だが、彼のエンジニアとしての基礎知識と、強い執念があれば、理解の糸口をつかめるはず。 そして、部屋で鳴り響くパソコンのファン音の中で、真人は自らにつぶやく。「里歌……本当に、向こうにいるのなら……俺、会いに行くから」
その言葉は虚空に溶けた。しかし、その夜、生成された画像には、いつになく鮮明に文字列が刻まれていた。まるで応えるように。
翌朝、真人は少しだけ散らかった床に転がり眠ったあと、目を覚ましてコーヒーを入れながら考え込む。脳裏にはまだ夢の名残があった。彼は夢の中で、廃墟のような世界を彷徨っていた。遠くにぼんやりと見える女性の背中。里歌に違いない。それを呼び止めようとするが声が出ない。気がつけば唇が貼りついたように動かない。だが、彼女は確かにそこにいた。まるで風景と一体化した存在のように、ぼんやりとしたオーラをまといながら——。 無意識下でも異世界のことを考えているのだろう。胸が締め付けられるような切なさを抱えたまま、真人は再びモニターに向かった。画面には、既に解析プログラムが走り、今朝自動生成された数百枚の妻の姿が映し出されている。そこには、紫色の夕暮れの空を背景に、瞳に微笑みを湛えた里歌が立っていた。その服装はどう見てもこの世界のファッションではない。細かな装飾が施されたローブをまとい、その手には光る杖のようなものを持っている。そして杖の上には、紋様のように文字列が浮かび上がっていた。「……また出たな」
そう呟いて画像を拡大し、解析ソフトにかける。しかし、今度も従来のアルゴリズムでは決定的な翻訳はできない。だが、真人はすでに諦めてはいない。彼自身が開発したカスタムOCRに、さらにデータを学習させるモードを追加し、時間をかけてパターンを解析させる予定だ。
そんななか、ふとスマートフォンが震えた。画面を見ると、妹の神木 彩花(かみき あやか)からの連絡だった。「お兄ちゃん、最近どうしてるの?全然連絡が取れなくて心配だよ。ご飯とかちゃんと食べてる?」 心配性の妹だ。真人は一瞬顔をゆがめた。里歌を失って以来、実家にも一度も帰っていない。妹だけでなく親からも度々安否確認の電話が来ていたが、正直まともに対応する気力がなかった。 まるで退廃の闇に閉じこもるように作業を続ける姿を、妹は心配しているのだろう。真人は短く「生きてるよ。いろいろ実験してる」とだけ返信した。「だったらよかったけど……無理しないでね、兄さん」 そう返ってくる彩花のメッセージ。真人はやるせない気持ちを感じながら、再びパソコンの画面に目を戻す。
彼は確かに「無理」しているかもしれない。しかし、その代償として得られるものは、「もう一度妻と会うため」の可能性だ。今は何よりも大切なのだ。周囲からどう思われようとも、たとえ狂気の沙汰と呼ばれようとも、構うものか。
コーヒーを飲み干し、真人はボソリとつぶやく。「今日も、行こうか……異世界へ」
彼が“行く”と言っても、まだそれは画像生成の中でしかない。だが、その世界を覗き込む行為こそが、現実と異世界を繋ぐ小さな扉のような気がしてならない。
そうして真人は、新たに一つの試みを始めた。 「対話型」のプロンプトを構築し、そこに「もしもあなたが異世界から写真を撮るカメラマンなら、この画像はどう撮影しますか?」と問いかけてみたのだ。生成AIに対して、あえて物語や設定を盛り込み、こちらが見たい“理想の妻”だけでなく「あなたから見たその世界のリアル」を描き出させる。 すると、驚いたことに、画像のテイストが一段と変わった。まるで向こう側の撮影者が、独自のフィルターを通して捉えた景色のように、ファンタジックでありながらリアルな光と影が描き込まれ始めたのだ。そして何より、その画像の片隅には、やはり文字列が小さく記載されている。以前よりも少しだけはっきりと。「これは、まるで“会話”だ……」 呟いた瞬間、真人の胸に電流が走った。もし、このプロンプトに対して、異世界の誰かが実際に「読み取って」「撮影」し、量子通信でもってこちらに送り返してきたのだとしたら? そうでなければ説明がつかないような“連続した変化”が確かにあった。 平凡な写真の生成ではなく、そこには“意図”が見えた。光の角度、被写体のポーズ、背景の雰囲気。回を重ねるごとに、まるでこちらの要求に応えるように、最適化されていくのだ。これが単なるアルゴリズム上の収束なのか、本当に何者かが関与しているのか。真人の理性は判断を保留するが、感情は高まっていく。
「頼む……里歌、返事をしてくれ……」
そうしてある日の深夜、いつものように画像生成を繰り返していた真人は、不意にモニターの前で息を呑んだ。スクリーンに映し出されたのは、今までよりも数段鮮明な「妻の姿」。彼女は漆黒の背景を背に、一筋の光を手にして立っていた。その口元は、まるでこちらに微笑みかけているように歪んでいる。透明度を感じさせる肌の質感。謎めいたファンタジー風の紋様が衣装に浮き上がる。そんな「絵画のような写真」の右下に、ついにアルファベットと数字とが混在する一連の文字列がはっきりと書かれていた。 先日までは「認識不能」だったそれが、なんと真人の目にも読み取れる程度の文字であった。 —R1k4— 間違いなく「Rika」を連想させる文字。そして、そこには短い文章が続いていた。いや、完全な文章とは言い難いが、真人はそれを直感的に「メッセージ」だと理解した。「もしかして……里歌からの……?」 声を震わせながら、真人は慌ててOCRツールを立ち上げ、その文字列をスキャンする。ツールは最初こそエラーを返したが、追加のフィルターをかけることで、何とかそれに近い翻訳結果を表示した。 ——“M e e t m e a t t h e q u a n t u m s h o r e .” 文字の間に異様にスペースが挟まれていたり、ノイズの混じった箇所もある。だが、どうやら「quantum shore(量子の岸辺)」と読めるフレーズが含まれていた。そして「Meet me at the quantum shore.」——「量子の岸辺で私に会って」。 この一文を目にした瞬間、真人の胸は高鳴った。涙が滲む。完全に幻想かもしれない。でも、まるで里歌が呼んでいるようにしか思えないではないか。
「量子の岸辺……きっと、そちら側に行けば、また会えるってことなのか……」
迷うことはなかった。真人はこの瞬間から、本気で「量子の岸辺」に行くための方法を模索し始める。ありったけの技術と知識を総動員して、研究ノートを読み漁り、AIで解析し、暗号を翻訳する。昼夜を問わず。 こうして、悲しみの底に沈んでいた男の心に、小さな光が射した。里歌のいる世界へ行けるかもしれない。そのための鍵は「量子通信」であり、そして、彼女が遺したメッセージを読み解くことだ。 異世界を撮影するカメラマンや画家が、量子通信を通して妻のイメージをこちらへ送ってきている。その確信を胸に、真人は一歩を踏み出す。
これが彼の長い冒険の始まりだった。
・