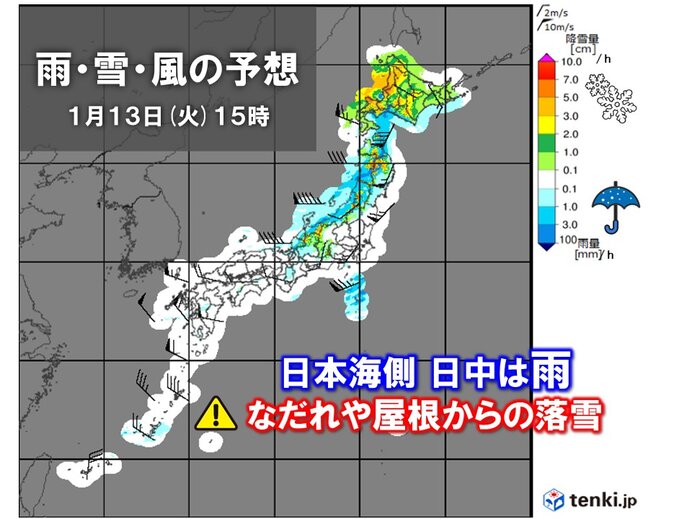宮崎の空自基地でF35垂直着陸訓練案、地元猛反発「話が違う」 : 読売新聞

南西防衛の拠点となる航空自衛隊 新田原(にゅうたばる) 基地(宮崎県)に配備される戦闘機「F35B」を巡り、防衛省の訓練計画に地元が猛反発している。住民への事前説明が不十分だったため、自衛隊の活動に理解を示してきた人たちも不信感を募らせている点が特徴だ。防衛力の抜本的な強化を進める上で、地元に丁寧に説明することの重要性を改めて示した。(溝田拓士、宮崎支局 波多江航)
宮崎の基地 「最小限」→100回
「信頼関係壊した」
「聞いている話と違うとのご意見は、 真摯(しんし) に受けとめる」。12日、新田原基地がある新富町(人口約1万5800人)の役場で開かれた住民説明会で、防衛省の担当者は声を絞り出した。
説明会には住民ら約60人が参加。「初めから新田原でやる考えで、後出しじゃんけんじゃないのか」と厳しい声が上がった。
基地には戦闘機「F15」が長年配備され、町(面積約60平方キロ)のほぼ全域が騒音区域に指定されている。離着陸のたびに 轟音(ごうおん) が響き渡る。
今後配備されるF35Bは、他の航空機のように通常着陸する時は高度約100メートルから約24秒で着地する。だが、垂直着陸の時は高度30メートルからホバリングに切り替えて降下するため約2分かかる。騒音がそのぶん長く続く。
同省は2021年、基地にF35Bを配備する方針を町に伝えた際、「垂直着陸は緊急時などを除いて行わない」と説明。「など」とは「緊急時を想定した必要最小限の訓練」と補足し、鹿児島県・ 馬毛島(まげしま) で整備中の訓練施設が完成すれば「(垂直着陸訓練は)基本的には馬毛島でやる」と強調していた。
こうした説明を受けた住民の間では、垂直着陸は緊急時以外行われないとの認識が広まっていた。
だが、同省が今年2月に示した計画では、月平均の垂直着陸訓練の回数は昼夜合わせて約100回に上っていた。これは、馬毛島の整備が完了する前の29年度の回数で、同島に訓練施設ができた後もパイロットの練度を維持するために、緊急時とは関係がない訓練を含め、約80回は新田原基地で行うことになっていた。
地元区長の一人、高正静夫さん(76)は「最初から垂直着陸訓練をやると言えば反発が大きいと思って、『など』と説明したのではないか。自衛隊を受け入れてきた地元との信頼関係を壊した」と憤る。
昨年8月には、福岡高裁宮崎支部で1審・宮崎地裁判決と同様に騒音の違法性を認めた判決が出た。同町の小嶋崇嗣町長は読売新聞の取材に「どこかの町が負担をしないと国防は保てない」としつつも、「これ以上の騒音は受け入れられない。計画の見直しを求める」と語った。
丁寧な説明必要
安全保障環境が厳しさを増す中で、防衛省は自衛隊施設や装備の拡充と合わせて、訓練も強化している。しかし、同省は過去にも地元との調整でつまずいてきた。
昨年4月、沖縄県うるま市のゴルフ場跡地に陸自訓練場を新設する計画が断念に追い込まれた。地元に説明する前に予算化していたことが「計画ありき」だとして、住民の信用を失った。反対の声は、自衛隊に理解を示していた保守層を含めて県全体に広がった。
訓練場新設は、陸自第15旅団(那覇市)を27年度までに師団へと格上げするのに伴い計画された。新たな候補地は見つかっていない。
20年にも地上配備型の迎撃システム「イージスアショア」の配備計画を撤回せざるを得なくなった。配備候補地だった秋田、山口両県の演習場に関する調査データに誤りが発覚し、秋田での地元説明会では同省職員が居眠りして反発を招いたことも影響した。
中京大の佐道明広教授(防衛政策史)はF35Bを巡る同省の対応について、「当初は住民の反対が起きない表現で進めようとしたのだろうが、将来的な方向性や可能性も可能な限り伝えなければ結局、不信感を生む。自衛隊にとってもマイナスになる」と指摘する。
佐道氏は、防衛力強化には相応の訓練が不可欠だと強調した上で、「自衛隊との共存を受け入れてきた住民の信頼を失わないように、手厚く、丁寧に説明することが極めて重要だ」と語る。
◆ F35B =米英などが共同開発した最新鋭の戦闘機で、レーダーに映りにくいステルス性に優れている。短距離の滑走による離陸と垂直着陸ができ、一部の護衛艦にも搭載できる。防衛省は今年度中に8機を新田原基地に配備予定で、将来的に導入する全42機を同基地に置く方針だ。通常の離着陸をする「F35A」はすでに青森・三沢基地などに配備されている。