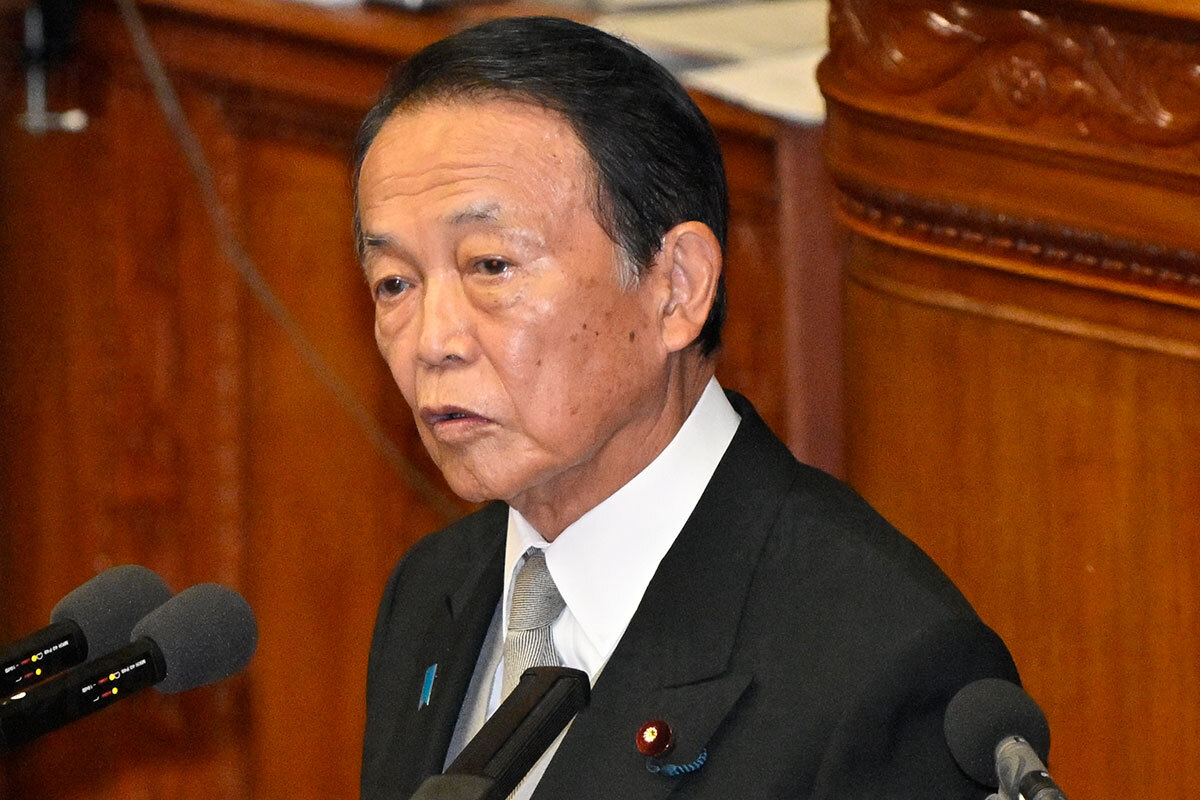「沖縄の住宅はコンクリート造」 長年の傾向に変化が 増えているのは

鉄筋コンクリート(RC)造の建物が並ぶ沖縄の街並みに、変化の兆しが表れている。
亜熱帯に位置する沖縄県では戦後、台風やシロアリの被害を受けにくいRC造の住宅が急速に普及し、長い間主流だったが、近年、新築の着工戸数で木造がRC造を上回る逆転現象が起きている。
民間シンクタンクの「りゅうぎん総合研究所」(那覇市)は3月、「沖縄の住宅市場は大きな転換期を迎えた」とする調査報告をまとめた。
Advertisement「憧れていたしっくいの壁と沖縄らしい赤瓦屋根の家を建てられて満足している。盆や正月に集まる親戚たちからの評判もいい」
沖縄県宜野湾市の自営業、松門安子さん(61)は約10年前、市内の実家を沖縄の伝統的な赤瓦屋根の木造平屋住宅に建て替えた。
老朽化していたRC造の旧家より気密性が高まったため、エアコンの利きが良くなり、近くにある米軍普天間飛行場からの騒音も少し遮断できるようになった。
沖縄本島で最大瞬間風速50メートル超を観測した台風が襲来しても、目立った被害はなかった。木造でも建物の耐久性に「不安はない」という。
りゅうぎん総研の調査報告によると、沖縄県内の戸建て住宅約20万戸(2023年10月現在)のうち、RC造の割合は85%で、木造の8%を大きく上回る。
全国平均では木造が88%で、RC造は5%。沖縄県の傾向のユニークさは際立っている。
だが、新築住宅では木造が年々シェアを拡大している。
年間の着工戸数を構造別に見ると、11年度はRC造が59%、木造が15%だったが、19年度に木造が44%、RC造が39%と逆転。23年度は新築全3516戸のうち木造が49%、RC造は39%だった。
特に建て売りの分譲住宅で木造の増加が顕著で、年間着工戸数は11年度が32戸だったが、23年度は1204戸になった。
りゅうぎん総研は、こうした変化の背景として、地価の高騰や建築費の上昇を挙げる。
沖縄県の住宅地の公示地価は全国平均を大きく上回る上昇率を記録しており、24年の県内の平均価格は全都道府県で9位。福岡県や広島県より高かった。
加えて、人手不足による賃金上昇や建築資材価格の高止まりで、建築単価も上がっている。
RC造の注文(持ち家)住宅の1坪当たりの建築単価は11年度の58・5万円から、23年度は95・8万円と1・6倍に。RC造の分譲住宅(23年度で87・5万円)や木造の注文住宅(23年度で82万円)も上昇している。
住宅取得費用が高騰する中で、相対的に割安感が出ているのが木造の分譲住宅だ。23年度の1坪当たりの建築単価は51・5万円で、この10年余り、ほぼ横ばいで推移している。
なぜ、価格高騰を免れているのか。
りゅうぎん総研によると、木造分譲住宅の多くは、14年ごろから沖縄に相次いで進出した本土資本の大手住宅メーカーが供給している。
メーカーは豊富な資金力でまとまった土地を購入。県外の工場で加工した木材を沖縄に搬入し、現地で組み立てる工法をとり、好立地で価格を抑えた住宅を、短い工期で完成させているという。
埼玉県の住宅メーカー「アイダ設計」もその一つ。14年11月に沖縄に進出し、近年は年間100~120戸の木造分譲住宅を契約者に引き渡している。沖縄の気候に合わせた住宅設計や建築技術の向上に取り組み、シロアリ対策の研究も進めた。
販売担当者は「当初の想定を上回る実績になっている」と手応えを語る。
ただし、一般的に住宅の耐用年数は木造よりRC造が長いとされ、沖縄ではRC造への信頼感も根強い。
りゅうぎん総研の我謝和紀(がじゃかずき)上席研究員は今後の見通しをこう言う。「木造とRC造のせめぎ合いは当面続く」【比嘉洋】