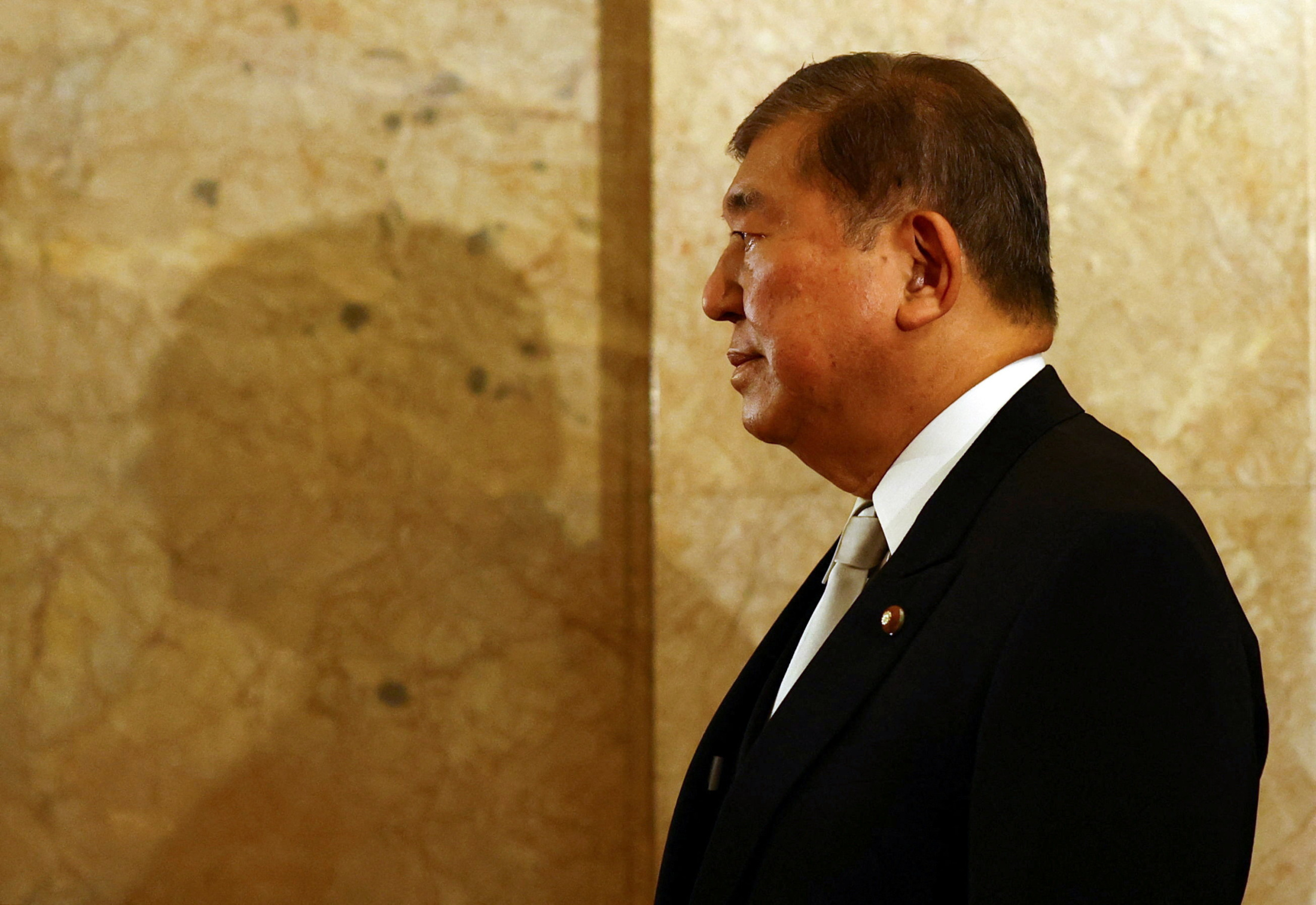オーストラリアの大型動物の絶滅、先住民の狩猟が原因ではなかった? 新研究

太古の豪州大陸に生息していた大型動物たちは約4万6000年前までに軒並み絶滅した/Peter Schouten
(CNN) オーストラリアで見つかった約5万年前のものと推定される二つの化石を最近分析したところ、同国の先住民は大型動物の肉だけでなく化石も重視していたとみられることが分かった。骨を収集し、長い距離を運んでいたことも示唆されるという。
科学者たちは数十年にわたり、大型動物の化石に残る切れ込みの痕を、オーストラリアの先住民による狩猟の証しと捉えてきた。またそうした狩猟は、当該の動物が絶滅に至るまで行われた可能性もあるとされていた。人類が初めてオーストラリアに到達した約6万5000年前、同大陸には、今では姿を消してしまった巨大な動物が生息していた。例えば長い鼻を持つ巨体のハリモグラ、体高約3メートルの、顔が短いカンガルー、ウォンバットに似た牙を持ったサイほどの大きさの有袋類などだ。しかし、約4万6000年前までに、これらの大型動物はすべて姿を消してしまった。
1960年代、科学者たちはオーストラリア南西部のマンモス・ケーブで09年から15年の間に発見されたカンガルーの脛骨(けいこつ)の化石に、人為的な切れ込みの痕を発見した。この痕跡を巡り、当時の研究では先住民が太古の大型動物を大量に殺した証拠だとする見方が打ち出された。
しかし研究者たちは最近、骨の内部構造をスキャンし、新たな解釈を提示した。骨に切れ込みが入ったのは、動物が死んでから長い時間が経過した後、おそらく化石化した後のことだったとみられる。この発見はカンガルーの虐殺を否定し、保存された骨にこそ価値があったことを示唆していると、研究者たちは29日付のロイヤル・ソサイエティー・オープン・サイエンス誌に発表した。
また論文著者らが研究で検証した二つ目の化石、絶滅した巨大ウォンバットの小臼歯は、先住民の化石コレクションに関する新たな手がかりとなった。この有袋類は、オーストラリア南部の化石堆積(たいせき)層ではよく見られるが、北部では知られていない。しかしオーストラリア北部のある先住民の男性は、この歯を樹脂に封入。人間の髪の毛で作った紐(ひも)で結び、お守りとして保管していた。(男性は60年代後半にこのお守りを人類学者に贈ったが、本人がどれくらいの期間このお守りを持っていたのか、またそれがどこで見つかったのかは判然としない)
この歯がオーストラリア北部で発見されたことについて、今回の研究の筆頭著者を務めたマイケル・アーチャー博士は「西オーストラリア州南西部で化石として採取され、その後、海岸沿いにキンバリー地方まで運ばれた可能性が高いと考えられる」と述べている。アーチャー氏はシドニーにあるニューサウスウェールズ大学の教授兼研究者。
大量殺害の証拠無し
アーチャー氏はCNNへのメールで、この歯と脛骨は先住民が「化石収集家」であったことを物語っていると述べた。また、先住民が狩猟によってオーストラリアの大型動物を絶滅させたという長年の仮説にも疑問を投げかけるものだという。この仮説の根拠となる化石の痕跡は、実際には狩猟者ではなく「収集家」によって付けられた可能性があるからだ。
「実際のところ、証拠が示唆するのは、人類とこれらの大型動物が少なくとも1万5000年は共存していたということだ。おそらく気候変動によってこれらの動物が徐々に絶滅するまでは、そのような状況が続いたのだろう」(アーチャー氏)
先住民が骨や貝殻を装飾品もしくは文化財として使用していたことは既に知られている。ニューサウスウェールズ大学の名誉准教授で、考古学者のジュディス・フィールド博士はそう指摘する。同博士は今回の研究には関与していない。
フィールド氏はCNNへの電子メールで、西オーストラリア州沖のバロー島で発見された1万年以上前の貝殻ビーズや、ニッチー湖付近で発見された約7000年前のタスマニアデビルの歯のネックレスなど、いくつかの例を挙げた。
「これらの発見は、人間の行動にまつわる我々の知見と相関する」「人々は物を集め、集めた物を土地の中で移動させる」(フィールド氏)
さらに、「オーストラリア大陸で、大型動物と人間が同時に同じ場所にいたと明確に言えるのは、カディ・スプリングスだけだ」ともフィールド氏は説明。人間は一部の大型動物の種と生活圏が重なってはいたものの、これらの動物の絶滅には人間の狩猟だけでなく、気候変動も要因となった可能性が高いと言い添えた。
骨の内側
80年、アーチャー氏は共同執筆した論文で前出の脛骨の切れ込み痕について、人間が当該の動物を屠殺(とさつ)した証拠であるとの見解を記した。しかし2013年、より高度な化石分析ツールが利用可能となる中、アーチャー氏はこの骨をさらに詳しく調べることで、これまで見過ごされてきた手がかりが見つかるのではないかと考えた。
そこで化石を傷つけることなく内部を観察できるマイクロCTスキャンで当該の脛骨を調べたところ、骨の乾燥時に生じる亀裂の存在から、切れ込み痕が生じたのは骨が化石になった後だったことを示す明確な証拠が見つかったという。
脛骨には複数の縦方向の亀裂があり、化石堆積物となる前に完全に乾燥していたことが分かる。一方、切れ込み痕がある箇所には、横方向の裂け目が確認された。 これは乾燥による亀裂が形成された後に生じたものだ。
「明らかに、(切れ込み痕は)人間がこの動物を殺したり、解体したりした証拠ではない」とアーチャー氏。「この痕は、先住民が好奇心から化石化した骨を収集する試みの一環として生じた。つまり彼らは化石の収集家だった。ちょうど我々と同じような!」
論文著者らは、先住民が大型動物を狩猟しなかったとは主張していない。しかし、先住民が大型動物を絶滅するまで狩猟したという考えは、西洋人の偏見に端を発する公算が大きいと、アーチャー氏はみている。そうした偏見は、オーストラリアの植民地化後に続いて起きた何世紀にもわたる大量絶滅のパターンによって確立したものだ。これらの絶滅はほとんどが欧州人の農業と、外来種の動物の導入によって引き起こされた。
「我々が示唆しているのは、少なくともオーストラリアにおいては、先住民が急速にこの大陸の生態系にとって不可欠な一部となった可能性があるということだ。彼らはこの大陸固有の生物相を尊重し、持続可能な形で利用してきたのであり、持続不可能な農業慣行に関与する外来種ではなかったと思われる。そのような農業慣行は、現在の我々がこの大陸に押し付けているものに他ならない」(アーチャー氏)