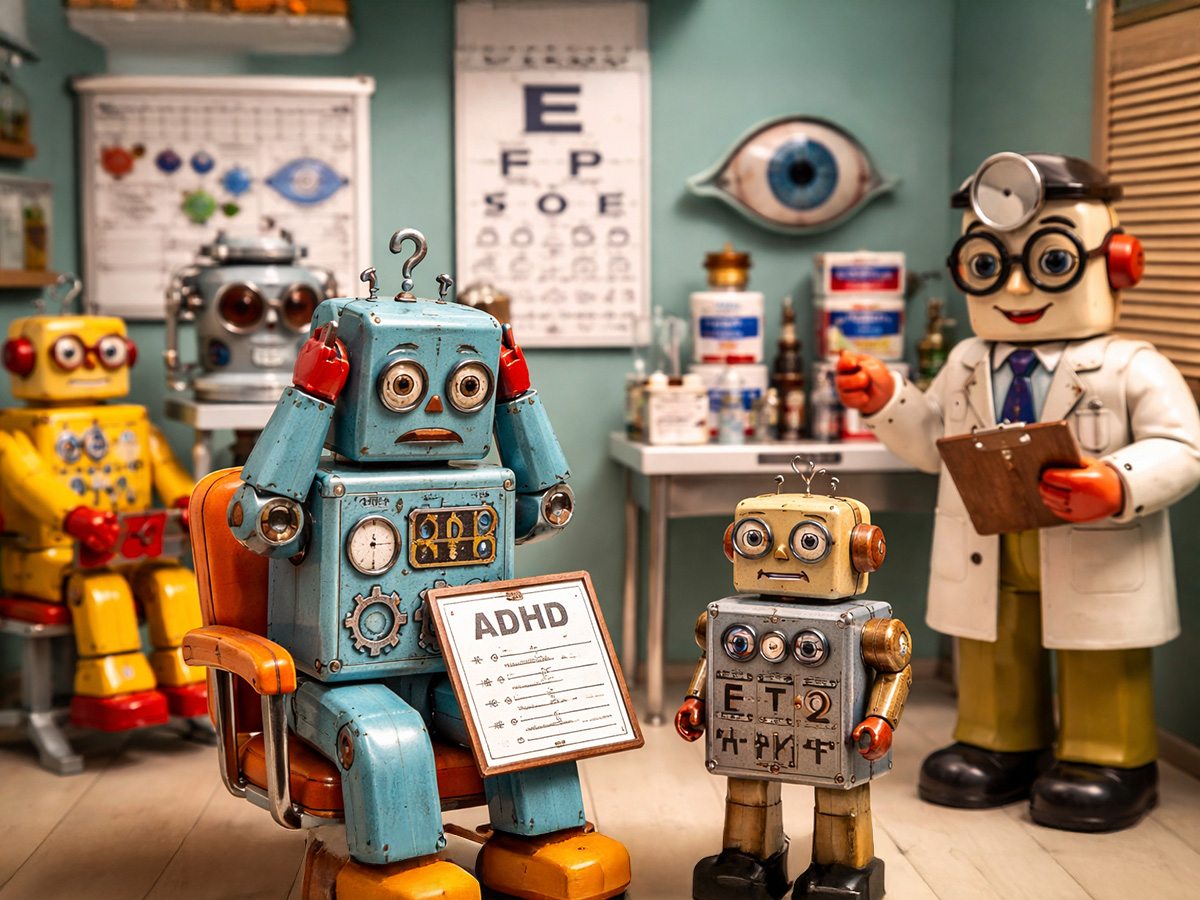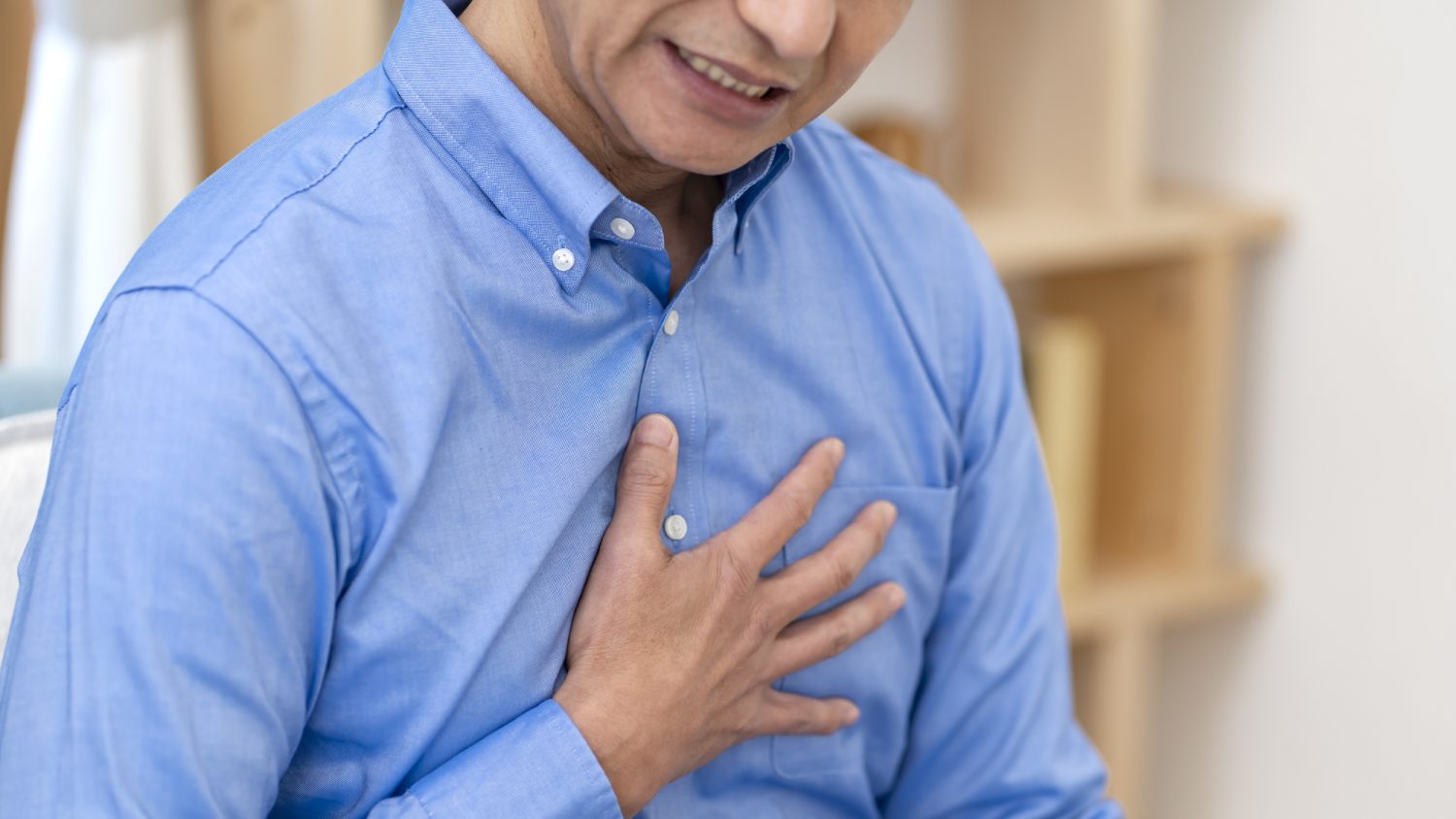「気になる方は、お医者さんに相談を」…現役医師がCMを見て病院に直行する人に知ってほしい

18:16 配信
疾患を啓発するたぐいのテレビ広告をよく見るようになった。東京科学大学医学部臨床教授の木村知医師は「視聴者の健康を純粋に願った公益広告かはなはだ疑問だ。医師の立場から見ると、視聴者の不安をいたずらに喚起しているように見える。慌てて病院に駆け込む前に知っておいてほしいことがある」という――。■「疾患啓発CM」は誰のために 「見逃さないで、MCI(軽度認知障害)」というテレビCMをご覧になったことはあるだろうか。母娘と思われる2人の女性が出演、「それ、さっきも言ってたよ。と、娘にいつも心配される」と母親役の女性の困惑した顔がクローズアップされてはじまる、あれだ。 その後CMは、この母娘のすわる食卓わきに、とつぜん白衣の男性医師が現れる謎の展開となり、「それは、認知症一歩手前の、MCIかも」との言葉に「MCI?」と目を丸くする彼女たちは、次のシーンでは診察室に。画面には「認知機能の低下が気になったら、お医者さんに相談を」というテロップが流される。そして最後、母娘が「見逃さないで、MCI」と笑顔で声をそろえて終わるのだ。 これはいったい何のCMだろうか。MCIという言葉を広く啓発する目的をもった純粋な公益広告なのだろうか。 注意深い方なら、この最後の画面の右下方に医薬品会社のロゴがあることに気づくかもしれない。そう、これは薬剤名こそあきらかに出されてはいないが、疾患の啓発によって医薬品需要を掘り起こす目的もかねたものなのである。■なぜ「薬の名前」を使わないのか 最近、この手のCMは非常に多い。 風吹ジュンさん出演の帯状疱疹の疾患と予防を啓発するCM、「聞いてみませんか? 帯状疱疹のこと」は帯状疱疹ワクチン製剤、藤本美貴さんの出演する新型コロナの早期診断・治療をうながすCMは抗ウイルス薬、といった具合である。 いずれも薬剤の商品名はふせられているものの、結果として、医薬品会社の戦略商品の販売促進につながる仕組みとなっている。 「広告であるにもかかわらず、それが広告であることを隠しておこなう宣伝活動」というと、ステルスマーケティングとの言葉を想起した読者もいるかもしれない。しかし、これらのCMがそうした悪質なものかというと、そこまでは言えない。 CMのなかで薬剤名を明確に宣伝しないことには理由がある。 薬機法(医薬品医療機器等法)によって、特定の医療用医薬品の効能効果を一般消費者に宣伝することが禁じられているからである。
そもそも街場のドラッグストアで消費者の自由意志で購入できる一般医薬品とはことなり、医療用医薬品は、医師が適切な診断のもと適応を判断して投与されるものである。よって、医薬品会社として戦略商品を販促のために宣伝するさいの対象は、一般消費者よりむしろ医師だ。
■医師への直接営業だけではダメなのか 今でこそ規制が厳しくなって禁じられているが、私が新人だった30年前は「販促」のための過剰接待がおこなわれていた。 その彼らの活動が、医師にたいして薬剤にかんする認知度を一定ていど高めたことは、たしかに否めない。だが接待を受けたからといって、医薬品会社の宣伝を鵜呑みに、その薬剤ばかりをめったやたらと濫用することもあり得ない。その薬剤を使おうにも、該当する患者さんが目の前にいないかぎりは使う機会にも遭遇しないからである。 つまり医薬品会社が戦略商品をより多く売りさばくためには、医師に薬剤について知ってもらうだけでは不十分で、投薬の対象となる「患者さん」をより多く医療機関に誘導する必要があるのだ。 そうした中で増えてきたのが、このような「疾患啓発CM」なのである。 医療用医薬品の薬剤名を出してのCMが打てない医薬品会社が、新規薬剤あるいは認知度が高くない疾患にたいする薬剤をひろく多くの人に使わせるためは、まずCMを見る一般視聴者に、こうした薬剤が使われる疾患について興味を持たせる必要がある。■MCIは「認知症一歩手前」なのか 疾患に興味を持たせるのにもっとも有効なのは、「不安」と「疑問」だ。 CMでは疾患の説明はほどほどに、むしろ不安や疑問を呼びさますシーンやセリフが多くつかわれ、「気になる方は、お医者さんに相談を」という殺し文句で、医療機関へ視聴者を誘導する手法がよく用いられる。 私の外来にも、このCMを見て不安になり、認知症検査を希望するとともに、「認知症でも早めに治療すれば治せる新しい薬が出たと聞いたのですが」と、CMが暗に「宣伝」している薬剤の情報を聞きたいと、慌てて親御さんを連れて来られた方もいる。 その薬剤とはレカネマブのことである。 1年半前に上梓した拙著『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』(角川新書)でもすでに取り上げているが、今一度、MCIとレカネマブについて触れておこう。 MCI(Mild Cognitive Impairment)とは、CMでもいわれているように軽度認知障害と訳されるが、これは病名ではなく、あくまで状態(症状)である。またMCIと診断されてもその全員が認知症を発症するわけではなく、正常認知機能にもどる場合があることは、まず知っておくべき重要なことだ。 とくに「年齢が若い」、「認知機能検査の点数が高い」、「社会活動への参加率が高い」といった人は正常にもどりやすいとされている。地域高齢者を対象としたある研究では、追跡期間3〜6年で28.2〜46.5%のMCIの人が正常認知機能に復していたという。[『医師・看護師のための 認知症プライマリケアまるごとガイド 最新知識に基づくステージアプローチ』(中央法規出版)]
こうした知見を踏まえれば、医師役の「認知症一歩手前」という、さもすべてのMCIが認知症になるかのようなセリフは、多くの視聴者を必要以上の不安に陥れかねず、CMで流すものとして適切さを欠いた表現ではないかと私は思う。
■認知症は“薬”で防ぐことができるのか さて一方のレカネマブ、これはいったいどういった薬だろうか。 簡潔に言うと、これは「MCIを治す薬」ではない。そして「MCIから認知症への移行を阻止する薬」でもない。あくまで「進行を遅らせる可能性がある」というものだ。 多くの人が知るアルツハイマー型認知症。この症状を呈するアルツハイマー病患者さんの脳内ではアミロイドβ(Aβ)という異常なタンパク質が蓄積する病理変化が起きていることが知られているが、レカネマブはこのAβを脳から除去する作用をもつ。 疾患の原因に直接働くものとして、従来の認知症の薬とはまったくことなる画期的なものとの期待は高まった。 ただその効果については専門家のあいだでも議論がある。 第III相試験(新薬開発における最終段階の臨床試験)では、脳内のAβが画像上減少し、認知機能の低下を統計学的有意に抑制する効果(進行抑制率27%)が示された。しかしこれはあくまで集団としてであり「個々の被検者レベルでAβ減少量と症状の改善度合いが直接相関すること」を明確に示したものではない。患者さんが日常生活で体感できるほどの明確な改善とは言えないと指摘する専門家もいる。 認知症というと、本人だけでなく介護者となる家族の負担について心配される人も多いと思うが、先述したようにレカネマブはMCIから認知症への移行を阻止するものではないため、将来的な介護費用を削減し得るかという点にも疑問が残る。■1人当たり年間約300万円という薬価 じっさい、薬価を検討する厚生労働大臣の諮問機関中医協=中央社会保険医療協議会では、レカネマブの1人当たり年間約300万円という薬価は、費用対効果から「高すぎる」と判断され、2025年11月1日から15%もの引き下げが決まった。これは医薬品の薬価引き下げ率としては過去最大だ。 それでも高いことに変わりないが高額療養費制度が適用されるため、個人負担は限定的ではある。だが当事者の負担は薬剤費のみに止まるものではない。治療は2週間に一度、約1時間をかけた点滴投与であり、これを1年半続ける必要があるからだ。しかも一般の診療所では治療できないため、治療可能な医療機関にアクセスしにくい人には通院の負担ものしかかる。
また副作用として、投与開始早期に見られる嘔吐、発熱、頭痛などのほか、脳内から蓄積していたAβが減少する「効果」によって脳浮腫や脳微小出血(アミロイド関連画像異常)が生じる可能性も指摘されており、これらの早期発見のため定期的なMRI検査を要すること、そしてこれら脳に生じる変化でむしろ認知症が誘発されるのではないかと懸念する医師もいることも知っておきたい。
■処方までには複数の高いハードルが さてこれらを踏まえても、「やっぱりMCIが心配だから、もし新しい治療薬があるのなら使って欲しい」と思ってしまった人はどうすればよいだろうか? もちろん、CMがうながしているように、まずかかりつけ医に相談してみるのがもっとも手っ取り早い。だがここまで私が書いてきたような、ごくごく基本的な情報さえも説明できる医師は巷に多くないかもしれない。 おそらく簡単な認知機能検査をおこなったうえで、認知症専門医のいる医療機関に紹介されることになるだろう。専門医療機関ではこの薬剤の適応があるかを決定するために脳内にAβが蓄積しているかの画像検査等をおこない、そのうえで、じっさいに投与が適切であるかを個々の患者さんのさまざまな背景を踏まえて慎重に判断され、十分な説明と同意のもと投与へと進む、というステップを踏んでいくことになる。 30秒ていどのCMを見るだけでは、不安や疑問だけが増幅され「早く医師に相談して薬でももらわないと認知症になってしまう……!」と焦ってしまう人もいるだろうが、じっさいには薬で認知症が止められるという事実はなく、さらに、医師に頼めばすぐに治療薬が処方されるというわけでもない。かなり高いハードルがいくつもあるのだ。■新たに増える医療費は無視してよいのか 国全体の医療費の問題も考える必要がある。 先の参院選でも社会保障費圧縮、医療費削減を主張する政党が躍進した。関心を持っている読者もいるかと思うので、この薬剤が医療費高騰に影響をおよぼす可能性についても指摘しておこう。 当然ながらこの治療の適応となる人が何人で、そのうち何人が治療を希望し、じっさい治療される人が何人かという見積もりは非常に困難だが、それを踏まえたうえで、少なめの前提でザックリ計算してみた。 MCIの人は厚労省の2022年推計で約559万人、先ほど示したように約半数が正常に復するとの前提でまず約280万人を候補とする。MCIのうちアルツハイマーが原因と推測されるのが約5〜6割とされるので、さらに半数として対象者は140万人にしぼられる。このうちレカネマブ治療をじっさいに受ける人が何%かはわからないが、かりに1%と過小に見積もると1.4万人だ。(ちなみに、中医協の資料によれば、ピークとなる2031年度で使用者数が約3.2万人と推計されている) 一方、レカネマブの薬剤費に定期的なMRI検査、そのほかの診療費を加味すると、医療費は月額約33万円。これを70歳未満で一般的な所得の人の高額療養費制度を適用させて計算すると、自己負担の月額は約8万円あまり。つまり残りの25万円が公費による負担となる。
すなわち1人当たりの年間公費負担は約300万円となることから、レカネマブだけで年間420億円(約300万円×1.4万人)かかることになる試算だ。もちろん不確定要素が多々含まれるゆえ、けっして鵜呑みにしないでほしいが、医薬品会社の推計よりかなり少なく見積もってもこれだけかかる。ざっくりではあるが、規模感のイメージを持っていても悪くなかろう。
■薬よりもまず先に優先すべきこと いかなるものごとにも優先順位がある。 高額療養費制度の見直しが政府から出されて、少なくない患者さんが、治療を断念しなければならない恐怖に陥れられた問題を覚えている方もいるだろう。いったんは見送りとなったが、また秋以降に議論が再燃することも予想される。レカネマブは果たして優先されるべき薬剤だろうか。 CMによるMCIの「啓発」自体に問題はないし、多くの人が興味を持つことは大切とは思う。ただ一方で、MCIを「早めに見つけて薬で治さねばいけない病気」のように思わせ、いたずらに不安を煽り必要以上に医療需要を誘発するものであるならば、個人にも公益にも利をもたらさないと言わざるを得ない。 CMを見て相談に訪れた人に対応する「お医者さん」も、医薬品会社の販促資料を鵜呑みにした説明に偏ることなく、薬に過剰な期待を寄せるよりは日々の健康管理や社会的交流の維持、社会活動への参加といったものの方が重要であるとの説明をすべきだろう。 今後もこうした「疾患啓発CM」を目にする機会が増えるだろうが、見ても慌てず、その“真の目的”を冷静に見定めることも、視聴者に求められるリテラシーといえるだろう。そして説明はほどほどに新薬をやたらに勧める医師にも気をつけたい。 視聴者がCMリテラシーを身につけ、利益相反のない医師を見抜くスキルを積んでしまうのは、販促にコストをかけた医薬品会社にすれば、はなはだ迷惑だろうけれども。----------木村 知(きむら・とも)医師/東京科学大学医学部臨床教授1968年生まれ。医師。東京科学大学医学部臨床教授。在宅医療を中心に、多くの患者の診療、看取りをおこないつつ、医学部生・研修医の臨床教育指導にも従事、後進の育成も手掛けている。医療者ならではの視点で、時事問題、政治問題についても積極的に発信。新聞・週刊誌にも多数のコメントを提供している。著書に『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』(いずれも角川新書)など。
----------
プレジデントオンライン
最終更新:9/3(水) 18:16