公開講座2024(後期)「粒子を冷やすってどういうこと?」を開催しました
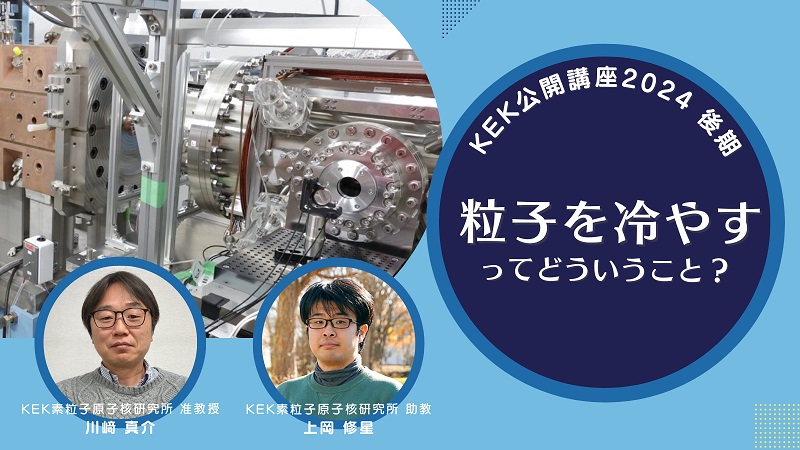
KEKでは研究で蓄積された知⾒や加速器科学について⼀般の⽅に広く紹介し、興味や関⼼を持っていただく⽬的で公開講座を開催しています。2024年度後期の公開講座は11⽉23⽇にKEKつくばキャンパスで開かれました。今回のテーマは「粒子を冷やすってどういうこと?」。KEKは粒子を光速近くまで加速していろいろな研究をしていますが、実は「冷やす」ことも大切だったりします。茨城県東海村のJ-PARCとカナダのTRIUMF研究所をベースに、粒子を冷やすことで極めて精密な測定に挑む2人の研究者が話しました。約52人の来場者が熱心に聴き入りました。
川﨑准教授は、絶対零度近くまで冷やした中性子をじっくり観察し、その性質を調べる実験の話をしました。
川﨑准教授はまず「冷やす」ということはどういうことか説明しました。温度とは物質が持っている運動エネルギーのことで、気体は粒子の運動が激しく、冷やすにつれてその運動が鈍くなっていきます。固体になってもさらに冷やしていくと、運動が止まってしまいます。その温度を0度としたのが「絶対温度」です。つまり、粒子を「冷やす」ということは運動エネルギーを減らすことだといいます。
川﨑准教授が扱うのは冷やした「中性子」です。中性子のビームは原子炉や加速器で作ることができますがその温度は100万ケルビンから10億ケルビンもあります。中性子そのものを知るには、中性子の動きを止めること、すなわち極限まで冷やす必要があるのです。
次に川﨑准教授は、中性子を冷やす方法について説明しました。まず水素の同位体である重水素を含む水(重水)の中に中性子を通し、液体重水素でも冷やします。これで液体重水素の温度である20ケルビンまで冷やします。
中性子をこれ以上冷やすには川﨑准教授は二つ方法があると説明しました。一つは移動できる壁を持つ容器を使う方法です。壁に中性子がぶつかるときに、同じ方向に壁を少し動かすと中性子の勢いを止められます。ボールの勢いをうまく殺して止める野球のバントと同じ要領です。二つ目は、スーパーサーマル法と言い、中性子のエネルギーを振動のエネルギーとして逃がす方法です。すると、ほとんど絶対0度である3ミリケルビンまで冷えた「超冷中性子」ができます。速さにすると約秒速5メートルまで冷えています。
超冷中性子を使って行われている実験として、中性子の寿命の測定と中性子の電気双極子モーメントの測定を紹介しました。特に中性子の電気双極子モーメントの測定について川﨑准教授は自身が参加している、カナダのTRIUMF研究所での「TUCAN」という国際共同実験について紹介しました。
電気双極子モーメントは、電荷の偏りを表す物理量です。中性子全体としては電気的に中性なのですが、実は内部ではプラスとマイナスの電荷の偏りがあるかもしれません。。ゼロでない有限の値の電気双極子モーメントが中性子にあると「CP対称性」が破れている証拠になります。宇宙が誕生した直後は、通常の物質とその反物質が同じ量あったと考えられていますが、今の宇宙には物質しかありません。反物質はどこかに行って消えてしまって物質優勢の宇宙ができたのですが、その背景にあると考えられているのが「CP対称性の破れ」です。
しかし、その全貌はいまだに分かっていません。そこで川﨑准教授らはCP対称性の破れを中性子を使って追いかけているのです。「中性子の電気双極子モーメント探しは70年前から始まっていて、実験感度は6桁向上していますが、まだ見つかっていません。現在の観測値は、スイスのPSIという研究所で測ったもので、『誤差の範囲でゼロ、上限値が1.8×10のマイナス26乗』というものです。大きさ10のマイナス13乗センチメートルの中性子を、地球と同じサイズまで大きくしたとして、電子と陽電子が1マイクロメートル離れているということを意味します。そんなすごい精度の実験をしているのです」とその難しさを語りました。
上岡助教は世界で初めて素粒子ミューオンを冷却し、ビームの品質を高めることに成功したチームの一員です。
上岡助教は「冷やす」という言葉を川﨑准教授が説明した意味と異なった意味で使っているということから説明をはじめました。川﨑准教授は「粒子を止める」ことを冷やすと呼んでいましたが、上岡助教は「ビームを同じ方向に揃え絞る」ことだと言います。ビームとは、粒子が固まりになったもののことです。上岡助教はビームの品質を懐中電灯とレーザーポインターで例えました。懐中電灯の光は広がっていてばらつきが大きい一方、レーザーポインターは一点を指すことができます。懐中電灯の光のようなビームではビームの中の粒子がバラバラに動いていて、温度が高いことに対応します。レーザーポインターのように、同じ方向に絞ったビームを出すことが、冷却にあたります。ビームがよく揃っていると精密な測定ができます。それが「ビームの品質をよくする」という意味です。
ミューオンは、それ以上分けられない粒子である素粒子の一種です。ミューオンは1秒間に手のひらに1個程度降ってきていますが、実験のためには人工的にミューオンをビームとしてつくる必要があります。まず加速器で陽子のビームを作り、炭素などの標的にぶつけます。するとパイ中間子という粒子が飛び出しますが、一瞬でミューオンに崩壊します。今は1秒間に1億個のミューオンを作れるようになっています。しかし、そのようにして作ったミューオンは品質が良くありません。それは、崩壊し散らばったミューオンを電磁石でかき集めているからです。ビームの品質の悪さが実験の可能性を制限しています。
冷やして高品質になったビームがあれば、それを使っていろいろな実験ができるようになります。その一つが、ミューオンの異常磁気モーメントの精密測定です。異常磁気モーメントとは、素粒子がどれくらい磁場と反応するかという量です。素粒子物理学者は「宇宙の最小単位が何で、それらはどういう法則に従っているのか」という宇宙の仕組みを明らかにしようとしており、これまでの集大成として「標準理論」があります。しかしまだ完全ではありません。異常磁気モーメントは標準模型で正確に計算できるのですが、アメリカのグループなどが実験で測定した結果が理論計算と合わず、このずれが本当なのか、気づいていない誤差があるのか確かめる必要があります。
そのあと、上岡助教はどのようにミューオンをどうやって冷やすか説明しました。冷却の難しい点は、ミューオンが崩壊する前に大急ぎで冷やす必要があることだと言います。上岡助教はエアロゲルという物質を使う独自の方法を開発していますエアロゲルにミューオンビームを打ち込むと、ミューオンが電子を獲得しミュオニウムという粒子になります。ミュオニウムは電気的に中性ですが、適した波長のレーザーを当てると電子を引きはがすことができ、プラスの電気のミューオンになります。出てくるミューオンは元のミューオン1000個当たりに1個程度と数は減りますがビーム品質は著しく向上します。
川﨑准教授が扱うのは「超冷」中性子ですが、このミューオンは「超低速」と呼ばれます。ミューオンの速度は毎秒5キロメートルと、感覚的には速いですが、光速の世界から比べるととてもゆっくりなのです。
最後に実験結果と今後の展望を語りました。上岡助教のグループは加速器の後ろに検出器を置き、レーザーを調整し、加速器も動いているときのミューオンの信号を観測しました。これが世界初の、冷却後に加速されたミューオンの信号です。個数は20秒に1個程度ですが、ミューオン冷却の原理を実証できました。ビームの質も数百倍よくなっていることが分かったと言います。
「最終的に光速の94パーセントまで加速したいので、専用の加速器を設計中です。また電子を引きはがす強力なレーザーも開発中で、1秒間に10万個の冷やしミューオン生産を目指して開発を続けています。2029年ごろから、異常磁気モーメントの精密測定をしたいと思っています」と意気込みを語りました。



