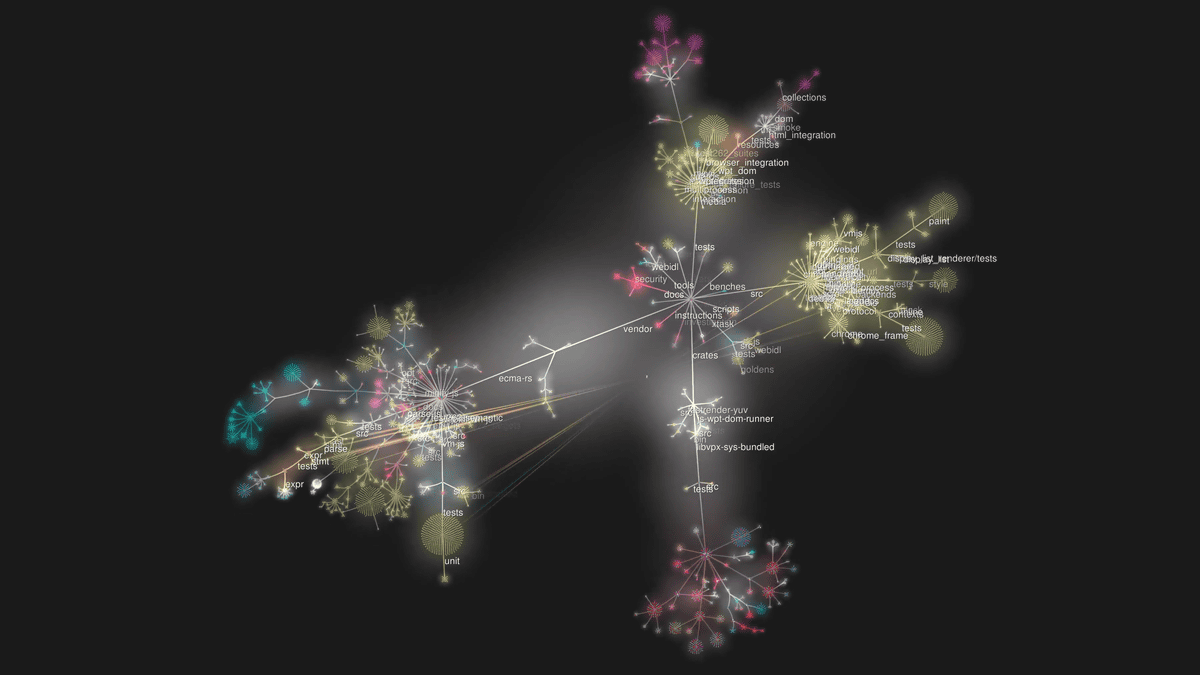「法的に規制するのも難しい」転売ヤーはなぜ消えない? 法律では防げない現実と任天堂の販売戦略

任天堂から家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」がいよいよ6月5日に発売される。次世代機の登場は、ゲーム業界でも大きな注目を浴びている。しかし、人気商品であるがゆえに避けて通れないのが“転売問題”だ。実際、発売前には応募条件が話題を呼ぶ抽選販売が実施された。企業はブランド価値を守り、ファンの信頼を損なわないために、どのような販売戦略を講じるべきなのか。また、転売行為がなくならない背景には何があるのか。転売問題に詳しい経営コンサルタントの諸勝文氏に話を聞いた。 【写真】「すごい高額にびっくり…」 ゲーム機だけではない、ファンを激怒させた高額転売の実際の出品画像 「Nintendo Switch 2」は日本語・国内専用が4万9980円(税込み)、多言語対応が6万9980円(同)。抽選販売では、他の製品とは一線を画す厳しい応募条件が設けられた。 ・2025年2月28日時点で、Nintendo Switchソフトのプレイ時間が50時間以上(体験版・無料ソフト除く) ・応募時点でNintendo Switch Onlineに累計1年以上加入していること ・ファミリープラン加入者の場合は利用券の購入者のみが上記条件を満たす対象 ・ニンテンドーアカウントの国設定が日本のユーザー限定 といった、かなり具体的な基準が求められた。 こうした条件は転売防止の狙いがあり、ネット上では「応募条件素晴らしい」と称賛する声がある一方、「プレイ時間が足りず応募できなかった」「Nintendo Onlineの加入期間が不足していて絶望」といった落胆の声も上がった。応募受付は4月17日午前11時で締め切られたが、任天堂は早くも第2回抽選販売を発表した。 任天堂の転売対策について経営コンサルタントの諸氏は次のように分析している。 「任天堂が“実際のユーザー”に対して直接販売することをかなり重視しているなと感じています。また、ユーザーに対して安く販売したいというのが、任天堂の戦略になってきているのかなと。このNintendo Switch 2を1つのプラットフォームにして、後からサードパーティー(当事者ではない第三者)が入りやすくなるとか、追加の課金機能を入れるとか、そういったものを将来的に入れていく予定なのか、もしくは文化的な発信源というものを抑えたいのかというところの狙いを感じました」 応募の窓口を狭くし、初回購入者のターゲットをコアユーザーに絞る一方で、価格はある程度、抑える配慮を見せた。そこから順次、機能等を拡大していく戦略が透けてみえるという。 Nintendo Switchでのプレイ経験を条件にしているため、転売目的の応募はシャットアウトされる。同時に、まったくの新規ユーザーも除外されることになり、転売撲滅を目指す任天堂の本気度がうかがえる対策となった。 「転売で価格を吊り上げようとする人を、どのようにして見極めるのかがすごく難しい話になってきますので、最初はそのNintendo SwitchからSwitch 2への切り替えを図っていくということを優先したという感じなんでしょう。ある程度、市場に出回って、先行して高値でも買いたいという人がいなくなってから、そういう条件が解除されてくるのかなと思います。今回、任天堂の場合はSwitch 2の販売にあたっては、基本的には既存ユーザーで、スノビッシュ(他人を見下すような態度や行動をする)なユーザーというのをターゲットにはしたくないと。実際にプレイするユーザーが欲しいという、そのメッセージを強く出したということになりますね」 任天堂がここまで規制したのは、メーカーと小売業者の関係も影響していると諸氏は指摘する。 現代では、メーカーが小売業者に対して販売価格を指示し、その価格を守らせる行為は法律で禁じられている。つまり、小売業者は仕入れた商品をいくらで販売しても自由。そのため、転売目的で商品を狙う人たちが市場に集まりやすくなっている構造があるという。 特に、話題の新製品には「持っているということに価値を感じる人」が一定数存在する。 「そういう人はお金をどれだけ払ってでも新製品を買いたいという考えを持っています。通常の流通のやり方をしていると、生産量が確保できない限りは、転売を通じて値段がどうしても上がってしまうということが確実に言えますので、そこをどういうふうにコントロールするんですか、という話になるわけです」 諸氏によると、転売ヤーの多くは「フラッシュ型」のビジネスを行っている。これは、短期間で素早く利益を上げるため一時的な商売をすることで、需要によって“仕入れ”の対象は異なる。 例えばコロナ禍の際には、マスクの転売が顕著に見られた。 「事業主さんが、手早く中国からマスクを仕入れて、高値で売ってたというのがあります。安倍(晋三)さんが『アベノマスク出す』と言ったあたりから、緊急事態宣言明けの大阪歩いてみたら、心斎橋の路上とかでホストクラブに勤めているような格好した人がマスクを売っているんですよ。ビジネス上の反射神経の強い人がフラッシュで動いて、売り切って終わりという商売になっているんですよね」 こうした転売行為は、アイドルコンサートのチケットやディズニーランドのグッズなど幅広い分野で行われている。共通する点は、希少性の高さだ。販売側がいくら対策を講じても、潜在ニーズが高いため、なかなか効果を上げているとは言いにくい現状がある。 さかのぼれば、1980年代には、ファミコンのゲームソフトが転売のターゲットになっていた。当時はネットもなく、“売買”の中心となったのはゲームソフト店。人気ソフトを大量に買い占めた上で、市場の流通を絞り、価格をつり上げる商法が横行した。さらに、不人気ソフトと抱き合わせて販売する手法も当たり前に行われた。「抱き合わせ販売」は法律上問題があったものの、当時は黙認されていた背景があった。 「結局、手に入れたい人の『払ってもいいな』という値段とメーカーが出している値段に差がある限りは、そこに必ず転売の余地が発生して、誰かがやるんですよね。それを法的に規制するのも難しいです。一旦手に入れたものを自由に売ってはいけないという法律というのは基本的にはできない。それはあくまで私的な契約の中では可能ですけれども、法的に何かそういうことを整備することはできません」 企業にとっては頭の痛い問題だが、今回の任天堂が示した転売対策は一つの模範になりそうだ。また、ほかにも諸氏は一案として「ダッチオークション」と呼ばれる方法の導入を提案。これは、商品の価格を高く設定しておき、徐々に下げながら購入者を募る方式で、最初はどうしても割高になることから、転売目的の大量購入者にとってはリスクが高くなるという。 いずれにせよ、人気商品を巡る転売問題は一朝一夕で解決するものではない。企業側の知恵と工夫、そしてユーザーのモラル意識の両輪が持続可能な市場環境をつくる鍵になるだろう。
ENCOUNT編集部/クロスメディアチーム