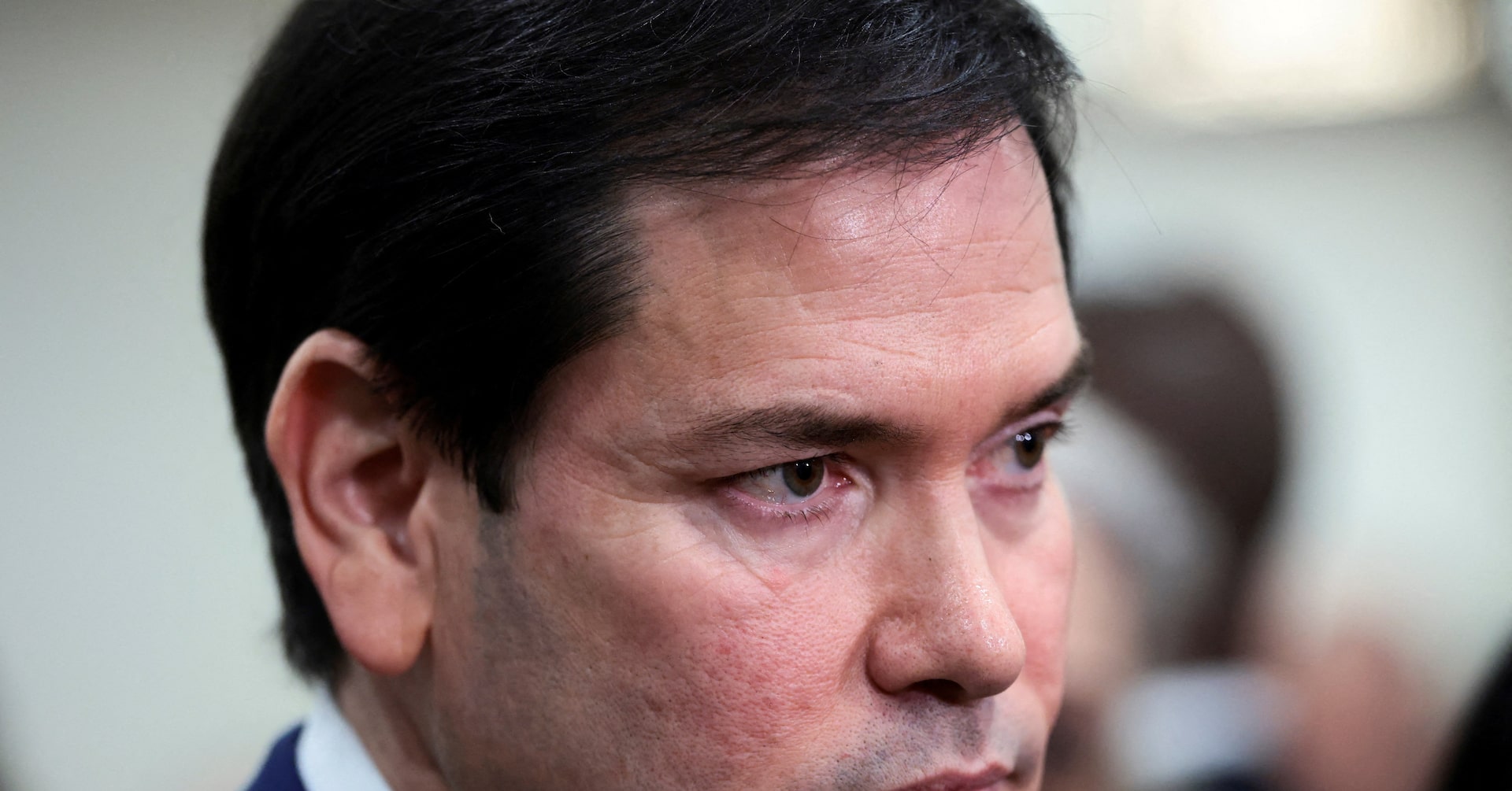安価な中国製品「コンテナで山のように流れ込む」 アフリカ製造業〝やる気〟なくす弊害も 国際舞台駆けた外交官 岡村善文氏(2)

公に目にする記者会見の裏で、ときに一歩も譲れぬ駆け引きが繰り広げられる外交の世界。その舞台裏が語られる機会は少ない。戦後最年少(50歳)で大使に就任し、欧州・アフリカ大陸に知己が多い岡村善文・元経済協力開発機構(OECD)代表部大使に、40年以上に及ぶ外交官生活を振り返ってもらった。
中国が架けた見事な橋
《外務省有数の〝アフリカ通〟として、中国のアフリカ進出をみたとき、アフリカの開発に必須なインフラ建設を中国がしっかり進めているのは紛れもない事実だという》
アフリカ西部ニジェールの首都ニアメのど真ん中をニジェール川という大きな川が流れています。かつて、両サイドをつなぐ橋は1本しかありませんでした。
朝から晩まで大渋滞が続き、渡り切るのに時間がかかって大変だった。しかし、中国が2011年、見事に2本目の橋を近くにバーンと完成させました。
アフリカ南部モザンビークの首都マプトを訪れたときも、空を駆けるような素晴らしい片側2車線の橋が海の対岸まで架かっていた。これも中国が手掛けたものです。これで、街の向こう側の土地の開発が可能となりました。
西側外交官も大喝采
アフリカ中部ウガンダの首都カンパラから40キロの場所に、エンテベ空港があります。かつては、田舎道の悪路を移動するのに、何時間もかかった。
ところが、そこに中国が高速道路を建設し、今では40分くらいで行けるようになっています。これには、移動の不便さを嘆いていた西側外交官たちも喝采したほどです。
北京の人民大会堂で、中国アフリカ協力フォーラム首脳会合に臨む習近平国家主席(手前中央)=ロイター中国製品、バラまくように売る
《中国のアフリカ進出には、アフリカ側にとって頭の痛い弊害もあるという》
アフリカは、中国国内の競争力のない工場製品の販路先にもなっています。中国人は自国から製品をコンテナで山のように持ってきて、アフリカ各国でばらまくようにして売っている。先進国に売れないものを低価格で売っているわけです。
可哀そうなのは、アフリカの製造業です。アフリカ人が作るよりはるかに安い製品が中国から流入し、地元の製造業が育たないのです。
中国人労働者、大挙押し寄せる
アフリカは、中国人労働者たちの出稼ぎ先にもなっている。インフラ建設需要がものすごくあるため、中国から労働者が大勢、押し寄せます。中国政府が送り込むというより、聞いたこともないような中国の中小企業や土建屋などがアフリカに活路を見い出し、どんどん送り込んでいるのが実態。いろいろな技術を持った建設業が入り込んでくるため、地元の建設業は育ちません。
《中国企業が自国から労働者を連れてくることには、同情の余地もあるという》
太陽に照らされるナミブ砂漠=アフリカ南西部ナミビア南アフリカのヨハネスブルグに出張し、帰路、香港経由のキャセイパシフィック便に搭乗しました。隣の乗客は中国人だった。
「アフリカで、何をしているのか?」と聞くと、ナミビアでウランを掘っているとのこと。香港に里帰りするのか聞くと、「違う。中国にエンジニアを募集しに行くんだ」と言っていました。
ナミビア政府から自国民を雇用するよう指示され、採用しようと思って探し回ったものの、質の高い労働者がいない。溶接のような簡単な作業も出来ないありさまだと言う。仕方なく、中国から連れて来ることにした、と言っていました。
中国はよく、「労働者を自分の国から連れてきて、アフリカの雇用増に貢献しない」と批判されますが、アフリカに人材が少ない、という中国側の言い分は分からないではない。彼らも一生懸命、努力しているようです。
中国民間企業のバイタリティ
コンゴ(旧ザイール)の首都キンシャサを訪れた中国の王毅外相(左)。中国とコンゴとの〝親密さ〟がうかがえる=(新華社=共同)《アフリカへの中国進出は、国家主導と民間独自の動きの両方があると考えている》
港湾や大統領府建設などの大規模インフラの建設はもちろん中国政府の資金でやっているのでしょうが、中国の民間企業も独自のバイタリティーでどんどん進出しているとみています。
中国政府としては、国内でやっていけない企業を潰すわけにいかず、アフリカに目を向けさせている面もあるに違いない。「アフリカに行けば、何とかなるから行ってみろ」などと指導しているのではないか。資源開発分野をみると、とにかくもう、無数の中国企業ががんがんアフリカに入り込んでいます。
一方、日本企業は「アフリカは大事」などと口では言うものの、十分本腰を入れているのだろうか? アフリカはあくまで世界戦略の一部に過ぎず、日本のビジネスマンたちは本社を見ながら仕事をしています。
中国人は〝骨うずめる〟覚悟
これに対し、中国のビジネスマンたちは、アフリカに〝骨を埋める〟覚悟で来ている。実際に商売をしたり、建設を進めたりしながらアフリカに入り込んでいる中国人のネットワークは、日本企業を簡単に跳ね返してしまうでしょう。
《日本を訪れるアフリカ人たちに接すると、日本の素晴らしさを一様に口にする》
欧米社会で彼らはどうしても「二級市民」に甘んじざるを得ません。ところが日本人は肌が黒い人たちを「違う人」とは思っても、見下したりはしない。だから「日本を好き」と言うのだと思います。
「日本として巻き返したい」
そういう意味では、アフリカの社会を支える中堅どころのエリートたち、たとえば官僚やエンジニア、マネジメントに関わる人たちを日本が育てていくのが望ましい戦略と考えます。
私が現在、副学長を務める立命館アジア太平洋大学(大分県)では、それを推し進めようとしている。日本に来るアフリカ人留学生の多くはエリート層です。教育を通じて日本との繋がりを持たせ、本国に帰ってもらう。そうした人たちの数を着実に増やそうと考えています。私には、日本として巻き返したい気持ちがあります。(聞き手 黒沢潤)
〈おかむら・よしふみ〉 1958年、大阪市生まれ。東大法学部卒。81年、外務省入省。軍備管理軍縮課長、ウィーン国際機関日本政府代表部公使などを経て、2008年にコートジボワール大使。12年に外務省アフリカ部長、14年に国連日本政府代表部次席大使、17年にTICAD(アフリカ開発会議)担当大使。19年に経済協力開発機構(OECD)代表部大使。24年から立命館アジア太平洋大学副学長を務める。