【z=25】ジェイムズウェッブが異次元の遠方銀河を発見か(宇宙ヤバイchキャベチ)
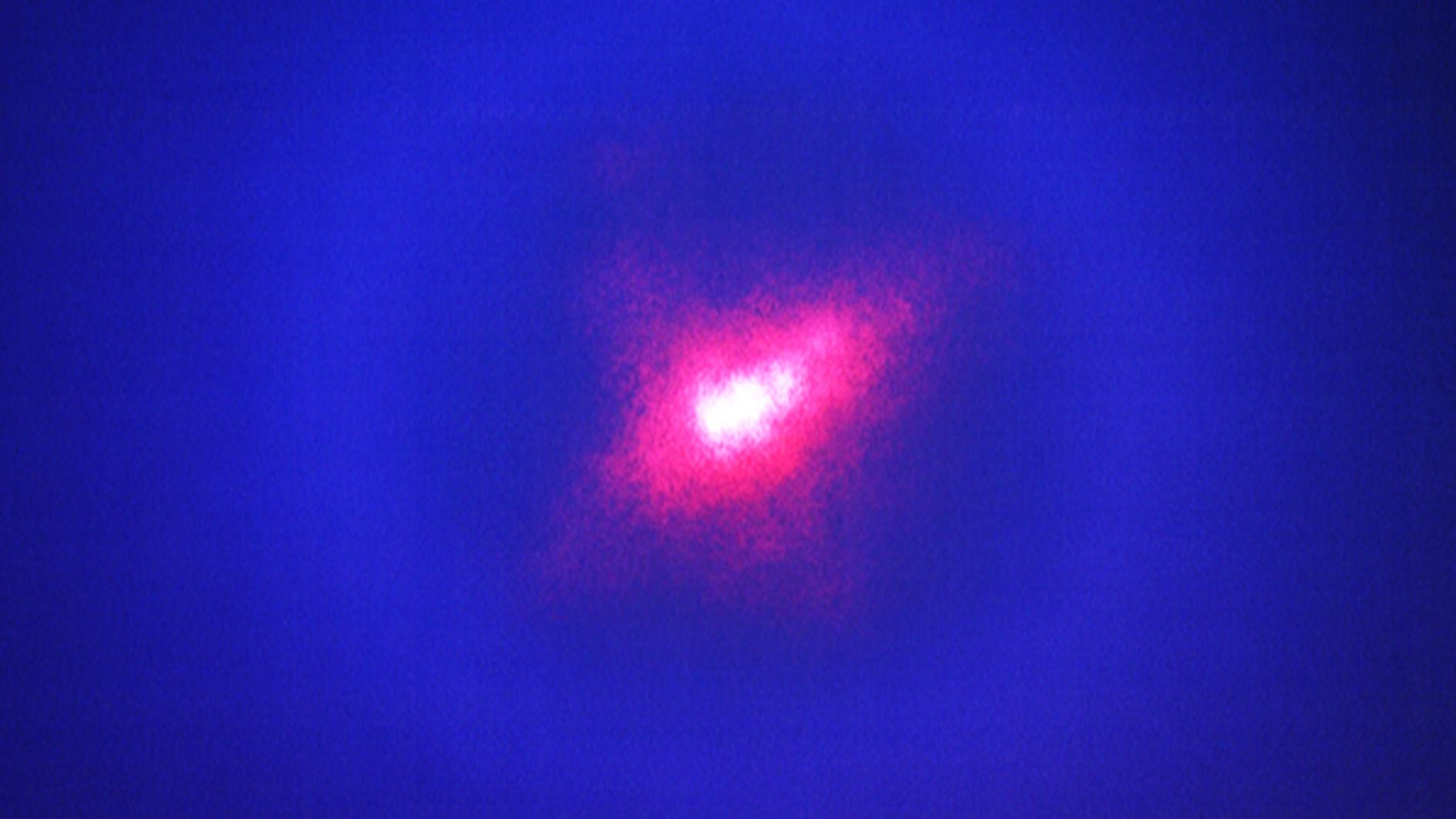
どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。
2025年7月、宇宙初期の銀河探査において画期的な成果が発表されました。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の超深宇宙観測データから、これまでの記録を大幅に塗り替えるほどとてつもなく遠方にある可能性のある、9つの銀河候補が報告されたのです。
これは標準的な理論予想を大きく超える大発見であり、天文学者たちを驚かせました。
Credit:ESAさらに興味深いことに、この観測結果を説明するために一部の研究者は「原始ブラックホール」という、ビッグバン直後のインフレーション時に形成されたという極めて特殊な仮説上のブラックホールが関与している可能性を提唱しています。
本動画では、この最新の観測成果とそれに挑む理論仮説について解説します。
●JWSTによる宇宙黎明期の銀河候補発見
JWSTはハッブル宇宙望遠鏡を凌ぐ赤外線観測能力を持ち、極めて遠方にある、宇宙最初期の銀河を探し出すことが期待されてきました。
Credit:ESA/ATG medialab光速は有限なので、遠くの天体ほど私たちに届くまでに長い時間がかかります。
100万光年先の銀河を見れば、その光は100万年前に放たれたものです。
つまり地球から「遠い天体」ほど「昔の宇宙」の姿が見えるのです。
Credit:NASA JPL-Caltech R. Hurt (Caltech-IPAC)さらに遠方の天体は地球からの距離が遠いほど、その波長が宇宙膨張によって長く(赤く)引き延ばされる「赤方偏移」という現象が見られます。
このずれの大きさは慣例的に z という記号で表し、z が大きいほど、私たちが見ているのはより「遠く・昔」の天体ということになります。
Credits: NASA, ESA, CSA, STScI, Brant Robertson (UC Santa Cruz), Ben Johnson (CfA), Sandro Tacchella (Cambridge), Phill Cargile (CfA)従来、ハッブルによる確実な観測で知られていた最遠の銀河はz=11程度(宇宙年齢約4億年の頃)でしたが、JWSTは早くもz=14(宇宙年齢3億年頃)の銀河を確認しています。
そして「さらにその先」、赤方偏移15以上という未踏の領域に目を向けたのが、スペイン宇宙生物学センターなどの国際研究チームです。
彼らはJWSTの観測時間をふんだんに使い、約11万個もの天体候補から高赤方偏移の天体らしきものを絞り込むというアプローチを取りました。
Credit:Pablo et al. 2025この観測では複数の波長フィルターを組み合わせた“ドロップアウト”手法が鍵となっています。
ある観測帯域では検出されないものの、より長波長では明るく見える天体があったとき、これが宇宙膨張による波長の赤方偏移により、短波長域で消えてしまっている可能性を検証します。
研究チームはこの方法で、z=17(宇宙年齢2.2億年頃)に相当する6つの銀河候補と、z=25(宇宙年齢1.3億年頃)に相当する3つの銀河候補を発見したのです。
Credit:Martin Kornmesser, Luis Calcada, NASA, ESA Hubbleなお、z=25の天体の「現在の距離」は、宇宙の膨張を考慮すると実におよそ370億光年と見積もられます。
ただし、これらの距離(赤方偏移)は現時点では見かけの色にもとづく推定値であり、今後分光観測による詳細な確認が必要です。
しかし現状でも、これほど初期の宇宙からの光をとらえた可能性が高い天体が9つも見つかったことは驚きです。
Credit:NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani●初期宇宙に「明るい銀河」が多すぎる問題
新発見の銀河候補たちが予想通りの超高赤方偏移天体なら、宇宙膨張で引き延ばされる前は「強い紫外線」を放っていたことになります。
これは星形成直後の若い大質量星団によるものです。
宇宙最初期には重元素(=水素とヘリウム以外の元素)が存在しないため、そこで生まれる初代星は理論上非常に大質量で高温となり、紫外線を大量に放射すると予想されます。
今回の9つの候補天体のうち3つは典型的な初代星によく一致する性質を示しています。
また、星からの光をさえぎる塵もほとんど無いとみられ、観測された光は星そのものの輝きだと考えられます。
これらの銀河の恒星年齢は平均わずか3000万年程度と算出され、ビッグバンからの経過時間を考えれば生まれたてほやほやの銀河だと言えます。
Credit:Springel et al. (2005)しかし、ここで大きな疑問が浮かびます。
「宇宙開始からたった数億年で、そんなにたくさんの星や銀河ができているものだろうか?」という点です。
標準的な宇宙モデルでは、ビッグバン後しばらく宇宙は高温かつ一様で、ガスが冷えて星や銀河が生まれるには時間がかかると考えられています。
Credit:NASA NCSA University of Illinois Visualization by Frank Summers, Space Telescope Science Institute, Simulation by Martin White and Lars Hernquist, Harvard University最初に重力でまとまり始めるのは目に見えないダークマターの“塊”であり、その重力にガスが引き寄せられて徐々に星形成が始まるのが定説です。
シミュレーションでは、だいたい宇宙誕生後数億年以上経ってようやく最初の星や小銀河がぽつぽつ生まれる、と予想されてきました。
「1億年そこそこで星ができ始めるのは難しい」と指摘する研究者もいます。
つまり9つの候補天体が存在していたと示唆されるのは、「まだ星も銀河もほとんど存在しないはずの時代」なのです。
このような理論予想と観測事実の矛盾に対して現在のところ根本的な解決策は存在していません。
●原始ブラックホールが宇宙を照らした可能性
Credit:ESAピサ高等師範学校などの研究チームは、JWSTの示した「予想外に明るい超遠方銀河」を説明する仮説として、"原始ブラックホール"が寄与した可能性を提案しています。
原始ブラックホールとは、その名の通り宇宙最初期に形成されたブラックホールです。
通常のブラックホールは大質量星の最期の崩壊によって生まれますが、原始ブラックホールはビッグバン直後のインフレーション時に物質の密度ゆらぎから生まれた特別なブラックホールだと考えられています。
Credit:ESAこのモデルでは、原始ブラックホールがダークマターの一部として振る舞い、重力的な足場を提供することで標準モデルを超える早さで星や銀河が生まれると期待されます。
原始ブラックホールがもし存在すれば、宇宙初期の超巨大ブラックホール形成やダークマターの正体といった難問も一挙に説明できる可能性があり、1970年代から議論されてきたものの、存在していた確証は得られないまま現在に至っています。
研究チームは星がまだ誕生していないはずの初期宇宙に明るい銀河が多すぎる問題に対し、この原始ブラックホールの寄与を加味したモデルで挑みました。
原始ブラックホールがもし本当にあったなら、銀河の見かけの明るさや“明るい天体の数”に効く寄与の仕方は大きく2通りあります。
まず一つ目は、原始ブラックホールが“先にある重力の芯”として働き、星づくりのスタートを早めることです。
原始ブラックホールの周囲にはガス(星の材料)が集まりやすくなるため、通常より早い時期から星が次々と生まれ、銀河全体の明るさが増しやすくなるという効果があります。
そしてもう一つが、ブラックホール自体が成長過程で銀河中心部で光って、銀河全体の見かけを明るくすることです。
研究チームが両方の効果を組み込んで計算したところ、原始ブラックホールが星づくりを早めた“星の光だけ”で説明しようとすると、宇宙背景放射など他の観測と食い違いやすくなる一方で、原始ブラックホール自身の光をほどよく加えると、初期宇宙に明るい銀河が多いという観測を無理なく再現できると分かりました。
この結果をかみ砕くと、「とても小さな原始銀河の中心で、原始ブラックホールという“灯り”がともり、その光が星の光に上乗せされるぶん、私たちには初期の銀河が実際より明るく見えている」という説明になります。
Credit:NASAs Goddard Space Flight Center CI Labまた、「そんな誕生直後の小さな銀河に、最初から“種”となるブラックホールがいるのか?」という疑問についても、原始ブラックホールは宇宙の初期から存在し得ると考えられているため、この点も矛盾なく説明できます。
原始ブラックホールを導入することは一見奇抜なアイデアですが、JWSTの発見が常識を覆すものであった以上、理論側も大胆な発想で挑まざるを得ないというわけです。
では、この原始ブラックホール仮説は観測的に確かめようがあるのでしょうか?
研究チームは「JWSTの今後の分光データで検証可能」と述べています。
ポイントの一つは銀河の見かけの大きさです。
・明るいbh動画
ブラックホール本体は銀河と比べて圧倒的に小さいため、ブラックホール由来の光であれば、遠方から見ると天体が点状に見えるはずです。
Credits: NASA, ESA, CSA, STScI, Brant Robertson (UC Santa Cruz), Ben Johnson (CfA), Sandro Tacchella (Cambridge), Phill Cargile (CfA)一方、星からの光であれば星々が銀河状に分布するためぼんやりと広がって見えるでしょう。
Credit:Pablo et al. 2025実際に最新の候補天体のサイズを測定したところ、「約3割ほどの候補は点源的で原始ブラックホールシナリオと矛盾しない」と結論付けられています。
残りの天体は広がって見えるので星形成銀河だと考えるのが自然ですが、9個中数個が点状というのは興味深い兆候です。
現状の撮像データだけでは星由来か原始ブラックホール由来かを区別するのは難しいですが、今後より詳細な観測でその違いが浮かび上がる可能性が期待できるのです。
Credit:ESA/Webb, NASA & CSA, G. Östlin, P. G. Perez-Gonzalez, J. Melinder, the JADES Collaboration, M. Zamani (ESA/Webb)極限まで遠い宇宙から届いた光は、私たちに「最初の銀河はいつ、どのように誕生したのか?」という根源的な問いを投げかけています。
今回の観測は、宇宙初期の星形成が私たちの想像以上に活発だった可能性を示しましたが、それを裏付けるには更なる証拠が必要です。
幸いJWSTは今後も稼働を続け、候補天体の分光追観測によって赤方偏移の確定や元素組成の手がかりが得られるでしょう。
Credit:ESA/ATG medialabまた新理論も刺激され、原始ブラックホールのみならず初代星の暴走的形成や未知の物理過程など様々な仮説が提案されつつあります。
いずれにせよ、宇宙黎明期に何が起こったのかを解明することは、宇宙論・天文学における最前線のテーマです。
宇宙ヤバイchでは今後も続報を追っていきます。
https://arxiv.org/pdf/2503.15594



![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)