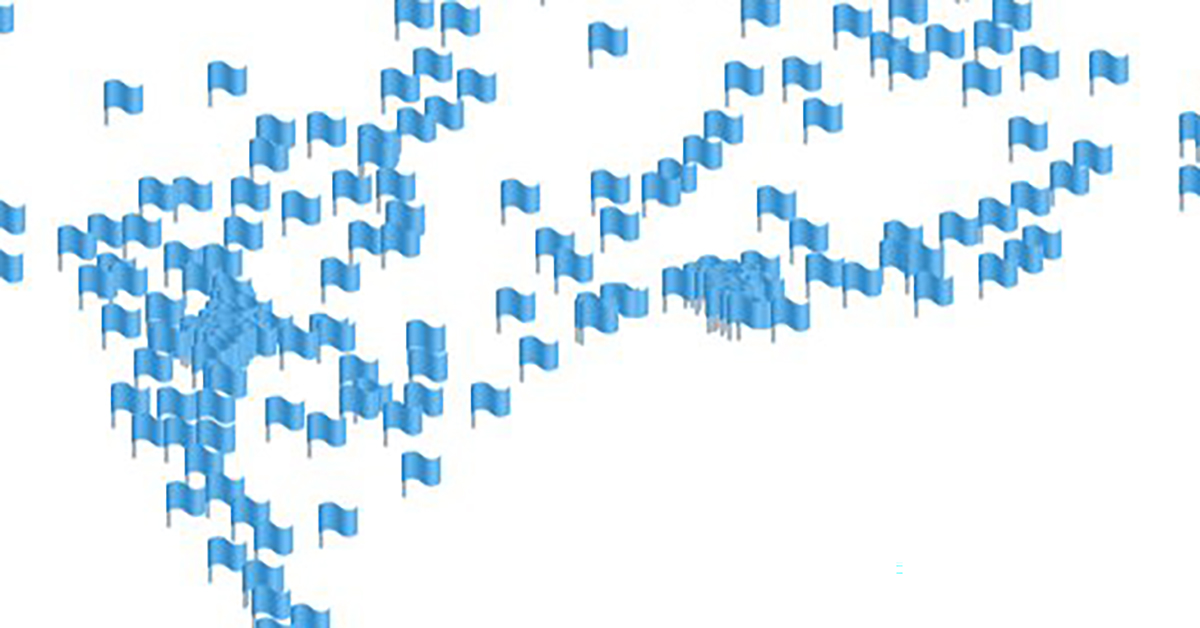人口ピラミッドから見る人口減少の背景

Fasai Budkaew/iStock
元旦にあわせて「未曽有の人口減少の時代に模索すべき日本外交の姿勢」という記事を書いた。日本の人口減少・少子高齢化のスピードが異常になっていること、その衝撃の緩和策は重要としても減少それ自体を止めることは不可能であること、などを書いた。
世代論とあわせて、もう少し追記しておきたい。日本の人口ピラミッドを見て気づくことがある。第二次世界大戦後のベビーブームの時代に生まれた「団塊の世代」が突出した人口比を持っている。「団塊の世代」が出産適齢期になった時期に生まれたのが「団塊ジュニア世代」だ。
2015年まで減少傾向にありながらも100万人台を維持していた出生数が、過去10年でさらにいっそうの減少幅を見せて、2024年には3割以上の減少となり70万人を切るまでに至っている。
この状況に関して、目の前の直近の社会現象の移り変わりにのみ関心が向けられることが多いが、人口ピラミッドを見れば、極めてわかりやすい推移であることもわかる。「団塊ジュニア世代」が出産適齢期を過ぎたのである。
「合計特殊出生率」が、「出産率」の統計指標として用いられることが多い。それはいいと思うが、よく注意しておかないと、読み間違る。15~49歳の幅で、統計の母数となる人口を摘出するためだ。実際には、平均初産年齢は31歳であり、30歳代前半が出産年齢のピークだ。49歳の出産数は、相当に少ないはずだ。
10年前に、「団塊ジュニア世代」が40歳代に突入し始めた。それとともに出産数が減少した。自然である。親の世代の人口が少なくなっているのだから、仮に一人当たりの出産率が同じままであっても、どんどん出生数は減っていくのは当然だ。他方、「団塊ジュニア世代」は、「合計特殊出生率」の対象にはとどまり続けたので、「出生率」がどんどん下がっていくのも当然だった。
今年から「団塊ジュニア世代」は、「合計特殊出生率」の対象からも外れていく。統計対象の母数も減少していくということである。これは「合計特殊出生率」を押し上げる効果を持つはずである。15歳になってくる人口も相対的に数が少ないので、統計対象となる人口の母数がどんどん減少していく。
ただし、人口の絶対数が減少しているわけなので、仮に実態として一人当たり出生率が同じなら、出生数が増えるとは思えない。今後は「合計特殊出生率」を見る際には、このことを念頭に置いておかなければならない。
いずれにせよ人口は激減していく。日本の人口ピラミッドを見れば、「団塊ジュニア世代」以降は、どんどん世代あたりの人口が減少していたことがわかる。もっとも現在の20歳台から30歳台前半にかけてだけは、出生数が維持されていたこともわかる。
日本経済の世界的シェアが最高だった1990年代から20世紀初頭の時期に生まれた世代だ。「団塊ジュニア世代」が出産適齢期に入るまでの時期に生まれてきた、親の世代が非常に人口の多かった時代の子どもの世代でもある。
この1990年代生まれの人口層を考えると、今後は、今の急激な人口減少を経験した後、ほんの少し人口減少に小康を得る時期があるかもしれない。だがその後は、さらにいっそう急激な大人口減少時代が待っている。
人間は、人間からしか生まれてこないので、人口が減少する時期が続いてしまったら、その子どもの世代も必ず減少する。必然である。逆もまた同じで、親の世代が多ければ、子どもの世代も多くなる。
日本の人口減少を鈍化させることは、急激な社会変化の衝撃を少しでも緩和させるために必要だが、それはあくまで鈍化であって、長的な傾向を覆すには、百年くらいの単位で見ていかなければ、無理である。
日本は、戦国時代が終わって安定した社会になったと考えられた江戸時代初期に、大きな人口増加を経験した。その後、江戸時代後期は、同じ人口水準を維持した。この傾向は、明治維新とともに変化した。
日本は、明治の近代化の開始以降、急激で止まることを知らない人口増加を経験した。この傾向は、第二次世界大戦でもとどまることなく、百年以上にわたって続いた。150年ほどの間に、日本の人口は4倍になった。
この止まることのない人口増加の時代に、日本は近代化を達成し、軍事大国になり、経済大国になった。人口が増えたから発展したのか、発展していたから人口が増えたのかは、鶏と卵の関係にある問いだ。両者に相関関係がある、としか言えないだろう。いずれにせよ人々は、社会の発展を非常に高い確率で起こっていることと信じて、家庭生活も営み、人口を増やし、増えた人口が、社会を発展させていった。
この間に成立した社会的制度は、暗黙の前提として、人口は増えるのが当然であるような推論の上に生まれた。社会保障制度が、その典型である。現在、SNSで高齢者擁護者と高齢者批判者が戦っていたりするが、日本の人口が拡大し続けていれば、そのような喧嘩は必要ではなかった(実際には現在人口は減少しているので喧嘩が終わることはない)。
21世紀になってから、日本は総人口でも減少を始めたが、すでに述べたように、それは適齢期に入ってくる人口が少ないことが、最も大きな構造的事情だ。つまり、「団塊ジュニア世代」以降、出生率が減り、世代人口が減ったことが、背景にある。
なぜ「団塊ジュニア世代」以降の人口は減ってしまったのだろうか。彼らが生まれた1970年代前半に、折り返し点がある。日本の出生数のピークは、1973年の209万人だ。合計特殊出生率で言うと、1971年の2.16がピークである。当時、ちょうど団塊の世代が出産適齢期に入ってくる時期だ。むしろ1970年代以降に、出生数は増えるのが、自然であった。ところが、現実は全く逆に、1970年代から、子どもが生まれなくなってきた。
日本の人口推移の歴史転換点は、1970年代前半にある。このあたりの時期の出生数の推移が異常になった。あとは継続して降下現象を続けているだけである。
上述の推論をあてはめると、1970年代から、人々が、社会の右肩上がりの進展を常識として信じなくなり、異なる生活様式を取るようになった。それにそって社会的諸制度の設計運営も変化した。社会科学者として関心をかき立てられるのは、この点だ。1970年代前半に何があったか。
日本の高度経済成長が終わった時期だ。それは1973年オイルショックによる物価高のみならず、1971年ニクソン・ショックによる変動為替制度への移行によっても特徴づけられる。1960年代まで、日本は1ドル360円という現在では考えられない比率での固定為替制度を前提にして、製造業を中心にした経済発展を成し遂げた。それが終わったのが、1970年代初頭だ。
終わった理由ははっきりしている。冷戦時代の前半に「反共の防波堤」としてアメリカから優遇措置を受けていた日本は、その間に発展させた製造業を通じてアメリカの製造業を脅かすような輸出攻勢をかけるようになった。その状況に、遂にアメリカが耐えられなくなり、変動為替制度への強制的な移行を果たしたのである。
安全保障面で言うと、冷戦時代前半にアメリカの安全保障の傘を前提にして「軽武装」路線を通していた日本は、1970年代以降は適切な負担を果たすように求められるようになっていく。1972年5月に沖縄返還が果たされたが、そこでは「基地自由使用」と「核持ち込み」の約束が盛り込まれた。日本は、より独立した国として認めてもらう代わりに、アメリカを中心にした安全保障システムに深く入り込んでいくようになった。
他方、佐藤栄作政権が沖縄返還を花道にして退陣した後に成立した田中角栄内閣は、内閣法制局を通じて、1972年10月に初めて、「集団的自衛権の行使は違憲」という見解を出す。新しい時代に直面し、ベトナム戦争も続行中だったアメリカの安全保障政策に、過度に「巻き込まれ」ることを避けたい心情の現れであったと言える。その直後、田中は、アメリカでのリークによる「ロッキード事件」で失脚する。
このようにして見ると、子どもを産まなくなった世代が、自己享楽的に資産を運用・消費していたバブル時代などは、取るに足りない重要性しかない時代であったようにすら思われる。もっともバブルの崩壊が、冷戦終焉の直後に発生しているように、さらにギアを入れ直して日本に厳しい政策を取り始めたアメリカの態度の変化という国際情勢が、バブルの崩壊にも影響していたことも、否定しがたい事実である。
このような歴史的展開を見ていくと、さらに色々なことに思いをはせることができるのだが、一言、はっきりしていることがある。
現在の日本で語られている「少子化対策」なるものが、いかに皮相で小手先の短期的な人気取りと予算正当化の術でしかないか、ということである。
人口減少の大きな傾向も、数十年先には、変化していくのだろうとは思う。だがそれは相当に先の話であり、いずれにせよその時までに日本は全く別の国になっているはずである。
今は、未曽有の人口減少の時代を通じて、個々人が、そして日本が、どうやって、それでも何とか生き残っていくことができるのか、を真剣に考えなければならない。
■
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。