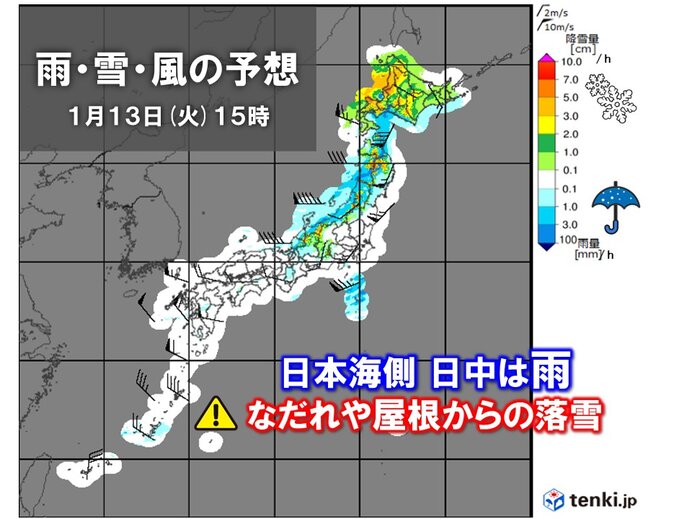参院選の偽情報、3人に1人が「事実と誤認」◆デマ拡散はテレビの訂正報道がきっかけ?#データの深層:時事ドットコム

7月の参院選では、膨大な数のSNS投稿や切り抜き動画が拡散し、その波に乗れたかどうかが各政党の獲得議席をも左右しました。ただ、そうした中には偽情報やデマなども多数あり、「35%の人が事実と誤認した」との調査結果も。なぜSNSが選挙に大きな影響を与えるようになったのか、偽情報はどう拡散したのか、だまされないためにはどうすればいいのか。専門家に話を聞きました。(時事ドットコム取材班 斉藤大)
【過去の特集▶】時事ドットコム取材班
【関連ニュース▶】過熱するSNS選挙◆専門家に聞く「フェイクニュース」「切り抜き動画」との向き合い方、2025年参院選特設ページ
半数近くが「SNS・動画を参考」
参院選で躍進したのが、国民民主党と参政党だ。一方で、石破茂首相率いる自民党は大幅に議席を減らし、野党第1党の立憲民主党は横ばいに甘んじた。公明党や共産党といった老舗政党も議席減となった。この背景には既成政党に対する不信に加え、SNSがあったとみられる。
時事通信の出口調査によると、投票先を決める際にSNSや動画サイトを参考にしたかとの質問に対し、「参考にした」と「ある程度参考にした」と答えた人は合わせて46.9%。「参考にしなかった」「あまり参考にしなかった」の50.0%に、わずかに及ばなかったが、半数近くが判断の材料にしていた。
「参考にした」層の比例代表の投票先は、参政が最も多く23.9%、2番手は国民の16.5%、自民は3位、立民は6位だった。「参考にしなかった」層の投票先は自民が1位、立民が2位で、参政は6位。はっきりとした傾向がうかがえる。
シニアのスマホ利用、9割に拡大
「シニア層も含め全世代がスマートフォンを持ち、SNSや動画を見るようになったことが投票行動に表出したのではないか」と話すのは、ビデオリサーチ「ひと研究所」の渡辺庸人所長だ。
同社が1万人を対象にメディア接触や意識の調査を行う「ACR/ex」のデータによると、55~65歳のスマートフォンでのネット利用は2014年に2割台だったが、24年には9割台まで上昇。もはや若い世代とほとんど変わらない水準だ。YouTube(ユーチューブ)の視聴やSNSの利用も一気に増加し、世代間の開きは縮小している。
渡辺所長は、SNSや動画サイトを利用する人や機会が増えたことに加え、近年のSNSのシステムやアルゴリズム(投稿表示の仕組み)の影響も指摘する。Xでは、23年に投稿の閲覧数の多いユーザーに報酬を支払う「収益化プログラム」を導入。デマであっても、差別を含んだり過激的だったりする内容であっても、とにかく「バズる」ことを目的とした投稿が増加した。他のSNSでも同様の仕組みがあり、こうした「アテンション・エコノミー」の過熱が偽情報拡散の背後にある。
情報は「やって来るもの」?
加えて、ユーザーの属性や検索・閲覧履歴から好みと思われる投稿や動画を表示する「おすすめ表示機能」により、情報との向き合い方が変化してきた可能性があるという。今やSNSに限らず、ニュースや音楽配信などさまざまなウェブサービスで提供されている。
「ACR/ex」の意識調査では、2000年以降に生まれた人は「情報収集は自ら積極的に行うほうだ」という質問に対して、上の世代に比べ肯定的な回答が減少するという結果が出た。
ひと研究所の調査グループは、仮説として「2000年以降生まれの人は、SNSなどのシステムからその人に合わせた情報を提供されることが当たり前になったため、上の『検索行動世代』よりも積極的に情報を集める必要がないという意識が強まっている」ことを挙げる。
若い世代で抵抗なく受け入れられている「おすすめ」。しかし、SNSではこの機能により、何度か特定の政治や選挙関係の投稿を見ると、次々に似た主義・主張のものばかりが表示され、異なる意見に触れにくくなる「フィルターバブル」という現象が起きている。渡辺所長は「SNSの仕様により誤った情報や極端な意見が拡散され、分断を生む構造になっている」と指摘。その上で「社会やメディアは、人々が何に不満を持っているのか丁寧に拾っていく必要があるのではないか」と語る。
1割強が「偽情報を拡散」
今回の参院選ではさまざまな偽情報やフェイクニュースが広まり、各メディアでも取り上げられた。実際、どれだけの人が偽情報に触れたのか。東洋大の小笠原盛浩教授(情報社会学)が7月20~23日に18~79歳の1500人を対象にオンライン調査を実施した。
選挙期間中に拡散した「外国人が生活保護の受給で優遇されている」「石破首相が党首討論で『なめない方がいい』とアナウンサーをどう喝した」など代表的な五つの偽情報に対して、59.7%の人が一つ以上を見聞きし、35.3%が事実だと誤認識し、11.2%が会話やSNSで偽情報を拡散していた。小笠原教授は「諸外国と比べ高い割合ではないが、有権者がネット情報を重要視してきており今後も同様の傾向が続くだろう」と分析する。
海外ではトランプ氏が初めて当選したアメリカ大統領選やイギリスの欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)の是非を問う国民投票が行われた2016年頃から、フェイクニュースが選挙に影響を与えてきた。一方、日本ではマスメディアを情報源とする人が比較的多く、かつ「自民1強」と言われた政治的状況だったため、偽情報の影響はさほど出ていなかったという。
ただ、最近はSNSを情報源とする人が増えたことに加え、政局が流動化。小笠原教授は、これらを背景に外国勢力が偽情報の拡散を通じ選挙介入を行った可能性も指摘。「生成AIの技術革新が進んだことで、これまで突破することが難しかった『日本語の壁』を乗り越えたのではないか」と、以前に比べ偽情報が格段に広がりやすい事態になったと警鐘を鳴らす。
テレビ打ち消し報道は逆効果?
参院選の調査では、偽情報を初めて見た情報源も聞いた。最も多かったのは「テレビ」で39.8%。Xなど「SNS」(20.6%)、ユーチューブやTikTok(ティックトック)といった「動画共有サイト」(6.2%)を大きく上回った。誤認した人の割合は「動画共有サイト」(68.6%)が、誤情報を拡散した人の割合は「政党・候補者がネットで発信した情報」(44.4%)が最も高かった。
「テレビ」の誤認率は44.3%、拡散率は16.0%と比較的低めだったが、最初の情報源となった比率が高かったことから「テレビニュースが積極的に行った打ち消しや訂正報道が、結果的に偽情報の拡散を促した可能性がある」(小笠原教授)という。
また、偽情報を誤認識した人とそうでない人の各メディアに対する信頼度を比較すると、誤認識した人はテレビニュースや新聞記事などマスメディアへの信頼度が低く、SNSや動画共有サービスの信頼度は高い傾向があった。
「ファクトチェック」は届いたか
2024年11月の出直し兵庫県知事選では、デマや誹謗中傷が広く拡散した。SNSなどで攻撃を受けた県議が自死するなど大きな禍根を残した。こうした状況を受け、新聞・通信・放送各社が加盟する日本新聞協会は今年6月、「インターネットと選挙報道をめぐる声明」を公表。「選挙の公正」を過度に意識しているとの批判に対し、各社が「有権者の判断に資する確かな情報を提供する報道を積極的に展開していく」との見解を示した。
多くの報道機関が6月の東京都議選や7月の参院選を前に、SNSなどで広がる情報の真偽を確かめる「ファクトチェック」など、選挙報道の拡充を宣言した。実際、NPO「ファクトチェック・イニシアティブ」の調べでは、今回の参院選のファクトチェック記事は183本に上り、昨年の衆院選時の5倍以上になった。
ただ、それでも大量の偽情報がまん延した。小笠原教授は「報道機関などがファクトチェックを続けることは大切だが、内容や伝え方に課題がある」とみる。「そもそもファクトチェックの言葉自体が『正しいことを教えてやる』という上から目線に感じる人もいる」とした上で、「結論ありきでデータをそろえていたり、国の公式見解をそのまま伝えるだけだったりする記事も散見されたほか、偽情報を事実と誤認してしまう人が持つ社会への不満に対する共感や寄り添う視点を欠いていた面もある」と強調する。
偽情報を広げないために
SNSに情報があふれる中、有権者はどうすればいいのか。小笠原教授は拡散されやすい偽情報の特徴として「面白かったり、(受け手が)びっくりしたりする内容」と説明。そうしたものを見聞きした際は、①「うそかもしれない」と考え、うのみにせず判断を保留する②ネット以外のルートで裏取りする③無理に真偽を決めつけない④情報拡散は控える―ことが大切だと呼び掛ける。
一方、マスメディアは偽情報にどう対処すればいいのか。小笠原教授はそのヒントとして、アメリカでの例を挙げる。かつて、トランプ大統領による事実に反する発言を欧米メディアがそのまま報道していたことで、読者や視聴者がそれらを「本当のこと」として受け止めてしまったという事例が繰り返された。
この反省に立ち、各社は偽情報を扱うニュース記事では最初に事実の概要を示し、中頃で偽情報に関する話題に触れ、最後に再び事実を書く「真実のサンドイッチ」という手法を取り入れるようになった。こうした先例を参考に「偽情報を扱う報道の仕方に工夫を」と注文した。
取材を終えて
参院選後、同業他社の人たちと話す機会があり、そこでは「SNSの影響が一気に高まった」「あまりにもデマや中傷が多すぎる」など懸念や戸惑いの声が多く聞かれた。マスコミ各社の選挙報道は以前より充実したが、「適切に有権者へ届いたのか」という点で課題が残った。この記事を書いている最中にも、アフリカ諸国との「ホームタウン事業」に対する誤解の拡散や、読売新聞の捜査対象取り違え誤報といった事案が相次いだ。情報をめぐる状況が急激に変化する中、その扱い方や向き合い方を改めて考えていかなければならないと思った。