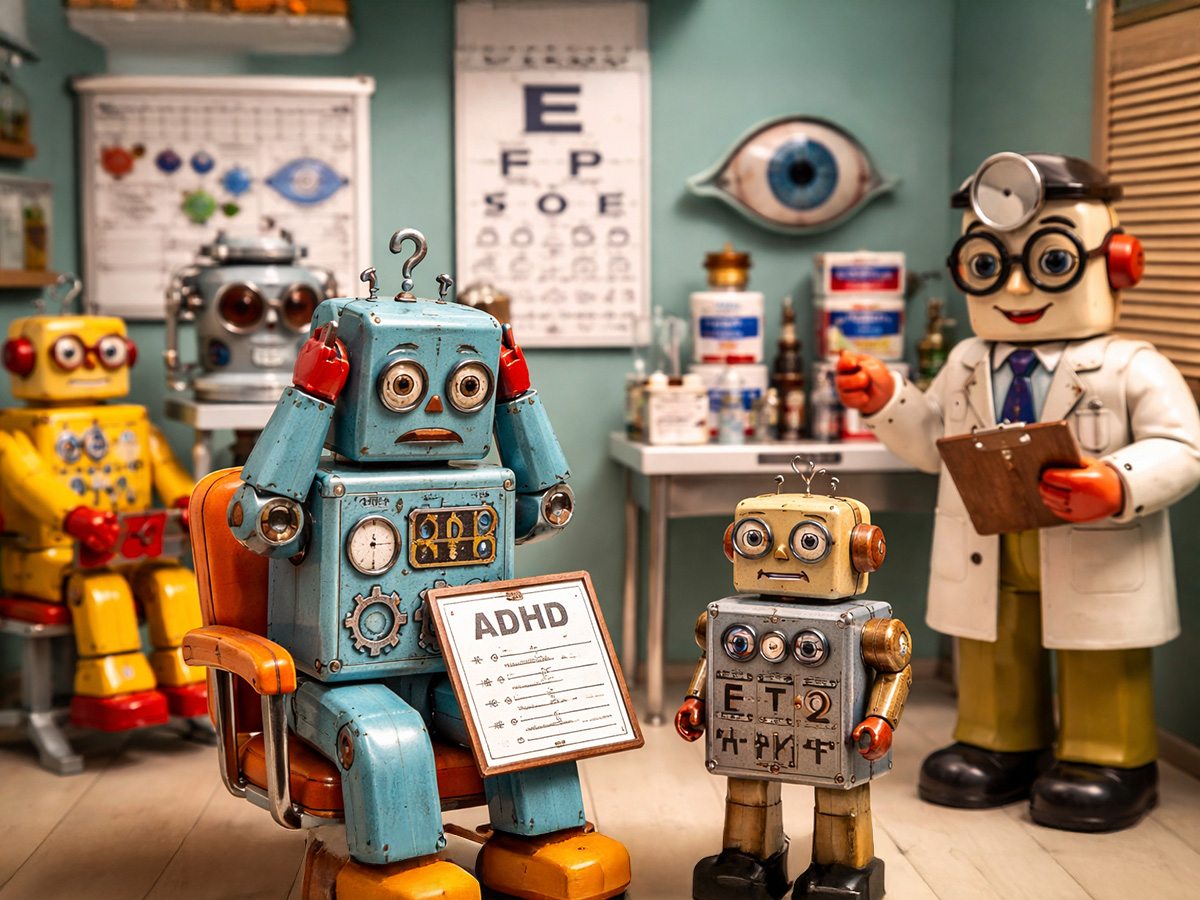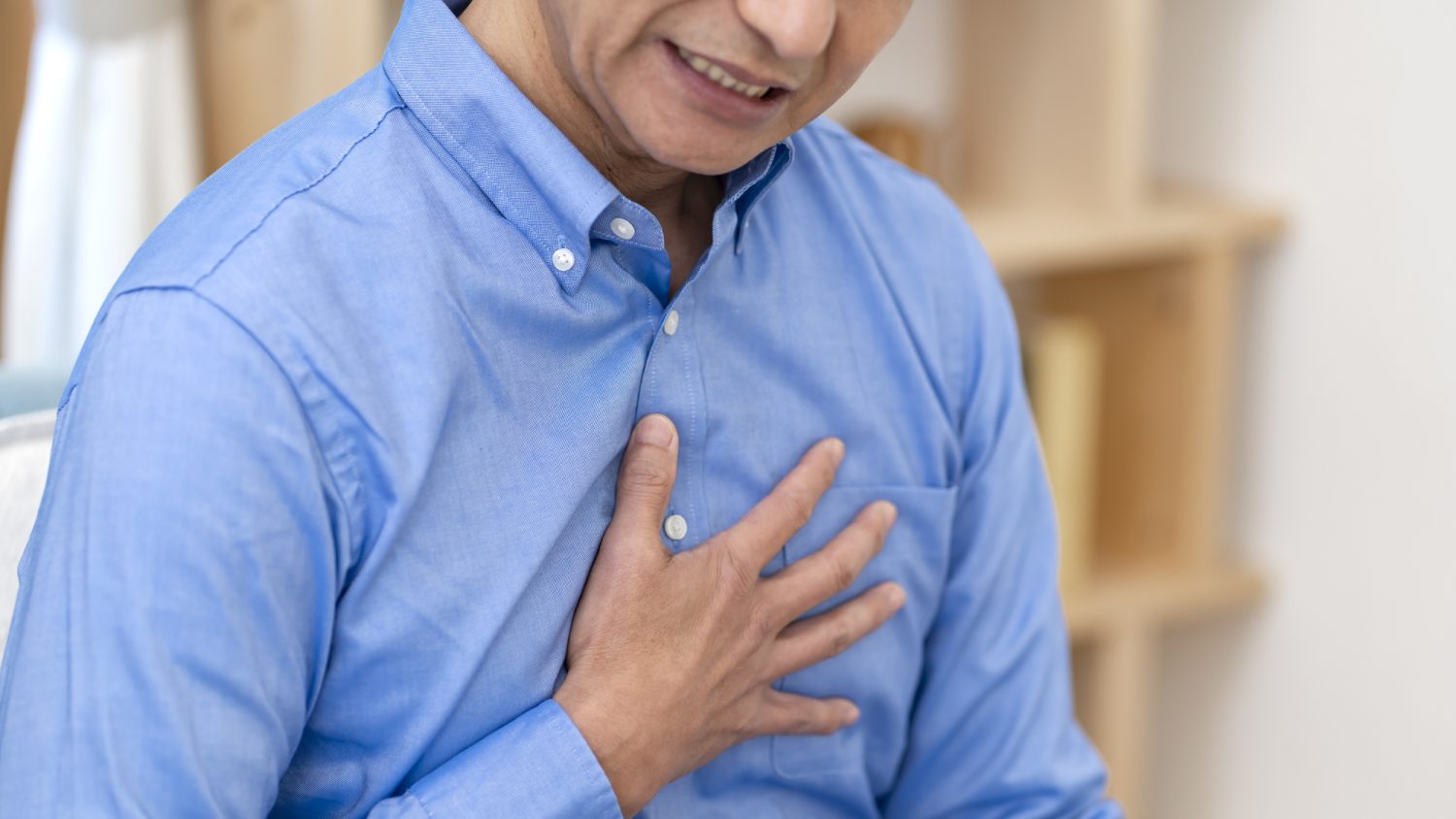夏場を抜けても…「隠れカビ」による“おうちデミック”に要注意! その咳や喉の不調、エアコンや加湿器、羽毛布団からくる『過敏性肺炎』かも

9/13 10:31 配信
家にいるとなんだか息苦しい。時には咳も出るのに、外出や旅行をすると症状がよくなる……という“ヘンテコ”な経験をしたことはないだろうか?
実はそれ、『過敏性肺炎』と呼ばれる、肺炎の一種かもしれない。原因はウイルスなどの病原体ではなく、あなたの“おうち”に潜むカビ! 重症化すると酸素吸入が必要になる場合もあるが、驚くべきことに、引っ越しやリフォームをするだけでケロっと治ってしまうこともあるのだ。
この『過敏性肺炎』とはいったい何者なのか。この病気について多くの論文を発表している、東京都・複十字病院 呼吸器内科の下田真史医師に詳しく伺った。■長引く咳、カビによるアレルギーの肺炎である可能性も
「まず、『過敏性肺炎』というのは、カビや細菌などの病原菌や鳥の蛋白質、金属粒子などを吸い込むことによって発症するアレルギーの肺炎です。さまざまな原因物質が報告されていますが、日本で最も多いのは、“夏型過敏性肺炎”と呼ばれる、木造住宅などに発生する『トリコスポロン』というカビが原因となるタイプです」(下田医師・以下同)
このカビは高温多湿な環境を好むため、「夏型過敏性肺炎」のピークは、梅雨でジメジメし始めた6月から8月だという。しかし、今年はまだまだ油断ならない。日本列島はかつてないほどの猛暑に見舞われ、6〜8月の平均気温は3年連続で統計史上最高を更新。そのうえ、気象庁の発表では、この9月以降も平年を上回る残暑が予測されている。
「例年でも9月、10月に入ってから症状が出る方もいらっしゃいますし、今月に入っても真夏並みの暑さが続く日もありますから、気が抜けません。“夏型過敏性肺炎”にかかると、まずは咳や息苦しさなど呼吸器系の症状が現れます。ほかには、喉は痛くないのに痰が出る、身体がダルいなど。時には、軽度から中程度の発熱が伴うこともありますね」
原因となるカビは木材でよく繁殖するため、下田医師によると、「築20年以上の木造住宅に長年、住んでいる方などの発症が多い」という。夏以外にも、住宅のカビが原因となって“住宅関連過敏性肺炎”が発症することもあるそうだ。 では、「うちは木造じゃない」「あとひと月もすれば暑さも落ち着く」と安心していいものだろうか。残念ながら、そうとは言い切れない。
「先ほどお伝えしたように、『過敏性肺炎』という大きなくくりで言えば、ほかの病原菌や金属粒子などを吸い込んだ場合にも発症事例があるのです。身近なものでいえば、エアコンや加湿器などにもこの病気の影は潜んでいます」
■エアコンも原因に。「加湿器肺」はコロナ禍に増加 昨今は夏場、冬場に限らず、ほぼ1年じゅう大活躍していると言っても過言ではない文明の利器・エアコン。エアコンは空気を吸い込み、冷やしたり温めたりして室内に送り出す仕組みを持つが、運転中、内部で大量の結露が発生していることをご存じだろうか。
下田医師によると、「そこに空気中のホコリや汚れが付着すると、カビにとって絶好の繁殖環境となり、『過敏性肺炎』の一種である“空調病”を引き起こす恐れがある」という。
エアコン内のカビの代表例としては、黒カビ「クラドスポリウム」があり、吹き出し口、フィン、内部全体で発生する。次に「アスペルギルス」。これは空気中に広く存在し、フィルター、ファン周辺に多く潜む。また、青カビである「ペニシリウム」は、内部の湿った部分全体で発生するそう。
次に、特に乾燥しがちな秋〜冬にかけて、多くの家庭が使用する加湿器。加湿器に発生するカビは主に白カビ、黒カビ、ピンク色のカビ(酵母菌や細菌)の3種類に分けられる。白カビは比較的取り除きやすいが、黒カビは健康への影響が大きいため、「発見次第すぐに対処が必要」と下田医師は警鐘を鳴らす。
そこにピンク色のぬめりも発生し、これらとバイ菌、またそれらが作り出す毒素「エンドトキシン」などが合わさって舞い上がると、これまた『過敏性肺炎』のひとつ、「加湿器肺」の原因になるとのこと。 「新型コロナウイルスの騒ぎに隠れてしまっていましたが、実は、この“加湿器肺”は、コロナ禍の時期に静かに増加していたのです。コロナ禍中に加湿器を購入する家庭が増えたことで、罹患者数がワッと増えたと考えられます」
コロナ禍では多くの人が、ちょっとした咳や発熱で「コロナにかかったかも」と心配したかもしれない。だが、それが実は「加湿器肺」だった可能性もあるということだ。
■キノコに金属、楽器…意外なものにも注意を 恐ろしいことに、『過敏性肺炎』はまだまだ幅広い。 「鳥を飼っている方もいらっしゃると思いますが、そんなご家庭でときどき見られる“鳥関連過敏性肺炎”も、その名のとおり『過敏性肺炎』の一種。これは、動物性タンパク質によるアレルギーなのですが、動物のなかでも特に鳥が原因となって出る症状です。
なぜ鳥由来が多いのかはよくわかっていませんが、鳥がアレルギーになるというなら、一般家庭で使用されているダウンジャケットや羽毛布団も、同じく“鳥関連過敏性肺炎”の原因になり得るということです。なぜか咳が続く場合などは、それらの使用を避けてください」
今後、1月から3月にかけて『過敏性肺炎』が再びピークを迎える可能性が高いという。エアコンや加湿器などの衛生面に不安がある人や、気になる症状が出た人は、クリーニングを検討しつつ、病院を受診してみると安心だろう。
さらに、農業で有機肥料の“鳥糞”を使う人やキノコ栽培業者、金属を削る仕事をしている人がかかるパターンもある。「一風変わったものでいえば、サックス奏者が『過敏性肺炎』になった事例も。原因はなんと、サックス内部で発生したカビでした」と下田医師。カビの繁殖力はなかなかにすさまじく、どこで発生するか予想しきれない。下田医師はこう続ける。
「住居内で言えば、洗い場、洗面所の水まわり……お風呂やトイレのタイルなどが思い当たるでしょう。でも、それだけではありません。畳やカーペット、寝具、本類、壁紙にカビが発生したり、もっとわかりづらいものでは、天井にいたりもします。型にはめて考えず、あらゆる場所に注意してください」
ただ、ここまでさまざまな『過敏性肺炎』について紹介してきたが、この病気の大きな特徴は、意外にも「原因となる環境から離れればケロっと症状がよくなること」だ。
さしづめ“おうちデミック”とでも形容できるような肺炎なのだが、なにぶん感染症ではないため、“おうち”から離れて過ごすなどアレルギー源との隔離により、大掛かりな治療に進むことなく、数日から数週間で改善が見られることも少なくないという。 その点では、そこまで怖がる必要はないものの、やはり重症化するケースもある。■「線維性過敏性肺炎」の場合、事態は深刻に
「例えば、『過敏性肺炎』と診断されず、他の病気を疑われて入院した患者さんの場合。入院中は原因から離れているので、すぐに治ってしまいます。ですが、退院して自宅に戻った途端、再びアレルギー源に曝露。たったの数時間で、すぐに再来院する方もいらっしゃるくらいです。このケースの再燃率は90%以上というデータがありますから、早めに原因を特定し、再発防止に努めることが重要なんです」
家じゅうに潜む“隠れカビ”がずっと放置されたままでは、『過敏性肺炎』が悪化してしまうのは当然のこと。その場合は薬で抑えることもできるそうだが、実は、もっと厄介な病態があるという。
「“夏型過敏性肺炎”をはじめとし、今までお話ししてきたのは、主に“非線維性過敏性肺炎”についてでした。ところが、これが“線維性過敏性肺炎”になると、場合によっては急激に症状が悪化し、酸素吸入が必須になることもあり、時には命にもかかわります」
「線維性過敏性肺炎」──? 初めて耳にした人も多いだろう。 「“非線維性過敏性肺炎”の場合には、一過性の症状で終わることもそれなりに多いんです。一方で“線維性過敏性肺炎”は、時間をかけて年単位で肺が“線維化”、つまり“肺が壊れた状態”になり、呼吸機能を徐々に低下させてしまいます。しかも、一度壊れた肺は、元には戻りません」
元に戻らないとは、穏やかではない。このタイプは急性の発症を繰り返して線維性に移行する場合と、潜在的にじわじわと進行する場合があるとのことで、「特に後者は初期段階では気づきにくく、医師側でも問診には注意が必要」と下田医師。つまり長引く咳などは、コロナや重い風邪でないとしても決して放っておいてはいけない。
■迅速かつ適切な対応がカギ。早めの通院を ゆえに、下田医師は問診を重要視する。
「大事なことは、不調の原因を一刻も早くつき止め、適切な対策をとることです。医師は患者に少しでも過敏性肺炎の可能性があれば、問診で住環境を詳しくヒアリングします。また、ただの風邪ではないと感じた場合にレントゲンやCTを撮る場合もあります。症状や身体所見だけではさまざまな病気が疑われますから、画像所見がすみやかな病気の特定につながることも多いんです。
その上で、原因になり得るものを見つけ、羽毛布団はやめてください、こことここをお掃除してください、クリーニングの業者さんを入れてください等、具体的に指示します。築年数が古い木造建築だった場合には、リフォームや引っ越しをすすめることも。ですから、“咳が続いておかしい”、“喘息が悪化したかな?”などと思ったら、迷わず身近な病院へと足を向けてください。医師と二人三脚で『過敏性肺炎』を治していきましょう」
東洋経済オンライン
最終更新:9/13(土) 10:31