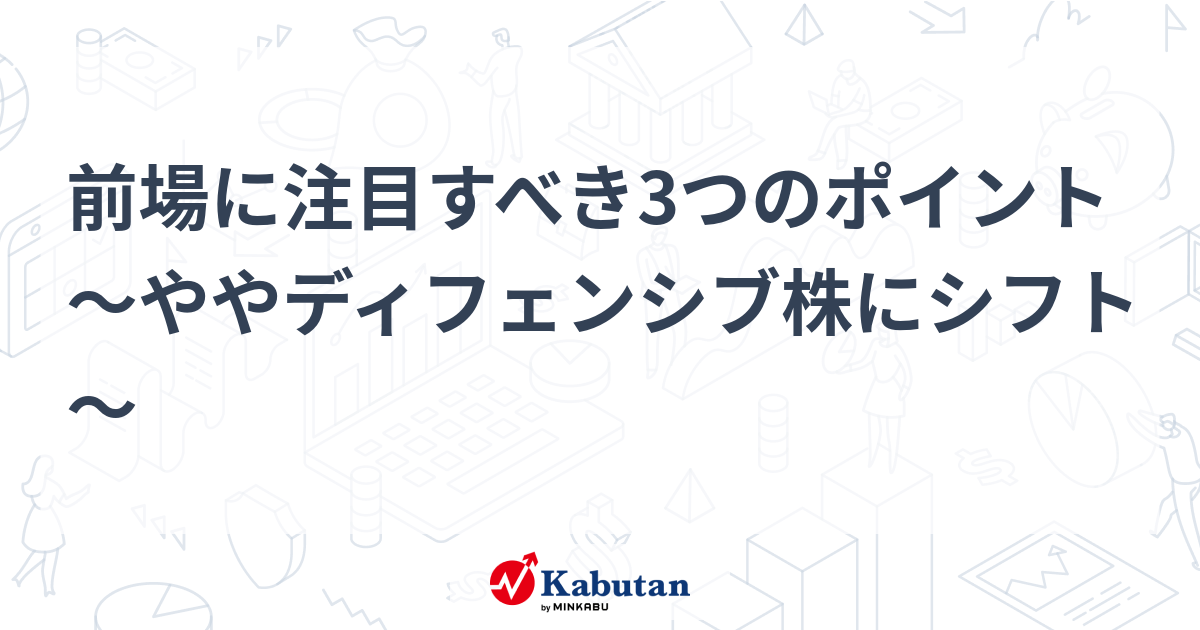7月の実質賃金、7カ月ぶりにプラス転換-名目は昨年12月以来の伸び

物価の変動を反映させた7月の実質賃金は7カ月ぶりにプラスに転じた。今年の春闘での高水準の賃上げが給与に反映される中、名目賃金の増加率が物価の伸びを上回った。日本銀行の金融政策正常化路線を支える材料となり得る。
厚生労働省が5日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数で算出した実質賃金は前年同月比0.5%増。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は4.1%増と、昨年12月以来の高い伸びとなった。
基本給に相当する所定内給与は2.5%増と、7カ月ぶりの高水準となった。賞与など特別給与の増加も賃金全体を押し上げた。
日銀は経済・物価が見通し通り推移すれば利上げを継続する方針を維持している。現状維持を決めた7月の金融政策決定会合では、消費者物価の見通しが上方修正された。今回の結果は賃金の上昇基調が続いていることを示しており、追加利上げの時期を探る日銀にとって追い風となる内容と言える。
野村証券の岡崎康平チーフマーケットエコノミストは、「徐々にではあるが、賃金が増えてきて消費に結びつくという動きが見えてきた」と指摘。日銀の金融政策への影響については、多少の外的ショックがあっても内需は底堅いという自信感が増すとし、「来年の1-3月期にかけて利上げの判断がしやすくなった」と語った。
統計発表後、東京外国為替市場の円相場は1ドル=148円台前半に上昇している。7月の実質賃金が7カ月ぶりにプラスに転じたことを受け、円買いが優勢になっている。
日銀の植田和男総裁は先月の講演で、大きな負の需要ショックが生じない限り、賃金には上昇圧力がかかり続けると指摘。氷見野良三副総裁は2日の講演で、経済・物価のメインシナリオが実現していけば「経済・物価情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことが適切だ」と語った。
物価高や人手不足を背景に、今春闘の平均賃上げ率は連合が掲げた目標の「5%以上」を2年連続で達成し、賃上げの勢い継続が確認された。7月発表の最終回答集計によると、平均賃上げ率は5.25%と34年ぶりの高い伸び。毎月の基本給を引き上げるベースアップ(ベア)は3.70%と、3%以上としていた目標をクリアした。
金融市場では年内の利上げ観測がくすぶっている。翌日物金利スワップ(OIS)は12月までに利上げが行われる確率を5割程度織り込んでいる。
実質賃金の算出に用いる消費者物価指数は「持ち家の帰属家賃を除く」が3.6%上昇、総合指数は3.1%上昇だった。3月分から公表を開始した、総合指数で算出した実質賃金は1.0%増と、7カ月ぶりにプラスに転じた。物価が高止まりする中、今後は実質賃金のプラス持続が焦点となる。
今後の賃金動向を巡っては、米国の関税措置による企業収益への影響が引き続き警戒される。トランプ大統領は4日、日本との貿易合意を実施する大統領令に署名した。これにより自動車・同部品を含む大半の日本からの輸入品に最大15%の関税が課されることになる。航空宇宙と自動車の輸入に対する措置は7日以内に発効する。
関連記事:トランプ氏、日本の自動車関税15%に引き下げ-大統領令に署名
参院選大敗を受けて自民党の森山裕幹事長らが辞意を表明する中、石破茂首相は物価高対策などに取り組むため、当面、続投する姿勢を示した。8日には、自民党の総裁選前倒しを巡り、所属議員らによる意思確認が行われる。実施されれば事実上の退陣につながり、経済対策に遅れが生じる可能性がある。
みずほリサーチ&テクノロジーズの酒井才介チーフ日本経済エコノミストは、少なくともデフレではない状況で、需給ギャップもマイナスではなくなってきており、「大規模な財政出動で需要を刺激しなければいけない必要性は乏しい」と指摘。「物価高対策がかえってインフレ圧力を強める」ことになりかねないとの見方を示した。
消費は3カ月連続増
総務省が5日発表した家計調査によると、7月の消費支出(2人以上の世帯)は物価変動の影響を除いた実質ベースで前年同月比1.4%増と、3カ月連続のプラスとなった。市場予想は2.3%増だった。
他のポイント
- 所定内給与に残業代など「所定外給与」を足した「きまって支給する給与」は前年同月比2.6%増と、30年7カ月ぶりの高い伸び
- 一般労働者(パートタイム労働者以外)の所定内給与は2.8%増-7カ月ぶりの高い伸び
- 特別に支払われた給与は7.9%増-前月4.4%増
- エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は2.9%増
- 所定内給与は全体が2.4%増、一般労働者は2.4%増