高齢者の栄養改善をケアプランに活かす!「高エネルギー高たんぱく食のポイント」オンデマンドセミナー開催
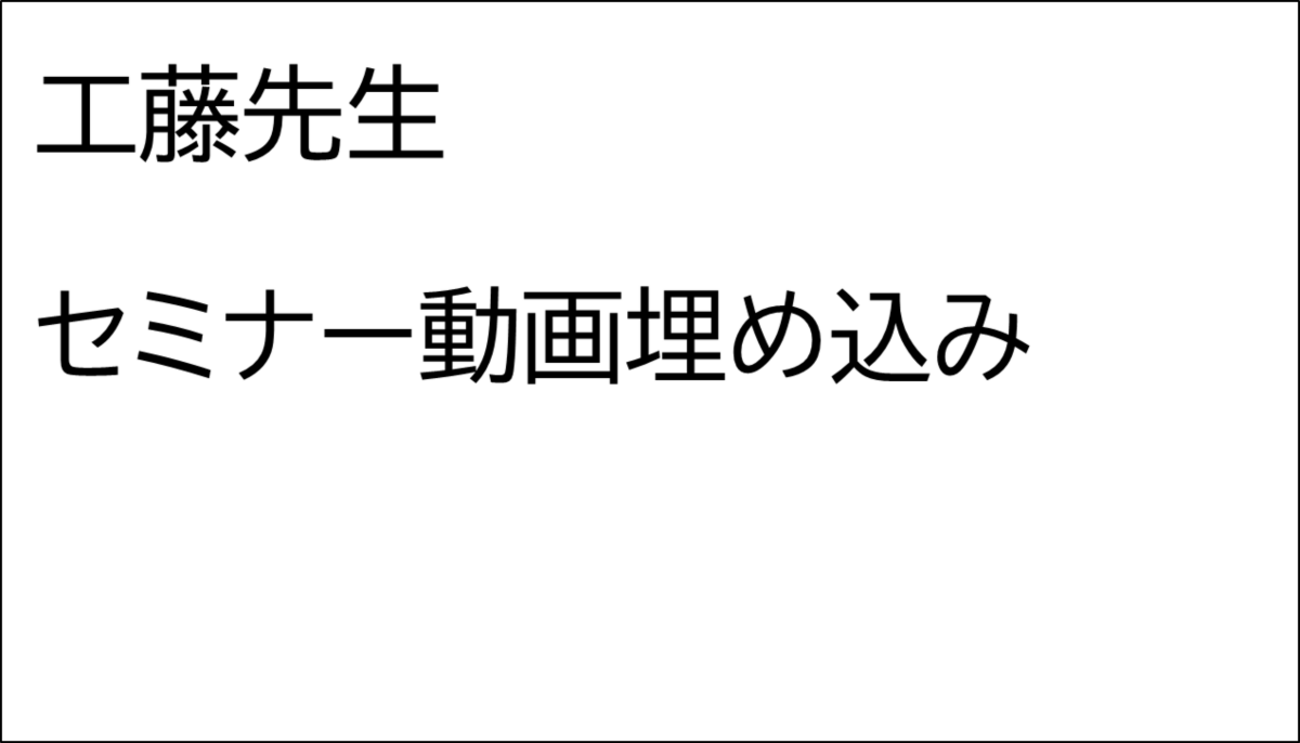
高齢者の健康管理において、「適切な栄養摂取」が重要であることは言うまでもありません。とはいえ、日々のケアプラン作成のなかで、栄養面まで十分に配慮するのは容易ではないと感じているケアマネジャーの方も多いのではないでしょうか。特に、加齢に伴う体重減少や筋力の低下は、生活の質(QOL)の低下に直結する重大なリスクです。こうした課題を予防・改善するためには、「高エネルギー・高たんぱく」の食事を取り入れる工夫が欠かせません。
今回のセミナーでは、「高齢者の栄養改善をケアプランに活かす!」をテーマに、管理栄養士の工藤先生をお招きし、高エネルギー・高たんぱく食の基礎知識から、現場で実践できる具体的な方法までをわかりやすくご講義いただきます。 利用者一人ひとりの栄養状態を的確に評価し、ケアプランに反映させていくための、科学的根拠に基づいた知識と実践的なアプローチを学べる貴重な機会です。 ぜひご視聴ください。
【オンデマンドセミナー】高齢者の栄養管理の基本と実践~高エネルギー高たんぱく編~
セミナー視聴のゴール
高齢者の体重減少を予防し、ケアチーム内で共有・工夫できる栄養管理の知識を習得していただきます。日々のケアプラン作成に活かせる実践的な内容となっております。
セミナー内容
工藤先生が、長年の臨床経験と豊富な知識をもとに、 ケアマネジャーがすぐに活用できる栄養管理のポイント を具体的に解説いただきます。
-
高齢者の栄養状態の重要性体重減少や栄養不良がもたらすリスク(筋力低下、免疫力低下、褥瘡の悪化など)
高エネルギー・高たんぱく食の必要性 を科学的根拠に基づいて解説
-
高エネルギー・高たんぱく食の具体的工夫高齢者が摂取しやすい食事形態や調理法(柔らかく飲み込みやすい工夫など)コンビニや市販品を活用 した簡単で実践しやすいメニューの提案
経口栄養補助食品(ONS) の適切な活用方法
講師紹介:工藤 美香先生(管理栄養士・ 在宅訪問管理栄養士)
病院・施設・在宅の栄養管理に長く携わっており、急性期病院勤務時にはNST(栄養サポートチーム)の中心メンバーとして活躍。現在は駒沢女子大学 健康栄養学科の教授として、臨床栄養学概論や臨床栄養学などの指導を担当するほか、日本在宅栄養管理学会理事も務めている。
セミナーを視聴して栄養面の視点をケアプランに生かそう
利用者の栄養状態を把握するための評価方法とは
ケアプランに栄養の視点を効果的に取り入れるため、以下の点について具体的に解説します
体重・BMI測定
BMI(ビー・エム・アイ)とはBody Mass Indexの略で世界共通の肥満度の指標です。身長と体重から簡単に測定することができ、標準値は「22」とされています。標準値の「22」に近いほど、さまざまな病気にかかるリスクが低いといわれています。
目標とするBMIの範囲(18歳以上) 年齢(歳) 目標とする BMI(kg/m²) 18~49 18.5~24.9 50~64 20.0~24.9 65~74 21.5~24.9 75以上 21.5~24.9出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」, 2019年
食事内容について
「さあにぎやかにいただく」 は、魚・油・肉・牛乳・野菜・海藻・芋・卵・大豆製品・果物 の10の食品の頭文字をとった合言葉です。毎日の食事の中で、同じような食品ばかりを食べていないか、不足しているものがないかを確認するために、この合言葉を活用するとよいでしょう。
高齢者にありがちな食事とは? 家族ができる栄養不足の気付きと対策【駒沢女子大学教授 工藤美香先生インタビュー:その6】<PR>はこちら
MNAなどのスクリーニングツール活用
高齢者の低栄養をチェックする指標の一つに、「MNAショートフォーム」があります。これは、「過去3ヶ月間で食欲不振や消化器の問題、そしゃく・嚥下の困難によって食事量が減少しましたか?」といった6つの質問に答えるだけで、栄養状態を簡単に評価できる方法です。専門的な知識がなくても実施でき、所要時間はわずか5分程度。定期的にMNAショートフォームを活用し、栄養状態の低下がないか確認する習慣をつけましょう。
MNA®-SFは、65歳以上の高齢者に特化した栄養スクリーニングツールです
フレイル予防のために知っておきたいチェック方法と対策ポイント【駒沢女子大学教授 工藤美香先生インタビュー:その7】<PR>はこちら
ケアチーム連携のポイント
訪問看護やケアチーム内での情報共有のポイント
(栄養状態の変化をどのように記録・連携すべきか)高齢者の栄養状態は、日々の食事や健康状態に大きく影響されるため、 訪問看護師、管理栄養士、介護職、医師、 など、ケアチーム全体での情報共有が欠かせません。適切な栄養管理を行うためには、 栄養状態の変化を的確に把握し、記録し、チーム内で共有する仕組み を整えることが重要です。 ・いつだれが体重を測定するのか。 ・それを共有する仕組みは?
・食事量や食事内容の情報共有
など、サービス担当者会議等で共有しておくことも必要です。
栄養管理における連携の流れ(例)
高齢者の栄養状態が悪化した際、スムーズに対応するための連携フローの一例を示します。
◎ ケース:訪問看護師が利用者の体重減少を発見した場合
訪問看護師が体重・食事摂取量を記録(1ヶ月で3%の体重減少を確認)ケアマネジャーに報告(必要に応じて管理栄養士や主治医へ相談)管理栄養士が食事改善の提案(食事内容の見直し、補助食品の活用など)ケアプランに栄養面の対応を反映(栄養補助食品の導入、摂食嚥下評価の実施など)
定期的なモニタリングを継続し、カンファレンスで評価・改善
◎地域に認定栄養ケア・ステーション(*1)や管理栄養士の相談が難しいこともあるかもしれません。通所系サービスのご利用で、栄養改善の取り組みとの連携等も行っていきましょう。
(*1)認定栄養ケア・ステーションとは、地域の皆さまが栄養ケアの支援・指導を受けることができる地域密着型の拠点として日本栄養士会から認定されている施設のことです。
特に栄養課題の懸念が著しい疾患
病気の特性上、特に栄養課題が起きやすい方がいます。かなりのエネルギー量を必要とする疾患をお持ちの方です。
アセスメントの際にも、疾患と栄養を考えるきっかけにしてください。
- COPD(慢性閉塞性肺疾患) 呼吸に多くのエネルギーを消費し、体力や筋肉が消耗しやすい。
食事中の呼吸困難により、食事摂取量が減ることで低栄養に陥る。
- 間質性肺炎(特発性肺線維症など) 肺が線維化し、徐々に呼吸機能が低下する進行性の疾患。 呼吸困難により食欲が低下し、栄養不足が深刻化 する。 低酸素状態が続くことで エネルギー消費が増大 し、低栄養や
サルコペニアを引き起こす。
- がん悪液質(がんカヘキシア) 進行がんの患者に多く見られ、腫瘍による代謝亢進や炎症によって 体重減少少、
筋肉量低下、食欲不振 を引き起こす。
- 慢性心不全(心不全カヘキシア) 心臓のポンプ機能が低下し、全身の血流が不足することで 代謝異常、
筋肉量減少、栄養不良 が進行する。
*一方で、たんぱく質の摂りすぎ等に留意が必要な疾患があります。
ご病気に合わせて、栄養について、医師や看護師へ確認が必要です。
まとめ:ケアプランに栄養管理を組み込む意義
高齢者の栄養状態は、 一度悪化すると回復に時間がかかる ため、「食事の変化」や「体重の減少」などのサインを見逃さず、チームで早めに対応することが重要 です。
◆ポイントのおさらい◆・ 体重・食事摂取量等の変化を記録し、ケアチームで共有・カンファレンスやICTツールを活用し、スムーズに情報連携・栄養管理の視点をケアプランに反映し、早期介入を実施
・栄養補助食品を上手に使い、栄養補給
栄養状態の管理を徹底することで、利用者の健康寿命を延ばし、生活の質(QOL)を向上させることができます。このセミナーを、事業所内の個別研修や、特定事業所加算の研修等にぜひご活用ください。
ケアチーム全体での積極的な連携を進め、より良いケアを提供していきましょう。
特定事業所加算応援コンテンツはこちら



