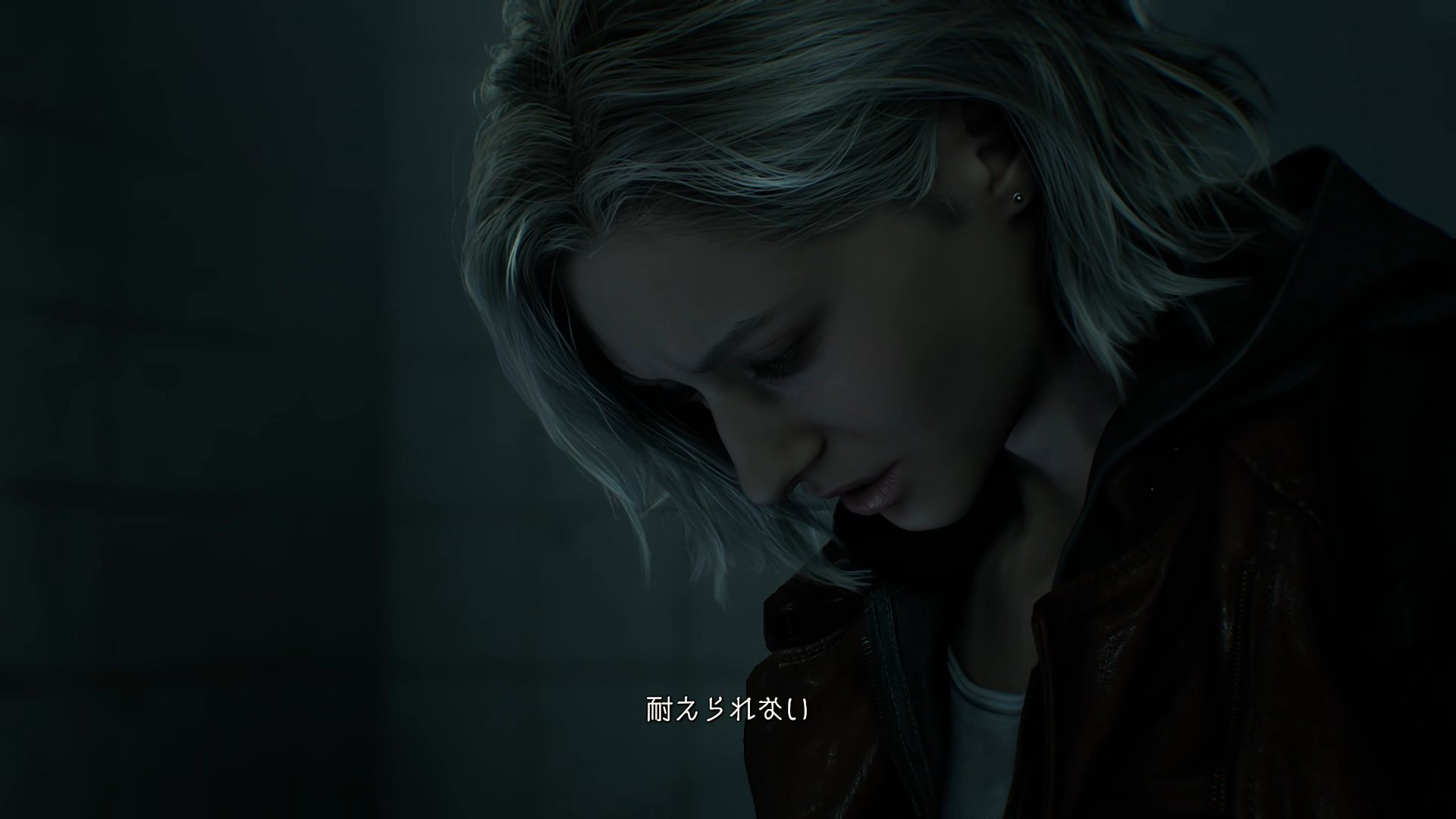【大河ドラマ べらぼう】第42回「招かれざる客」回想 画業の全盛期を迎えた歌麿、蔦重との亀裂は決定的に ロシア情勢にも通じた定信の心配は江戸湾の守り

すれ違い決定的に 蔦重と歌麿
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、第42回「招かれざる客」では、長くドラマの骨格を成してきた蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)と喜多川歌麿(染谷将太さん)の蜜月関係にヒビが入り、すれ違いが決定的になるまでが描かれました。歌麿が蔦重以外の版元とも組むようになった史実にフィクションを織り交ぜ、両者の軋みの過程が巧みに浮き彫りにされました。「招かれざる客」であるロシアの接近は、松平定信(井上祐貴さん)の命運にも大きく関わります。(ドラマの場面写真はNHK提供)
全盛期迎えた歌麿の画業
寛政4年から5年(1792∼1793)にかけて、大首絵の美人画「婦人相学十躰」「婦女人相十品」の大ヒットで一躍、江戸の浮世絵界のスターになった歌麿。それまで主流だった全身像による美人画から離れ、クローズアップした女性の姿の表現を通じて、その個性や内面に迫る画期的な作品群でした。
重要文化財 喜多川歌麿筆「婦人相學十躰・浮気之相」江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)歌麿と蔦重のコンビによる快進撃はこれに留まりません。美人の町娘を描いた「看板娘」のシリーズも人気を集めます。鈴木春信ら先人の絵師たちにも町娘をモチーフにした作品は多く、やはりモデルになった女性は現実でも人気を集めました。さらにキャラクターを明確に反映した歌麿の浮世絵は、実在の人物を強く意識させるもの。作品がきっかけになってより店が流行り、絵もさらに売れるという相乗効果が働きました。「推し」の画像や動画に夢中になり、それを見ればリアルイベントにも足を運びたくなる現代の私たちと変わりがありません。
難波屋のおきた。浅草の水茶屋の娘です。当時16歳。お茶の持ち方と目線にひたむきな人柄を感じさせます。
こちらは両国の煎餅屋のおひさ。当時17歳。団扇の持ち方で気風のよさそうな個性を表現していました。ドラマでもそれにあわせたキャラクターに。
吉原の芸者の豊ひな。浄瑠璃の富本節の名取で、作品も大人びた印象です。芸者は身体を売る女郎とは職種が違いますが、表情や物腰には色里に暮らす女性らしい艶っぽさが強調されます。実に繊細な表現。
3人合わせて「寛永の三美人」などともてはやされます。店には高い代金を払っても長蛇の列。豊ひなもお座敷の指名が殺到します。
喜多川歌麿筆『江戸三美人・富本豊雛、難波屋おきた、高しまおひさ』 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)現代の「会いに行けるアイドル」そのもの。会ったり、声を掛けてもらったりするのに割高な「課金」が必要なシステムも一緒です。200年以上前の江戸時代の流行ですが、そのマインドの近さにドキリとします。
治済も町娘に夢中 お忍びで「会えるアイドル」に会いにいっていました 「田沼病の再現だ」と、定信は取り締まりを強化します身勝手が目立ちはじめる蔦重
天下にその名をとどろかせた歌麿。キャリアの全盛期を迎えました。蔦重にとっては金の卵を産む存在です。
その勢いにのって蔦重、「歌麿先生は江戸中の美人を描きつくすつもりです」と、歌麿に聞きもせず勝手に今後の制作方針を決めます。「え、そうなの?」と歌麿は違和感をはっきり口にしたのですが、蔦重は気にも留めません。
看板娘ブームを江戸の商人たちが見逃すわけもなく、次々と舞い込む制作依頼を片っ端から引き受ける蔦重でした。「そんなにたくさん描けるわけがない」と難色を示す歌麿にも「弟子に歌麿そっくりに描かせて、歌麿が手を入れれば立派な歌麿作だ」とゴーストライターによる制作を勧めます。当時は一般的に行われていたことかもしれませんが、「自分にしか描けない」に拘ってきた歌麿からすれば、気がすすみません。自分の名前が出ない作品を描かされる弟子の思いも無視できない歌麿。蔦重に対する不信感が徐々に募り始めます。
吉原にもまだ借金が残る蔦重。好色本の刊行の科で「身上半減」の処罰を受けた際、返済を待ってもらったこともあり、こちらの手当ても急を要します。結局、返済にかえて歌麿に女郎たちを描いた作品を制作させ、世に広めるという条件で交渉がまとまりました。
借金のカタに俺を売った?
「借金のカタに俺を売ったってこと?」。また事前の相談もなく、吉原での仕事の段取りを勝手に決めてきた蔦重。制作の謝礼は支払うとは言っても、歌麿からそうなじられても仕方ない蔦重の行状でした。不信から怒りへ。歌麿の気持ちはさらにマイナスの方向へと傾いていきます。その直前には気になる指摘をされたばかりでした。
協業の打診にきた西村屋(西村まさ彦)とその二代目、万次郎(中村莟玉かんぎょくさん)から、美人画の隅の印について、蔦屋の下に歌麿の署名があるのはおかしい、順番が逆ではないのか、と言われてしまいます。「騙されているとは申しませんが、都合よく扱われているのでは?」というもっともな見立てまで。後述しますが、確かに他の版元では上下が逆になっているものがあるのです。
アーティストのマインドに鈍感な蔦重
蔦重と言えば社会の空気を読み、売れ筋を見極めるセンスが突出しています。あるいは困難を突破して成果物を完成させる粘り強さにも秀でています。ところが自分の企画を進めることに熱中するあまり、繊細なアーティストのマインドには鈍感なところがあります。年齢を重ねても変われない蔦重の編集者としての弱点でしょう。山東京伝(古川雄大さん)にも、「書籍作りに携わる者としての社会的責任だ」でごり押しし、無理やり作品を作らせようとしたエピソードは記憶に新しいところです。
「ふんどし(定信)に抗っていかないと、戯けられない世になるって言ってんだよ」と京伝を叱り飛ばす蔦重(第37回「地獄に京伝」より)とりわけ歌麿に関しては「自分が見い出して、育ててやったんだから、俺が言えば大丈夫」という甘い気持ちが無かったとはいえないでしょう。主人公だからといって、根っからの善人にもスーパーマンにもしない、欲も見栄も欠点もある普通の人として描かれていくドラマです。
危機に気付いていた母・つよの不在も痛く
折悪く、蔦重の母のつよ(高岡早紀さん)がこの世を去りました。このことも蔦重と歌麿の関係悪化に大きく関係したでしょう。
寛政4年のこの時期、蔦重の母が病気で亡くなったのは史実通りです。
蔦屋重三郎の菩提寺である東京・浅草の正法寺には母つよ(墓碑の表記では「津与」)の碑文が残されています。母の死に際し、蔦重が「私は七歳で母と別れさみしい思いをしたが後に再会し一緒に暮らすことができて今の自分がある。願わくば片言の言葉を墓に捧げてその苦労に報いてやりたい。」と語ったと記してあり、蔦重が母に深く感謝していたことが伺われます。
「本当に歌に捨てられるよ!」と予言
歌麿の微妙な思いを分かっていたつよは、蔦重に「もっと歌を大事にしないと、そのうち本当に捨てられるよ!」と警告していました。これまで、2人の間に入って緩衝材の役割も果たしていたつよの不在も、事態を悪化させることになりました。
「子供が」「泣き落とし」に歌麿は…
蔦重の提案に、なかなかいい顔をしない歌麿。弱った蔦重は「頼む。ガキも生まれるんだ。お前だけが頼りなんだ。身重のていさんには苦労をかけたくない」と頭を下げ、泣き落としです。
命の恩人でもある蔦重からここまで言われれば、さすがに断ることはできない歌麿です。しかしこの瞬間、歌麿の心の中で何かがパチンと音と立てて弾けてしまったようでした。
長いつきあいの2人ですが、こと仕事に関しては「面白いものを作りたい」「世に良い作品を届けたい」という作品本位の姿勢で常に向き合ってきました。しかしここにきて蔦重は「店が」「子供が」「妻が」という仕事とは関係ない個人的な事情を持ち出し、仕事を引き受けるよう説得してきました。厳しくも互いに妥協することのない真摯な協業こそが2人のコラボレーションの真価だっただけに、蔦重が情実を絡ませてきたのなら、自分にも考えがある、というのが歌麿の思いだったのではないでしょうか。
「もう蔦重とは終わりにします」。きっぱり西村屋に伝えた歌麿。蔦重との関係はどうなるのでしょうか。
蔦重以外の版元の仕事も増やした歌麿
史実としても、それまでは蔦重との仕事が大半だった歌麿が、寛政6年(1794)ごろから、他の版元との協業が目立って増えてきます。まもなく鶴屋とのコンビ作品も出てきます。
喜多川歌麿筆『當時全盛美人揃・越前屋内唐土、あやの、をりの』江戸時代・寛政6年(1794) 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)版元は若狭屋与市その理由としては、売れっ子になった歌麿に他の版元からオファーがあった、写楽の出現で歌麿が蔦重から離れたなど諸説あります。問題になった「印」ですが、上記の作品のように歌麿の署名が上、版元の印が下、というものも確かにあります。様々なモチーフにつよの死などの史実を合わせ、ていの妊娠などフィクションも交えて描かれた蔦重と歌麿の心の亀裂。心は痛みましたが、見事なドラマでした。
「国民を苦しめる政治は虎より恐ろしい」
「身上半減」の罰から徐々に立ち直って来た蔦重。医学書、仏教書、儒書など堅い内容の本も扱う書物問屋も兼ねて、体制を整えました。
北斎が描いた名高い江戸名所絵本。ドラマのセットもそこに描かれたおなじみの耕書堂の構えに寄せてきました。
浅草庵 作 ほか『画本東都遊 3巻』,享和2 [1802] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533327扱っている書籍の中でドラマでは「礼記」をクローズアップ。ちょっと意味深だったかもしれません。儒教の基礎的なテキストです。この一節で有名です。
『礼記正文』(周南市立鹿野図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100237536「苛政猛於虎也」。「苛政は虎よりも猛なり」。苛政の人民への害は、虎の害より甚だしい。蔦重の思いでしょうか。
名古屋の有力版元、永楽屋東四郎(佃典彦さん)とも接点ができました。永楽屋は葛飾北斎の『北斎漫画』や本居宣長の著作の刊行で知られます。ドラマの終盤に向けて、蔦重にとって重要な出会いになるのかもしれません。
ロシアの脅威を認識していた定信
光格天皇が父に太上天皇の尊号を贈ろうとした「尊号一件」など、難しい問題が次々に降りかかってきた定信。周囲からは独断専行を指摘されるようになり、同僚の離反も激しくなります。しかしとりわけ対ロシア外交は、定信にとって間違いの許されない国難でした。寛政4年(1792)10月、幕府にロシア船の蝦夷地来航の一報が伝わりました。アダム・ラクスマン率いるロシア船が、大黒屋光太夫ら日本人漂流者を乗せてネモロ(根室)に到着。漂流民を幕府に届けるために江戸へ向かいたい、という意向が松前藩経由で伝えられたのでした。定信が恐れていた事態でした。
「〈ロシア〉」が変えた江戸時代」(岩﨑奈緒子著、吉川弘文館)によると、ラクスマンの来航に際して、定信は意見書で「一番心配なのは、安房国・上総国・下総国(千葉県)と伊豆国(静岡県)で、この辺りは幕府領か小大名の領地で一向に備えがない。外国船が浦賀まで乗り入れ、品川まできてしまったら、大井川や箱根は全く無意味で、恐るべきことだ」と江戸湾の弱点を指摘しました。
ロシアが指折りの強国で、強力な軍艦を多数擁していることも定信は知っていました。無防備な江戸の姿を知られたら不測の事態を招きかねず、一隻たりとも江戸湾に入れることは許されません。ラクスマンらを刺激することなく、いかに江戸に寄らせずに帰国させるかに定信ら幕閣は腐心することになります。
定信が苦境に陥っていたタイミングで、定信から明らかに距離を取っていた老中格の本多忠籌ただかずらがなぜか「上様に叱られました。この国の守りを心より考えているのは、越中守(定信)ばかりではないかと」といい、頭を下げてきました。
定信は本多らの言葉を文字通りに受け止め、協力者が増えて大喜びでした。しかし、なんともきな臭い展開。この男の影を感じないわけにはいきません。どんな絵図を描いているのでしょうか。
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから