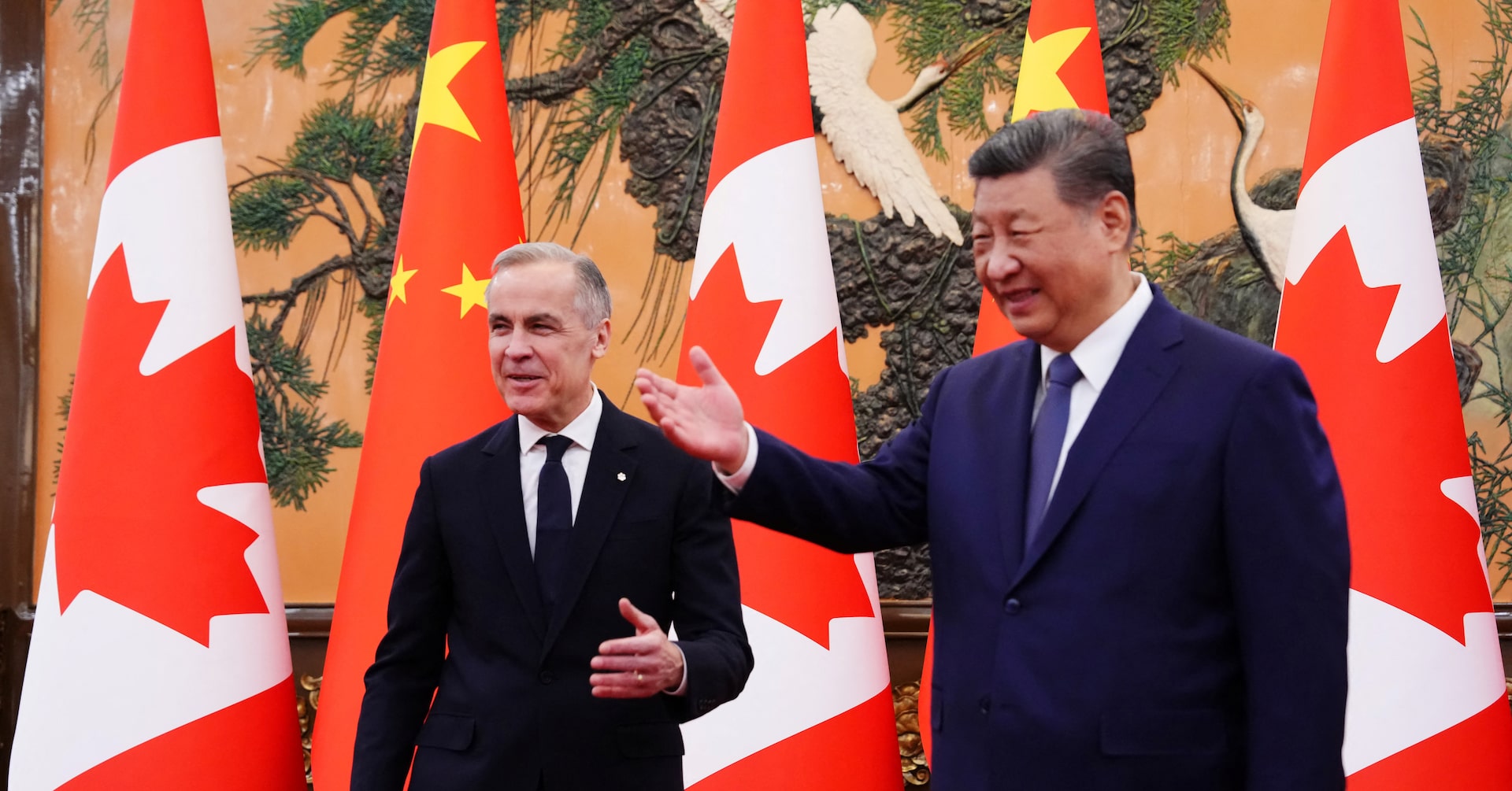「水道貧困」、米国の裕福な大都市で急増-政権はインフラ支出削減へ

清潔な水道水へのアクセスは、長年にわたり経済発展の重要な指標とされてきた。しかし、世界で最も豊かな国である米国の中でも、いくつかの裕福な都市において、この基本的なサービスを利用できない世帯の割合が上昇している。トランプ大統領が水道インフラへの連邦支出を大幅に削減する方針を掲げる中、こうしたトレンドに注意を払う必要があると研究者は指摘している。
キングス・カレッジ・ロンドンで環境正義論を教えるケイト・ミーハン教授は長年、米国で「水道貧困」と呼ばれる現象を研究してきた。この問題は、料金未納や賃貸物件の管理不備による上下水道サービスの停止が主因だ。
数十年間、水道のない生活は主に農村部に特有の現象だった。しかし、ミーハン氏が昨年12月に「ネイチャー・シティーズ」誌に発表した論文によると、住宅市場の変化に伴い、この問題が1990年代に都市部に拡大し始めた。低金利とサブプライムローン急増により住宅価格と家賃が上昇し、手ごろな住宅の供給が減少。低所得の米国民、特に有色人種は、より劣悪な住居に追いやられ、支払いを滞納する人も増えた。2008年の不況後、水道貧困の都市化が加速し、現在は水道水のない世帯の72%が都市部に居住しており、1970年代初頭の2倍余りとなっている。
ヒューストン、フェニックス、オレゴン州ポートランドなど多くの裕福な地域では、2017年から21年(完全な国勢調査データが利用可能な最新の年)にかけて問題が深刻化した。ポートランドは、高騰する生活費が低所得世帯が適切な生活水準を維持するのを困難にしているという状況を、特に顕著に示している。急速な経済成長と進歩的な社会政策の拠点としてのイメージにもかかわらず、同市は主要な大都市圏の中で最も急激な水道貧困の増加を記録している。
ポートランドで水道設備のない世帯の数は、2000年から21年にかけて56%増加した。ミーハン氏は、高騰する住宅費や停滞する賃金、手ごろな住宅の不足が、水道設備をぜいたく品とする状況に住民を追い込んでいると指摘する。
全体として、水道のない世帯の数は1970年代以降、減少傾向にある。しかし、その改善は主に白人世帯に限定されている。現在、15の大都市のうち12都市では、水道のない世帯は有色人種に偏っている。
一方、連邦政府による水関連の投資は過去50年間で急激に減少しており、1977年には資本支出の63%を占めていたが、2017年にはわずか9%にまで低下している。トランプ大統領は2026年度予算案で、上下水道への連邦支援を供給する2つの主要基金への拠出をほぼ90%削減する方針を示した。これらの基金は、地域レベルで安全かつアクセス可能な水を確保する上で不可欠なリソースだ。
ミーハン氏の研究によると、手ごろな住宅は水道を維持する上で同様に重要かもしれない。しかし、コスト上昇が明確な要因である一方で、ミシガン州立大学の社会学教授で水道貧困を研究するスティーブン・ガステイヤー氏は、この問題に進展をもたらすためにはより良いデータが必要だと指摘。「われわれは後退すべきではない」と述べている。
(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)