「胃がん」はピロリ菌、乱れた食生活が原因 専門医が指摘する“注意すべき食べ物”
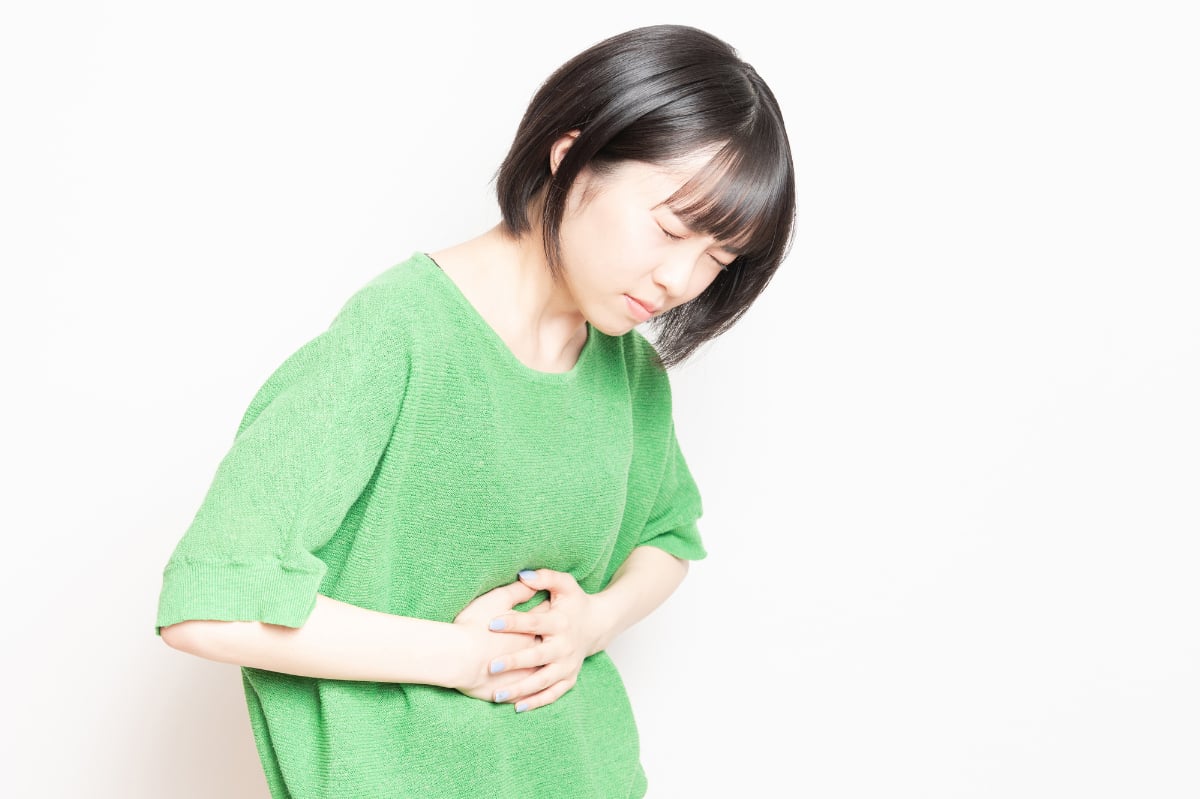
胃がんを予防するには、どのような生活習慣を心掛けるべきなのでしょうか。消化器内科医が解説します。
多くの日本人が発症するがんの一つが「胃がん」です。がん検診の普及によって死亡率は年々減少傾向にあるとされていますが、依然として多くの人の命を脅かす病気であることに変わりありません。
日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック(東京都中央区)院長で消化器内科医の石岡充彬さんによると、胃がんは日頃の生活習慣を見直すことである程度、予防できる病気だということです。胃がんの発症のメカニズムや発症リスクを高める食生活、すぐに実践できる予防対策などについて、石岡さんに聞きました。
Q.そもそも、なぜ胃がんを発症するのでしょうか。
石岡さん「胃がんを発症する最大の原因は『ヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)』への感染です。ピロリ菌は胃の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、長い年月をかけて胃がんの土台を作っていきます。実際に、一般的な胃がんの約99%は、現在もしくは過去にピロリ菌に感染していた人に発生します。感染経路としては、かつては井戸水や衛生環境が原因とされていましたが、現在では幼少期の家族間感染が主流となっており、今の若い世代でも一定数、ピロリ菌の感染者が存在しています。
胃がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどないため、発見が遅れることも珍しくありません。だからこそ、症状が出ていない段階、あるいは食欲の低下や胃もたれなどのちょっとした体のサインを感じた段階で検査を受けるのがとても重要です。
特に家族にピロリ菌の感染歴がある人や、胃がんや胃潰瘍の病歴を持つ人がいる場合は、自覚症状がなくても、胃カメラ検査とピロリ菌の検査を一度受けておくのをお勧めします」
Q.胃がんの最大の原因はピロリ菌とのことですが、食生活が原因で胃がんを発症することはあるのでしょうか。胃がんの発症リスクを高める食べ物について、教えてください。
石岡さん「胃がんの発症リスクを高める食べ物として特に注意が必要なのが『高塩分食』です。IARC(国際がん研究機関)やNCI(米国国立がん研究所)も、高塩分食が胃がんの明確なリスク要因と位置付けています。
日本人の食生活は世界的に見ても塩分が高めです。厚生労働省が公表する塩分摂取量の推奨値は、男性で1日7.5グラム未満、女性で6.5グラム未満です。WHO(世界保健機関)はさらに厳しく、1日5グラム未満としています。しかし、例えばカップラーメンや袋入りのラーメンを食べるときにスープまで飲み干した場合、それだけで6〜7グラムの塩分を摂取するケースもあり、あっという間に1日の上限を超えてしまいます。
さらに、塩分過多は肥満の原因にもなりやすく、肥満そのものもまた、がんのリスクを高める要因とされています。『ラーメンを食べるのをやめるべき』とまでは言いませんが、『スープは残す』『減塩タイプの商品を選ぶ』『調味料の追加を控える』などの食べ方を意識することから始めてみてはいかがでしょうか」
Q.実は健康的に見える食べ物が、胃がんの原因になることはあるのでしょうか。
石岡さん「一見すると『体に良さそう』と思われる食品の中にも、実は胃がんリスクと関係しているものがあります。その代表的な食べ物が漬物です。漬物は発酵食品として、腸内環境に良いイメージを持つ人も多いですが、その反面、塩分濃度が非常に高いものも多く、毎日大量に食べることは、胃の健康にとって決して好ましいとは言えません。
また、保存中に発酵が進む過程で、発がん性物質である『N-ニトロソアミン』が生成される可能性があるという研究報告もあります。漬物の摂取量が多い人は少ない人に比べて胃がんのリスクが1.24倍高くなるという報告があり、漬物の摂取量が1日40グラム増えるごとにリスクが1.15倍上昇するといわれています。
同様に、梅干しやみそ汁なども、健康的なイメージが強い一方で、塩分の過剰摂取につながりやすい食品です。梅干し1粒にはおよそ2グラム前後の塩分が含まれているほか、みそ汁1杯には1.5グラム程度の塩分が含まれています。
もちろん、これらの食品を避ける必要はありませんが、『健康的=食べ過ぎても大丈夫』というわけではないという意識は重要です。味が濃い漬物を食べるときは少量にとどめ、梅干しやみそを購入する際は塩分控えめの商品を選ぶなど、摂取量と摂取頻度に気を付けることで、胃を守る食べ方が可能となります」
Q.胃がんの発症リスクをできるだけ減らすために、塩分の過剰摂取を控えるほかに、日頃からできる対策はありますか。
石岡さん「果物や野菜の摂取は、胃がんの発症リスクを下げる可能性があるとされています。果物にはビタミンCやカロテノイドなどの抗酸化物質が豊富に含まれており、胃粘膜の損傷や炎症を軽減する働きによって、果物の1日の摂取量が100グラム増えると胃がんのリスクが約5%減少するという報告もあります。
『野菜や果物をたくさん食べていれば胃がんにならない』とまでは言えませんが、日々の食事の中にもう一皿サラダを加えたり、菓子の代わりに果物を取り入れたりするといった食習慣を積極的に取り入れるとよいでしょう」
Page 2
Q.ちなみに、近年、ピロリ菌に感染していないのに胃がんになる人が増えているという話を聞きますが、このような話は実在するのでしょうか。
石岡さん「実在します。ピロリ菌の除菌治療が普及してきた近年の傾向として、ピロリ菌陰性(未感染)の人でも胃がんになるケースの増加が指摘されています。特に『食道胃接合部がん』という、胃の入り口付近にできるがんの割合が相対的に増えてきています。この食道胃接合部がんは、従来のピロリ菌由来の胃がんとは発生経路が異なると考えられており、そのリスク因子として注目されているのが『飲酒』や『肥満』です。
飲酒量が多いほどがんの発症リスクは高まりますが、特に1日に3杯以上のお酒を飲むと、リスクは顕著に上昇するとされています。さらに、男性に多い内臓脂肪型肥満も、食道胃接合部の慢性的な炎症や負担の原因になります。つまり、ピロリ菌に感染していないからといって胃がんとは無縁ではないということです。ピロリ菌の有無にかかわらず、『飲酒量を見直す』『週に2日は休肝日を設ける』『適正体重を保つ』といった工夫が、今後の胃がん予防にはますます重要になってきています。
胃がんを予防するためには、まず日々の生活習慣を見直すことが大切です。胃がんのリスク因子である高塩分食や過度な飲酒、喫煙、肥満は、日々の意識と工夫で改善することができます。
ただし、それでも最も重要なリスク因子はピロリ菌の感染であることを忘れてはなりません。食道胃接合部がんなどの『ピロリ陰性胃がん』が増加しているとはいえ、ピロリ菌に感染していない人が胃がんになる確率は極めて低く、ピロリ菌の有無を調べることは胃がん予防における最初の一歩です。だからこそ、まずは自分がピロリ菌に感染しているかどうかを知ること、そして必要に応じて除菌治療や胃カメラ検査を受けることが、将来の健康を守る大きな一歩になります。
症状がない人にとっては、今こそがピロリ菌の検査を受けるのに適したタイミングです。大切な自分自身の体のために、そして家族のために、ぜひ一度検査を受けてみてください」
(オトナンサー編集部)



