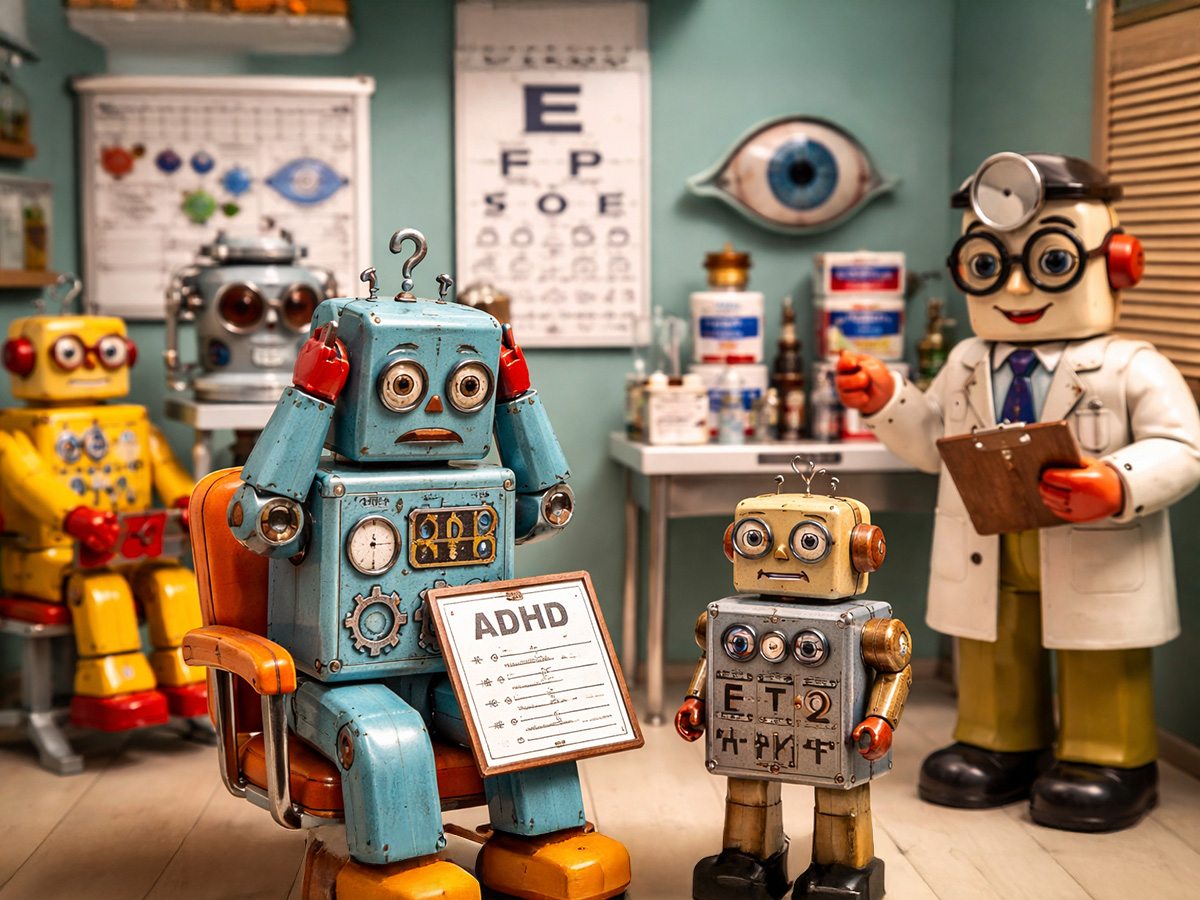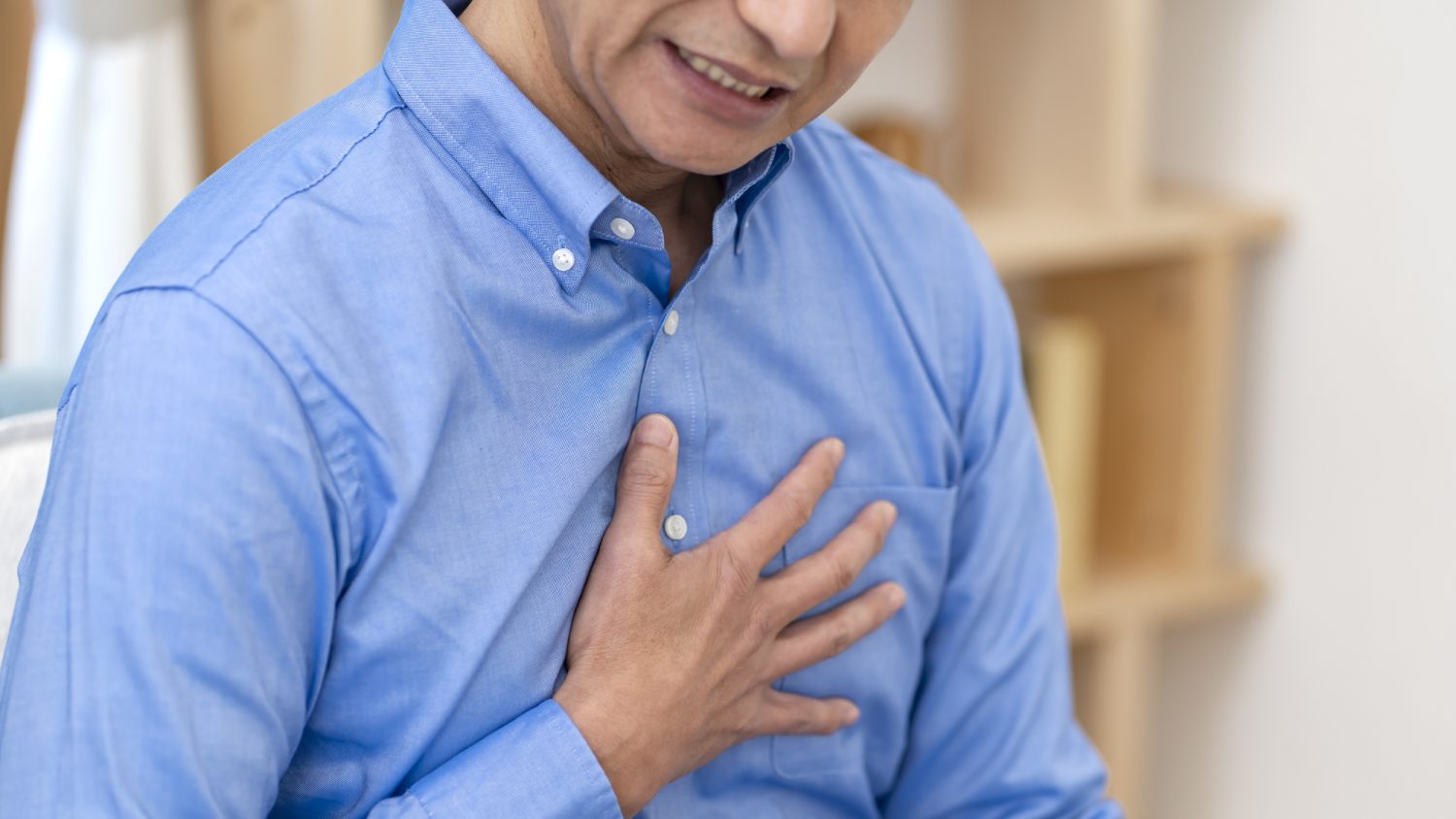健康情報のウソ・ホント!「なんだか体調が優れない」原因は体温調節の機能不全?(東洋経済オンライン)

10/20 7:01 配信
日本オリンピック委員会(JOC)の情報・科学サポート部門長や、日本陸上競技連盟科学委員会委員長などを歴任してきた杉田正明氏が新刊『トップアスリートが実践している世界最強の健康マネジメント』で、最前線の健康術を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。■「100%」「勝つ」「消える」には要注意
スマートフォン1つでインターネットにつながり、世界中のさまざまな情報にアクセスできる現代において、論文だけが根拠でないとなると、「いったい、何を信用したらいいの?」となる人も多いでしょう。
ネットの情報も玉石混淆ですので、相当慎重に確認していくことが大事です。 まず、「がんが消えた」のような誇大広告的なものは、1回立ち止まってみる必要があります。なぜなら100%効果があるものは存在しないからです。
がんの患者さんにとっては、藁にもすがる思いなのも理解できますが、「100%」「必ず」「死滅」「勝つ」「消える」というように表現が断定的なものや、強い言葉を使っている広告は、効果が誇張されている可能性もあります。
ただし私は、民間療法(代替療法、代替医療)についてはなから否定的な立場ではありません。 たとえば、がんの療法には「断食をする」「にんじんジュースを飲む」「ショウガで身体を温める」「酵素風呂に入る」といったものもあり、中には医師が提唱しているものもあります。
私は、ものにもよりますが、試してみても良いと思っています。「これは明らかに違う」というものは別として、標準治療と並行してにんじんジュースを飲んだり、酵素風呂に入ったりして自分に合うか合わないかを確かめてから判断しても良いと思っています。
がんに関して言えば、1868年にドイツの学者が、高熱にうなされた数日後にがん細胞が消えたという症例を初めて報告しました。 そして、熱に対する生体防御のための特殊なタンパク物質が体内で生産されることが発見されました。これがヒートショックプロテイン(HSP)と命名され、そこからヒートショックプロテインは免疫力を向上する効果があるということが世に知られるようになりました。
ヒートショックプロテインは、熱から体を守るだけでなく、壊れた細胞の修復をしたり、寒さや活性酸素から守ったり、重金属やアルコール、炎症などの体のストレスに対処し、疲労回復を助ける役割もあります。
日本では昔から湯治(とうじ)と言って、温泉地に長期滞在して温泉に入って病気を治したり体調を整えたりしていました。ヒートショックプロテインが起これば延命治療になるということについては、いくつかのエビデンスも出ています。■検索結果をうのみにしてはいけない
医療従事者でない人にとって、何が「トンデモ医療」「インチキ医療」で、何が「代替療法」や「代替医療」であるかを区別するのは難しいことかもしれません。
インターネットで検索をしたり、今ならChatGPTなどのAIに聞くこともできますが、AIの精度もまだまだ低い状況です。ちなみに以前、私自身の名前を調べたところ、別の大学の教授として出てきました。 おいしいお店や観光情報などを調べる分には情報が間違っていても「いい加減だなぁ」と笑い話で済みますが、健康に関わるような情報や治療法を100%信じるのは危険です。
また、テレビや雑誌、インターネット上の情報を妄信してしまうのも良くありません。通常の番組や記事のように見えて、実は広告記事として制作されているものも少なくないからです。
こういった広告記事は、「広告」「PR」「Sponsored」という単語の明記が義務付けられていますが、欄外などに小さい文字で書かれていたりするので、見逃してしまう人も多いと思います。
好感度の高い芸能人や有名人が出ていると、「あの人がおすすめしているから良さそう」「信頼できそう」と漠然と思ってしまいますが、「本当に良いものかもしれないし、でも違うかもしれない」という視点を常に持つことが大切なのです。
■新しい成分ほど摂取のリスクを視野に入れる たとえば、ビタミンCやビタミンDのように昔から使われている栄養素であれば、幅広い分野でのさまざまなエビデンスや知見もたまっていますが、新しい成分などは、新しければ新しいほど情報もないので、まだ海のものとも山のものともつきません。今は良くても10年後、20年後にどんな副作用があるか、誰も答えることはできません。
ですから、そういうものについてはある程度のリスクを視野に入れながら自己責任で摂るしかありません。ただ、アスリートの場合はドーピング検査があるので、サプリメントにしても風邪薬にしても、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)と呼ばれる世界的なドーピングに関する機関が禁止しているものは摂ることができません。
WADAでは、人体に害があるものはドーピングの禁止薬物に指定していますし、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)のホームページでは、何が該当するか検索システムで調べることもできます。 このように健康情報は巷に横濫していますが、まずはデータ元がしっかりしているのか、厚生労働省や学会など公的機関が認めているものなのか、営利目的の広告宣伝文ではないかをポイントに精査することが重要です。
本書では基本的に国内外の論文や、私の研究室で行ったデータをベースにしていますが、人間が生物としての普遍性を持つと同時に個別性という要素を持ち合わせており、アスリートを対象としたサポートでは、どちらの立場に偏っても良い成果は望めないと実感しています。
普遍性を追求する科学研究とそれだけでは解明できない個別性の問題を追及する実践研究とは、それぞれの限界を補完し合いながら、まさに車の両輪のように、互いの長所を活かし合う関係であるべきと考えています。
なかなか一般の人が論文の元を辿って調べるといったことは難しいのですが、情報については一次情報(実際に本人が体験したこと)なのか、二次情報(実際に体験した本人から聞いたこと)なのか、三次情報(出所不明な情報)なのか、なるべく発信元を辿ってチェックすると良いでしょう。
■日常生活に潜むさまざまな不調の原因 コロナ禍のときは、行く先々で検温をする機会があったと思いますが、みなさんはご自身の平熱を知っていますか? 37℃に近いと「平熱が高い」、35℃に近いと「平熱が低い」というイメージがありますが、実は私たちの体温は1日の中で変動があります。
そもそも、生物には24時間周期のリズム(サーカディアンリズム、概日リズム)があります。これは、体内時計と言うとわかりやすいかもしれません。
覚醒したり、眠くなったり、ホルモンが分泌されたり、体温が上下したりと、人間の体の中では、あらゆる生理現象が24時間周期のリズムで繰り返されています。 外部配信先ではグラフなどの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。
グラフを見ていただければわかるように、夜中に深く眠りについているときは体温が低くなります。この温度は深部体温と呼ばれ、脇の下よりも約1℃ほど高くなっています。
この深部体温は、夜中の2時から徐々に上がってきて、日中の12時から15時ぐらいがピークとなります。そこからだんだん体温が下がり、寝る直前に最も下がります。つまり人間の活動のサイクルとともに上がり、夜にかけて下がってくるのは、体を休める必要があるというサインでもあるのです。
グラフのように①起床時に体温が36℃以上、②ピーク時は正午から15時ごろ、③起床時と就寝時の差が少ないことが正常な体温リズムなのです。
しかし、このリズムが狂ってしまうと心身の調子も狂ってしまいます。 たとえば健康な中高生452名を対象とした起床時体温の標準体温群と低体温群の比較があります。 起床時に36℃以上ある子ども(標準体温群)と、起床時に36℃以下の子ども(低体温群)を比べたところ、体温が低い子どものほうが学習や運動の意欲が低下してしまうことがわかりました。
これは、起床時の体温が低いほうが脳や体の働きが鈍くなり、心身に不調が起きやすくなるためです。
標準体温群の子どもたちは、昼の12時から体温がピークになりますが、低体温群の子たちは夕方18時がピークになります。極端な話、半分眠った状態でずっと活動しているわけですから、意欲やパフォーマンスが下がるのも当然です。 実際に、スポーツのパフォーマンスとの関係を調べたデータもあります。
25名(女性13名、男性12名)の競泳選手に、丸2日間にわたり200mの競泳タイムと体温の関係を調べました。すると競泳タイムは体温に比例しており、1日の中で体温の高い時間帯が、より競技成績が良いという結果になりました。
体温が高いとスポーツのパフォーマンスが向上することについて、勉強や仕事、日常生活においても同じことが言えます。 逆に、体温が低いときは、体が何らかの不調を抱え、悲鳴を上げている状態だと考えられます。「防衛体力」は測ることができませんが、ある意味、体温は防衛体力を表す、非常に意味のある指標でもあるのです。■頑張る人ほど要注意! オーバーヒートの落とし穴
なぜ体温リズムが狂ってしまうのか。これにはいくつか理由が考えられると思いますが、本来人間が持っているリズムが先天的に狂っているという人は、ほとんどいません。
高体温の人でも低体温の人でも、日中にピークになり夜は下がるというリズムは同じです。低ければ低いなりに相似形になるので、夕方に体温のピークになるというのは、後天的な原因が考えられます。たとえばスマホの使いすぎで、夜中目が爛々として朝起きられなくなる、というようなことがその理由だったりします。
学生に限らず、社会人で出勤意欲がなかったり、主婦で午前中は家事をしたくないという人は、この体温のサーカディアンリズムが狂っている可能性が高いのです。
また、反対に午前中に体温が高くなるパターンの人もいます。たとえば、毎日ものすごくハードに勉強している子どもは、午前中の体温が高いのです。これは、体が過剰に興奮しているからです。 勉強を頑張っていると、親や先生は安心するかもしれませんが、勉強のしすぎは疲労につながります。夜型生活をしていないから良いというわけではありません。大人も朝からエンジン全開で仕事をしているとリズムが狂ってしまいます。
この状態をスポーツ選手の場合はオーバートレーニング症候群、仕事をしている人はワーカホリックと言ったりしますが、過集中はサーカディアンリズムが崩れ、慢性疲労症候群をひき起こしますので注意が必要です。
疲れがたまれば、免疫力が弱まり、風邪もひきやすくなります。
東洋経済オンライン
最終更新:10/20(月) 7:01