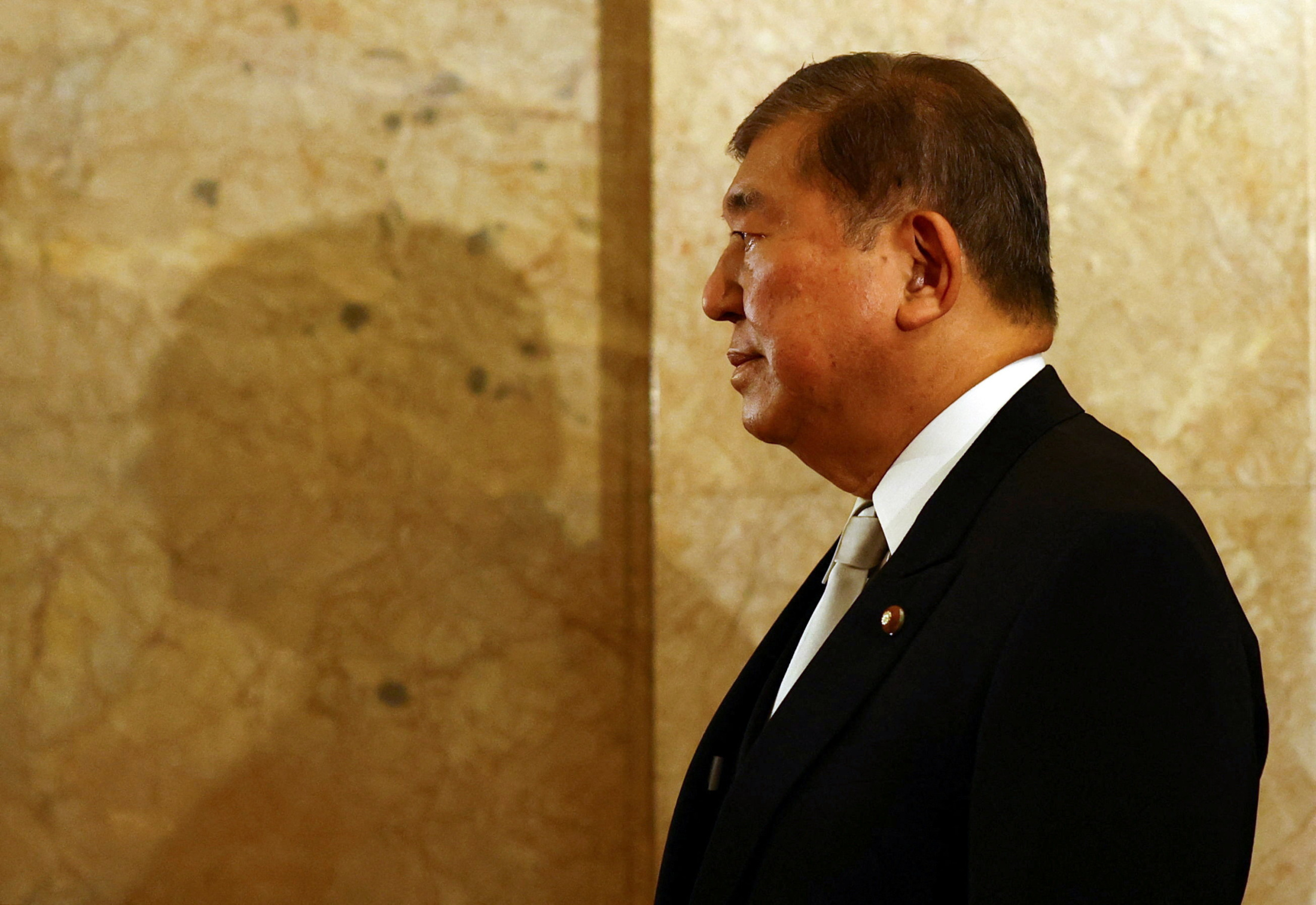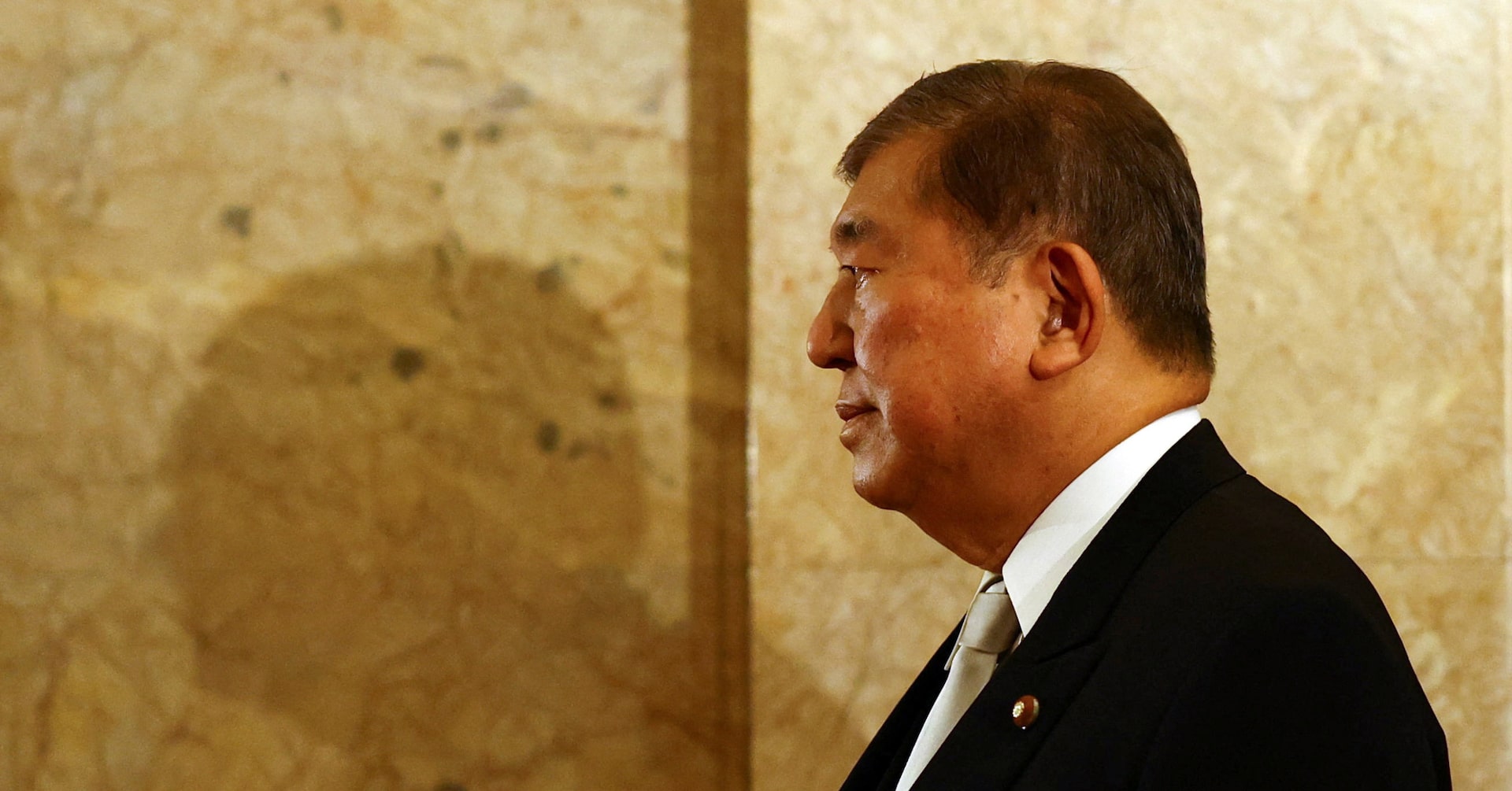疫病が4000年前に欧州からアジアへ謎の蔓延、原因を解明か

発掘調査によって青銅器時代の家畜の骨が数千点発見された/Courtesy Taylor Hermes
(CNN) 古代のユーラシア大陸では、ある疫病が数千年にわたって繰り返し発生し、急速に広まった。ネズミに寄生する感染したノミにかまれることで人間にも広がるペストは、14世紀には「黒死病」として悪名をはせた。ノミにかまれることが現在でも最も一般的な感染経路だ。
青銅器時代のころは、ペスト菌である「エルシニア・ペスティス」は、後の系統がノミによって拡散することを可能にする遺伝子ツールをまだ開発していなかった。科学者は、なぜこの病気が当時まで存続できたのかいまだ理解できずにいる。
国際的な研究チームが、ヒト以外の宿主である、現在のロシアにあたる地域で約4000年前に生息していた青銅器時代の家畜羊から、初めて古代のペスト菌のゲノムを回収した。この発見により、科学者は、古代におけるペスト菌の伝播(でんぱ)と生態について、より深く理解できるようになり、家畜がユーラシア全土への病気の蔓延に何らかの役割を果たしたと考えるようになった。今回の研究結果は学術誌セルに掲載された。
マックスプランク感染生物学研究所の博士研究員で論文の筆頭著者のイアン・ライトマカ氏は「ペスト菌は先史時代に出現した、ヒトと動物の間で感染する人獣共通感染症だが、これまで古代のDNAを用いた研究はすべて人骨から採取されたもので、ヒトがどのように感染したのかという点については多くの疑問が残り、答えはほとんど得られていなかった」と述べた。古代人から回収されたペスト菌のゲノムは約200個あるという。
ライトマカ氏によれば、動物の体内に古代の細菌が見つかったことは、細菌の系統進化の過程を理解するのに役立つだけでなく、現代の疾患の理解にも影響を与える可能性がある。「進化はときに『怠惰』で、似たような問題に対して、同じ種類の解決策を独自に発見することがある。ユーラシア大陸全域で2000年以上ものあいだペスト菌が繁栄するために役立った遺伝子ツールが再び使われる可能性がある」
青銅器時代の疫病の謎を解明する
ユーラシア大陸でペストを引き起こした古代の細菌は、現在では後期新石器・青銅器時代の系統として知られ、欧州からモンゴルに広がり、6000キロにわたって病気の証拠が見つかっている。
発表によれば、最近の証拠は、現代人の病気の大半が過去1万年以内に出現し、家畜やペットなどの動物が飼いならされた時期と一致していることを示唆している。科学者は、げっ歯類以外の動物も青銅器時代のペスト感染という大きな謎の一部であると疑っていたものの、動物の宿主から回収された細菌のゲノムがなかったため、どの動物だったのかは明らかでなかった。
研究者は古代のペスト菌のゲノムを見つけるため、ロシアの「アルカイム」として知られる遺跡から出土した青銅器時代の動物の骨を調査した。この集落は畜産における技術革新で知られるシンタシュタ・ペトロフカ文化と関連があった。研究者はそこで、失われたつながりを発見した。それは、この地域の人々にみられるペスト菌と同じ菌に感染した4000年前の羊の歯だった。
論文の共著者でアーカンソー大学のテイラー・ハーミーズ助教(人類学)は、感染した家畜の発見について、家畜化された羊が人間と感染した野生動物との橋渡しの役割を果たしていたことを示唆していると述べた。
ハーミーズ氏によれば、ユーラシア・ステップに住んでいた青銅器時代の遊牧民がどのようにして他の地域にも影響を及ぼす可能性のある病気の伝播の舞台を整えていたのかを解明しようとしている。「後世だけでなく、はるか遠く離れた地域にも影響を及ぼした可能性がある」
ハーミーズ氏によれば、この時期のユーラシア・ステップでは、一部の墓地は遺体の最大20%がペストに感染し、そのために死亡した可能性が高い。これにより、ペストはきわめて広範囲に蔓延した病気だったことが示されている。家畜は一見、ペストの蔓延の一因となっているようにみえるものの、それはパズルのピースの一つに過ぎない。動物における細菌系統の特定は、この病気の進化だけでなく、欧州で黒死病を引き起こした後代の系統、そして、今日まで続く系統を研究する新たな道を切り開くものだという。
マクマスター大学の古代DNAセンター所長で進化遺伝学者のヘンドリック・ポイナー氏は「驚くことではないが、古代の動物から(DNAが)分離されるのを見るのは本当に素晴らしい。人間で見つけることは非常に困難で、動物の遺体で見つけるのはさらに困難だ。そのため、これは本当に興味深く意義深い」と述べた。ポイナー氏は今回の研究には関与していない。
ヒトと動物の間で菌株が相互に伝播していた可能性が高いが、どのように伝播したのか、そして、そもそも羊がどのようにして感染したのかは不明だ。羊が食べ物や水を通じて細菌を拾い、汚染された動物の肉を介してヒトに感染させた可能性もあるという。
ポイナー氏は、これはこの細菌がいかに大きな成功を収めたかを示していると思うと述べた。ポイナー氏は、さらなる研究によってこの古代の系統に感染した他の動物が発見され、病気の蔓延と進化についての理解が深まることを期待していると述べた。
青銅器時代に存続したペスト菌の系統は絶滅したが、エルシニア・ペスティスはアフリカとアジアの一部、米西部、ブラジル、ペルーに今も存在している。だが、この細菌に遭遇することはまれで、ペストの症例は世界中で年間1000~2000件にとどまる。
家畜やペットの扱いに関しては、心配する必要はないとハーミーズ氏は語った。今回の発見は、動物が人間に感染する病気を保有していることを改めて認識させるものだ。ハーミーズ氏は、肉を調理する際や動物にかまれた際には注意が必要だと指摘した。