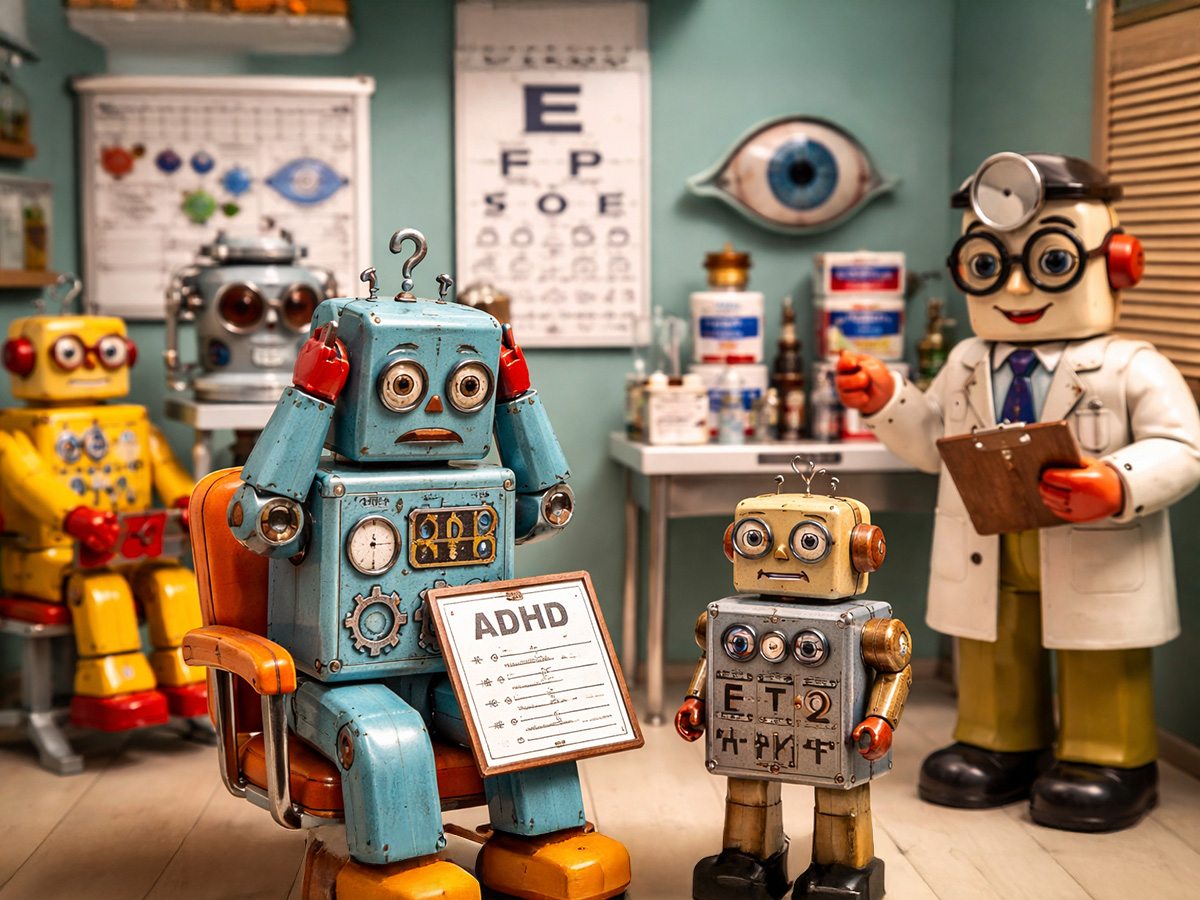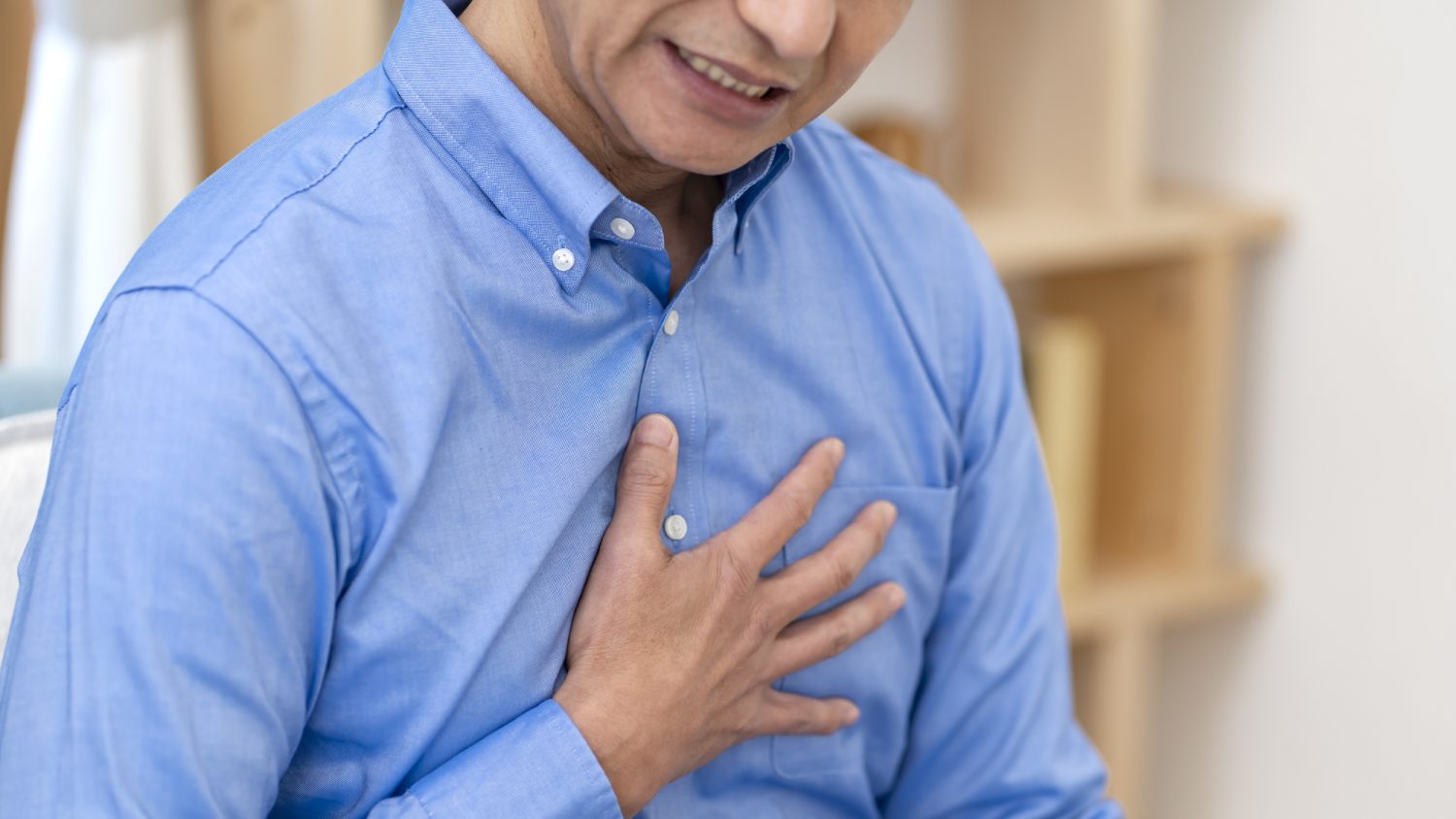「アルツハイマー」の痕跡がありながら、亡くなるまで“ほぼ症状が出なかった”シスターの【脳の密度】(東洋経済オンライン)

10/12 12:31 配信
年を取っても頭がシャキッとして、「なんであの人、高齢なのにあんなに元気なの?」という人っていますよね。名城大学特任教授の遠藤英俊氏によれば、こうした人は、脳の一部の機能低下を補う「予備脳」が発達しているといいます。何歳からでも鍛えられるというこの「予備脳」。本稿では、その驚くべき力を示したあるシスターの事例について、遠藤氏の著書『こうして脳は老いていく』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
■「脳の偏り」が起きても老化の症状が現れない人たち
人は年を取ると、多かれ少なかれすべての人に脳の偏り(正常に機能しているところもあれば、低下しているところもある状態)が起きます。年を取っても、まったく脳が衰えないという訳にはいかないのだから、当然ですよね。 しかし、あなたの周囲にも、年を取っても頭がシャキッとして、言葉も明瞭で、動作もそこまで遅くならずに、「なんであの人、高齢なのにあんなに元気なの?」という人がいるのではないでしょうか。
そうです。世の中には年を取っても老化の症状があまり現れない人がいます。現れたとしても、ちょっと「若い頃より記憶力が落ちたかな」という程度。脳の偏りはたしかに起きているはずなのに、「なぜ?」と思いますよね。
その謎を解明するヒントとなる研究が、1986年からアメリカで行われた「ナン・スタディ」という高齢期の脳と認知機能に関する大規模な縦断的疫学研究です。 この研究は、後に研究者でもあったデヴィッド・スノウドン博士によって『100歳の美しい脳 アルツハイマー病解明に手をさしのべた修道女たち』(ディーエイチシー)にまとめられ、世界の人に広く知られることになります。
研究対象者は、アメリカのノートルダム教育修道女会にいる678人のシスターたち(70〜100歳代の高齢女性)です。研究方法は、生前の生活、健康状態、認知機能テストの追跡調査と、死後の脳提供による病理解析。
彼女たちは、自分たちの人生を誰かのために役立てたいという思いで研究に参加したといいます。シスター・リタという人は、「私たちは子どもを産まなかったけど、脳を研究に提供することで未来の人たちにプレゼントを贈れる」と言っています。
なぜシスターたちが選ばれたのかというと、彼女たちの暮らしがとてもシンプルで、みな同じような環境で生活をしていたからです。さらにいえば、修道院の規律でタバコやアルコールといった嗜好品の影響を、研究結果から排除することができたからです。
この研究で、とても驚くような発見があります。100歳を超えても記憶力や判断力が保たれていて、日常生活もほぼ自立していたシスターの脳を亡くなった後で解剖してみると、重度のアルツハイマー病レベルの病変があったのです。
脳内に典型的なアルツハイマー病の痕跡が多数見られながら、そのシスターは亡くなるまで読書や書き物を楽しみ、会話もスムーズだったそうです。一方で、アルツハイマー病の症状が現れたシスターの脳を亡くなった後で解剖すると、当然のごとく病変が確認されました。
症状が現れる人と現れない人の違いはどこにあるのでしょうか。それが、これからお話しする、脳の偏りからあなたの脳を守る「予備脳」という概念です。研究が始まったばかりですが、介護や誰かのお世話になることなく、最後まで人生を楽しむための考え方として期待されています。■脳の機能の衰えをバックアップする「予備脳」
予備脳は、予備という言葉から推測できるように、いざというときに備えて前もって準備しておく脳のことです。いざというときとは、脳の老化が始まったときです。脳にこんな機能があるなんて、初めて知ったという方も多いことでしょう。
予備脳とは脳の特定の部位のことではありません。脳全体に張り巡らされた神経ネットワークが、衰えた機能を支える役割を担っているということです。 目的地にたどり着く道路がたくさんあれば、例えばひとつの道が通行止めになったとしても、別のルートを使えばたどり着けます。「小指を動かす」という回路がひとつだとその回路が衰えると小指を動かせませんが、別の回路があれば小指を動かせるということです。
脳の偏りによって一部の機能が低下しても、バックアップできる回路がある。それによって老化の症状が抑えられることがあるし、現れないこともある。予備脳とはそういうものだと考えられています。
■脳の密度が高いほど「予備脳」の力が強い それでは、予備脳はいかにしてつくられるのかというと、参考になるのは、先ほどの病変があったのに症状が現れなかったシスターの生活です。
そのシスターが20代の頃に書いた自己紹介文は、言葉が豊かで、たくさんのアイデアや考えが詰まっていたといいます。若い頃から考えたり、学んだりすることが好きだったのでしょう。修道院に入ってからも読書を楽しみ、日記を書き続けていたそうです。
ある研究者は、予備脳を「脳の貯金」と言っていますが、若い頃からの脳を使うことの積み重ねが予備脳をつくるのは間違いなさそうです。 修道院での生活も予備脳に大きく影響したと考えられています。編み物をしたり、仲間と奉仕活動をしたり、野球の試合を楽しく観戦したり、共同生活で孤立することなくいつも誰かとおしゃべりをしたりなど、脳を使う機会が多かったと思われます。
ここまでの話でお気づきかもしれませんが、予備脳は、先天的というより、後天的な影響が大きい能力だということです。
予備脳に影響したかどうかはわかりませんが、ストレスが少なく、決まった時間に起きて、きちんとご飯を食べて、規則正しい毎日を送るという修道院での生活は、脳の老化を早めることはなかったのでしょう。 シスターの生活を参考にすると、脳をたくさん使ってきた人ほど予備脳が強くなるということは言えると思います。つまり、脳の密度が高いほど予備脳が強いのではないかと考えています。
脳の密度が高いとは、脳の中にある神経回路が縦横無尽に張り巡らされているイメージです。 先ほど、ひとつの道がふさがっても、別の道が使えるとご説明しました。
しかし、その別の道がふさがったらやっぱり目的は達成できません。では、道が3つ4つ、5つとあればどうでしょうか。 何かあってもバックアップが可能ですよね。つまり、神経回路という道ができるだけたくさんあるほうが、バックアップ機能が働きやすくなるというわけです。
脳にある神経細胞は、ピーク時には約860億個もあります。その神経細胞が縦横無尽につくるネットワーク(神経回路)は壮大なスケールです。加齢とともに、その細胞や回路は少なくなりますが、多少減ったところで、もともとのスケールを考えるとカバーできます。
それができることを証明したのが、アルツハイマー病の病変がありながら、症状が現れなかったシスターだと思っています。そのためには、たくさん脳を使って回路を密にすることです。 ※外部配信先ではイラストを全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください■予備脳は90歳でも強化できる
脳をたくさん使ってきた人のほうが強力な予備脳を備えていることになります。つまり、予備脳が強いかどうかは、後天的な要素が大きいということです。
ここで気になるのは、予備脳強化は何歳まで可能なのか? 「私は、若い頃そんなに脳を使っていなかったから『脳の貯金』が少ないかも」「きっと予備脳が働かない、もうダメだ」と思う人もいるかもしれませんが、おそらく何歳になっても予備脳は強化できます。
筋肉は90歳を過ぎても鍛えると強くなるといわれますが、予備脳も同じです。90歳からでも鍛えると強くなります。なぜなら、脳には「可塑性」という特性があるからです。
脳の可塑性とは、新しい経験や学習、環境の変化に適応して、構造や機能を変化させる、脳に備わっている素晴らしい能力のことです。例えば、外国語を学んだり、ピアノを練習したりなど、それまで経験したことがないことに挑戦すると、脳はそれに合わせて新しい神経回路をつくります。
そして、くり返し使うことでその回路はどんどん太く、しっかりしたものになります。この変化は粘土をこねて自由に形を変えるような柔軟さで、脳が自らアップデートしていくのです。
あなたは、けがで手が使えなくなって足で絵を描く人を見たことがありますか? これを可能にするのも脳の可塑性。脳の一部が損傷しても、それを補うための神経回路がつくられるからです。■脳は一生、新しいことに応じて変化し続ける
驚くべきことに、この脳の可塑性という能力は90歳を過ぎても失われません。若い頃と比べると変化のスピードは遅くなるかもしれませんが、脳は一生を通じて新しいことに応じて変化し続けることができるのです。
また、脳は、90歳になっても新しい神経細胞を生み出す力を持っています。ただし神経細胞は再生力が低いのは事実です。 そのため、大人になると新しい神経細胞はつくられないと考えられてきました。しかし、近年の研究で、特定の場所ではつくられることがわかってきたのです。 現在確認できている場所は2つで、ひとつは、記憶や学習をつかさどる海馬、もうひとつは、前頭葉の下のほうにある、匂いを感じる「嗅球」です。
一般的に加齢とともに少なくなりやすいといわれる海馬の細胞が少しでも増えるなら、それだけで記憶力の低下を抑えられることになります。
90歳でも増えるというのはうれしいニュースです。もちろん、先ほども述べたように細胞を生み出す力も、若い頃と同じようなスピードでというわけにはいきません。しかし、筋肉がそうであるように、90歳になってもあきらめなければ、脳もしっかり応えてくれるのです。
東洋経済オンライン
最終更新:10/12(日) 12:31