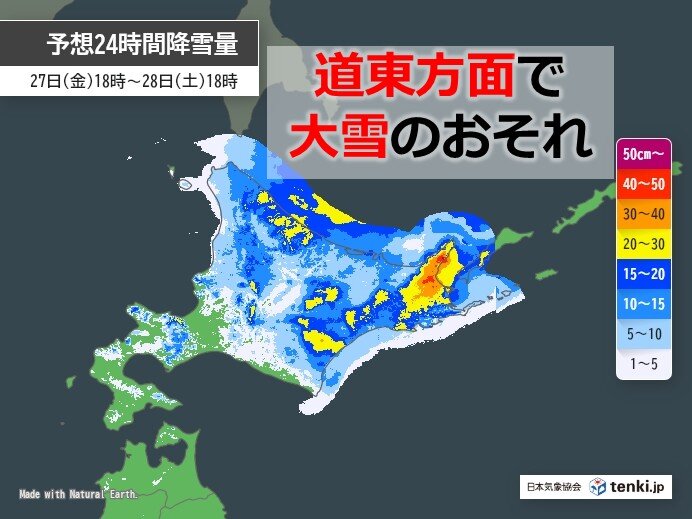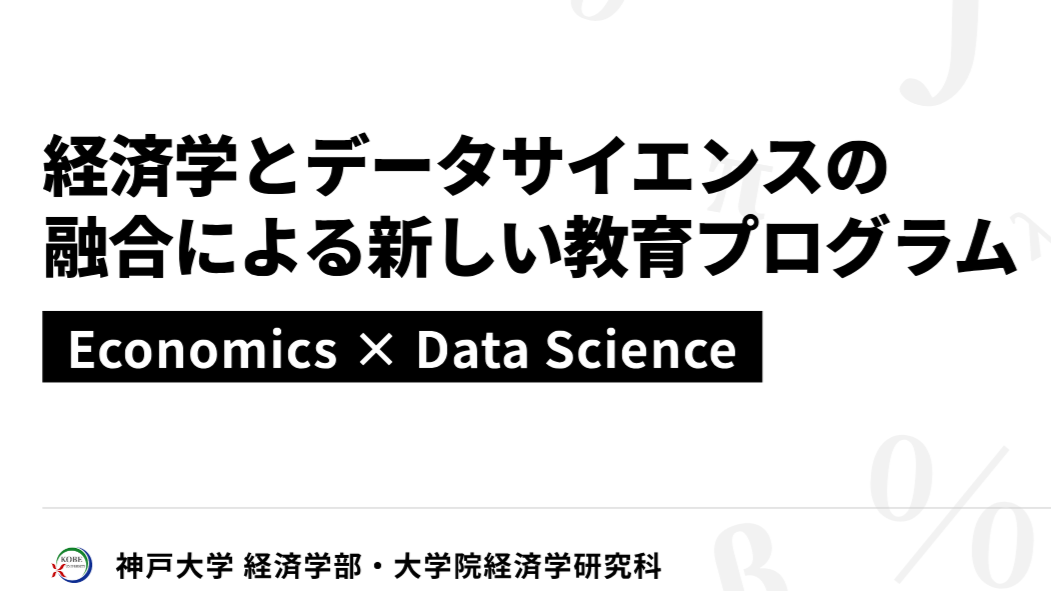八潮陥没、穴の近くの「雨水管」破断で排水機能に大きな支障…大雨などで市内全域が氾濫の恐れも

埼玉県八潮市は26日、県道陥没事故に伴い、陥没した穴の近くを通っていた雨水管が破断し、雨水の排水機能に大きな支障が出ていると発表した。大雨などの際に市内全域で氾濫が起きる恐れがあるといい、市は早急に対策を検討する。
大山忍市長が同日の定例記者会見で説明した。
市などによると、破断したのは「大正第一幹線」という雨水管の幹線で、2・1メートル四方のコンクリート製。市北部から市中心部を経由して陥没地点を通り、市南部の垳川に通じていた。1月28日の陥没事故で宙づりになり、同30日、雨水管自身の重さで崩落した。
雨水管などによって、同市では1時間あたり約47ミリまでの雨量に耐えられたという。だが、同幹線が破断して排水機能は大幅に低下。梅雨など雨が多い時期や大雨の際に、広範囲で浸水被害が起きる可能性があるという。
市は、県や国と対策を協議しているが、陥没地点周辺の復旧工事が進まないと、雨水管の本格復旧も困難とみている。当面は仮設の雨水管の設置を急ぎ、大雨の際は別の雨水幹線に流れるようにするなどの応急策を検討し、浸水を食い止める方針だ。
大山市長は26日の記者会見で、2025年度当初予算案には陥没事故の関連経費を計上せず、24年度中は予備費で、25年度は補正予算で対応する考えも示した。予備費では、避難所の運営費や電話対応に関わる職員の人件費などを手当てする。「負担について県と協議したい」とも話した。
八潮市が進める下水道緊急点検、慎重に作業
点検のため、マンホールを開け下水道の中に入る作業員(26日、八潮市で)八潮市は、市が管理する下水道(20・5キロ)の緊急点検を進めている。26日は、陥没地点の東側約600メートルでの点検作業を報道陣に公開し、作業員がマンホールを開け、流れに異常がないかなどを確認していた。
市独自の点検で、231地点を対象に20日から実施している。
26日は、委託を受けた下水道調査会社「三郷興業」(三郷市)の作業員が、地下約8メートルの下水道に入り、壁面のひび割れや 堆積(たいせき) 物の有無などを確認。専用の検知器で、腐食の原因となる硫化水素ガスの濃度も測定した。
同社の中村博明専務は、「水位は10センチほどで通常の範囲内。壁面の異常や堆積物などはなかった。事故後、不安に思っている市民が多いと思うので慎重に作業を進めたい」と話した。
市によると、点検は3月末までに終えて結果を公表する予定という。
「道路陥没」の最新ニュース