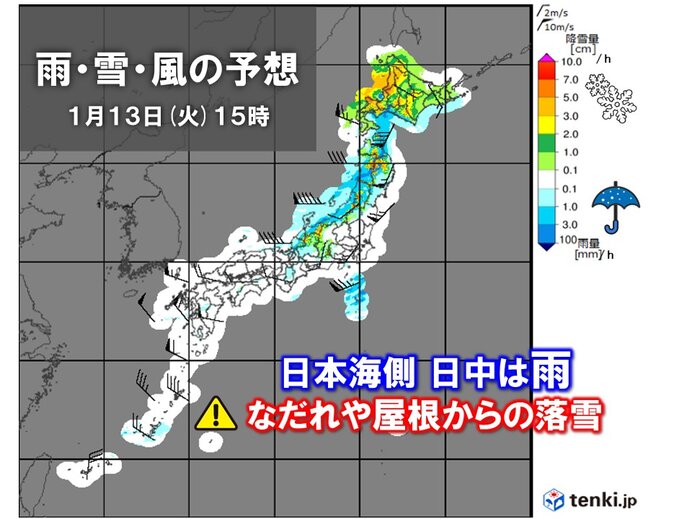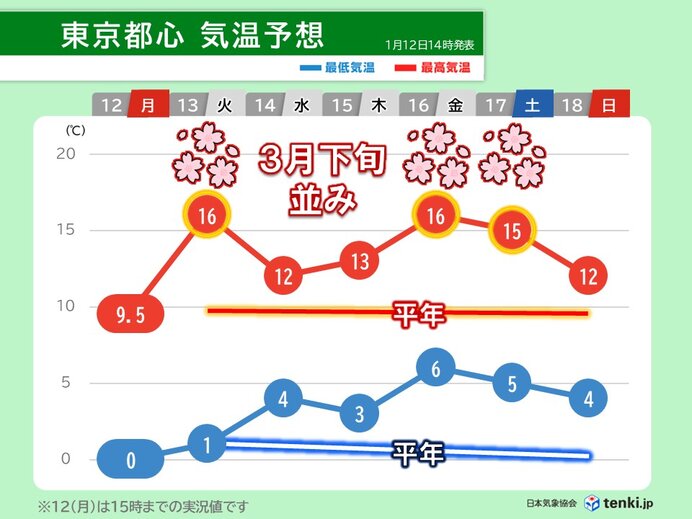八潮陥没から10週間、運転手の行方は不明のまま…5月中旬にも捜索再開か

埼玉県八潮市の県道が陥没しトラックが転落した事故で、下水道管内に取り残されたとみられる男性運転手(74)の捜索に向けて、現場では三つの工事が並行して進められている。流れ込む下水量を減らすバイパス管整備などで、県は目標としてきた5月中旬の完了に向けて、昼夜を問わず工事を続けている。
陥没現場では捜索に向けた工事が進められている(10日午後、埼玉県八潮市で)事故で穴に落ちたトラックの運転席部分は、現場から約30メートル下流の下水道管内にあることが確認されている。運転手の捜索に向けて、県は〈1〉現場に流れ込む下水を 迂回(うかい) させるバイパス管整備〈2〉運転席部分真上から直径4メートルの穴の掘削〈3〉運転席部分の上流側からの斜め方向の掘削――の三つの工事を進めている。
陥没現場で進められている三つの工事〈1〉は3月中旬から掘削工事を開始し、今月からは管の設置も始めた。〈2〉は3月下旬から開始し、下水道管の上部にたどり着いたら、管に穴を開ける見通しという。〈3〉も今月から開始した。〈2〉〈3〉の完成後は、消防隊員が下水道管内に入る捜索ルートとして使われる見込みだ。
事故は1月28日午前に発生し、男性運転手がトラックごと落下。その後も周辺の陥没が続き、穴は最大幅約40メートルまで拡大した。二次被害の危険があることから、消防による捜索は手詰まり状態となった。本格的な捜索の実施に向けて、県は2月11日、バイパス管整備などの土木工事によりまず安全を確保する方針を示した。
県は3か月ほどでの工事完了を目指している。進ちょくについて、大野知事は「ほぼ予定通り。もしくは数日前倒しで進んでいる」としており、5月中旬にも完了し、捜索活動が始まるとみられている。
県の調査では、現場周辺の地盤は「シルト」と呼ばれる砂よりも細かい粒子の層で、非常にもろいという。薬液の注入や矢板を打ち込むことで地盤を強化しながらの工事が続いている。
工事が進む一方で、原因究明に向けた動きは緒に就いたばかりだ。県は、下水に含まれる有機物から発生した硫化水素が原因で管内部が損傷したと推測している。ただ、2021年度に行われた下水道管の定期点検では、「ただちに工事が必要な状況ではない」と評価されており、破損に至った詳しいメカニズムは分かっていない。
原因究明を目指す第三者委員会は3月14日に1回目の会合を開いた。今夏をめどに中間取りまとめを行う見通しだ。
続く通行止め、振動・悪臭も
陥没した交差点を中心に周辺道路では依然として通行止めが続いている。工事による振動や騒音、流れ込む下水による悪臭などの影響も出ている。県は運転手の捜索活動の終了後に、現場を埋め戻して道路が使えるようになるのは「12月以降」としている。
2月下旬に開かれた現場周辺の住民に向けた説明会では、参加者から「家も車も臭い」「深夜に揺れを感じる」といった声が多く上がった。県は穴の一部に防臭シートをかぶせる対策を実施。また周りの5地点で、臭気や振動などを毎日計測し公表している。
近くの小学校では通学路を変更した。県は通学路の安全点検を行い、今月5日までに計18か所の交差点で、横断歩道と「止まれ」表示の引き直しや、ポールの設置などを実施した。
記者が周辺を訪れた10日には時折、硫黄のような臭いが漂っていた。近くに住む主婦の女性(86)は「風向きによって臭いを感じる日はある。規制も不便だが仕方がない。とにかく早く運転手さんが見つかってほしい」と祈っていた。
「道路陥没」の最新ニュース