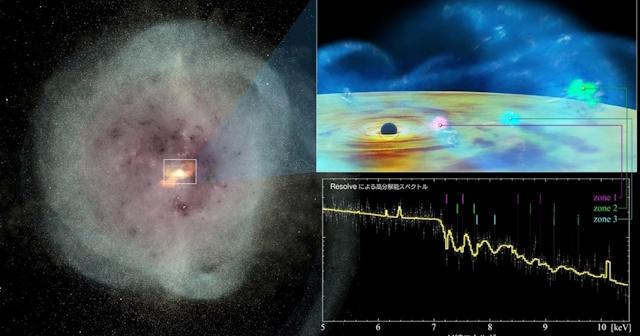「テクノロジーで人間の能力は衰えた」はウソだ/生成AIが迫る「何が能力なのか」の大転換(東洋経済オンライン)

あるベテランの生物学研究者から、こんな話を聞いたことがある。 かつて、生物学者にとって「老眼」は致命傷だった。顕微鏡の接眼レンズを長時間覗き込み、微細な構造を見極めるには、強靭な視力と集中力が不可欠だったからだ。視力の低下は、実験室からの引退を意味していた。 しかし現在では、高精細なモニターに拡大像を映し出し、複数人で議論しながら観察できる。視力の低下と、研究者としての能力は切り離されたのだ。 これは単なる道具の進化ではない。能力そのものと、それを発揮するための「身体的なインターフェース」が分離されたという、より本質的な変化である。
実際、近年のノーベル生理学・医学賞の受賞者を見ても、高齢でありながら現役の研究者として第一線に立つケースが増えている。 たとえば、2025年の受賞者である大阪大学特任教授の坂口志文先生(74歳)も、その1人だ。1976年に京都大学医学部を卒業して以来、約50年にわたって免疫学の研究を続け、制御性T細胞の発見という偉業をなし遂げた。 かつての基準であれば、体力や視力の衰えとともに引退を余儀なくされていたかもしれない。しかし、研究環境の技術革新が、研究者としての寿命を延ばしたのである。
■「絵心」が不要になった日 歴史を遡れば、生物学者にはもう1つ、必須の技能があった。それは「スケッチ」である。 カメラが普及する前、観察結果を残す唯一の手段は、自分の手で描き写すことだった。顕微鏡をのぞき、対象のどこが重要かを見抜き、それを線と形に落とし込む。スケッチは単なる記録ではなく、観察結果を抽象化し、検証可能な形で残すための高度な職人芸だった。 しかし、写真技術の普及により、この能力は急速に不要になった。「絵がうまいかどうか」は、研究者の評価軸から完全に消え去った。
ここで起きたのは、研究者の能力低下ではない。「どこを見るべきか」「その違いは何を意味するのか」という研究の本質と、それを記録するための周辺的技能(画力)が切り離されたのである。 ■キーエンスが支持された本当の理由 この変化を現代で象徴するのが、顕微鏡市場におけるキーエンスの採用の広がりである。 顕微鏡といえば、かつてはニコンやオリンパスといった伝統的な光学機器メーカーの独壇場だった。彼らは「レンズの性能」という極限を追求していた。
Page 2
ところが近年、研究現場ではキーエンスの採用が広がっている。その理由は「光学性能の高さ」ではない。「誰でも使える自動化」にある。 従来の顕微鏡は、暗室にこもり、微妙なノブ操作でピントや照明を調整する熟練の技が必要だった。対してキーエンスの製品は、明るい部屋で、モニターを見ながらマウスをクリックするだけで、誰でも均質な画像が撮影できる。 評価されたのは、「がんばればすごい写真が撮れる道具」ではなく、「がんばらなくても撮れる設計」だった。ここでも、手作業の巧みさという周辺技能が剥ぎ取られ、観察と解釈という本質だけに集中できる環境が選ばれたのである。
いま、同じ構造変化が、文章作成や企画立案といった知的生産の現場で起きている。 これまでは、「考える・構成する・文章を書く・推敲する」というプロセスを、すべて1人の脳内で、手作業で完結させることが求められていた。それは、暗室で顕微鏡をのぞきながらスケッチを描くような、孤独で負荷の高い作業だった。 生成AIの登場は、このインターフェースを一変させた。思考の断片をAIに投げかけ、構造化させ、表現を試させる。私たちはモニター越しにその結果を確認し、「ここは違う」「もっとこう表現すべき」と指示を出す。
これは、顕微鏡が接眼レンズからモニターへ移行したのと同じだ。知的生産が「職人的な手作業」から「モニター越しのディレクション」へと進化したのである。 技術革新は、人間の能力を奪うのではない。 それまで不可分だった「本質的な判断力」と「手段としての作業力」を切り分け、何が本当に重要だったのかを露わにするフィルターの役割をはたす。 スケッチが描けなくなった研究者が、写真によってより多くの発見を成し遂げた。暗室操作から解放された学生が、より多くのサンプルを観察できるようになった。これと同じことが生じているのだ。
■生成AIで「何が能力か」が問われる 生成AIは私たちから「書く苦労」や「まとめる手間」を奪うかもしれないが、それによって「何を問うべきか」「何に価値があるのか」という判断力は、むしろ純粋な形で問われることになる。 スケッチから写真へ。接眼レンズからモニターへ。そして、思考からAIへ。技術が変わるたびに問われるのは、私たちが「能力」だと思ってきたものが、本当に本質だったのかどうかである。 私たちはいま、能力が失われる時代ではなく、能力の本質がようやく裸にされた時代に立っている。
大竹 文雄 :大阪大学感染症総合教育研究拠点特任教授