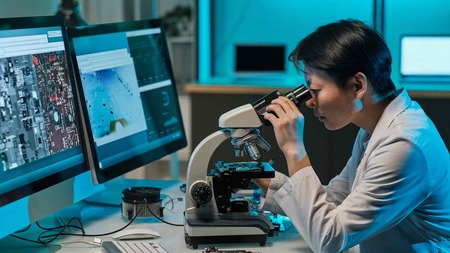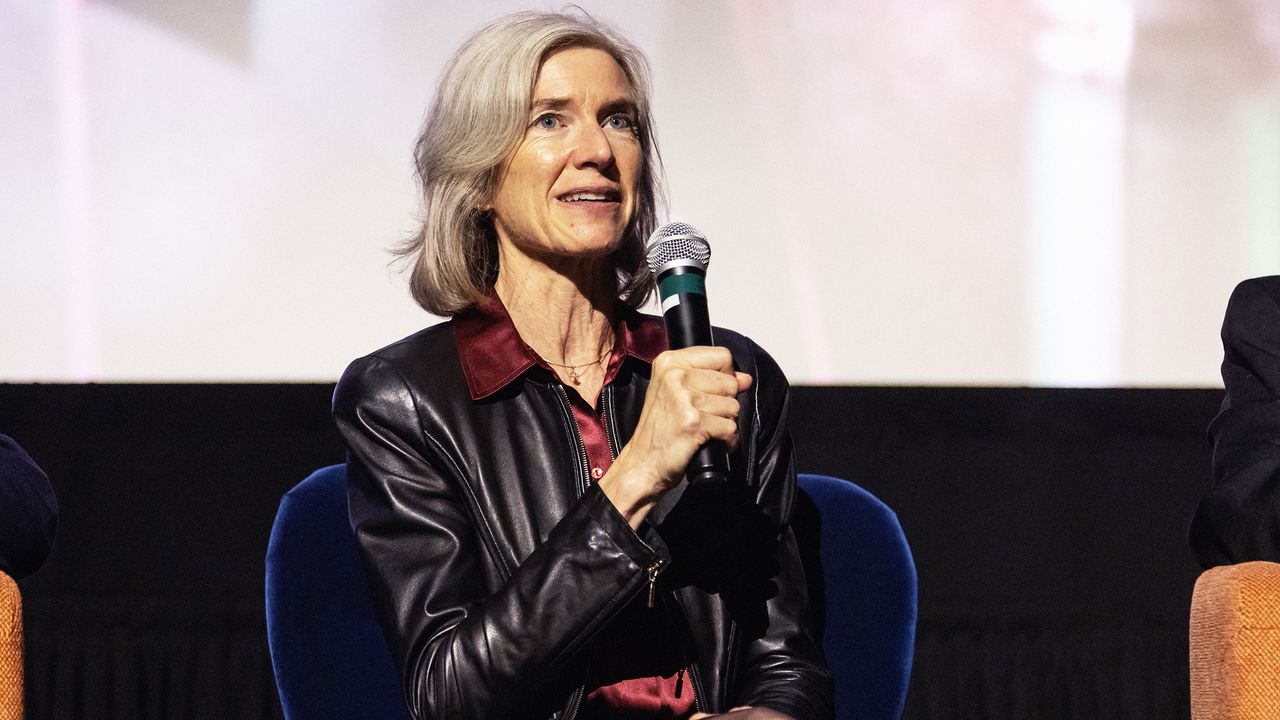なぜ人は「法隆寺は地震に強い伝統構法で建てられているので1000年以上倒れていない」を信じてしまうのか フェイク情報にまどわされなくなるヨボヨボ頭の鍛え方

「古い建物が多数現存するのは、日本古来の建築技術が地震に強いからだ」。これをあなたは信じるか。構造設計一級建築士であり、耐震工学のエキスパートでもあるバッコ博士は「言い切り型の情報はわかりやすいが、必ずしも正しいわけではない。シンプルゆえに内容が変質していることもある。情報を受け止めるには、考える姿勢が必要だ」という――。
※本稿は、バッコ博士『教養としての建築』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
建築業界に氾濫するウソの情報
いろいろな専門領域において、新しい理論や新しい考え方が日々提案されています。その中には間違っているものもあり、それらは時間の経過の中で淘汰されていきます。最初は誰にも注目されなかった理論の正しさが時間の経過とともに実証されたり、逆にみんなが信じていた理論に穴が見つかったりします。
もちろんこれは、建築の構造に関しても同様です。ある建物が地震で倒壊してしまった理由は何か、その観測結果の解釈はそれで正しいのか、などなど、専門家の間で議論が交わされています。
そのため専門書や教科書では、しっかりとした理論的な裏付けがあるものや、まず間違いないものだけが掲載されます。まだ議論の余地があるものはコラムとして取り上げるか、評価が定まっていないことを明示したうえで掲載する場合が多いです。
しかし、昨今は個人での情報発信が容易です。ブログや動画配信など、いろいろなツールを使って自由に情報発信ができます。有益な情報が手に入りやすくなりましたが、その一方で中には間違った情報を無責任に垂れ流しているようなものもあります。
そして一番の問題は、正しい意見が主流になるとは限らず、間違った意見が正しいかの如く広まってしまう場合があることです。こうなってしまってはもう収拾がつきません。
写真=iStock.com/MasaoTaira
※写真はイメージです
なぜ誤情報が生まれるのか
日常的に交わされる質問について考えてみましょう。質問に対する回答はシンプルなものが好まれます。とにかくこうすればよい、絶対にこうすべきだ、という言い切りの表現です。場合によっては違う、だとか、やり過ぎると逆効果になる、というのはシンプルな回答ではありません。
インターネットの世界ではわかりやすさが優先されるので、正確な表現というのは敬遠される傾向にあります。正確な表現を心がけると、あいつは説明が下手だ、という烙印すら押されかねません。
しかし、建築の構造、あるいは耐震工学というのはそんなに簡単なものではありません。建築に限らずどの専門分野でも同じです。シンプルに回答できることもあれば、できないこともあります。それがわからず、無理にシンプルにしてしまうことで情報が変質し、ウソ・間違い・誤情報となるのです。
伝統構法の建物が地震に強いというのもその一例です。神社仏閣や古民家が現存するということは、自然災害の多い日本において、何十年、あるいは何百年と耐え続けてきたということです。一方で、最新の基準に従って建てられているはずの新築の住宅が、大地震によって無残に倒れてしまうこともあります。どうしてそのようなことが起こるのでしょうか。
Page 2
耐震が難しいのは、その建物が地震に耐えられるかどうかの答え合わせが数十年、あるいは数百年に一度しかできないことです。また、建物ごとに条件がまったく違うので、答え合わせ自体が難しい。
そのため、大地震が起こるまでは間違った情報を流し続けてもばれませんし、仮に起こってもばれない可能性が高いのです。なんともウソがまかり通りやすい状況がお膳立てされているものです。
写真=iStock.com/SAND555
※写真はイメージです
バッコ博士『教養としての建築』(かんき出版)
未知ゆえに間違うことはあります。ですが、無知ではいけません。この記事を読んでくれている方の多くは、「いい国(1192年)つくろう鎌倉幕府」と習ったことでしょう。しかし今では「いい箱(1185年)つくろう」と習います。常識は常に変化しているのです。
また、前提となる基準や法律を疑うことも重要です。本来の意味を取り違えていないか、初心に返って考えてみる必要があります。勝手な解釈をして、適用範囲を超えるような使い方をしていないでしょうか。
大事なのは「無知の知」です。「私はわかっていない」ということを知っている、という態度が間違いに気づかせてくれるはずです。
- 構造設計一級建築士、京都大学博士(工学)、コンクリート主任技士耐震工学のエキスパート。専門は超高層ビルの振動制御。大手建設会社にて構造設計および開発業務に従事。電波塔から超高層ビルまで、幅広い建物を担当。考案した独自の構造システムが超高層ビルに適用されている。免震・制振に関する特許出願は20件を超える。