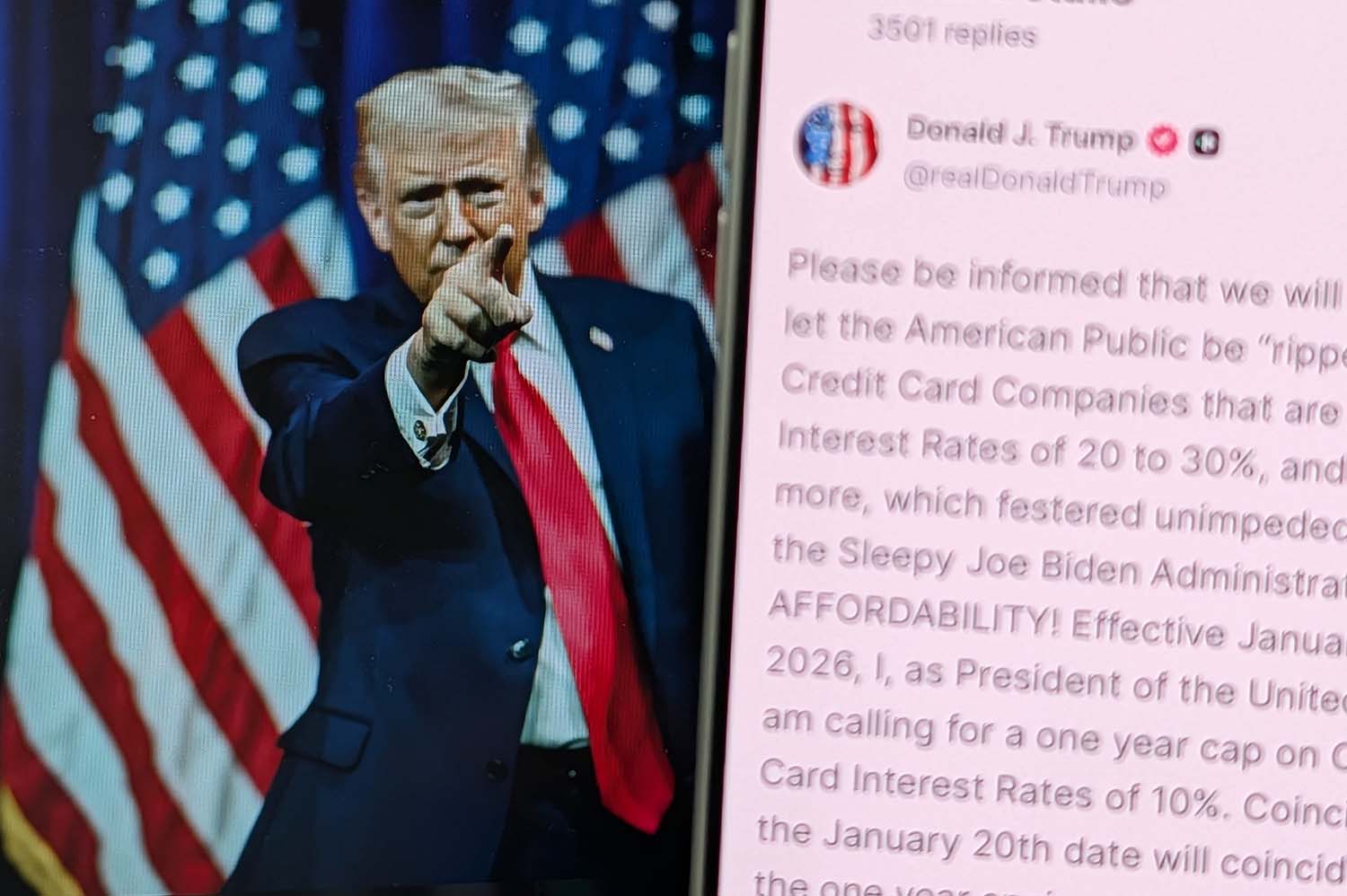万博で変貌した「負の遺産」夢洲 跡地利用計画に財界が「待った」 鉄道延伸負担も課題に

13日に閉幕する大阪・関西万博の会場となった大阪湾の人工島・夢洲(ゆめしま)(大阪市此花区)。かつて市が開発に失敗し「負の遺産」と揶揄(やゆ)された。活性化の切り札として誘致した万博は盛況のうちに終わるが、大阪府市が策定した跡地利用計画に財界から「待った」がかかった。夢洲で2030年秋ごろに開業するカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の成否、鉄道の延伸費用負担なども課題として横たわる。
「IRの誘致と万博の成功を経て、ようやく夢洲の行く先にめどが立ったという思い。これからの再開発が正念場だ」
万博誘致を牽引(けんいん)した地域政党「大阪維新の会」幹部はそう感慨深げに語った。
夢洲は1977年、大阪市が廃棄物や建設残土の処分場として整備を開始。6万人が居住する住宅地とする計画はバブル崩壊で頓挫した。誘致を目指した2008年夏季五輪で選手村の設置をもくろんだが、中国・北京との誘致合戦に敗れた。
その後、維新の松井一郎大阪府知事(当時)、橋下徹大阪市長(同)らが万博とIRの誘致を提唱。18年11月に万博誘致に成功し、IRは23年4月に国から区域整備計画の認定を受けた。荒涼としていた夢洲には万博開幕後の半年間、以前からは想像できないほど大勢の人が詰めかけた。
閉幕後の跡地はパビリオンなどが解体され、いったん更地になる。府市は夢洲を「国際的な観光拠点」とする青写真を描き、跡地利用について今年4月に基本計画を策定。アリーナ、ウオーターパークといったエンタメ施設を整備する案を示している。万博のシンボル「大屋根リング」は北東約200メートルを保存し、一帯を公園・緑地として整備することも決定。来春ごろまでに最終的な計画をまとめ、開発事業者を募集する。
その北側に開業を予定するIRは工事が進み、カジノのほかホテルや国際会議場、エンタメ施設などが整備される予定で、年間来場者は約2千万人、年間売上高は約5200億円を見込む。
しかし、関西経済連合会の松本正義会長は今月6日のインタビューで、跡地利用の基本計画に、国際的モータースポーツ拠点など万博とは必ずしも関係ない施設が導入例として記載されている点を疑問視。「経済界や専門家などの了解も得て、計画の策定を進めるべきだ」と述べた。
夢洲への交通網整備もにぎわい持続に欠かせない。府市は今年8月、JR西日本と京阪電気鉄道がそれぞれ夢洲へ延伸する案が優位とする試算を公表した。見込まれる事業費は計約3500億円。JR西の倉坂昇治社長は、府市や国などによる公的資金拠出などの方向性を見定める考えを強調している。京阪電鉄を傘下に置く京阪ホールディングス(HD)の平川良浩社長も、公的資金による財源確保は必須との考えを示している。
横山英幸市長は今月9日の記者会見で「かつてこの場所には万博があったと思い起こしてもらえるような仕組みが必要。圧倒的な非日常空間をつくりたい」と意欲を語った。巨額の事業費が予想される夢洲開発を進めようとすれば、万博と同様に官民の連携が問われる。(石橋明日佳)
70年万博で生まれ変わった大阪
万博は単なる一過性のイベントにとどまらず、開催に合わせた交通インフラ整備や会場の跡地利用により、開催地のまちづくりの起爆剤となってきた。過去の成功例では、閉幕後を見据えた設計や計画が鍵を握る。
1970年に大阪府吹田市で開かれた大阪万博では、北大阪急行電鉄により万国博中央口駅までの臨時の「会場線」が開業した。輸送力を補うため、天神橋筋六丁目駅(大阪市)と北千里駅(吹田市)を結ぶ阪急千里線も、69年に私鉄で初めて地下鉄と相互乗り入れを始めた。現在では一般的な相互乗り入れの先駆けで、同線は今も市民の足として使われている。
さらに、大阪市を南北に走る御堂筋から接続する新御堂筋が、70年に大阪市北区から万博会場に近い大阪府箕面市までの区間で開通。その後に京都府亀岡市までつながり、全国有数の主要道路となった。ほかにも、会場に水を供給するため水道が拡張され、上下水道の整備も進んだ。
2005年愛知万博は現在の愛知県長久手市などが会場となり、愛知高速交通の東部丘陵線「リニモ」が開業。名古屋市の都心部とのアクセスを向上させ、長久手市の人口増加や地価上昇をもたらした。跡地の愛・地球博記念公園は開催翌年に開園し、その後は場内にスタジオジブリ(東京)の映画の世界観を再現した公園施設「ジブリパーク」も開業したことで、地域に大きな経済効果をもたらしている。
海外では、前回のドバイ万博の跡地が、開催前からの計画に沿ってサステナブル(持続可能)な都市として開発された。万博施設の8割がオフィスや住宅、展示場などに再利用され、国際的イベントの跡地活用のモデルとなっている。(井上浩平)
りそな総合研究所・荒木秀之主席研究員「観光市場予測し、事業者と未来像共有を」
大阪・関西万博そのものに対する評価は今後、「未来社会の実験場」というコンセプトに沿ったレガシー(遺産)を活用できるかどうかにかかっていると考える。あまたある社会課題の解決につながるような技術やアイデアが社会で実用化され、中長期の成長に結びつくことが、万博を開催した意義や価値になっていくはずだ。
夢洲はIRの開業を控える今、観光の一大拠点として活用されるべきだという見方が強い。万博跡地とIRとのシナジー(相乗効果)を考えた開発が求められる。
大阪府市は、今後の観光市場の予想を立てて夢洲の大きな未来像を描き、事業者と認識を共有する必要がある。そうすることで企業は商機を見いだしやすく、投資の流れが生まれるのではないか。(聞き手 石橋明日佳)