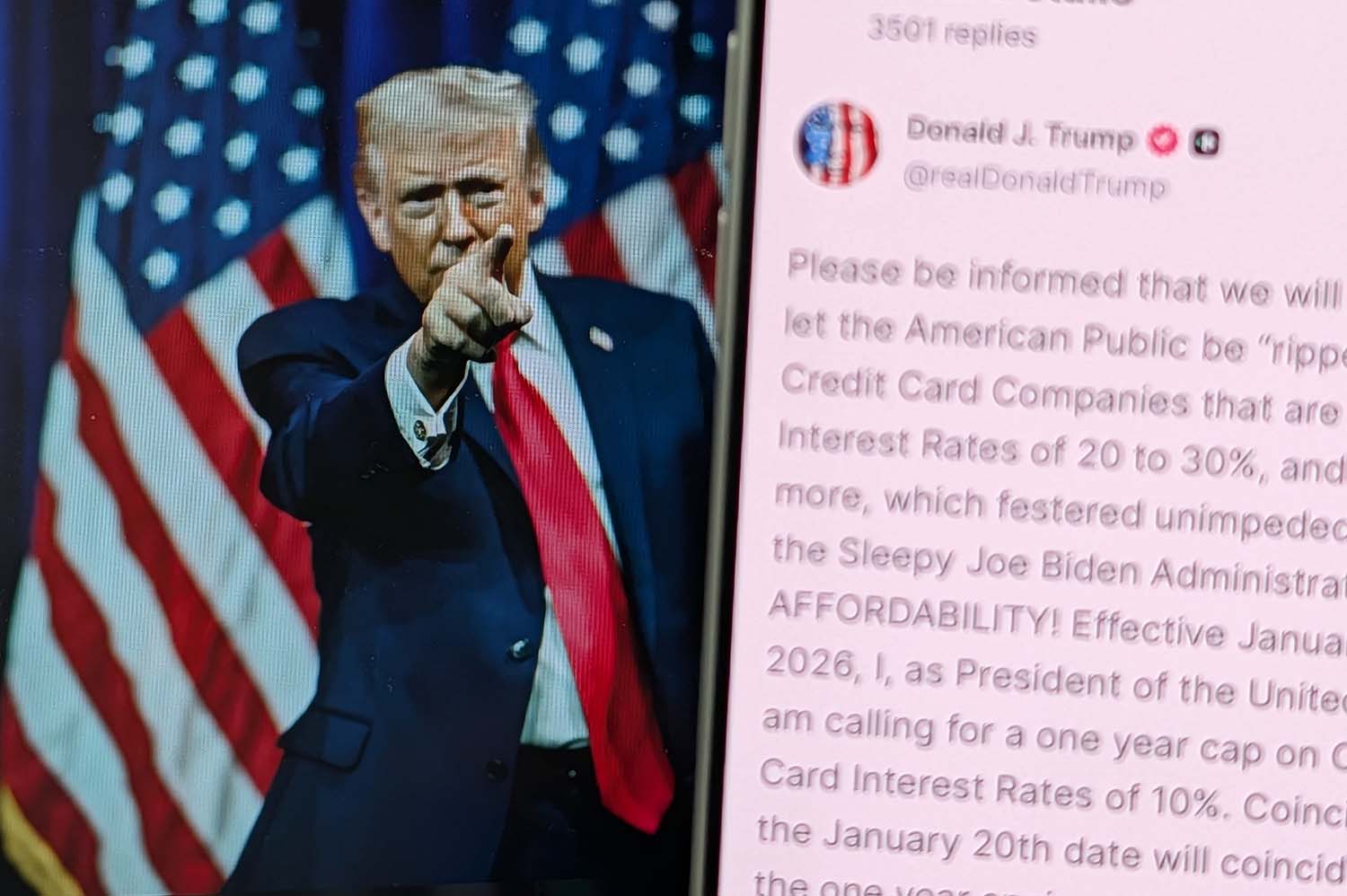まさかのミャクミャク人気、グッズ好調で万博黒字化の救世主に 来場者数は夏休み前に一服 万博展望㊦

大阪・関西万博の会場で、開会式の舞台となったEXPOホール「シャインハット」前に主要パビリオン顔負けの人気スポットがある。
カランカラン-。7月11日、ホール前の店舗で「当たり」を知らせる鐘が何度も響いた。万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のぬいぐるみを抱いて出てきた大阪府交野市の女児(8)は「ベッドで一緒に寝たい。最初は『何これ』と思ったけど、お尻にも目があるし今はかわいい」と笑顔を見せた。
全長80センチの1等か、46センチの2等、23センチの3等のいずれかが必ず当たる「ミャクミャクぬいぐるみくじ」で1回2200円。待ち時間は連日2時間を超える盛況ぶりだ。
ミャクミャクは今でこそファンを中心に親しまれるが、奇抜なデザインに当初は「気持ち悪い」などと散々ないわれようだった。万博を運営する日本国際博覧会協会の関係者は「正直ここまで人気になるとは思わなかった。万博を機運醸成だけでなく、資金面でも支えてくれている」と話す。
「ペイラインは超える」
会場管理など万博の運営費は1160億円で、このうち969億円(約84%)を入場券収入で賄う計画。これに加え、グッズや飲食関連を110億円(約9・5%)としている。
入場券販売について協会は、運営費を黒字化できる「損益分岐点」について、入場券の価格(平日大人6千円)などに基づき1840万枚と設定している。入場券販売は7月4日時点で約1554万枚となり、1500万枚を突破。協会幹部は「ペイラインは間違いなく超える。あとはどれだけ上積みできるかだ」と強調する。
ただ、入場券販売の最終目標は2300万枚としており、損益分岐点は最低限のラインに過ぎない。何度でも入場できる通期パス利用者が多いことに加え、夏休み期間中はさらに割安な夏パスも投入される。協会のもくろみ通りの収益になるかは未知数だ。
8~10%がロイヤルティー
このためグッズ販売への期待は大きい。ミャクミャクを主軸とした公式グッズは、協会とライセンス契約を結んだ企業が製造している。定番のキーホルダーや菓子など約7千種類があり、一部は品薄でインターネットのオークションサイトなどで高額転売されている。
入店を待つ人の行列ができることも珍しくない万博会場のグッズ店=6月、大阪市此花区公式グッズは価格の8~10%がロイヤルティーとして企業から協会に支払われる。協会関係者によると、ここから万博の知的財産管理団体に一部が割り当てられ、残りが万博の運営費に入る。
協会は詳細な売り上げを公表していないが、関係者は「非常に好調」と顔をほころばせる。協会は11日、人気のミャクミャクぬいぐるみくじの台数を増やすなどの拡充策を発表した。黒字化に向けてグッズ販売も大きなカギを握っている。
500円でも徳島には…
大阪・関西万博の会場から約100キロ離れた徳島港(徳島市)のフェリーターミナルでは、観光客数人が「徳島県への招待状」と記されたチケットを手にしていた。
チケットは万博会場の徳島県ゾーンを訪れた人に同県が配布したもので、徳島までの往路の交通費が一律500円になる。県によると、万博来場者に徳島県を訪問してもらう狙いがあり、6月1日時点で約2万5千枚を配布し、延べ926人が実際に使用した。
県万博推進課の担当者は「交通費割引の原資として約2500万円を確保し、約7500人に使ってもらえる計算」と説明する。ただ、予算に対する使用率は10%台にとどまり、担当者は「夏休みの〝ブースト〟に期待している」と話す。
3兆4000億円の効果は不透明
万博の経済波及効果について、アジア太平洋研究所(APIR)は会場外の大学や研究施設、観光地をパビリオンに見立て、万博来場者の周遊を促す「拡張万博」を実現することで約3兆4千億円の効果を予測するが、大阪以外への波及効果は不透明な状況だ。
万博は期間中の来場者想定を約2820万人としており、達成には1日平均15万人以上が必要。APIRの稲田義久研究統括は、1日の来場者が15万人を超えたのが開幕以来4日しかなく、6月下旬から1週間の来場者数が減少に転じたことを不安視する。「期待通りの経済効果には、まずは入場者数の目標達成が欠かせない」とした上で、「残り3カ月しかない。『万博は成功だった』とするためにも、来場者が再訪したくなるコンテンツのさらなる造成が必要」と強調した。
提言 来場者満足度向上の施策を
大阪・関西万博の来場者数の伸びは勢いを欠くが、それでも地下鉄駅直結で利便性の高い東ゲートには長蛇の列ができ、人気パビリオンは予約が取れない盛況ぶりとなっている。ただ連日の暑さもあり、その混雑に来場者から不満の声が目立つ。
収益を増やすには来場者の満足度を高める必要があるが、会場ではユスリカが大量発生したり、水辺でレジオネラ属菌が検出されたりといった問題が噴出し、運営主体の日本国際博覧会協会の対応は後手に回ってきた。
来場者からの「夜に楽しめる場所が少ない」との指摘を受けて、協会は会場の飲食店やグッズ店の営業時間を7月から最長で午後9時45分まで延長した。黒字をしっかりと確保するためにも、来場者の満足度向上につながる施策を今後も積極的に打っていくべきだ。