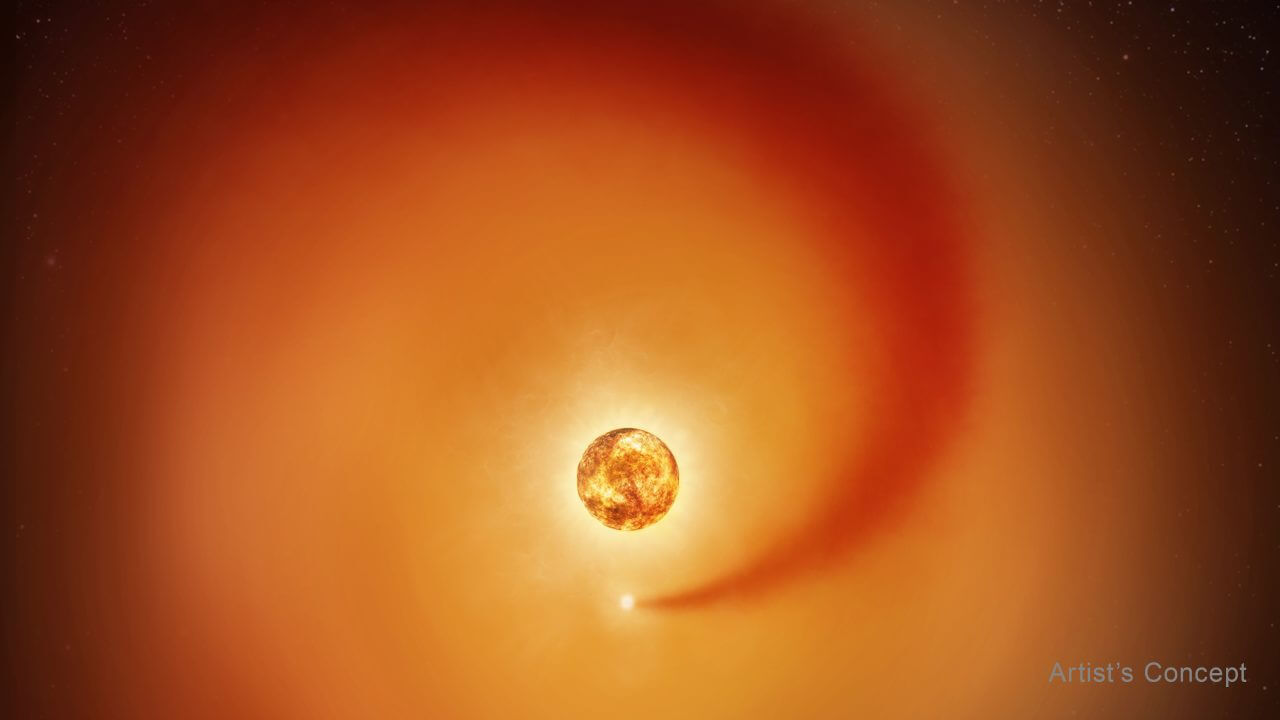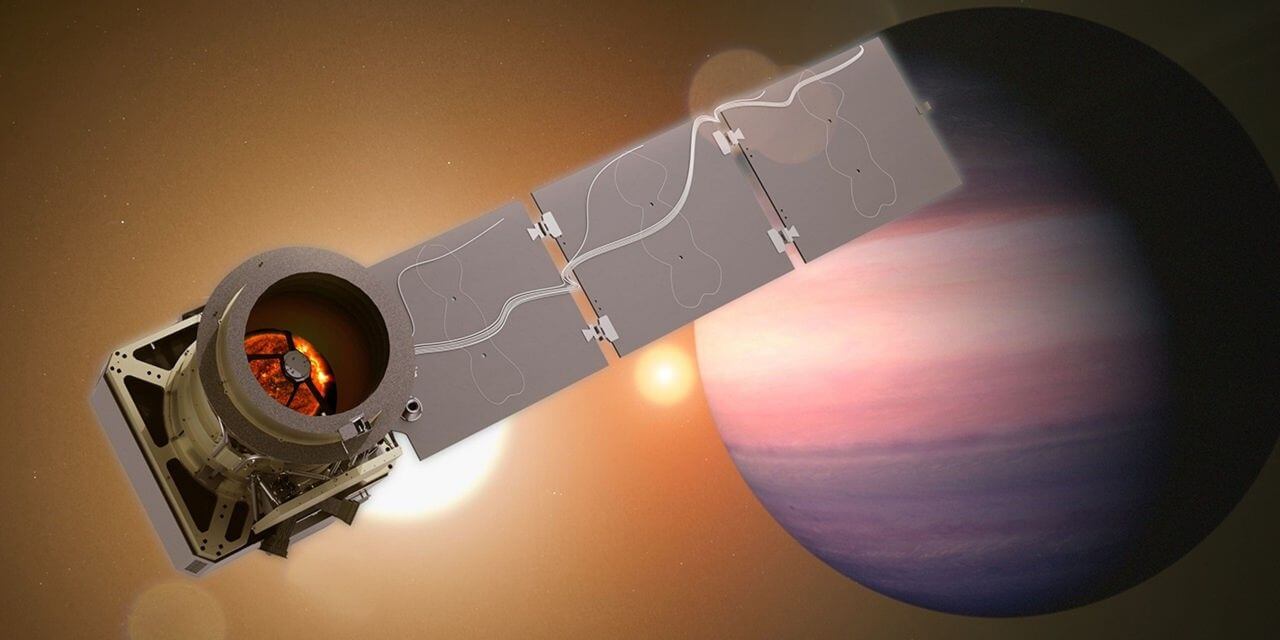地層ってひっくり返ることがあるの? 北海の海底で起きていること

地層がひっくり返ることってあるんだ…。
地層学の世界では、浅い場所の堆積物の方がその下の層よりも年代が若い…はずなんです。しかし、北海でこの常識をひっくり返す巨大な砂の隆起物が見つかりました。しかも、科学者がこれまで見たこともないくらい大規模なのだとか。
海底に奇妙な砂山がごろごろ
ノルウェーとイギリスの研究チームは、北海の海底で数百に及ぶ砂山を特定。不思議なことに、砂山は海底に深く沈み込んで、より古い地層と入れ替わっているといいます。つまり、沈んだ新しい層の砂山の上に、古い地層が乗っかってしまったというわけ。
研究チームは、この現象を「Sinkites(シンカイト: おそらく"sink"と鉱石や岩石名に付けられる接尾語の"-ite"からの造語)」と名付けています。今回発見された地層逆転現象は、これまでに知られている中でも最大規模で、二酸化炭素(CO2)の貯留プロジェクトに大きな影響を与える可能性があるとのこと。
マンチェスター大学の地質学者であるMads Huuse氏は、大学の声明で次のように述べています。
今回の発見は、これほどの規模では確認されたことがない地質過程を明らかにしています。私たちは、高密度の砂がより軽い堆積物の中に沈み込み、軽い堆積物が砂の上に乗り上げた構造を発見しました。その結果、従来あるべき地層がひっくり返って、海底に巨大な隆起物が形成されました。
数百万年前にできた巨大な砂山
研究チームは、直接採取した岩石のサンプルや、高解像度の3Dイメージング技術などのデータを用いて、「細粒堆積物に埋もれた高さ数百メートル、長さ数十キロメートルに及ぶ砂の隆起や海嶺(尾根)」を調査しました。研究論文は、学術誌Communications Earth and Environmentに掲載されています。
チームは、後期中新世(1040万~500万年前)から鮮新世(500万~160万年前)にかけて、地震や地圧の変化によって砂が液状化し、海底に生じた亀裂を伝って沈み込んだことでSinkitesを形成したと推測しています。
この流動によって、より深部にあった、小さな海洋化石を含む硬いわりに多孔質な堆積層が押しのけられて砂山の上へ浮上したため、地層の順番が逆転してしまったようです。
Huuse氏は声明の中で、次のように説明しています。
本研究は、流体や堆積物が地殻内で想定外の動きをすることを示しています。Sinkitesの形成過程を理解することは、炭素回収と貯留に不可欠な、地下貯留層や密閉性、流体移動の評価方法を大きく変える可能性があります。
気候変動緩和策としての可能性
人間活動由来の気候変動を減速させるには、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量削減だけでなく、大気中に放出される前にCO2を回収・貯留する技術を確立する必要があると多くの科学者が指摘しています。
海底へのCO2貯留は、その候補のひとつとして挙げられます。世界で初となる商業規模の炭素貯留プロジェクトにおいて、北海の海底にCO2を注入する作業を終えたばかりだそうです。
研究チームによると、Sinkitesの発見は、このようなプロジェクトの安全性や、石油やガスの埋蔵場所を予測する上で重要になるとのこと。
Huuse氏は、声明でこう結論づけています。
多くの科学的発見と同じように、懐疑的な声も少なくありませんが、新しいモデルを支持する声もたくさん寄せられています。このモデルの適用範囲の広さは、今後のさらなる研究によって明らかになるでしょう。
海底だと、万が一漏れたときにフタをしにくそうな気が…。
Source: The University of Manchester, Nature, The Australian Museum, Ocean Visions, CBS NEWS