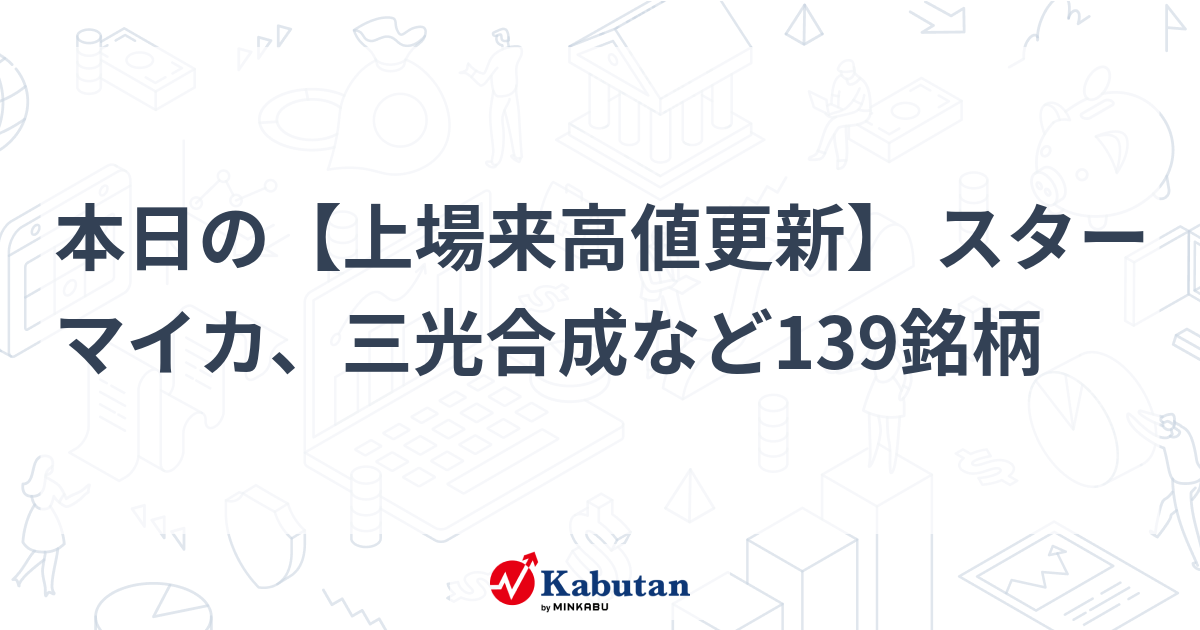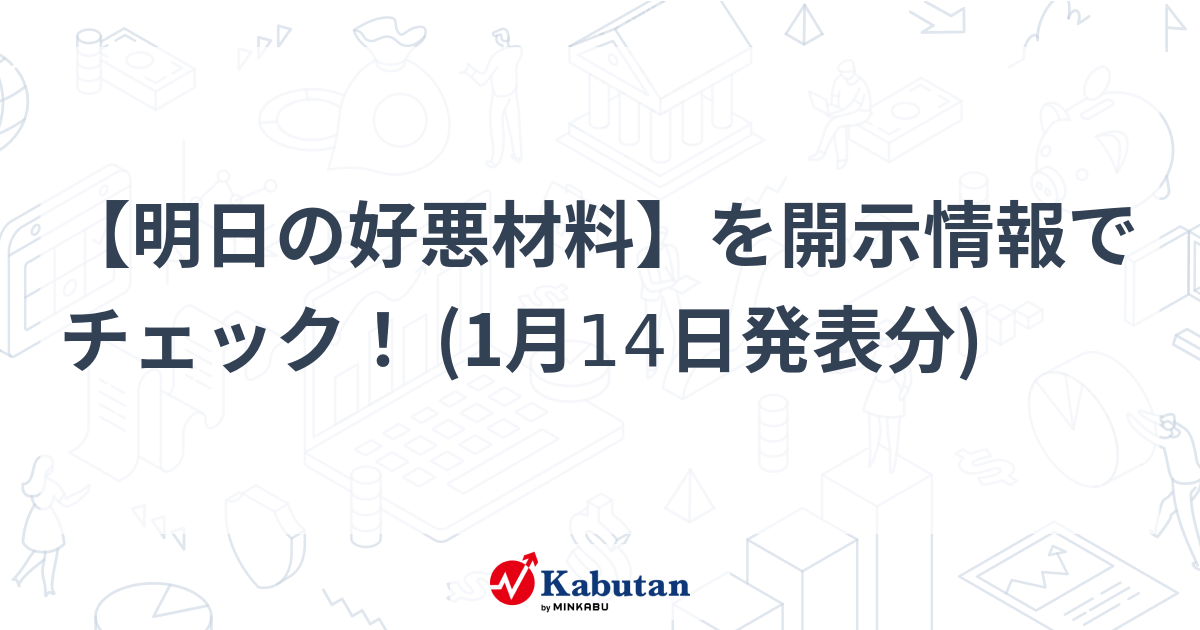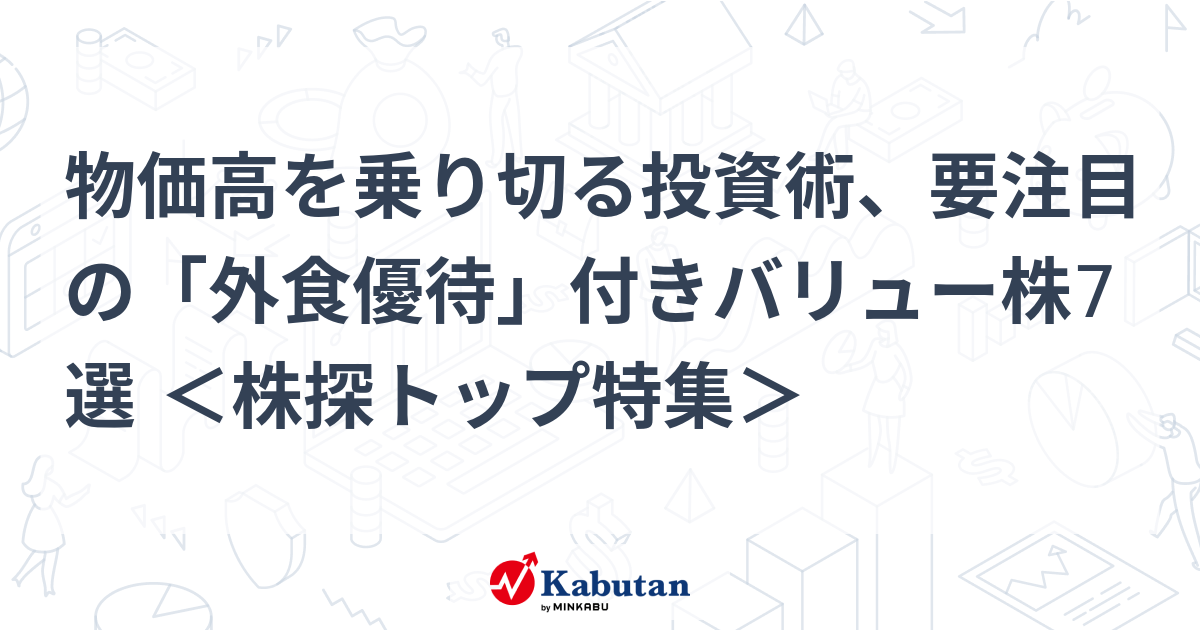ある意味「53年ぶり」の新型車両? システム面も特徴が! 京成3200形を詳しく見る

鉄道を含む交通業界では、以前から続く少子高齢化や人口減少、そしてコロナ禍を契機としたリモートワークの普及によって、輸送需要に大きな変化が見られます。京成では、近年は訪日外国人旅行者の増加という好材料がある一方、やはり輸送需要の変動リスクは課題だといいます。
3200形は、そのような流動的に変化する輸送需要に対応すべく、編成を分割できる設計で開発されました。
3200形が3600形から3100形までの車両と異なるのは、2両単位で編成を組みかえられる点。先頭車と中間車の2両で1ユニットを組み、4両編成、6両編成、8両編成を組成可能です。
これまでの京成の車両を見ると、3600形は登場時は6両固定編成、後に8両固定編成(一部を除く)で、3700形、3400形、3000形、3100形(同形式は8両編成のみ)は、6両編成と8両編成しか組成できないシステムでした。今回登場した3200形は、これまでの車両よりも組成自由度が上がるため、変化する輸送需要に柔軟に対応できます。
ただし、現役の京成の車両でも、最古参となった3500形だけは、3200形と同様に2両単位で編成を組みかえられる仕組みとなっています。3200形は今後、3500形を置き換えるために順次導入するとのことですが、新型車が置き換え対象車と同様の組成自由度を維持したともいえます。
この2両単位で組成を変更できるという思想で開発された3200形は、内部的には複雑なシステムが採用されています。
先頭車と中間車を連結した部分3200形では、車両のさまざまな情報を統括するモニタ装置が搭載されています。3200形では、どの車号をどの位置に連結したかを判別する仕組みを採用したとのこと。たとえば、3200形の製造が進んだ時点で、3201-3202+3239-3240+3205-3206という車号の順番で連結した場合(もちろん3239-3240号車は2025年現在未製造です)、ただ連結しただけで、3240号車が上野方に運転台を持つ先頭車である(実際の車号や向きは未定)、と判別できる仕組みとなっています。組成した編成の車号・位置をすべてモニタ装置が把握することで、先述した連結部の警報音をどの車両が流すべきか、などの判定に使うのだそう。説明を聞いた、京成電鉄 鉄道本部 車両部設計課 課長の廣瀬昌己さんは、「JRや京急でもやっていない(高度な)内容なのでは」と話していました。
3200形運転台にあるモニタ装置の画面。各機器の動作状況や走行位置などのほか、組成した個々の車両の番号も表示されていますその連結方法ですが、現時点では6両しか存在しないため、4両編成か6両編成の2パターンのみが可能です。将来車両が増備された際には、8両編成を組むことも可能だということ。8両編成の場合は、先頭車どうしを向かい合わせにした組成が基本となるようです。ただし、システム上は連結方法の自由度は高く、2+4+2両編成のような組成も可能だといいます。
3200形の組成方法。8両編成の場合は「パターン1」が基本とのことですが、「パターン2」のような組成も可能だといいますところで、京成の車両では、3000形と3100形において、車号にハイフンを使用(たとえば3000形第1編成の8号車は「3001-8」号車)する附番方法が採用されていました。一方、3200形では、以前のハイフンを使用しない方法へと戻っています。これについては、編成を組み替えた際の混乱を防ぐためとのこと。車両の組み合わせが変わる3200形でハイフンを使用すると、どの位置の車両なのかわからなくなるおそれがあるということで、こちらも組成変更に対応している3500形と同様、ハイフンなしで3201から順番に番号を振っていく方式としたそうです。
余談ですが、3200形が置き換える3500形がかつて8両編成を組んでいた際は、2+4+2両編成という、変則的な組成となっていました。先述したように、先頭車の先頭部には転落防止幌がないため、旅客が転落するおそれがあります。3500形では、先頭車どうしではなく、先頭車と中間車を連結することで、少なくとも片側には転落防止幌がある状態としていました。3200形も先頭部に転落防止幌はありませんが、同形式では警報音声を流すことができるため、これで問題ないと判断しているようです。
こちらは3200形ですが、右側の中間車にある転落防止幌が、左側の先頭車にはありませんまた、実際にそのような運用が実現するかは別にして、途中駅での分割併合運用(たとえば上野方面からの列車を京成津田沼駅で成田方面・千葉方面に切り離すような運用)については、3200形はシステム面では対応しているとのことでした。